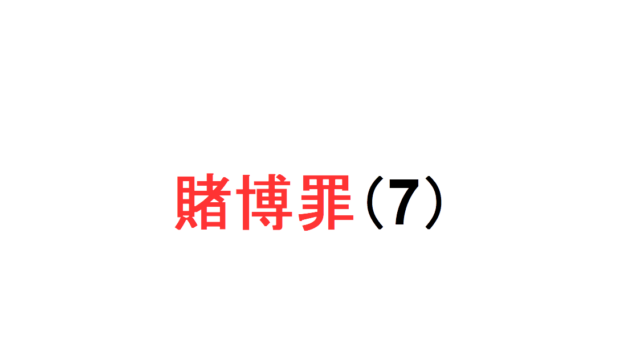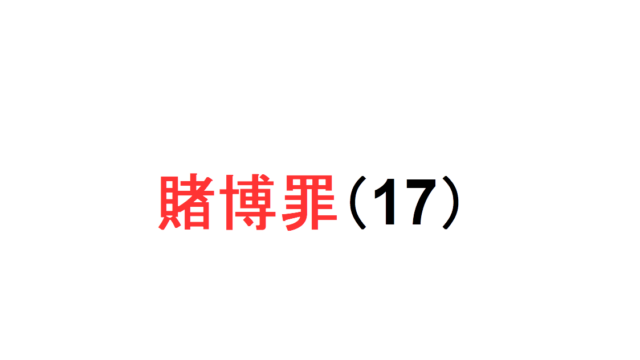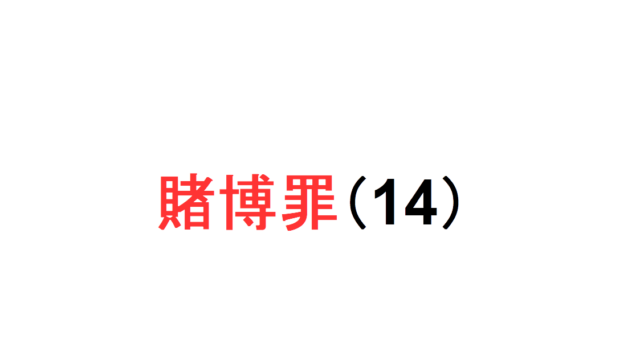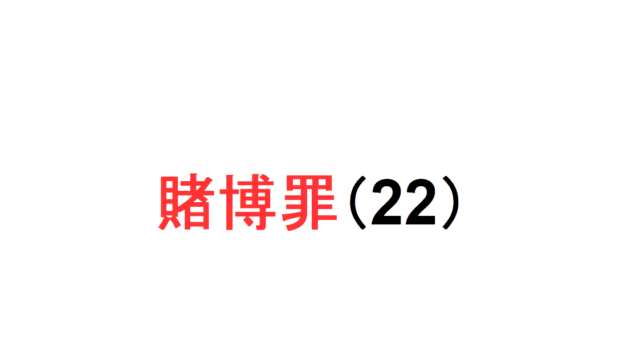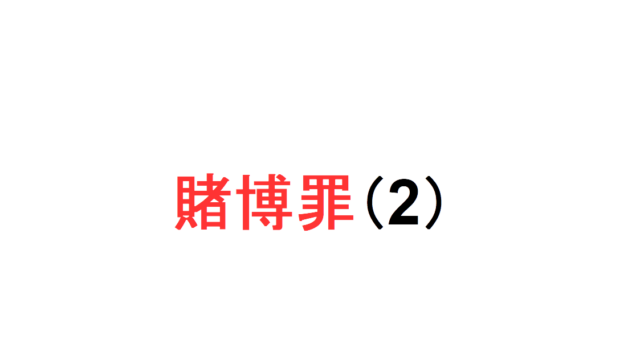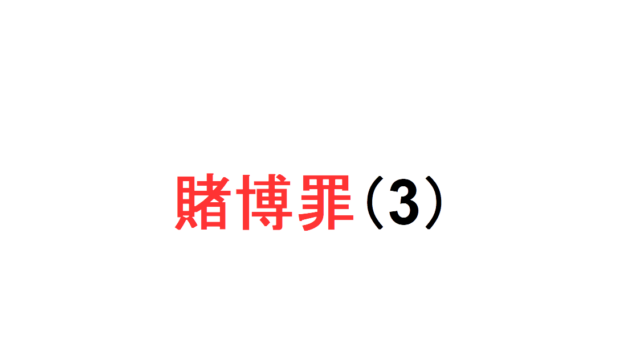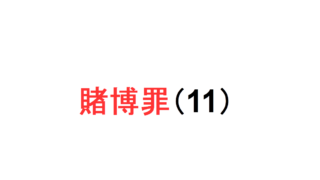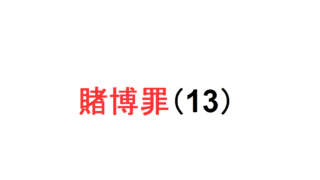賭博罪(12)~「風俗営業の許可を受けた遊戯設備による賭博行為と賭博罪の成否」を説明
前回の記事の続きです。
風俗営業の許可を受けた遊戯設備による賭博行為と賭博罪の成否
風俗営業の許可を受けた遊戯設備による賭博行為と賭博罪(刑法185条)の成否について説明します。
外形的には客相手に賭博的要素を含む遊技を行う形態の営業行為であっても、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の規定するところにより風俗営業の許可を受けた者がその許可条件に従って客に遊技をさせる場合には、「一時の娯楽に供する物を賭ける場合にあたる」として賭博罪の成立が否定されます。
「一時の娯楽に供する物を賭ける場合にあたる」とは、賭博罪の規定である刑法185条の
- 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない
という規定のただし書き部分に当たり、賭博罪の成立が否定されることを意味します。
この点につき、最高裁判決(昭和28年11月10日)は、
- 本来被告人が公安委員会の許可を受けて行つていた色合せと称する遊戯営業行為は判示のとおりの方法であつて、結局せんじつめれば営業者と客とが偶然の勝負によつて財物を賭けるという性質を帯びていることは否めないのであるが、公安委員会が特に許可した理由は、その方法にいくつかの制限を設けこの条件の範囲内において行うならば一時の娯楽に供する物を賭ける場合にあたると認めたものと解するのが相当であり、またそのように認めたことに違法はない
と述べ、公安委員会の許可(風俗営業の許可)を受けた者がその許可条件に従って客に遊技をさせる場合には賭博罪は成立しないとします。
しかしながら、風営法の許可条件に違反して客に遊技をさせる場合は、賭博罪が成立し得ます。
この点を判示したのが以下の裁判例です。
札幌高裁判決(昭和28年5月31日)
裁判所は、
- 被告人が留萌市公安委員会からABC三色のビンゴゲーム遊戯場の営業許可を受けた許可条件は遊戯券1枚10円とし、1人に3枚以上を販売し購入せしめざる制限を付したものであるが、被告人はその制限に従わず100円の遊戯券を発売し、原判示犯罪事実に記載の方法により100円賭けのABC三色ビンゴゲームと称する賭博をなしたことが認められるのであって、単に行政上の許可条件の違反に止まるのみであるということはできないし、また所論は留萌警察署営業課長が100円の遊戯券の発売を黙認したというが、暗黙にもせよ警察当局が積極的に100円券の発売を許容したとの事実は認められないから違法性を阻却する理由があるということはできない
- 従って原判決が被告人の所為を刑法第185条の賭博罪に問擬(もんぎ)したのは相当
と判示しました。
札幌高裁判決(昭和28年6月23日)
裁判所は、
- 論旨は被告人が営業として行っていたABC三色ゲームの遊戯場は(中略)留萌市公安委員会より許可を受けていたものである
- 然るに原判決はこの許可の事実を認めていないのは事実を誤認したものであるというのであって、被告人が所論のような許可を受けていたことは原判決挙示の証拠により認められるが右許可には一定の条件が付されているのである
- もし被告人が許可条件に従った営業であれば違法性を阻却するものであるが、原判決は「被告人が許可の条項を厳格に守って営業して来た場合は犯罪の成否について考究すべき点もあるが被告人はその営業許可の条項を守らず許可の営業形式を利用して、判示のように賭博行為をしたもので、その行為が犯罪を構成するのであるから」と判示しているのであって、許可外の行為を賭博罪に問擬していることが明かであって、原判決挙示の証拠によると原判示事実のような競技方法が許可されていないことが明かであるから、原判決にはこの点の事実の誤認はない
と判示しました。
裁判所は、
- 本来被告人が公安委員会の許可を受けて行っていた色合せと称する遊戯場営業行為は判示のとおりの方法であって、結局せんじつめれば営業者と客とが偶然の勝負によって財物を賭けるという性質を帯びていることは否めないのであるが、公安委員会が特に許可した理由は、その方法にいくつかの制限を設けこの条件の範囲内において行うならば一時の娯楽に供する物を賭ける場合にあたると認めたものと解するのが相当であり、またそのように認めたことに違法はない
- しかるに原判決の認定するところによると、被告人が許可の条件に違反して1人1回10円の制限を越えた遊戯券を発売し、また遊戯券を買受けた客が空気銃の弾を発射する条件を変更し多数の客を一括し任意の3名を代表として発射せしめ、さらに賞品も煙草、菓子の制限を越えて客の要求により遊戯券の購入に充てることのできる券又は現金の給付をもなすに至り、判示の期間これを繰り返したことが認められ、これを挙示の各証拠と照合してみるとその認定に誤りは認められない
- してみれば被告人が許可条件を全く無視し判示に示されたような遊戯営業行為をするに至っては、被告人の行為は許可によって一時の娯楽に供する物を賭ける場合に当るという性質を全く失い、単に許可条件に違反したという風俗営業取締法違反の限界を越え、純然たる賭博行為と認められるに至ったと見なければならない
- 従って原判決が被告人の行為をもって常習賭博を構成するものと判断したのは正当であって、法令の解釈又は擬律につきなんらの違法を認めることはできない
と判示しました。
裁判所は、
- 本来被告人が長野県公安委員会の許可を受けて行っていた遊戯営業行為は、原判示のとおりの方法であって、結局のところ、営業者と客とが偶然の勝負によって財物を賭けるという性質を帯びているものであることは否定できないところであるが、長野県公安委員会が特にこれを許可した理由は、その方法にいくつかの制限を設け、この条件の範囲内において行うならば、一時の娯楽に供する物を賭ける場合にあたると認めたものと解するのが相当であって、そのように認めたことには違法はないものといわなければならない
- しかして、原判決の認定したところによれば被告人は、右許可の条件に違反して、一人1回20円の制限を越えた遊戯券を発売し、また、遊戯券を買い受けた客が玉を突く条件を変更し、多数客のうちの任意の1名を代表として玉を突かせ、更に景品についても、許可の制限を越えて、客の要求により、遊戯券の購入に充てることができる券又は現金までも給付することとして、このような方法を繰り返し営業として行っていたというのであって、該事実は原判決援用の証拠によって優にこれを肯認することができ、記録を調べてみても、原判決の右認定が誤っているとは考えられないのである
- このように、被告人が長野県公安委員会の許可条件を無視して、右原判示のような遊戯営業行為をしていたとすれば、被告人の所為は、右許可によって一時の娯楽に供する物を賭ける場合に当たるという性質を失い、単に許可条件に違反したという風俗営業取締法違反の限界を越え、純然たる賭博行為と認められるに至ったものといわなければならない
と判示しました。