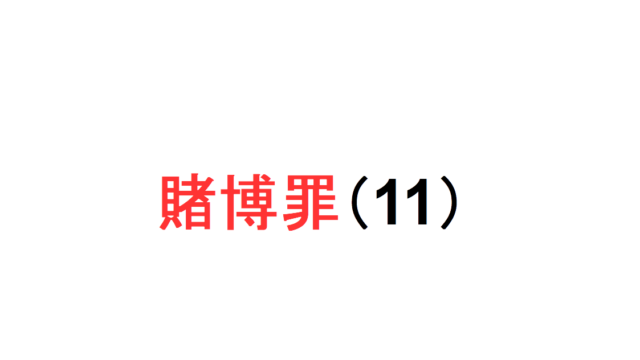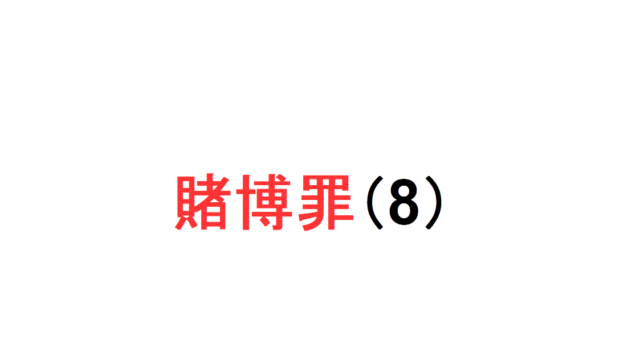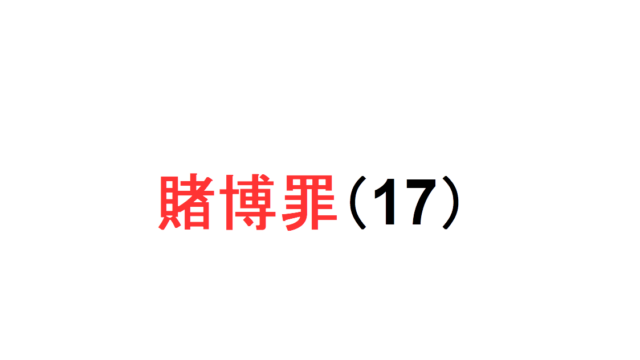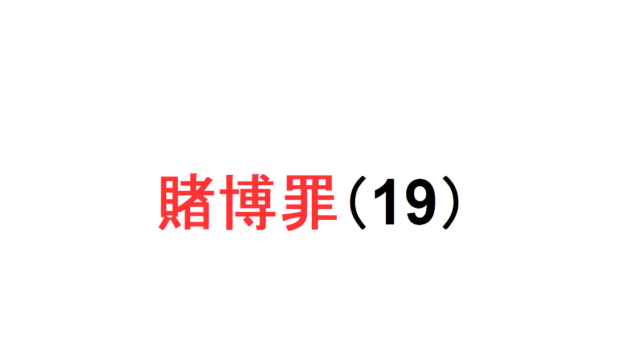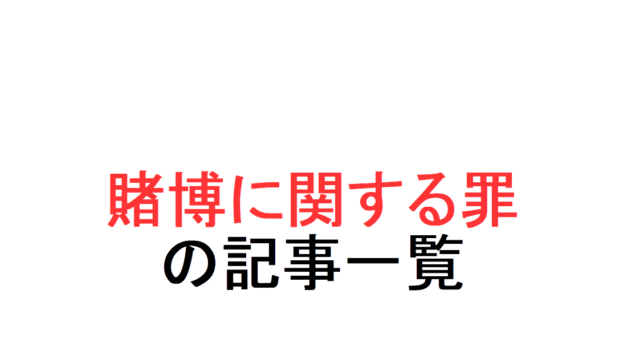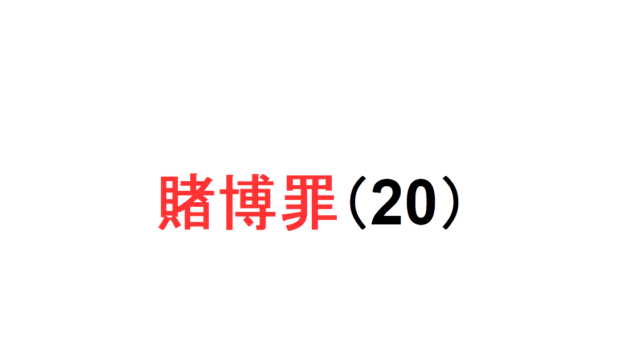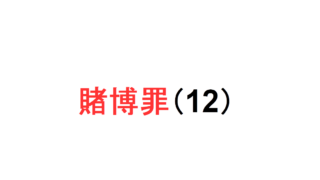賭博罪(13)~「賭博罪の実行の着手時期」を説明
前回の記事の続きです。
賭博罪の実行の着手時期
賭博罪(刑法185条)の実行行為は、
です。
そして、賭博罪の実行の着手時期が何であるかは、個々の賭博の態様ごとに具体的に決せられます。
以下で、
- 花札賭博等の場合
- ゲーム機賭博の場合
に分けて賭博罪の実行の着手時期を説明します。
① 花札賭博等の場合の実行の着手時期
花札賭博のように配付された札により偶然の勝敗を争う形態の賭博については、判例は、
- 札の配付
又は
- 金銭を賭ける行為
があれば実行の着手ありとしています。
大審院判決(大正6年11月8日)
裁判所は、
- 花札の使用による博戯においては、相共に約してその博戯を為す当事者一同が花札の配付を始めたるときは、ここにその偶然の事情により勝敗の運命を決する行為は既に開始せられたるものにして、すなわち賭博行為はその責行の程度に及びあるものといわざるべからず
と判示しました。
大審院判決(大正11年7月4日)
裁判所は、
と判示しました。
大阪高裁判決(昭和24年12月19日)
裁判所は、
- 賭博罪は賭者の間において勝敗を決する方法を協定した上、現に金銭を賭し又は骨牌の配付に着手したときに成立するのであって賭博の結了によって勝敗の決したことは必要ではない
と判示しました。
親を決めるための花札の配付であっても賭博罪の実行の着手ありとした判決です。
裁判所は、
- 金銭を賭け花札を使用してする博戯において、当事者が既に賭銭をその場に出し花札を配付(たとえそれが、親をきめるためであっても)したときは、その博戲は実行の範囲に入ったものであって賭博罪に骸当するものと言わなければならない
と判示しました。
大審院判決(昭和8年4月17日)
花札の配付が開始された以上、全員に配付し終えていなくとも実行の着手が認められるとした判決です。
裁判所は、
- 被告人Xにおいて親となり花札及びメンコを配付したる上、賭銭の額を定むべきことを申し合せ、同人が既に被告人Yに花札及びメンコを配付したるに止まり、未だ被告人Zに配付を終わらざるに先ち事発覚したるため、博戯の勝敗により金銭を得喪したる事実なきはもちろん、未だ賭金額も確定せざりしことを認むるに足れりといえども、判示事実の存する以上は、賭金額の確定前においても該賭博の実行の着手ありたることを認むべく
と判示しました。
大審院判決(大正15年10月19日)
花札等の配付が終了した後、手札が悪いために勝負から離脱したとしても、既に賭博罪が成立しているとした判決です。
裁判所は、
- 当事者が単た花札を手に為したるに過ぎざる場合といえども、またその配付を受けたるある者が花札を検閲し、自己に不利となして数回連続して連続して行わるべき博戯の当事者たることより一時脱退したる場合といえども、右博戯が金銭の得喪を目的と為させるものなる以上は賭博に着手したる者としてその所為を論ずべきものとす
と判示しました。
広島高裁判決(昭和25年8月2日)
裁判所は、
- 苟も賭銭博戯を為すため既に賭金を提出しており、なお花札の配付をも受けた以上は、たとえその都度手札が悪くて1度も現実の勝負に加はらなかったからといってもはや賭博の実行の範囲に入っているものというべく賭博罪の既遂を以て論ずべきものである
と判示しました。
② ゲーム機賭博の場合の実行の着手時期
ゲーム機等を店舗等に設置して行う形態の賭博の場合、ゲーム機を設置し客がいつでも使用できる状態に置いた後は、個々の賭博行為ごとにあらためて営業者の行為があるわけではないことが多く、どの段階で実行の着手を認めるべきかが問題となります。
この点につき、
- 営業者については、遊技機を設置し、客が遊技しようとすればいつでも作動するような状態に機械をセットし、遊技開始の際右状態を保持していることが実行行為であるとする見解
- それでは足りず、客が遊技機を使用するため、店舗経営者らにコインの購入を申し込むとか、遊技機の使用を約したと認められる態度に出たときに実行の着手があるとする見解
があります。
「① 営業者については、遊技機を設置し、客が遊技しようとすればいつでも作動するような状態に機械をセットし、遊技開始の際右状態を保持していることが実行行為であるとする見解」の裁判例として、以下のものがあります。
東京高裁判決(昭和60年3月19日)
裁判所は、
- 営業者が店舗に遊技機を設置し、来店した個々の客をして遊技機を利用させて現金の得喪を争うという本件賭博の特質にかんがみると、賭博の一方当事者である営業者については、店舗を備えて各遊技機を設置し、原判示営業期間を通じ、来店した客が遊技しようとすればいつでも作動するような状態に機械をセットし、遊技開始の際右状態を保持していることが、まさに賭博の実行行為であると解される
- ただし、来店した客が右のような状態にある遊技機に現金を投入し遊技を開始することによって、即時に営業者と客の間に偶然の輸えい(勝敗)に関し財物の得喪を争う関係が成立するのであるから、たとえ営業者がその時点で犯罪場所に居合わせ、当該客と相対することがなくても、営業者の叙上行為が賭博の実行行為として欠けるところはない
と判示しました。
「② それでは足りず、客が遊技機を使用するため、店舗経営者らにコインの購入を申し込むとか、遊技機の使用を約したと認められる態度に出たときに実行の着手があるとする見解」の裁判例として、以下のものがあります。
札幌地裁判決(昭和51年3月17日)
裁判所は、
- 相手方が未だ全く居合わせていない判示各店舗に、右各遊技機を設置したというだけでは、不特定多数の者に対し、右設置者(以下行為者という)が、前示約束の申込み(得喪関係を設定したい)をしたとはいいえても、いまだもって相手方との間に前示関係が設定されたものとは認められないのである
- 店舗の来客などが、右遊技機を使用するため、遊技機を管理している店舗経営者ら(中略)に対し、コインの購入を申込むとか、遊技機の使用を約したと認められる態度に出たとき、ここに行為者らと客との間に、偶然の勝敗に関し、財物の得喪を争う旨の関係が成立し、賭博罪は既遂に達すると解すべきである
と判示しました。