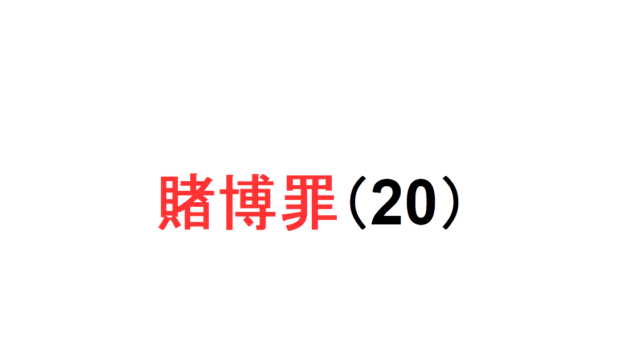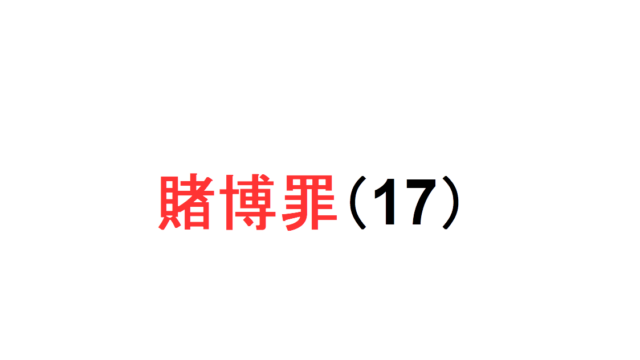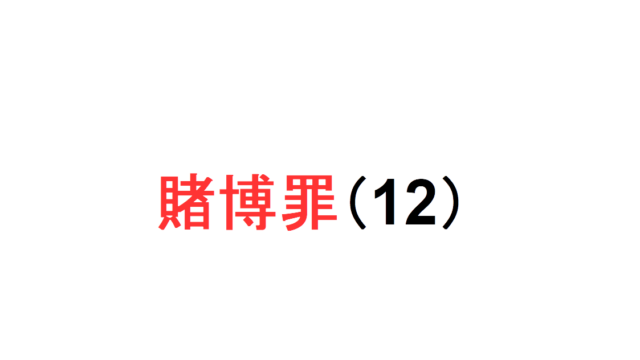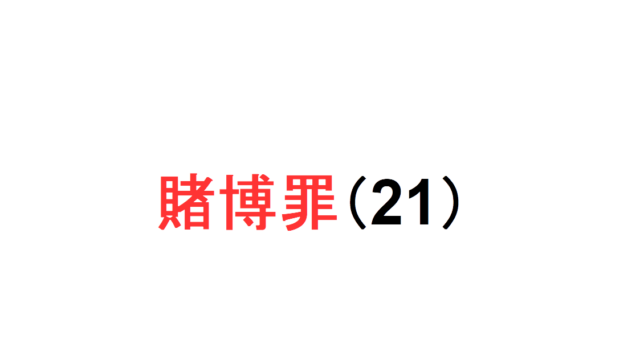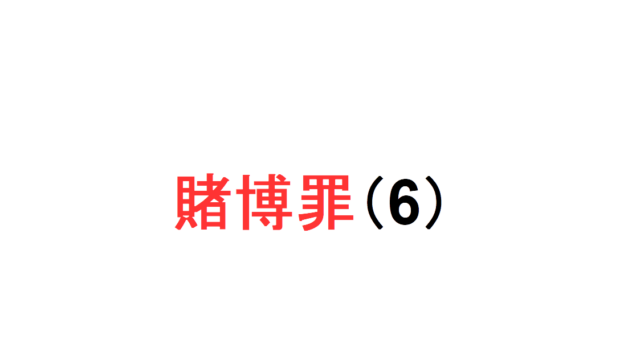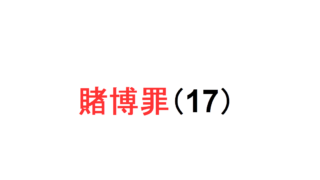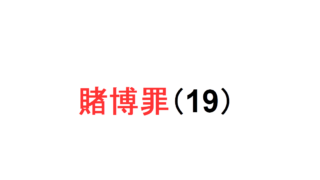賭博罪(18)~「賭博罪と賭場開張図利罪との関係」を説明
前回の記事の続きです。
賭博罪と賭場開張図利罪との関係
1⃣ 賭場開張者が自ら賭客の相手方となり賭博行為を行った場合、賭場開張図利罪(刑法186条2項)とは別個に賭博罪(刑法185条)が成立します。
この場合の賭博罪と賭場開張図利罪の関係につき、判例は併合罪であるとします。
大審院判決(大正3年10月7日)
裁判所は、
- 賭場開張と常習賭博とは別個の犯罪行為なるをもって原判決の認むるがごとく同一期間同一の場所において賭場を開張し、かつ常習として賭博を為したる場合といえども、賭場開張と常習賭博との二罪を構成するものなれば、原判決がこれを併合罪として処断したるは不法にあらず
と判示しました。
大審院判決(大正12年4月6日)
裁判所は、
- 賭博開張罪と賭博罪とは、その性質を異にし、その構成を異にするをもって、前者は後者を包含せず、また連続犯若しくは想像的併合罪(※観念的競合のこと)の開係に立つことなく、各自独立して実質的併合罪に該当するものとす
と判示しました。
東京高裁判決(昭和38年9月5日)
裁判所は、
- 賭場開張図利罪と賭博罪もしくは常習賭博罪とは、各その構成要件を異にする別個独立の犯罪であって、同ー人が賭場を開張して利を図るとともに、その賭場における賭博に加わることも可能であり、この場合には、賭場開張図利罪が成立するほかに、常習性の有無に従い、賭博罪もしくは常習賭博罪が成立するものといわなければならない
と判示しました。
2⃣ 賭博罪と賭場開張図利罪とは観念的競合の関係にはないとした以下の判例・裁判例があります。
大審院判決(明治42年5月7日)
裁判所は、
- 賭博罪と賭博開張罪とは、各その構成要件を異にする別個の犯罪行為にして、しかも同一被告人が同時にこれを実行し得べきものなれば、判文上、一面において被告人が他人を対手として賭博を為したる事実を認定し、他の一面において同一被告人が賭場を開張して利益を図りたる事実を判示するも不法に非ず
- 賭博罪と賭博開張罪とは別個の犯罪行為より成立し、一行為にして二個の罪名に触るる場合(※観念的競合に触れる場合)に該当せず
と判示しました。
大審院判決(明治43年11月8日)
裁判所は、
- 被告がその営業所に賭場を開き、賭博者を誘引し手数料の名義をもって利を得んことを図りたる行為と、その賭場においてAらと賭博を為したる行為との2個ありて、その行為は全く別個独立のものにして1個の行為に非ざれば、原院が刑法第54条第1項前段(※観念的競合の規定)の規定を適用せざるは正当
と判示しました。
大審院判決(大正6年4月7日)
裁判所は、
- 賭場を開張して利を図るとその賭場において博奕を為すとはもとより別個の行為なるをもって、縦し賭場開張の者が自己の開張したる賭場に自ら他人と博奕を為すもこれをもって―行為にして二罪名に触るるものというを得ず(※「観念的競合に当たらない」という意味)
と判示しました。
東京高裁判決(昭和27年4月26日)
裁判所は、
- 刑法第186条第2項の賭場開張罪は、一定の場所に賭場を設け、人をして賭博を為さしめ利益を図ることを構成要件とし、開張者自ら賭博を為すことを要件としないから、同法第185条の賭博罪とは別個独立の犯罪であって、開張者が自らも賭博をしたときは右賭場開張罪とは別個独立の併合罪とし処断すべきものであって、所論のように一個の行為にして数個の罪名に触れる場合と解し得ないところである(※「観念的競合に当たらない」という意味)
と判示しました。
3⃣ 賭博罪と賭場開張図利罪とは手段と結果の関係になく、牽連犯の関係にはないとした以下の判例があります。
大審院判決(明治44年2月23日)
裁判所は、
- 賭博開張の行為と賭博の行為とは、その間に手段結果の関係ありというを得ざるが故に、本件賭博開張罪は賭博罪と共に刑法第54条第1項後段(※牽連犯)により一罪として論ずべきものにあらず
と判示しました。
大審院判決(大正4年1月28日)
裁判所は、
- 空米相場による賭博を為す行為とその賭博につき賭場を開張する行為とは互いに手段又は結果の関係を有するものに非ず
と判示しました。
大審院判決(大正4年3月30日)
裁判所は、
- 自ら賭者となりて賭博を為す方法の下に賭場を開張して利を図りたるときといえども、その賭場開張行為と賭博行為との間には刑法第54条第1項後段にいわゆる手段と結果たる関係を有するものというを得ず
と判示しました。
4⃣ 賭博罪と賭場開張図利罪とは包括一罪の関係にはないとした以下の判例があります。
大審院判決(大正12年3月15日)
裁判所は、
- 賭博開張は、犯人自ら主催者と偽り開設したる賭博場において、他人をして賭博を為させしむるをいうものにして、賭博は、その支配下に行わるるものなれば、賭博開張は賭博の幇助罪となるものに非ずして独立の一罪を成すものとす
と判示しました。
5⃣ 開張行為として不可欠な行為が同時に賭博行為を含んでいる事例(バカラ賭博)について、賭場開張図利罪のみで評価すべしとした裁判例があります
東京高裁判決(昭和52年4月14日)
裁判所は、
- 被告人が、賭客と同じ立場で、両サイドやタイベット(※引き分けにベットすること)に金銭を賭けて勝負を争ったというのではなく、ディーラーの立場で、前示のように両サイド間の賭金の差額を得喪したりタイベットにおける賭金を得喪したりすることを目して賭博行為としているものと解される
- しかし、この両サイド間の賭金の差額負担やタイベットにおける危険負担は、被告人がディーラーとして本件の「バカラ」賭博場を開張したことにともなう必然的なものであって、その自由な意思にまかされたものではない
- それゆえ、被告人によるその負担等が賭博行為といえるかについては問題があるが、この点はしばらくおくとして、そのディーラーとしての負担等は、右に述べたようにディーラーとしての役割に必然的にともなうものであって、本件で賭博開張図利の事実が認められる以上、これにふくめて評価がされるべきであって、別個に(常習)賭博罪として可罰性をもつものではないと解するのが相当である
と判示し、賭場開張図利罪のみが成立するとしました。
大阪高裁判決(平成17年1月20日)
バカラ賭博店が賭客と勝負していたことは、店が寺銭を取得して利益を得るための手段として行われていたもので、賭博開張図利罪に含めて評価され、これとは別個の常習賭博罪は成立しないとした上、店が賭客と勝負して得た勝金を含めて組織犯罪処罰法に基づき犯罪収益として追徴された事例です。
裁判所は、
- 店が客と勝負していたことがあるという事実は、原判決も説示するとおり、それ自体としては、店側において、賭客のバカラ賭博を成立させることによって、店がコミッション(寺銭) を取得して利益を図るための手段としての性格を有していたものに他ならないから、賭博開張図利罪に含めて評価されるべきものであり、賭博開張図利罪とは別個の常習賭博罪を構成するものではないと解され
る
- 本件において、店側が客と勝負していたことがあったこと及び検察官が追徴対象として主張する金額の中に、そのように、店側が客と勝負して得た勝金が含まれていることは事実である
- しかしながら、店が客と勝負していたことそれ自体は、前記説示のとおり、店において、バカラ賭博を成立させることによって、店かコミッション(寺銭)を取得して利益を図るための手段として行われたもので、賭博開張図利罪に含めて評価され、これとは別個の常習賭博罪が成立するものではないと解されるから、そのような手段として行われた行為によって得られた勝金も、賭博開張図利罪によって得たものと評価して差し支えない
- そして、これを実質的にみても、さらなる賭博開張図利の犯罪に再投資され得る性質を持ったものであったと認められるから、このような場合、店が客と勝負して得た勝金についても、賭博開張図利罪によって得た収益に当たり、これを、前記法条に基づき、任意的没収の対象とすることができると解するのが相当である
と判示しました。
6⃣ 賭博罪(勾留状の被疑事実)と賭博開張図利幇助(起訴状の公訴事実)との間に事件の同一性はないとした判例があります。
裁判所は、
- 被告人が、昭和43年3月28日にa公園において賭博をしたとの勾留状記載の事実と、同日同所においてAらがした賭博開張図利を、賭具を貸与して幇助したとの起訴状記載の事実とは併合罪の関係にあるものであるから、事件の同一性を欠くものと解すべきである
- したがって、これを同一性があるとした原判断は、法令の解釈適用を誤ったものというべきである
と判示しました。