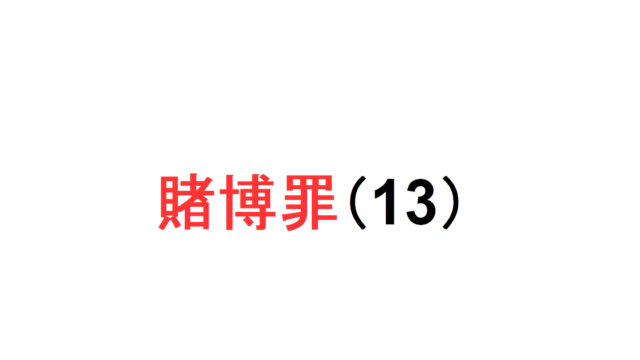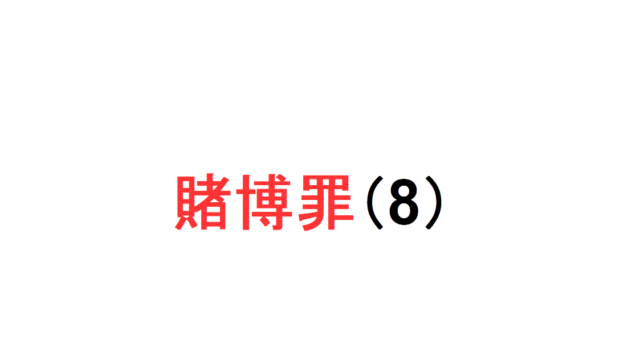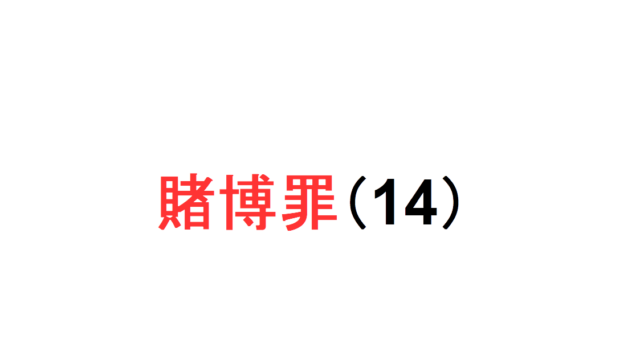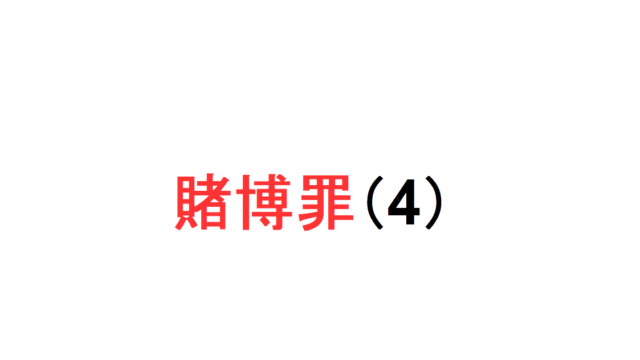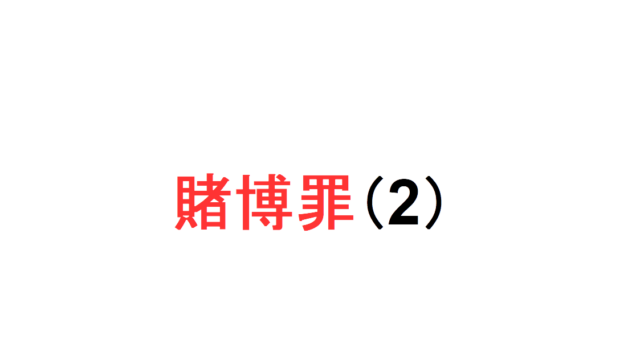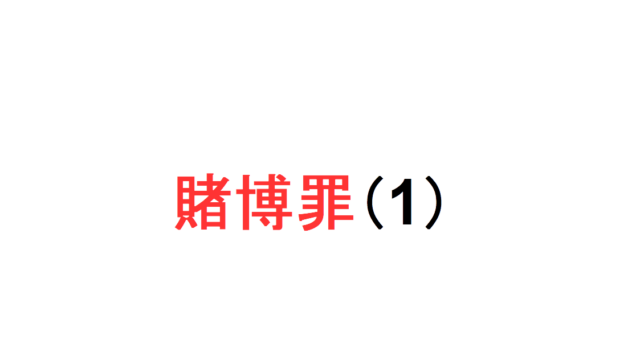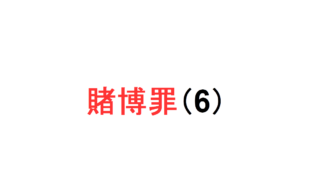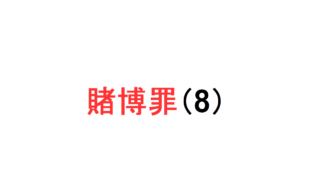賭博罪(7)~「『財物を賭けてその得喪を争うこと』とは?」を説明
前回の記事の続きです。
「財物を賭けてその得喪を争うこと」とは?
賭博罪(刑法185条)の成立要件として、
- 「偶然の勝敗」に関するものであること
- 財物を賭けてその得喪を争うこと
という要件が必要になります。
今回は、②の「財物を賭けてその得喪を争うこと」の意義を説明します。
財物を賭けてその得喪を争うことが必要とされる理由
賭博罪の成立には、財物を賭けその得喪を争うことが必要です。
このことは、平成7年の刑法改正による表記平易化前においては、賭博罪の条文である刑法185条が「偶然の輸贏(勝敗)に関し財物をもって博戯又は賭事を為し」と規定されていたことから明らかでした。
しかし、同改正により、現在は単に「賭博をした者」という規定となりましたが、同改正は本条の内容に変更を加えるものではないので、賭博罪の成立には、依然、財物の得喪を争うことが必要となります。
このように、財物を賭けてその得喪を争うことが必要とされる実質的理由は、単に偶然の勝敗を争うだけの行為は賭博罪の保護法益をなんら害しないためです。
なお、賭博罪の保護法益は、
- 労働による財産の取得という経済社会における道徳律、あるいは、国民一般の健全な経済観念・勤労観念
です(詳しくは賭博罪(1)の記事参照)。
「財物」とは?
賭博罪における「財物」とは、
- 有体物又は管理可能物に限らず、広く財産上の利益であれば足り、債権等を含む
とする見解が通説・判例の立場です。
「財物の得喪を争うこと」とは?
「財物の得喪を争うこと」とは、
勝者が財産を得て、敗者はこれを失うこと
を意味します。
当事者の一方が財物を失うことがない場合は、財物の得喪を争うものとはいえません。
当事者の一方が財物を失うことがない場合に関し、
- 宝くじの販売
- ゲーム機賭博(例えば、胴元が手数料を取って賭博ゲーム機を客に提供し、客が金銭を賭け合う)
が賭博に当たるかが問題となるところ、この点を以下で説明します。
宝くじの販売は賭博とは区別される
富くじの販売は販売者が財物を失うことはなく、この点からも賭博と区別されます。
この点に関する以下の判例があります。
大審院判決(元年10月3日)
裁判所は、
- 富くじは、財物を拠集し抽選により利を僥倖せしむる行為にして、その発売者は如何なる場合といえども危険を負担することなしといえど、これと異なり賭博は財物を賭する行為にして胴元と張方との間に取引の関係を有し、両者いずれも危険の負担に当たるものとす
と判示しました。
大審院判決(大正3年7月28日)
裁判所は、
- 賭博なるものは、偶然の輸贏(勝敗)により財物の得喪を決するの行為にして、その富くじと異なるは、
- (1)賭博に在りては抽選の方法を用いず偶然の輸贏により財物の得喪を決するものなるに、富くじに在しては抽選の方法により損益を決し、
- (2)賭博に在りてはその勝敗の決するまで、ただその財物を提供するに過ぎずして、これが所有権を失うものにあらず、その勝敗の定まりたるとき初めて勝者はその財物を取得し、敗者はこれを喪失するものなるに、富くじに在ありては、その拠出したる財物は直ちに富くじ発売者においてこれを取得すべく、
- (3)賭博に在りては、賭博に干興する胴元と賭博の二者共に危険の負担に任ずるものなるに、富くじに在りては、富くじ発売者は何ら財物を賭することなきをもって、あるいは、富くじ購買予定数に達せざるがため、損失を被ることあるべきも、その賭したる財物を損失する危険一つも存するところなし
- 以上は、これ賭博と富くじとを区別すべき主要なる標準なりとす
と判示しました。
ゲーム機賭博は賭博とされる
ゲーム機賭博(例えば、胴元が手数料を取って賭博ゲーム機を客に提供し、客が金銭を賭け合う)の事案においては、個々の客との関係ではともかく、大数的には店主が損をすることはないのが通例です。
そのような場合でも財物の得喪を争ったものといえるのかが問題となりますが、ゲーム機を設置した店主につき常習賭博罪(刑法186条)の成立を認めるのが定着した判例・裁判例となっています。
この点につき、参考となる以下の判例・裁判例があります。
福岡高裁判決(昭和50年9月16日)
裁判所は、
- もっとも右遊技機の配当率は構造上、69ないし76パーセントに装置されているから、賭博行為が多数回累行される場合には、設置者側が損害をこうむる確率は極めて小さくなる訳であるが、そのために本件所為の賭博性が否定されるものではない
と判示しました。
裁判所は、
- 被告人が(公安委員会の)許可の条件に違反して一人1回10円の制限を越えた遊戯券を発売し、また遊戯券を買受けた客が空気銃の弾を発射する条件を変更し多数の客を一括し任意の3名を代表として発射せしめ、さらに賞品も煙草、菓子の制限を越えて客の要求により遊戯券の購入に充てることのできる券又は現金の給付をもなすに至り、判示の期間これを繰り返したことが認められ、これを挙示の各証拠と照合してみるとその認定に誤りは認められない
- してみれば、被告人が許可条件を全く無視し判示に示されたような遊戯営業行為をするに至っては、被告人の行為は許可によつて一時の娯楽に供する物を賭ける場合に当るという性質を全く失い、単に許可条件に違反したという風俗営業取締法違反の限界を越え、純然たる賭博行為と認められるに至ったと見なければならない
と判示し、常習賭博罪(刑法186条)の成立を認めました。