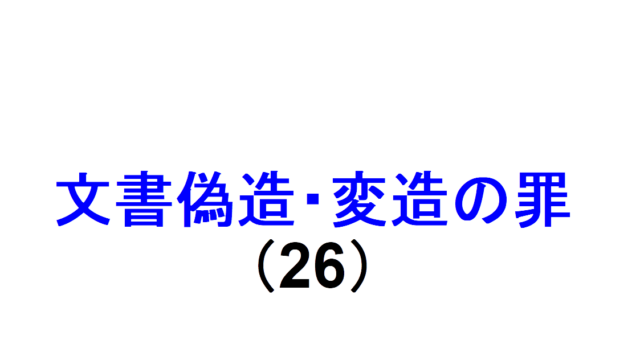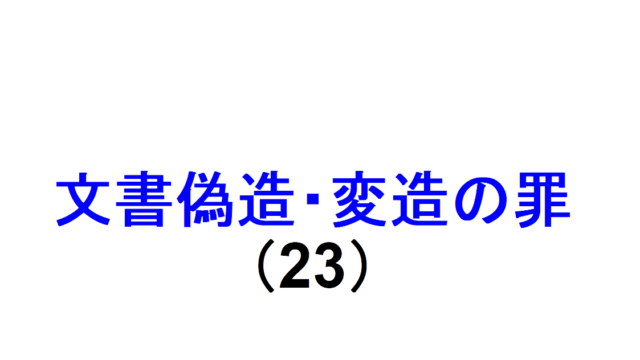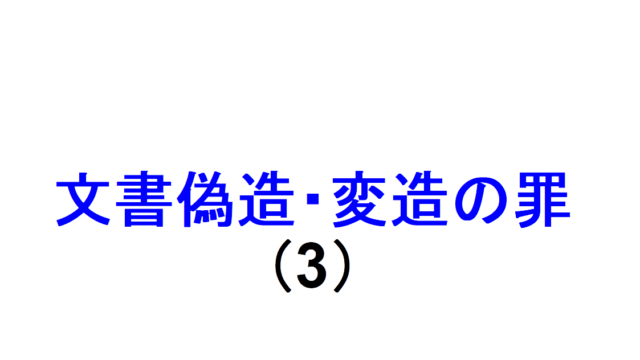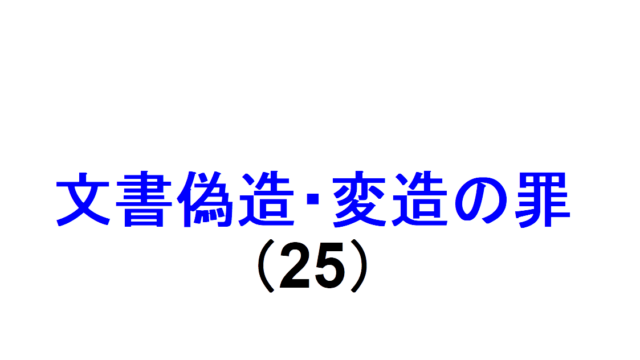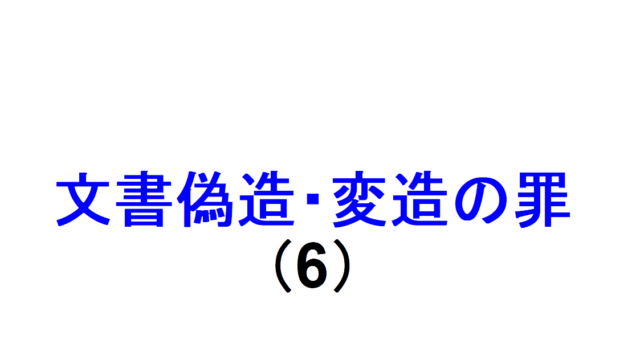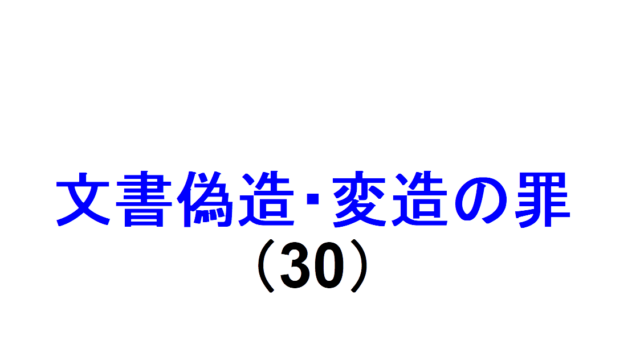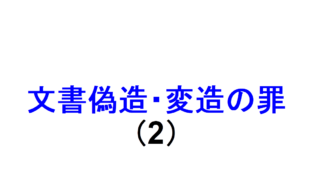文書偽造・変造の罪(1)~「天皇文書・公文書・私文書の区別」を説明
これから複数回にわたり、文書偽造・変造の罪(刑法18章)の共通概念を説明します。
天皇文書・公文書・私文書の区別
刑法は、文書を
- 天皇文書
- 公文書
- 私文書
とに区別し、それぞれの偽造に対して法定刑に差などを設けています。
「天皇文書」は、「詔書その他の文書」であり、広い意味では公文書の一種です。
刑法は、天皇文書の偽造・変造罪の法定刑に無期懲役刑を規定するなど、刑法は通常の公文書と区別して特別の取扱いをしています。
「公文書」とは、判例は、公務所又は公務員がその権限内において職務執行上作成すべき文書を汎称し、その職務執行の方法及び範囲が法令に基づくと内規又は慣例によるとを問わないとしています(大審院判決 昭和12年7月5日)。
「私文書」は、「天皇文書」・「公文書」以外の私人の名義で作成される文書をいいます。
「みなし公務員」が作成すべき文書は公文書偽造罪の対象となりますが(最高裁決定 昭和32年6月27日)、外国の公務所又は公務員が作成すべき文書は、私文書偽造罪の対象となります(最高裁判決 昭和24年4月14日、最高裁決定 昭和32年4月25日)。
このように、「公文書」と「私文書」とが区別される標準は、内容の点ではなく、作成名義の点にあります。
それゆえに、公務所又は公務員の作成すべき文書である限りは、公法関係において作成されたものと、私法関係において作成されたものとを問わず、公文書偽造罪の対象になります。
この点、大審院判決(昭和14年7月26日)は、
- 公務所又は公務員がその職務権限内において作成したる文書は、私法上の契約に関する場合においても公文書なりとす
と判示しました。
また、当該公務所又は公務員には作成権限がなくても、一般人をして公務所または公務員の職務権限内で作成されたと信じるに足る形式・外観を備えている文書も公文書に含まれます(最高裁判決 昭和28年2月20日)。
しかし、
- 公務員が作成した退職届(大審院判決 大正10年9月24日)
- 公務員の肩書を付して政党機関誌に出された広告文(最高裁決定 昭和33年9月16日)
などは、「公務所又は公務員がその権限内において職務執行上作成すべき文書」に該当しないため、公文書ではなく、私文書となります。
刑法が、公文書と私文書を区別し、「公文書」については、
- その偽造をより重く処罰すること
- 虚偽文書の作成も一般的に処罰すること
- 公正証書の原本等につき公務員を介して行う不実記載(刑法157条)も処罰すること
としているのに対し、「私文書」については、
- 偽造の処罰を原則とすること
- 客体も権利義務に関するものと事実証明に関するものに限定した上、虚偽文書の作成はごく一部に限って可罰的としていること
としているのは、私文書よりも公文書の方が信用力において厚いためです(大審院判決 昭和6年3月11日)。
つまり、公務所又は公務員が、職務権限に基づき作成する「公文書」は、その性質上、一応公正とみなされ、公共的信用も高く、その分、偽造された場合の被害の程度も大きくなるものとして扱われています。