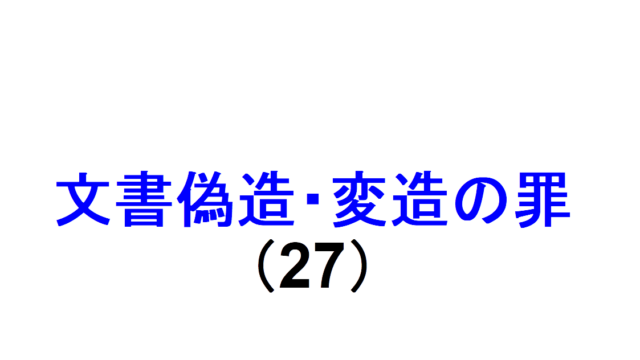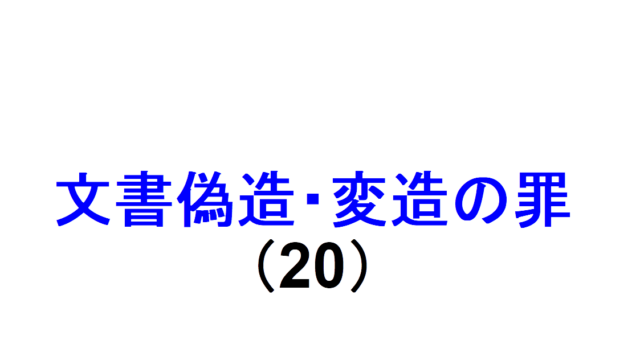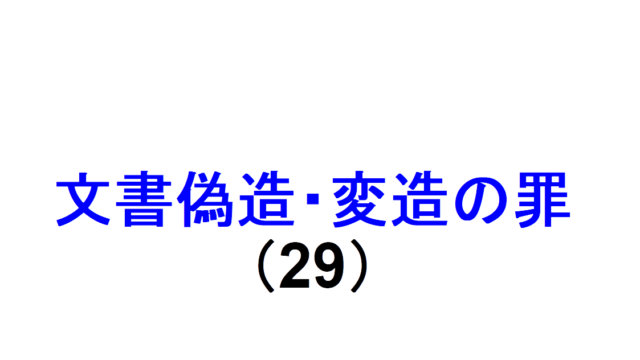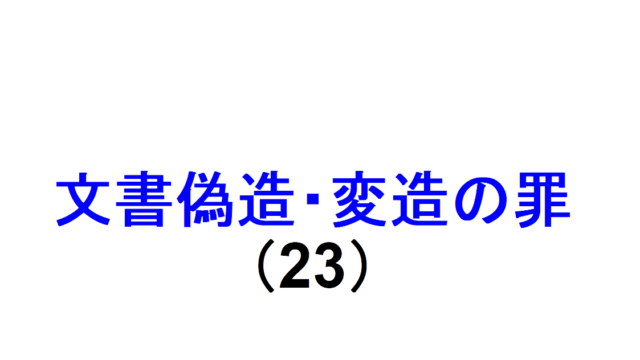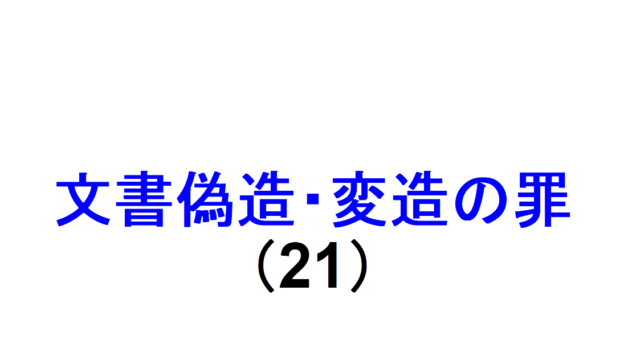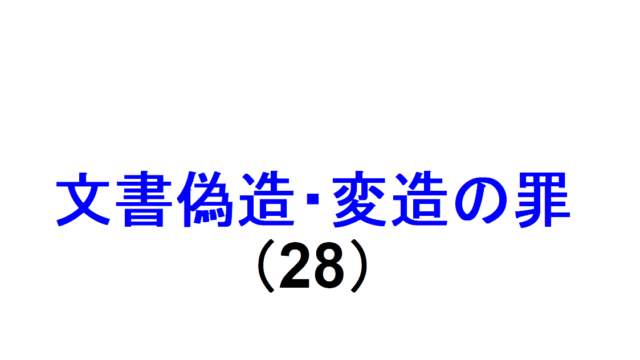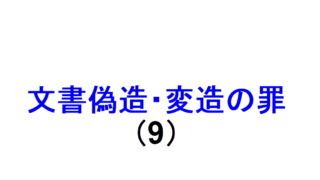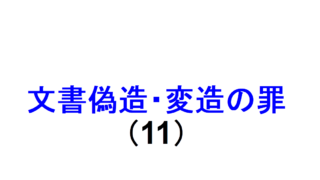文書偽造・変造の罪(10)~偽造の概念②「偽造の方法」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、文書偽造・変造の罪(刑法18章)に共通する概念を説明します。
偽造の方法
文書の偽造の方法に制限はありません。
既存文書の重要部分に改ざんを加える行為は、文書変造罪ではなく、文書偽造罪が成立する
既存文書(完成済みであると、未完成であるとを問わない)に改ざんを加える場合でも、それが本質的部分の重大な変更であり、変更前の文書と全く別個の新たな文書を作成したとみられるときは変造ではなく、偽造となります。
この点、参考となる以下の判例があります。
大審院判決(大正3年11月7日)
裁判所は、
- 既存の正当なる文書中、作成名義若しくはその他重要なる点を変更し為に、そのその変更前の文書と全然別個独立なるものと為すときは、文書の偽造にして変造に非ず
と判示しました。
世帯主A名儀の家庭用米穀通帳に、新たに世帯主B名儀を書き加えた行為について、公文書偽造罪が成立するとした事例です。
裁判所は、
- 家庭用米穀配給通帳は、各世帯毎に交付せられるものであって右通帳における世帯主の氏名の記載はその通帳を特定するためには極めて重要な記載であって、世帯主A名儀の通帳と同B名儀の通帳とは、たとえ通帳自体は同一物が利用せられ、従ってその通帳の作成名儀者は同一であっても、全く別個の通帳と認めざるを得ない
- されば、原判決が前示被告人の所為をもって村長Aの作成にかかる世帯主被告人名儀の通帳を利用して世帯主B名儀の新なる通帳を作成したものと解し、これを公文書偽造罪に問擬(もんぎ)したのは正当であって、右は公文書変造罪にあたるものであると主張する論旨はあやまりである
と判示しました。
裁判所は、
- 外国人登録証明書に貼付してある写真をほしいままに剥ぎとり、他人の写真を貼り代えた場合には、公文書偽造罪が成立する
としました。
偽造に使われた既存文書は真正なものでなくても文書偽造罪が成立する
偽造に使われた既存文書は真正なものであると否とを問いません。
この点、参考となる以下の判例があります。
偽造運転免許証中の記載の一部を改ざんした行為は、公文書偽造罪を構成するとした事例です。
裁判所は、
- 自動車運転免許証に有効期限として表示されている日時の経過後に右免許証の一部をなす交付年月日及び有効期限の各記載を改ざんして、これが有効期間内のものであるかのような外観を作り出した場合には、免許証全体の偽造をもって諭すべきであり、右の場合、従前の免許証が真正なものであるか偽造にかかるものであるかは問うところではない
と判示しました。
偽造部分のある文書を改ざんする行為は、文書偽造罪が成立する
偽造部分のある文書を改ざんする行為も文書偽造罪を構成します。
この点、参考となる以下の判例があります。
一部偽造の箇所のある輸出証明書用紙を素材として、その未完成部分に虚偽の事実を記入した行為について、公文書偽造罪の成立を認めた事例です。
裁判所は、
- 一部偽造の箇所のある輸出証明書用紙を素材として、その未完成部分にさらに虚偽の事実を記入しその偽造を完成したときは、公文書僞造罪を構成する
と判示ました。
公文書の内容に改ざんを加えて、そのコピーを作成した行為について、たとえ当該改ざんが公文書の原本自体になされたのであれば未だ文書の変造の範ちゅうに属するとみられる程度にとどまっているとしても、原本とは別個の文書を作り出すものとして、文書の変造ではなく、偽造であるとした事例です。
裁判所は、
- 行使の目的をもつて、ほしいままに、営林署長の記名押印がある売買契約書の売買代金欄等の記載に改ざんを施すなどしたうえ、これを複写機械で複写する方法により、あたかも真正な右売買契約書を原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を備えるコピーを作成した所為は、その改ざんが原本自体にされたのであれば未だ文書の変造の範ちゅうに属するとみられる程度にとどまっているとしても、刑法155条1項の有印公文書偽造罪に当たる
と判示しました。
文書偽造は、名義人本人を利用した間接正犯によっても行い得る
文書偽造は、名義人本人を利用した間接正犯によっても行い得ます。
間接正犯は、
他人を道具として利用し、他人に犯罪行為をやらせ、犯罪を実現する犯罪
いいます。
例えば、AがBをして、B名義の文書を作成させた場合に、Bがその文書の内容を知らず、又は他の文書と誤信して署名・押印した場合は、文書偽造罪の間接正犯(間接偽造)となります。
この点、参考となる以下の判例・裁判例があります。
東京高裁判決(昭和28年8月3日)
公文書につき、情を知らない公務員に職員を押捺させて同人の作成権限のある公文書(運送契約書)を作成させた事案です。
裁判所は、
- 原判示の運送契約書は、その作成権限ある農林省千葉木炭事務所長Nが兎角書類に盲判を押捺することのあるのに乗じ、Nがその情を知らない間にNをしてこれにその職印を押捺せしめて作成されるに至ったもので、該契約書の内容に相当する運送契約は、この種契約締結権限を有するNの意思に基ずかないものであることが明らかであるから、これが契約書は全く虚偽の内容を記載もた公文書と言わざるを得ない
- 該運送契約書は、Nにおいてその虚偽の内容たるの情を知らずして、その職印を押捺したところに基いて作成されたものである以上、本来その作成権限のない被告人YらにおいてNをして右文書を作成せしめた所為は、行使の目的をもって公務員の印章を使用して公務員の作るべき文書を偽造したものというべきである
と判示しました。
大審院判決(明治44年5月8日)
私文書偽造の事案です。
裁判所は、
- 人を欺罔し、他の文書なりと誤信せしめ、これが内容を了知せしめずして、その署名押捺ある権利義務に関する文書を作成し、これを自己に交付せしめたるときは、文書偽造罪を成立せしめ、別に詐欺罪を構成するものに非ず
- 文書偽造罪における部署は、必ずしも偽造者若しくは情を知らざる第三者においてこれを作成するを要せず
- 署名者をして他の文書なりと誤信せしめ、又はその内容を知悉せしめずしてこれを作成する場合においても文書偽造罪の成立を妨げず
と判示しました。
大審院判決(大正4年10月19日)
私文書偽造の事案です。
裁判官は、
- 文書の内容を偽り、他の事項に関する文書なるがごとく欺き、これに作成者として他人に署名押捺せしめ、これを利用して一定の文書を完成したるときは、たとえその署名者若しくは代筆者が署名中のある文字を誤記したる場合といえども、当該署名者の文書を偽造したるものという得べきものとす
と判示しました。
大審院判決(大正5年5月9日)
私文書偽造の事案です。
裁判所は、
- 署名者をして証書の内容を誤認せしめたる結果、これに署名捺印せしむるにおいては、その欺罔手段は証書偽造の手段にほかならずして、署名者は偽造の機械に使用せられたるものなれば、証書の内容を認識しながら詐欺手段によりてこれを騙取せられたる場合と相異なること論を俟たず
と判示しました。
名義人本人をだまして文書を作成させた場合は、文書偽造罪は成立しせず、詐欺罪が成立する
Aが、Bをだまし、Bに文書の内容が真実であるものと誤信させ、BにB名義の文書を作成させた場合には、文書偽造罪は成立しません。
この点を判示したのが以下の判例です。
大審院判決(昭和2年3月26日)
裁判官は、
- 金銭の授受完了に先立ち作成したる借用証書を、既に受領ありたるものの如く偽り、これを利用して不正の利得を為さんがため、他人をして保証人としてその証書に署名捺印して交付せしめたるときは、証書騙取による詐欺罪を構成す
と判示しました。