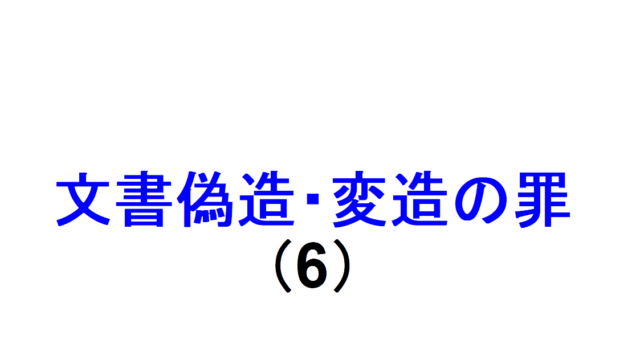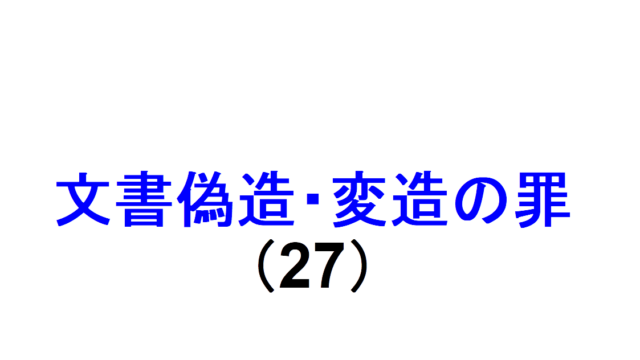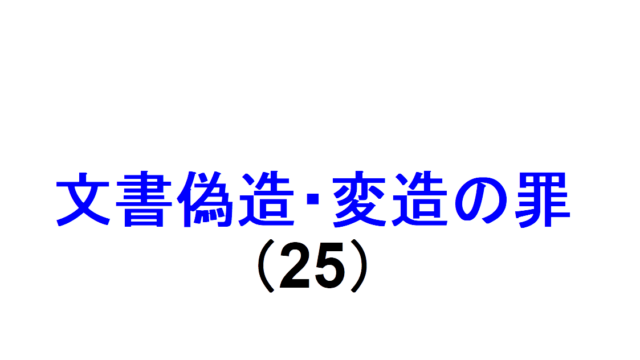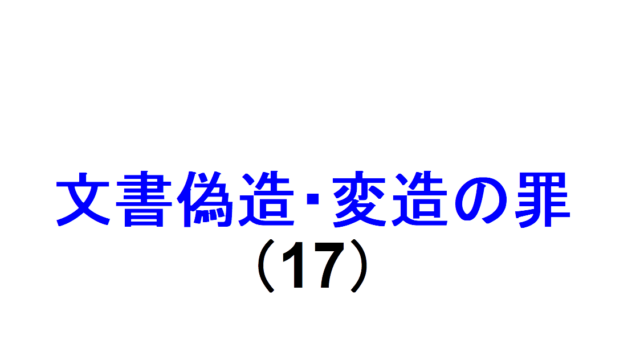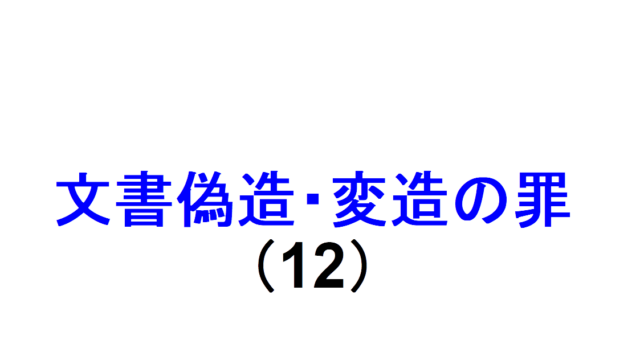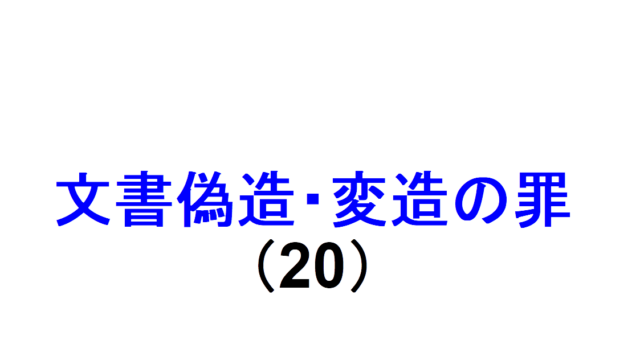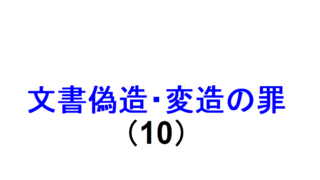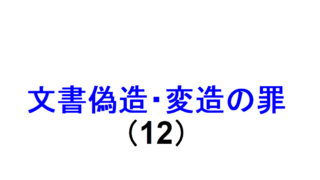文書偽造・変造の罪(11)~偽造の概念③「偽造の程度(偽造文書は、一見して真正文書と誤信されるようなものでなければならない)」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、文書偽造・変造の罪(刑法18章)に共通する概念を説明します。
偽造の程度
偽造文書は、一見して真正文書と誤信されるようなものでなければならない
偽造文書が、文書に対する公共的信用を害すべき危険性を有するためには、当該文書自体が、
一見して真正文書と誤信されるようなもの
でなければならなりません。
そのため、偽造文書は、
一般人をして、作成権限を有する者が、その権限内で作成した真正文書であると誤信させるに足りる程度の形式や外観を備えていること
を要します。
そのようなものである限り、形式や要件に多少の不備があっても、文書偽造罪の成立を妨げません。
この点、参考となる以下の判例があります。
大審院判決(大正15年11月2日)
裁判所は、
と判示しました。
空白部分がっても公文書偽造罪は成立するとした事例です。
裁判官は、
- 行使の目的をもって公文書の形式を偽り、一般人をして公務所若しくは公務員がその権限内において作成したものであると信ぜしめるに足る形式外観を備える文書を作成し、もって公文書の信用を害する危険を生ぜしめたときは、他の記載事項欄が空白であっても公文書偽造罪が成立する
と判示しました。
裁判所は、
- 原判決が「第一院判決挙示の証拠によると、同判示の偽造公文書は、いずれも、当該公文書の信用を害する危険がある程度の形式外観を具えていることが認められる」旨の判示並びに『第一審判決の判示各偽造外食券に「当該地方食糧配給公団名及び交付配給所名のなつ印」の要求されるのは、整理上交付配給所を明らかにするためで、これを欠くからといつて外食券でないという趣旨ではないと解すべき』旨の判示は、いずれも正当であると認められる
と判示しました。
偽造程度が、一見して真正文書と誤信されるようなものと認められるか否かが争点となった事例
偽造程度が、一見して真正文書と誤信されるようなものと認められるか否かが争点となった事例として、以下のものがあります。
大阪地裁判決(平成8年7月8日)
金融会社の無人店舗に設置された自動契約機を悪用し、他人に成り済まして融資金入出用カードを詐取しようと企て、自己の運転免許証の上に他人の運転免許証の写しから、その氏名、生年月日欄等を切り取って該当箇所に置き、氏名欄の氏の部分に更に別の他人の氏の記載のある紙片を置いて、その上からメンディングテープを貼り付けて固定するなどしたものを、融資申込みの際の身分証明書として、金融会社の自動契約機のイメージスキャナで読み取らせ、これを同社係員の前に設置されたディスプレーに表示させた行為につき、有印公文書偽造・行使罪の成立を認めました。
裁判官は、
- 直接手に取って見れば容易に不正な加工を見破られる余地もあるが、電子機器を通しての提示・使用も含め、運転免許証については、様々な行使の形態が考えられ、一応形式は整っていて真上から見る限りでは、表面の切り貼り等も必ずしもすぐ気付くとはいえないので、一般人をして真正に作成された文書であると誤信させるに足りる程度である
としました。
札幌高裁判決(平成17年5月17日)
無人の自動契約機のスキャナーを通して端末画面に表示させようと考え、窃取した他人名義の自衛官診療証を白黒コピーし、同コピーの生年月日欄の「年」の上に修正テープを貼って、その上にスタンプを使って数字を記入する方法により自衛官診療証と誤信させるような文書を作成するなどした行為につき、一般人がそれだけで改ざんされたものと判断できるようなものでなく、スキャナーを介して提示したという行使態様を併せて考慮すれば一般人から見て、真正に作成された文書であると誤信させるに足りる形式、外観を備えていると認められるとして、有印公文書偽造罪の成立を認めました。
東京高裁判決(平成20年7月18日)
ファクシミリで画像データを送信し、相手方の端末機の画面に表示させて従業員に閲覧させようと考え、国民健康保険被保険者証(本件保険証)のA4判の白黒コピー3枚を作成し、その1枚の被保険者証の生年月日、住所欄等に、他の2枚から切り抜いた数字を貼り付けたもの(本件改ざん物)を、保険証の大きさに切り取ることなく、A4判のサイズのままファクシミリで送信した行為につき、裁判官は、
- 本件改ざん物の色合いや大き奄等の客観的形状からみて、電子機器を介するのではなく肉眼等で観察する限り、本件保険証の原本であると一般人が認識することは通常考え難いから、これを作出したことをもって保険証の偽造を遂げたとみることはできない
としつつも、
- 国民健康保険被保険者証のコピーは、身分確認の一手段として、原本と同様の社会的機能と信用性を有しているものと認められ、本件改ざん物は、これを直接手に取るなどして見分すれば紙片を貼り付けた状態のままの部分があることから、改ざんが認知される可能性はあるものの、国民健康保険被保険者証のコピーの提示・使用の形態にも様々な態様が考えられ、相手に渡すことなく示すにとどまる場合もあることを想起すれば、本件改ざん物は、本件保険証のコビーそのものではないが、一般人をして本件保険証の真正なコピーであると誤認させるに足りる程度の形式・外観を備えた文書と認められ、保険証の写しの偽造罪が成立する
としました。
東京地裁判決(平成22年9月6日)
公安委員会から交付を受けていたビニール製ケース入り駐車禁止除外指定車標章の有効期限欄や発行日欄の数字記載部分に、元の記載と異なる数字が印字された紙片を置いて密着させた上、ビニール製ケースとの間に挟み込むようにして同紙片を固定した行為について、公文書偽造罪の成立を認めました。
偽造された文書が、一般人をして、公務所又は公務員の職務権限内において作成したものと信じさせるに足りる形式・外観を備えている以上、名義人である公務所又は公務員にその権限がない場合でも、公文書偽造罪が成立する
偽造された文書が、一般人をして、公務所又は公務員の職務権限内において作成したものと信じさせるに足りる形式・外観を備えている以上、名義人である公務所又は公務員にその権限がない場合でも、公文書偽造罪を構成します。
この点、参考となる以下の判例があります。
大審院判決(昭和11年9月11日)
裁判所は、
- 市学務課長の作成作成名義を冒用し、青年学校服代金等の支払承諾書を作成したときは、同課長に係る文書を作成する権限なしといえども、公文書偽造罪は成立す
と判示しました。
作成権限がない大分県議会事務局名義の工事委託書について、
- 偽造公文書が一般人をして公務所または公務員の職務権限内において作成せられたものと信ぜしめるに足る形式外観を具えている以上は、その作成名義者たる公務所または公務員にその権限がない場合においても、刑法155条の偽造公文書というを妨げないものである
と判示しました。