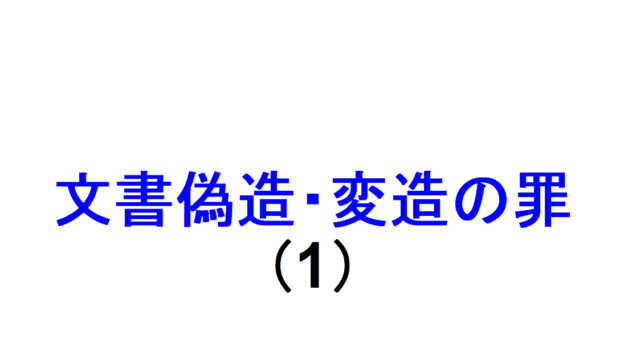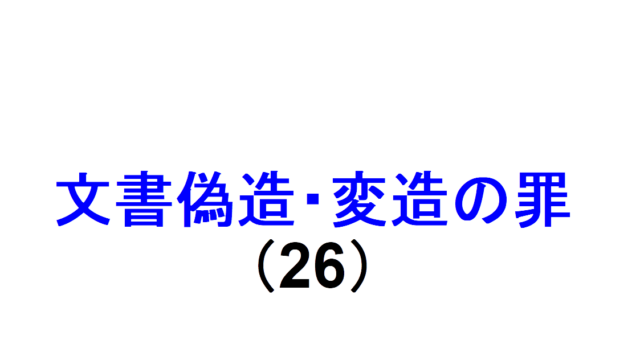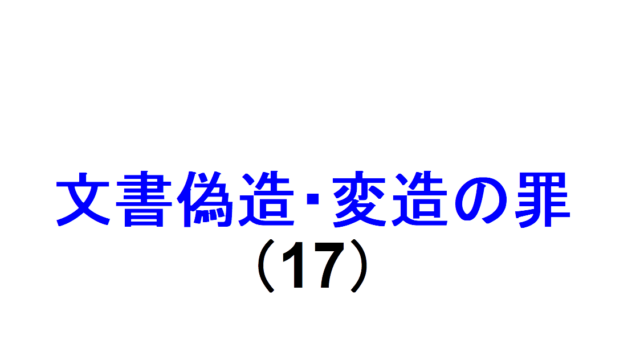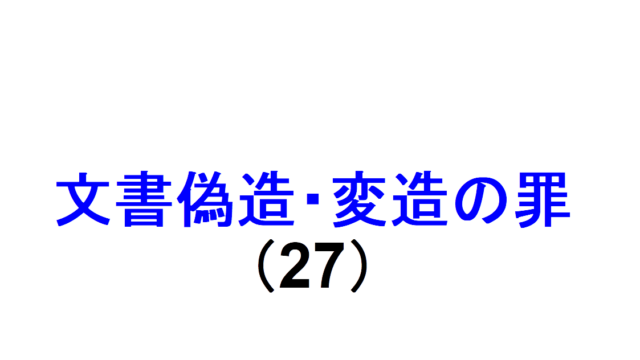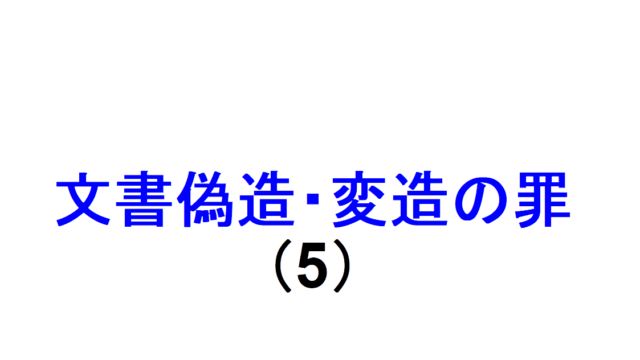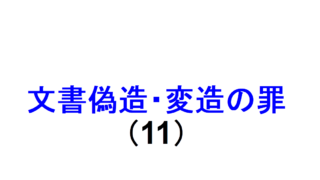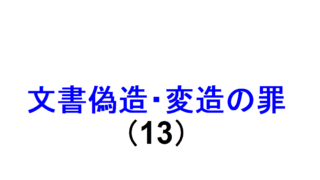文書偽造・変造の罪(12)~偽造の概念④「偽造罪の既遂時期」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、文書偽造・変造の罪(刑法18章)に共通する概念を説明します。
偽造罪の既遂時期
偽造された文書が、一般人をして真正文書と誤信させ得る程度にいたれば、文書偽造罪は既遂に達します。
文書偽造罪の既遂を認めるに当たり、実害が発生することは要しません。
この点を判示したのが以下の判例です。
大審院判決(昭和9年2月8日)
裁判所は、
と判示しました。
裁判官は、
- 上田市公安委員会の補助機関として、法定の要件を備えた者に対する運転免許証の作成交付の事務を担当していた上田市警察署長の事務補助者として運転免許証の作成交付の事務を担当していた警察官(巡査)が、法定の要件を備えていない無資格者に対する自動車運転免許証をほしいままに作成するときは、公文書偽造罪を構成する
と判示しました。