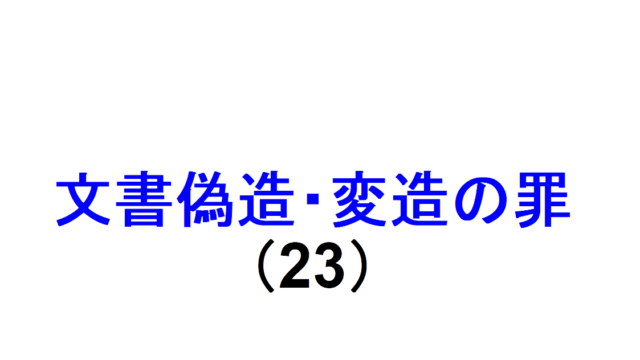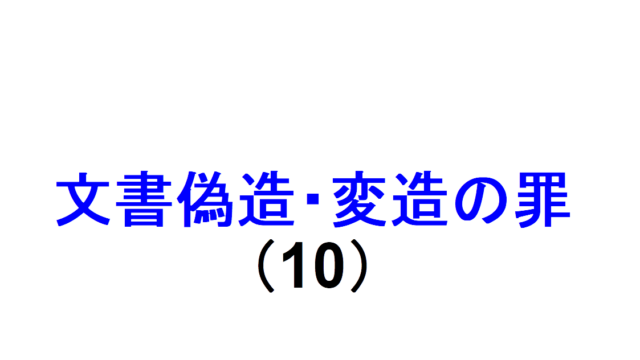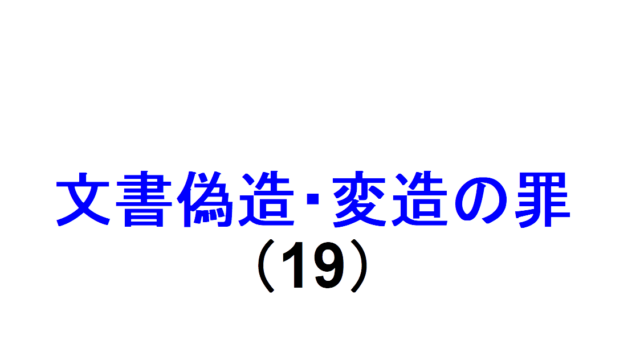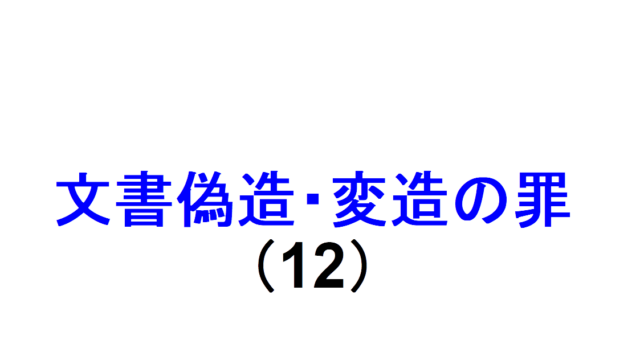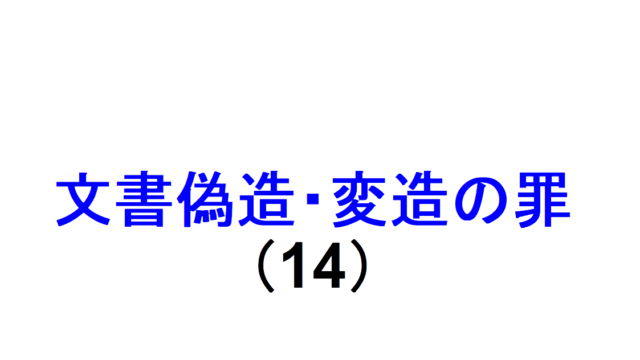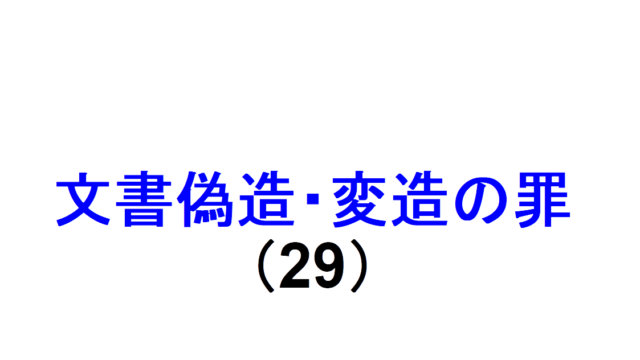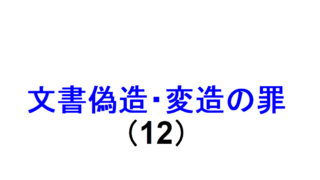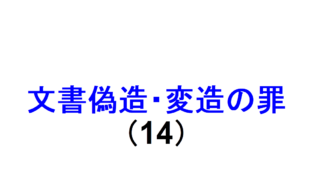文書偽造・変造の罪(13)~偽造の概念⑤「『文書の名義人』と『文書の作成者』は区別される」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、文書偽造・変造の罪(刑法18章)に共通する概念を説明します。
「文書の名義人」と「文書の作成者」は区別される
文書偽造罪の客体である文書には、文書の名義人(作成名義人)が必要ですが、
- 文書の名義人
と
- 文書の作成者
とは区別されます。
「文書の名義人」は、文書の記載内容から理解され、文書の意識内容の主体となる者です。
「文書の作成者」は、文書の内容を表示した者を指します。
そして、文書の性質として、「文書の名義人」と「文書の作成者」が一致しているものを
- 真正文書
といい、一致していないものを
- 不真正文書
又は
- 偽造文書
といいます。
また、真正文書のうち内容が真実に反しているものを
- 虚偽文書
といいます。
特に、私文書に関しては、虚偽文書の作成は原則として処罰されないので、「文書の名義人」と「文書の作成者」が一致するかどうかは、重要な問題となります。
「文書の作成者」を定める基準
「文書の作成者」を誰と解するかに関しては、基本的に、
- 物理的な作成行為と捉える「事実説」
と
- 文書の作成が自らの意思に基づいていることとする「観念説」
とが対立しています。
「事実説」が、現実に文書を記載した者を作成者と解するのに対し、「観念説」は、文書の記載をさせた意思の主体を作成者と解します。
両説の相違は、例えば、Aの承諾を得たB又はAの代理権を有するBが、A名義で作成した文書を「真正文書」と解するか、「不真正文書」と解するかに現われます。
「観念説」によれば、このような文書は、承諾や代理権を与えたAが作成者であり、作成者と名義人が一致するから真正文書とされるのに対し、「事実説」によれば、現実に文書を記載したBが作成者であり、作成者と名義人が一致しないから「不真正文書」とされます。
ただし、「事実説」からも、Bに対する承諾又は代理権の付与があるから、違法性は阻却され、その法的効果は承諾や代理権を与えたAに及ぶことになります。
事実説と観念説では、観念説が有力説である
「事実説」は、判断基準が形式的かつ一義的であり、生活関係が単純な社会においては有用でしたが、生活関係が極めて複雑化し、人的交渉の範囲が大規模になっている現代社会にあっては、形式的にすぎて適用し得ません。
例えば、ある者が、秘書や印刷工をして原稿どおりにタイプさせた文書は、事実説からは、秘書や印刷工を作成者とみることになりますが、それでは不適当です。
そもそも、現代社会では、名義人の名称や商号等が機械的に複製され、他人によって作られた文書に基づき、契約その他の事務処理が迅速かつ大量に行われているのであり、自筆による文書が使われることは少ないです。
そこでは、名称や商号等を記載したり印刷したりする行為自体に特別の意味があるわけではなく、その名称や商号等が文書に表示されていることに重要な意味があるのであって、このことを看過する点で、事実説は相当でなく、観念説によらざるを得ないとされます。