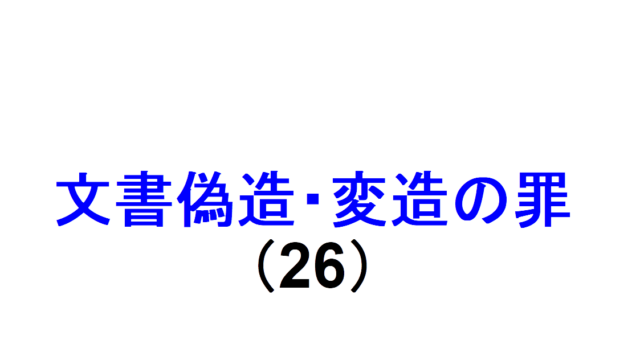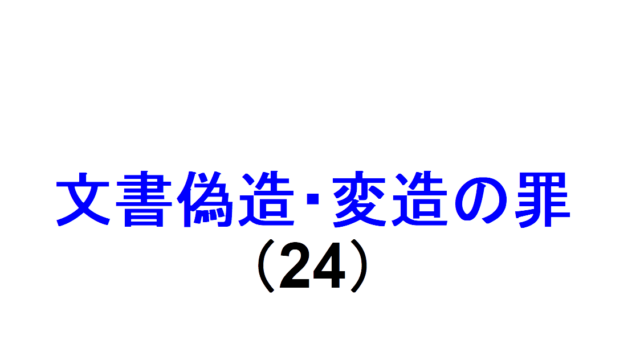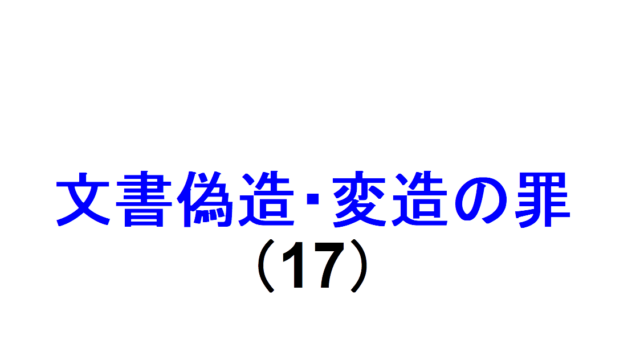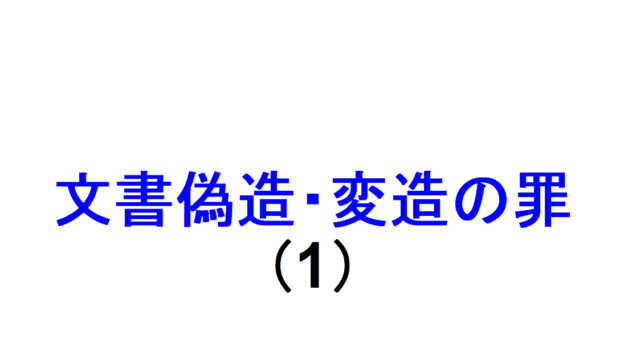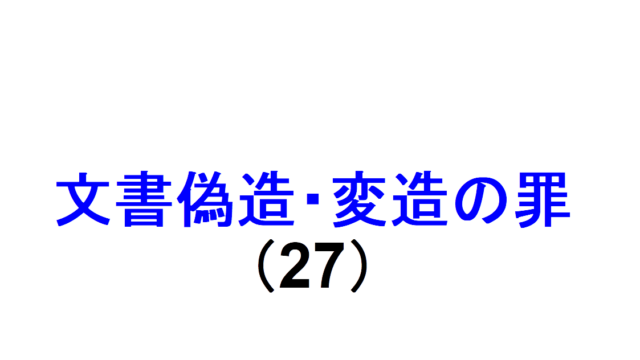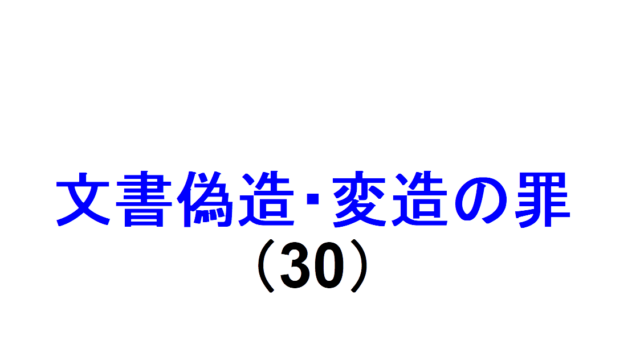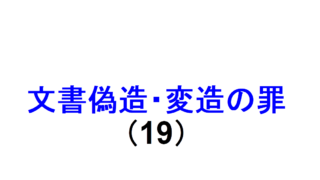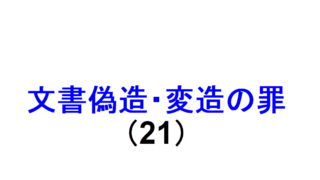文書偽造・変造の罪(20)~行使の概念①「偽造・変造文書の『行使』とは?」「偽造・変造・虚偽文書行使罪を認めるに当たり、実害発生は不要である」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、文書偽造・変造の罪(刑法18章)に共通する概念を説明します。
偽造・変造・虚偽文書の「行使」とは?
偽造・変造文書の「行使」とは、
偽造・変造に係る文書を真正な文書として使用すること
をいいます。
虚偽文書についても同様であり、内容虚偽の文書であるにもかかわらず、これを内容の真実な文書として使用することは「行使」となります。
行使罪は、
文書の真正に対する公共の信用が侵害されることを防止しようとするもの
です。
上記のように偽造・変造文書を真正文書として使用することは、その真正に対する公共的信用を害する危険のある行為であると捉えられます。
この点に関する以下の判例があります。
大審院判決(明治44年3月24日)
裁判所は、
- 偽造の銀行預金通帳を真正のものとして預け、人に交付したる以上は、真正の文書に対する公の信用を害する危険を生じたることもちろんなれば、その所為は、偽造文書行使の既遂犯を構成するものとす
と判示しました。
大審院判決(大正6年4月12日)
裁判所は、
- 偽造若しくは変造文書行使罪は、偽造若しくは変造に係る文書を真正のものとして他人に呈示するによりて成立するものにして、文書の内容の旨趣を主張してその作成名義人に対し、これを行使すると否とは犯罪の成立に影響なきものとす
と判示しました。
使用の意義
上記のとおり、偽造・変造・虚偽文書の「行使」とは、
偽造・変造・虚偽に係る文書を真正な文書として使用すること
をいいます。
ここでいう「使用」したといえるために、
文書を真正に成立したものとして他人に交付、提示等して、その閲覧に供し、その内容を認識させ又はこれを認識し得る状態に置くこと
を要します。
上記の「使用した」といえる状態になって、偽造・変造文書行使罪にいう「行使」に当たります。
参考となる以下の判例があります。
裁判所は、
- 自動車を運転する際に偽造に係る運転免許証を携帯しているにとどまる場合には、いまだこれを他人の閲覧に供しその内容を認識し得る状態に置いたものというには足りず、偽造公文書行使罪に当たらない
旨判示しました。
したがって、偽造文書の内容、形式を口頭又は文書をもって他人に告知するだけでは、いまだ行使には当たりません。
この点を判示したのが以下の判例です。
大審院判決(明治43年8月9日)
裁判所は、
- 偽造文書の行使は、その文書の原本を真正に作成せられたるものとして他人の閲覧に供するにより成立す
- 従って、該文書謄本を他人に示し、若しくはその内容形式を口頭又は文書により他人に告知するのみにては未だ偽造文書を行使したるものというを得ず
と判示しました。
行使の客体としての偽造・変造・虚偽文書
行使の客体となる文書は、
偽造・変造され、あるいは虚偽記載がされた文書
であれば足ります。
必ずしも行使の犯人自らが偽造・変造をした文書であることを要せず、他人が偽造・変造をした文書について、これを真正なものとして使用すれば行使罪が成立し得ます。
この点につき、参考となる以下の判例があります。
大審院判決(明治41年12月21日)
裁判所は、
- 刑法第159条第1項は、他人の署名又は偽造したる他人の印章を使用して文書を偽造して未だ行使せざる場合を処罰し、また、同法第161条第1項は、他人の偽造したる文書を犯人が行使したる場合を処罰するのみならず、犯人が自ら偽装したる場合をも処罰するものなることは、その条文に徴して判然たり
と判示しました。
また、偽造・変造が犯罪行為によるものである場合に必ずしも限定されません。
例えば、他人が偽造・変造をした文書について、たとえその他人が偽造・変造の際に行使の目的(故意とは別途に必要とされる主観的要件である)を有しておらず、その意味でその者につき偽造罪が成立しない場合であったとしても、その文書が客観的に見て偽造文書である以上は、行使の客体となり得えます。
この点に関する以下の判例があります。
大審院判決(明治45年4月9日)
裁判所は、
- 刑法第161条第1項は、偽造・変造の文書を行使したる者を罰するの旨趣にして、その偽造・変造の行為が犯罪行為たると否とはこれを問う要なし
と判示しました。
偽造・変造・虚偽文書に該当しないものを使用したとしても、行使罪は成立しない
一方で、偽造・変造文書や虚偽文書に該当しないものを使用したとしても、行使罪は成立せず、こうした文書は行使の客体には当たりません。
この点、以下の判例があります。
非公務員である被告人が、日本において兵役に服したことがない旨及び選挙に投票したことがない旨それぞれ虚偽の内容を記載した証明願を村役場係員に提出するなどして、村長名義の虚偽内容の証明書を作成させた事案です。
裁判所は、
- 公務員でない者が虚偽の公文書偽造の間接正犯であるときは刑法157条(公正証書原本不実記載罪)の場合のほかこれを処罰しない趣旨と解するのが相当であり、同証明書が刑法157条の権利義務に関する公正証書の原本又は免状、鑑札若しくは旅券のいずれにも当たらないことはいうまでもなく、虚偽の公文書とはいえないから、たとえ被告人が米国領事館係員に対し、同証明書をあたかも真実の内容を記載したものであるように装い提出行使したとしても虚偽公文書行使罪に当たるとはいえない
としました。
偽造・変造・虚偽文書を偽造・変造文書として使用する場合は「行使」に該当しない
行使とは、偽造・変造・虚偽文書を真正な文書として使用することをいうので、偽造・変造文書を偽造・変造文書として使用したり、あるいは、虚偽文書を虚偽文書として使用したりすることは行使に該当するものではありません。
例えば、民事訴訟の場において、偽造文書を真正文書として提出するのであれば、行使に該当することになりますが、そうではなく、あくまである文書が偽造されたものであることを明らかにする趣旨で当該偽造文書を提出するなどといったことは通常よく行われることであり、これが犯罪に該当しないことは明らかです。
偽造文書を真正な文書としてではなく、偽造文書として行使した裁判例として、以下のものあります。
山口地裁判決(昭和34年1月19日)
かねて被告人が偽造した町長名義の領収書の回収を町長から求められたことを受けて、当該偽造領収書に相違ないものとして提出する意図から別途領収書を偽造してこれを町長に提出したという事案です。
裁判所は、
- 作成名義の真正でない文書をそのとおり作成名義を偽ったものとして使用する以上、たとえ文書の同一性を偽り作成名義の同一な他文書として使用するとしても偽造文書行使罪の要件たる行使に該当しない
としました。
偽造・変造・虚偽文書行使罪を認めるに当たり、実害発生は不要である
偽造・変造・虚偽文書の行使罪は、文書の真正に対する公共の信用が具体的に侵害されることを防止しようとするものです。
なので、文書を真正に成立したものとして他人に交付、提示等して、その閲覧に供し、その内容を認識させ又はこれを認識し得る状態に置けば行使に該当するのであって、そうした行使の結果、現実に実害を生じ又は実害を生ずるおそれがあることなどは特に要件とされておらず、不要といえます。
この点を判示した以下の判例があります。
大審院判決(大正3年9月22日)
裁判所は、
- 行使の目的をもって文書を偽造し又は偽造文書を行使したる以上は、直ちに文書偽造罪又は偽造文書行使罪を構成すべく、これによりて現実に実害を生じ、又は生ずるおそれあることを必要とせず
と判示しました。