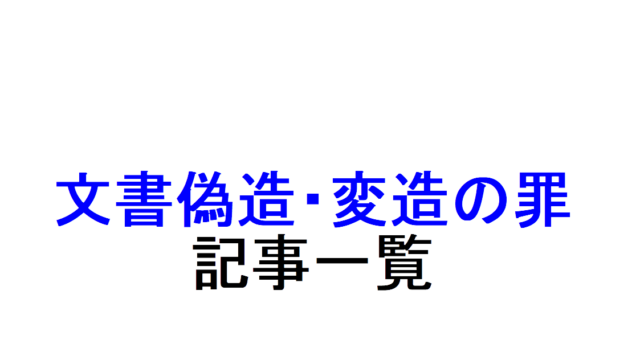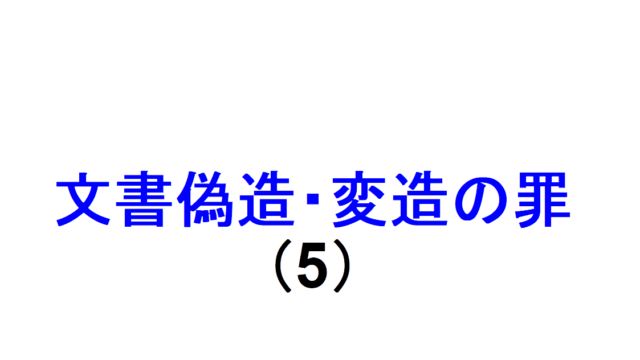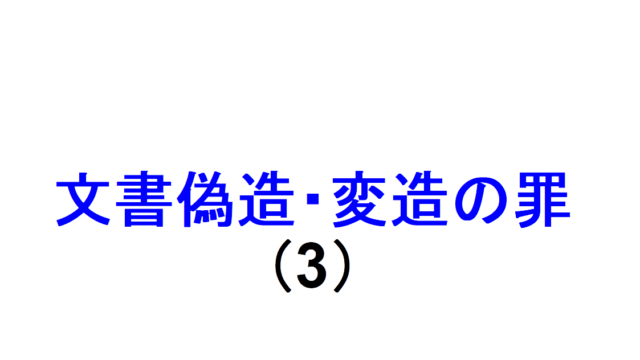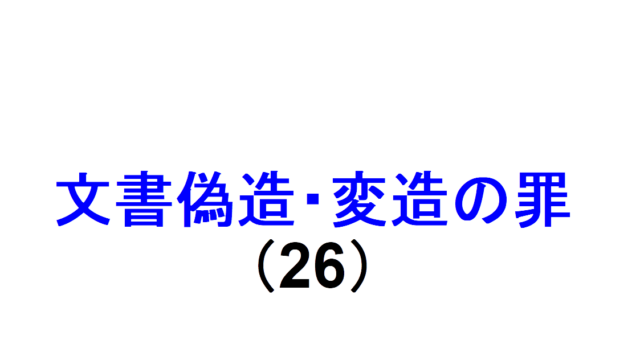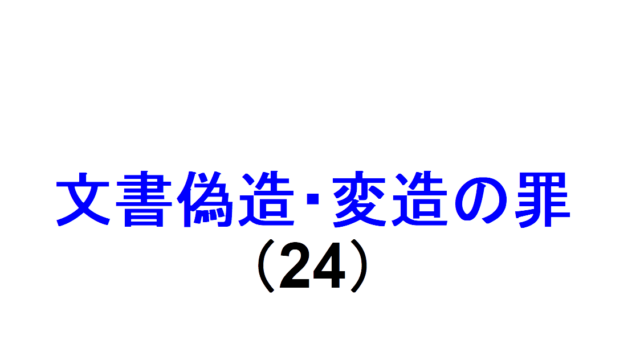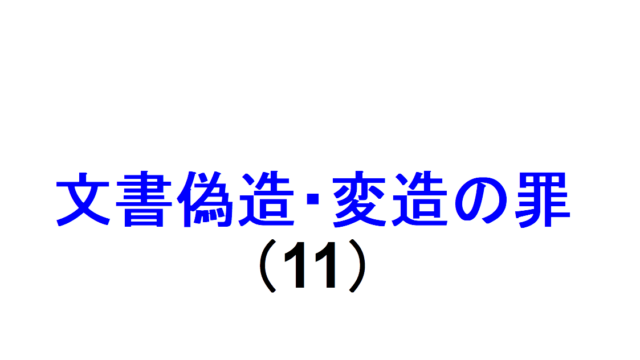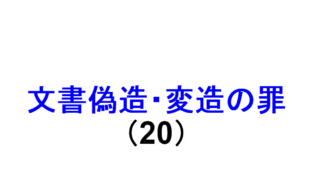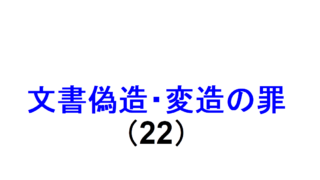文書偽造・変造の罪(21)~行使の概念②「文書偽造・偽造罪の成立を認めるに当たり、犯人が『文書の内容が真実である』との主張をしている必要はない」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、文書偽造・変造の罪(刑法18章)に共通する概念を説明します。
文書偽造・偽造罪の成立を認めるに当たり、犯人が「文書の内容が真実である」との主張をしている必要はない
文書偽造・偽造罪の成立を認めるに当たり、作成名義人との関係において、「文書の内容が真実である」という趣旨を主張した上で交付をする必要があるかどうかについて、判例は、これを不要とする立場をとっています。
大審院判決(大正6年4月12日)
他人所有の金銭を自己名義で第三者に貸し付ける周旋をしていた被告人が、10円を第三者に貸し付けるとともに5円を妻に貸し付けておきながら、15円全部を第三者に貸し付けた旨金主に説明するため、第三者が作成した10円の借用証書(被告人宛て)を15円の借用証書に変造した上、これを貸付けの証明書類として金主に交付したという事案です。
裁判所は、文書を真正の文書として提示した以上は、文書の信用を害し又は害するおそれがあることを理由とし、
- 行使罪は偽変造に係る文書を真正のものとして他人に呈示することによって成立し、文書の内容の趣旨を主張して作成名義人に対しこれを行使すると否とは犯罪の成立に何らの影響はなく、変造文書行使罪が成立する
としました。
大審院判決(大正3年11月18日)
偽造した借用証書を真正なものとして確定日付を得るため公証人に提出した事案です。
裁判所は、
- 偽造文書の行使は、必ずしも文書の内容に従いその証拠力を対抗する場合にのみ成立するものではなく、いやしくも偽造文書を真正な文書としてある目的のため他人に提示する以上は、文書の信用を害する点において、書面記載の内容によって使用したのと別に異なるところがない
旨判示して、偽造私文書行使罪の成立を認めました。