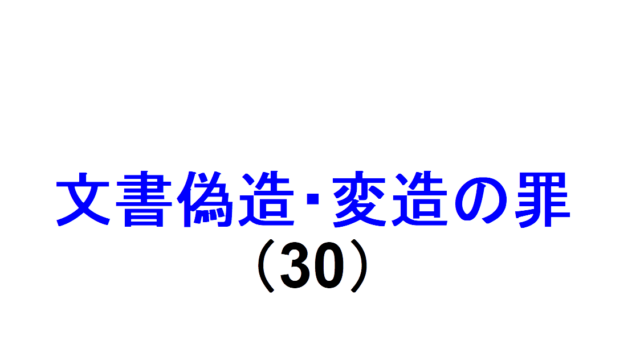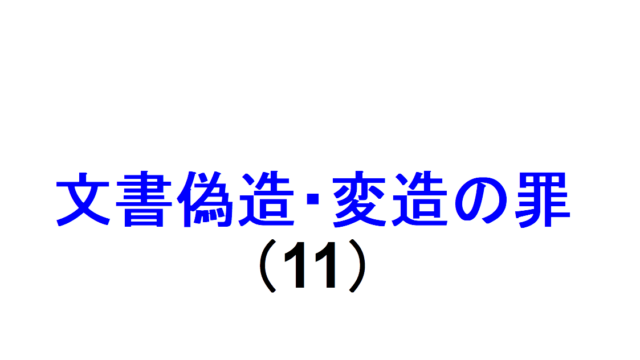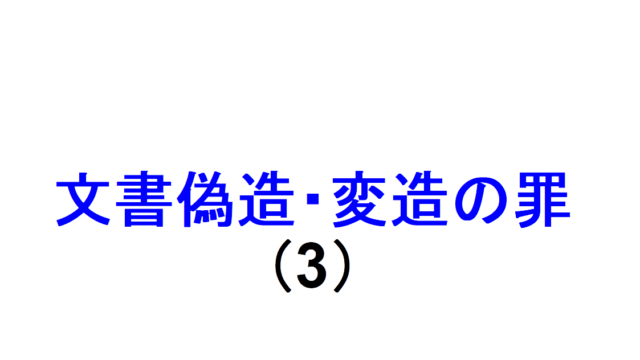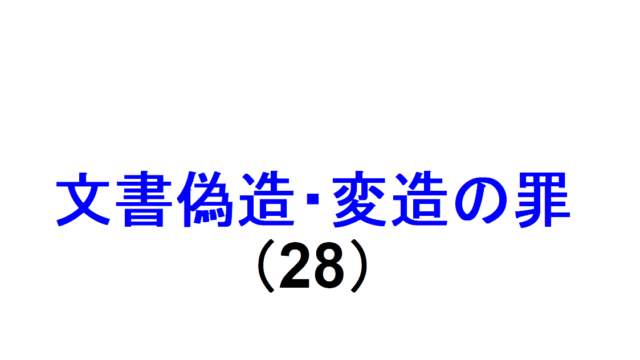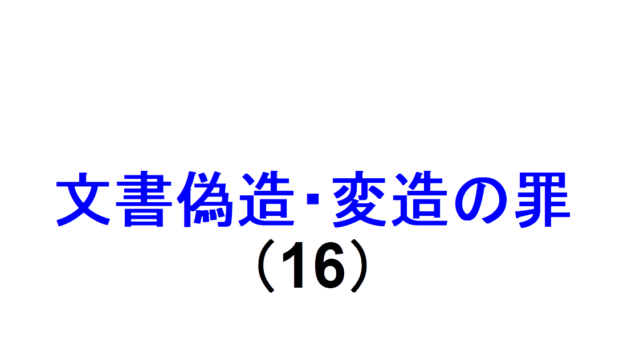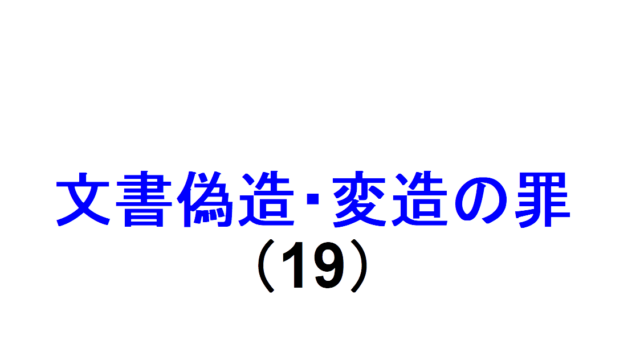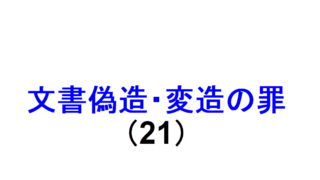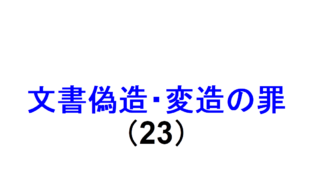文書偽造・変造の罪(22)~行使の概念③「本来の用法に従ったものではないが、真正な文書として偽造文書を用れば、偽造・変造文書行使罪、虚偽文書行使罪が成立する」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、文書偽造・変造の罪(刑法18章)に共通する概念を説明します。
本来の用法に従ったものではないが、真正な文書として偽造文書を用れば、偽造・変造文書行使罪、虚偽文書行使罪が成立する
本来の用法に従ったものではないが、真正な文書として偽造文書を用いれば、偽造・変造文書行使罪、虚偽文書行使罪が成立します。
この点、判例は、偽造・変造文書、虚偽文書の行使は、
必ずしも文書をその本来の効用に従って使用する場合に限られるものではなく、別途の目的から他の―定の効用を果たすべく真正な文書としてこれを用いれば足りる
としています。
大審院判決(明治35年6月12日)
裁判所は、
- 官文書作成の目的及びその本来の効用如何にかかわらず、これを他の目的に使用し、本来定まれる効用以外の効用を致さしむることを得、従ってこの場合においても官文書偽造行使罪を構成す
と判示しました。
裁判所は、
- 文書偽造罪における行使の目的は、必ずしも本来の用法に従って、これを真正なものとして使用することに限るものではなく、真正な文書としてその効用に役立たせる目的があれば足りる
と判示しました。
判例・裁判例
必ずしも本来の用法に従ったものではないが、真正な文書として偽造文書を用いた以上、行使罪が成立すると判断された裁判例として、以下のものがあります。
大審院判決(大正3年11月18日)、大審院判決(明治41年12月21日)
偽造した借用証書を真正なものとして確定日付を得るため公証人に提出した事案で、偽造文書行使罪が成立するとしました。
大審院判決(明治44年3月24日)
他人Aの同意を得ることなく偽造したA名義の銀行預金通帳を、真正なものとしてAに預けて交付した事案で、偽造文書行使罪が成立するとしました。
大審院判決(大正3年10月6日)
司法警察官が犯罪捜査のため被告人の供述を聴取するのに対して偽造文書(債権の存在を証する偽造の借用証書)を呈示した事案で、偽造文書行使罪が成立するとしました。
大審院判決(大正9年2月5日)
犯人がその犯した犯罪を警察官に覚知されるのを恐れて、自ら進んで行動の潔白を装うため偽造証書(偽造の売戻契約証書)を警察官に提示し、事実を証明した事案で、偽造文書行使罪が成立するとしました。
裁判所は、
- 真正な文書として偽造証書を提示して事実証明の用に供したものであって、これにより真正な文書に対する公の信用を害したものというべきであるから、行使と論断し得る
としました。
大審院判決(昭和7年6月8日)
私通の相手方女性Bから将来のために貯金をしてくれるよう懇請されたものの、預金すべき金員がなかったことから郵便貯金通帳を偽造してこれをBに贈与しようと考え、偽造した通帳を真正に作成したもののように装ってBに交付した事案で、偽造文書行使罪が成立するとしました。
この事例は、偽造通帳を単に私通相手Bに対して行使するにとどまらず、Bの下宿先に対しても未払下宿料等の担保とする趣旨でこれを交付して行使し、料金支払を一時免れて財産上不法な利益を得たという事案です。
札幌高裁判決(昭和27年5月9日)
政府が雑穀を売り渡した場合に食糧事務所分任食糧会計官吏が作成し買受人に交付される荷渡指図書は、買受人が現物の引渡しを受けるため農業協同組合の倉庫に提出するのが本来の用法であるが(他方、あらかじめ同会計官吏が所轄食糧事務所経由で農協倉庫宛てに荷渡通知書を作成送付するなどして、買受人に同書記載の雑穀を引き渡すよう指図しておき、倉庫において、荷渡指図書と照合の上、これと引換えに現物を交付するシステムになっている)、偽造に係る荷渡通知書を食糧事務所出張所宛てに郵送するとともに、それが正規の手続によって送付されたものであると誤信させるため、同出張所長に対し、偽造に係る荷渡指図書を真正に作成したもののように装って呈示した事案で、偽造文書行使罪が成立するとしました。
市選挙管理委員会の主事として委員会に関する事務に従事していた被告人が、市長及び市会議員選挙の終了後に投票通知書又は投票通知再交付書を再製してこれを市選挙管理委員会事務局に備え付けた事案で、偽造文書行使罪が成立するとしました。
裁判所は、
- 被告人において、投票通知書又は投票通知再交付書を市町村選挙管理委員会が公職選挙法施行令31条の規定(市町村の選挙管理委員会は特別の事情がない限り投票の期日の前日までに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならないとの規定)に基づき投票期日の前日までに選挙人に交付すべき入場券に代わるべき文書としての本来の用途に供する目的はなかったが、同委員会が同令45条の規定(選挙に関する書類を当該選挙によって公職に就任した者の任期間当該選挙管理委員会で保存しておくことを命じている規定)により選挙人が投票期日に出頭し投票したととを証する資料として保存しなければならない文書として使用する目的があった以上、行使の目的があったものといわなければならない
旨判示しました。
東京地裁判決(平成9年3月24日)
情を知らない弁護人を介して、他人名義を冒用して作成した金銭受領書及び覚書を、公判期日において取調べのため展示させた上、裁判所に提出させた事案で、偽造文書行使罪が成立するとしました。
司法書士に対し、金銭消費貸借契約証書に基づく公正証書の作成の代理嘱託を依頼するに際して、偽造の同契約証書を真正な文書として交付した事案で、偽造文書行使罪が成立するとしました。