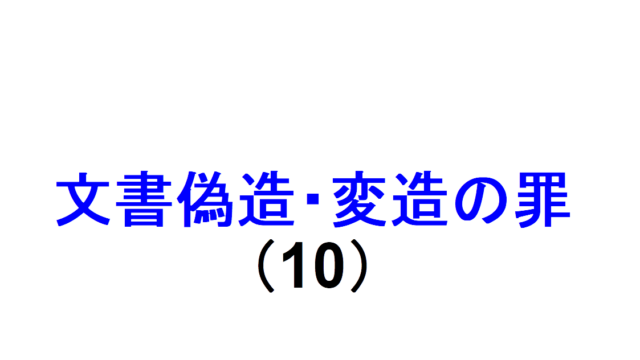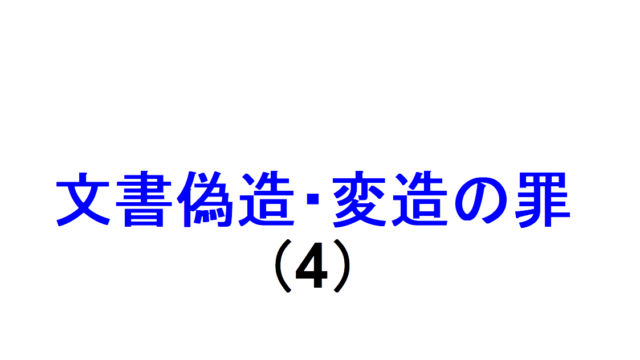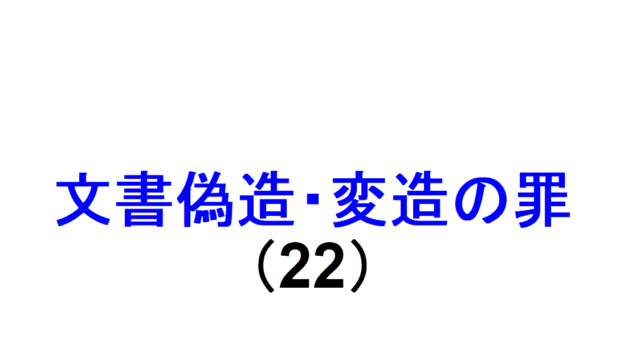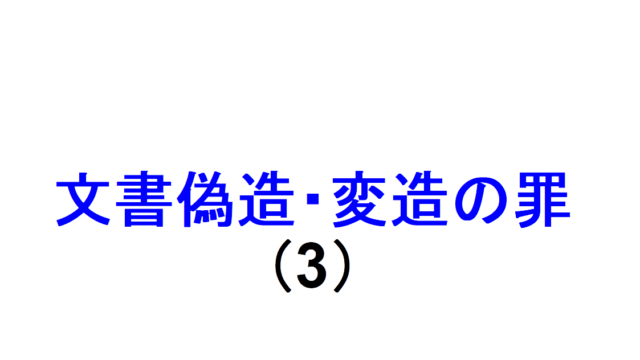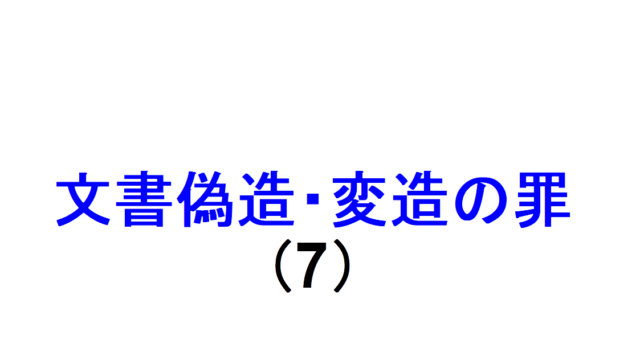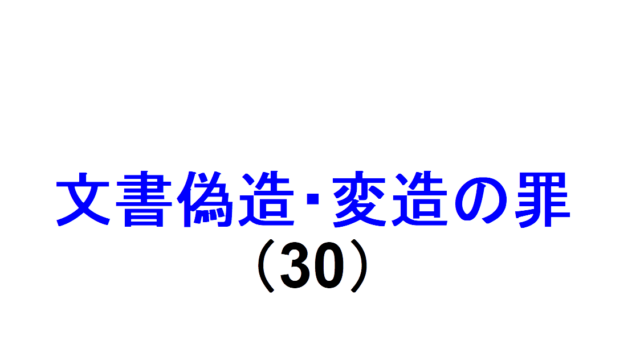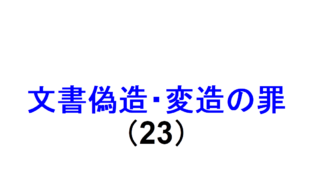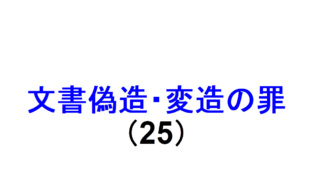文書偽造・変造の罪(24)~行使の概念⑤「偽造・変造・虚偽文書の『備付け行使』」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、文書偽造・変造の罪(刑法18章)に共通する概念を説明します。
偽造・変造・虚偽文書の「備付け行使」
1⃣ 偽造・変造・虚偽文書の行使の方法について、文書を相手方に直接交付するのではなく、れを
一定の場所に備え付けること
によっても行使と認められる場合があります。
こうした「備付け行使」も行使の一態様として位置付けられています。
典型的には、刑法157条1項(公正証書原本不実記載罪)、刑法158条1項(偽造公文書行使罪)に該当する場合のように、公務員に対して虚偽の申立てをして、
- 登記簿、戸籍簿その他の権利義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ(公正証書原本不実記載罪:刑法157条1項)
あるいは、
- 権利義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせ(電磁的公正証書原本不実記録罪:刑法157条1項)
た上で、
- この原本を一定の場所に備え付けさせるような行為(不実記載公正証書原本行使罪に該当する行為)
が挙げられます。
備付け行使は、不実記載公正証書原本の場合に限られるものではなく、私文書であっても備付けの態様によって行使する類型というのが考えられます。
2⃣ 備付け行使は、一定の場所に偽造文書を備え置くことによって特定又は不特定の人間が当該文書の内容を認識し得る状態を作出しているのであり、これが文書の真正に対する公共の信用を害する危険のある行為といえることから、行使罪における行使の一態様として認められているものです。
ここにいう内容を認識し得る状態とは、特定の利害関係人が認識し得れば足りるものであり、必ずしも一般公衆の認識可能性までは要求されません。
かつ、備え付けた文書を実際に他人が閲覧することを必要としません。
この点に関する以下の判例があります。
大審院判決(大正11年9月27日)
商業登記簿に関する事案です。
裁判所は、
- 登記簿は登記についての利害関係を有する者の閲覧に供するため登記所に備え置くものであるから、その文書の行使は、備付けにより特殊関係人が閲覧し得る状態に置けば足り、特定人が閲覧することを要するものではない
と判示しました。
したがって、備付け場所が公開の場所である必要はありません。
この点に関する以下の判例があります。
大審院判決(大正6年12月20日)
銀行の帳簿に関する事案です。
裁判所は、
- 帳簿の備付けによる行使は、その備付けにより特殊の関係を有する者が観覧し得る状態に置けば足り、公開の場所に設備する必要はないので、銀行の休業中か否かを問わず銀行の帳簿に一部分の偽造をして銀行内の特殊関係者の観覧し得る状態に置くときは、備付けによる行使があったものと認めるに妨げはない
と判示しました。
3⃣ また、備付け文書の謄本等の下付申請を待ってからでないと行使の効果が発生しないというものではありません。
この点に関する以下の判例があります。
大審院判決(大正11年5月1日)
商業登記簿に関する事案です。
裁判所は、
- 商業登記簿は、常時、登記官庁に備付け、相当官吏若しくは一般人においてこれを閲覧するを得べき状態に在るものなるが故に、登記官吏に対し、不実の申立をなし、同官吏をして不実の登記を為すに至らしむるときは、その登記あると共に、当然その不実記載部分もまた同官庁に備え付けられ、これと同時に不実登記を為さしめたる者においてこれを行使する効果を生ずべく、何人かこれを閲覧し、若しくはこれが謄本等の下付の申請を待ちて始めて行使の効力が生ずるものに非ず
と判示しました。
判例・裁判例
備付け行使が認められた判例・裁判例として、以下のものがあります。
大審院判決(明治41年12月21日)、大審院判決(明治42年2月8日)
公証人に虚偽の事実を申し立てて権利義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、これを公証人役場に備え付けさせた事案で、偽造文書行使罪の成立を認めました。
大審院判決(明治42年3月25日)
戸籍吏に対し、偽造の養子縁組届書を偽造と告げて提出して単に受理させただけではなく、戸籍吏をして同届書を受け付けて戸籍役場に備え付けさせた事案で、偽造文書行使罪の成立を認めました。
裁判所は、
- 戸籍吏に対する偽造文書の提示はいまだ行使とはいえないが、戸籍吏をして戸籍役場に備え付けさせた場合には、その届書は真の文書として同役場に保管すべきものであるから、ここに行使の事実を生じ、行使罪を構成する
と判示しました。
大審院判決(明治42年6月17日)、大審院判決(明治42年11月25日)、大審院判決(大正11年5月1日)、大審院判決(大正11年9月27日)、大審院判決(明治42年2月8日)
登記官吏に対して不実の申立てをして、登記簿に不実の記載をさせ、これを登記官庁に備え付けさせた事案で、偽造文書行使罪の成立を認めました。
大審院判決(明治42年11月25日)
合資会社の清算人が会社の帳簿書類を偽造して会社に備え付けた事案で、偽造文書行使罪の成立を認めました。
大審院判決(大正6年12月20日)
偽造した銀行の帳簿を銀行内の関係者が観覧し得る状態に置くなどして備え付けた事案で、偽造文書行使罪の成立を認めました。
大審院判決(大正11年11月30日)
村役場備付けの村歳入整理簿に虚偽の事項を記入するなどして偽造し、役場に備え付けた事案で、偽造文書行使罪の成立を認めました。
福岡高裁宮崎支部判決(昭和29年10月6日)
町収入役が、偽造銀行預金通帳を正規の保管方法に従って町役場の金庫に備え付けた事案で、偽造文書行使罪の成立を認めました。
裁判所は、
- 文書の行使というのは、一定の文書を真正な文書としてその効用に役立たせることをいうのであるが、銀行預金通帳には、銀行に対する金銭の預入払戻の経過、並びに現在高を証明する作用があって、町収入役が、その名義の儀造銀行預金通帳を正規の保管方法に従い町役場の金庫に備付けるときは、直ちにその証明的作用を発揮すべき状態に置かれるわけであるから、未だこれを他人に呈示しなくても、ここに偽造銀行預金通帳の行使ありというべきである
- しかも、その金庫の保管者が何人であるかは問うところでない
- また、文書の備付が行使となるには、何人でも何時でも閲覧できる場所に置いた場合に限るとの所論(※弁護人の主張)は、銀行預金通帳については当てはまらない
- すなわち、偽造銀行預金通帳を町役場の金庫に備付けたことをもってその行使ありとなす原判決は正当である
と判示しました。
市選挙管理委員会の主事として委員会に関する事務に従事していた被告人が、市長及び市会議員選挙の終了後に投票通知書又は投票通知再交付書を再製してこれを市選挙管理委員会事務局に備え付けた事案で、偽造文書行使罪の成立を認めました。
地方公共団体の内部部局における支出事務に関する稟議書を偽造し、これを証拠書類として所定の箇所に備え付けた事案で、偽造文書行使罪の成立を認めました。
裁判所は
- 地方公共団体の会計事務(就中部局における支出)に関して作成される「禀議書」は法規慣例に基き、当然作成すべき書面であるから、その形式および内容の真正につき、法律によって保護を受けるに値し、文書偽造の罪の客体たる公文書に該当する
- 「禀議書」の名義人は、分掌事務を担当する主任吏員のほか、決裁関係記載部分については支出命令権者たる部局長がその名義人であり、その決裁以前の段階において、他の関係吏員が意見を附記するときは、その記載部分についてその吏員もまた名義人である
- 而して、主任吏員、部局長あるいは関係吏員が「禀議書」中所定の欄に捺印するのは、自らその名義人であることを表示するため、公務員としての印章を押捺するものである
- 偽造若しくは変造の「禀議書」または虚偽の「禀議書」は、それが証憑書類として所定の箇所に備付けられるとき、その行使罪が成立する
と判示しました。
東京高裁判決(昭和57年7月27日)
転居をした事実がないのに、転居した旨内容虚偽の住民異動届を所轄町役場の吏員に提出し、住民基本台帳の住民票の原本に不実の記載をさせて、これを同役場に備え付けさせた事案で、偽造文書行使罪の成立を認めました。