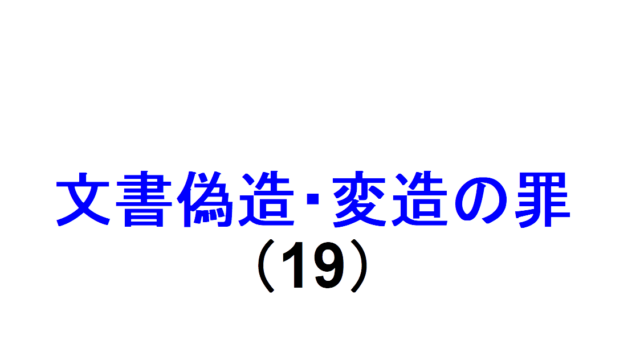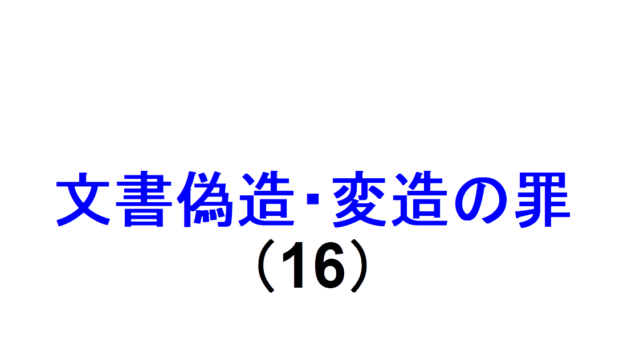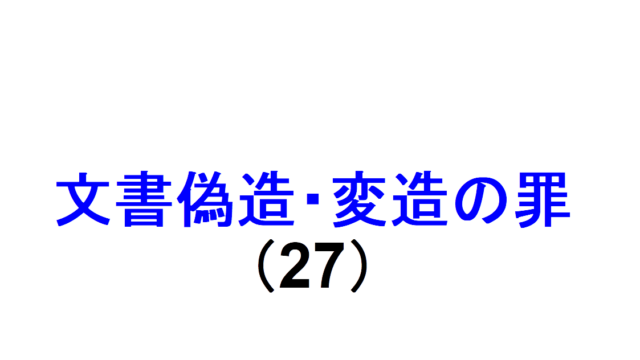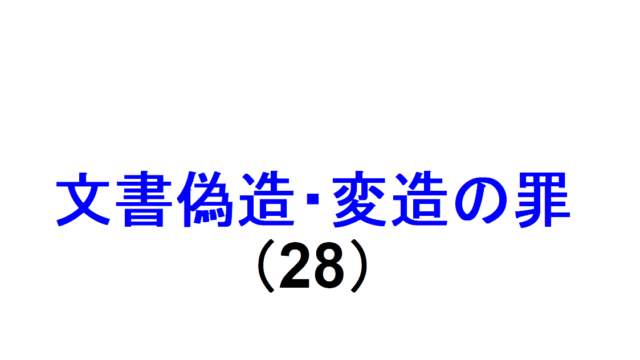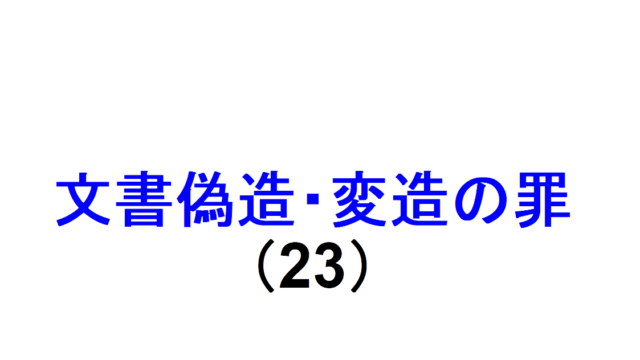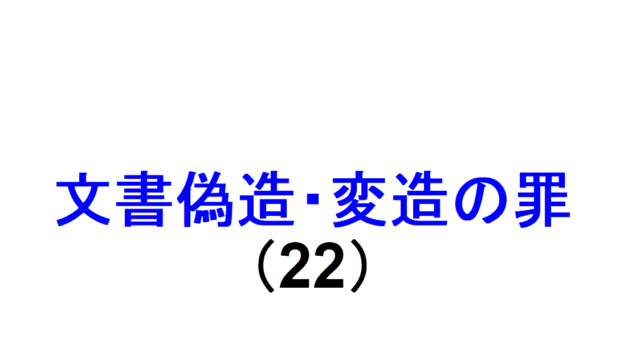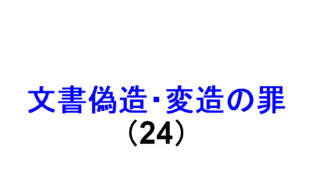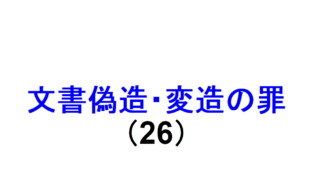文書偽造・変造の罪(25)~行使の概念⑥「偽造・変造・虚偽文書の行使の相手方に制限はない」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、文書偽造・変造の罪(刑法18章)に共通する概念を説明します。
偽造・変造・虚偽文書の行使の相手方に制限はない
1⃣ 偽造・変造・虚偽文書の行使の相手方について、法文上、特に制限は設けられていません。
例えば、捜査機関に偽造文書を提出するような類型について考えてみても、行使の相手方(司法警察官、巡査等)が捜査権限を有するか否かは、行使罪の成否において特段問われるところではありません。
この点、参考となる以下の判例があります。
大審院判決(大正3年10月6日)
裁判所は、
- 文書の被呈示者が捜査権を有する官吏か否かを区別する必要はなく、司法警察員が犯罪捜査のため被告人の供述を聴取するに際し、これに対して偽造文書(債権の存在を証する偽造の借用証書)を呈示すれば、行使に該当する
と判示しました。
大審院判決(大正9年2月5日)
裁判所は、
- 巡査は司法警察員の補助機関であり独立して犯罪捜査権限を有していないが、捜査の方法によらず風評伝聞実験等により犯罪を覚知したときはこれを司法警察員に報告すべき職責を有する者であるから、犯人がその犯した犯罪を巡査に覚知されるのを恐れて、自ら進んで行動の潔白を装うため偽造証書(偽造の売戻契約証書)を巡査に提示し、事実を証明した場合においては、真正な文書として偽造証書を提示して事実証明の用に供したものであって、これにより真正な文書に対する公の信用を害したものというべきであるから、行使と論断し得る
と判示しました。
2⃣ また、行使の相手方が、本来そうした文書の受理権限を有するか否かも問いません。
この点、参考となる以下の判例があります。
大審院判決(明治43年10月28日)
裁判所は、
- 駐在巡査には海外渡航許可願に関する書類を受理する権限はないが、警察署長の事務執行の補助機関であり、本来警察署長に提出すべき書類を受け取って進達すべき職責を有するのであるから、これに偽造書類を提出した行為は行使に該当する
旨判示しました。