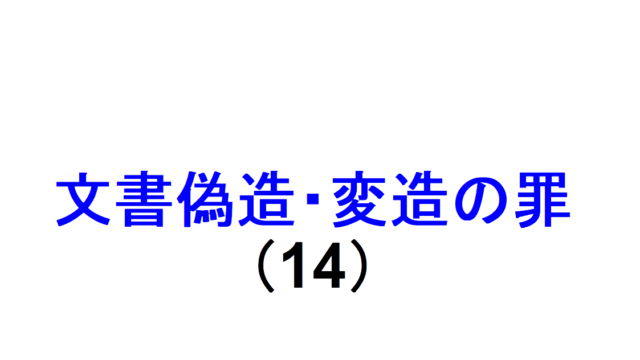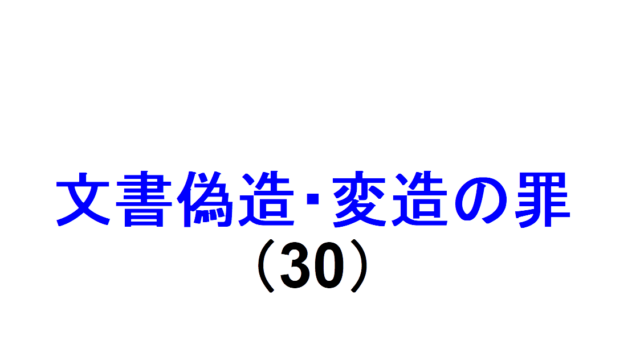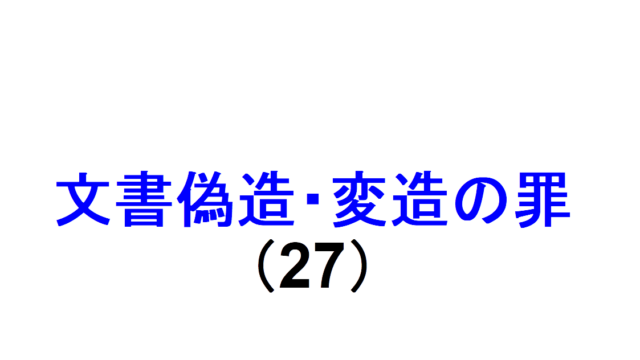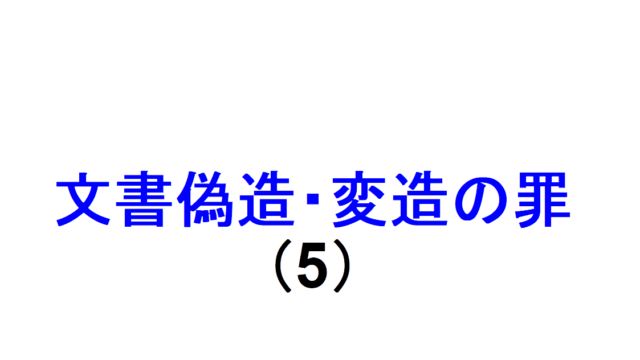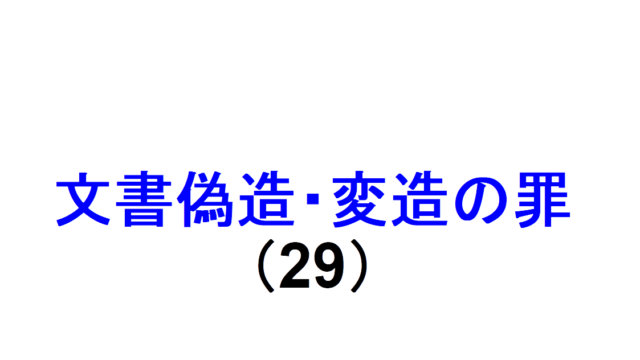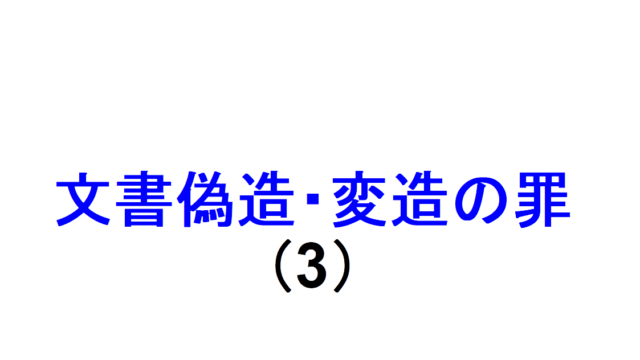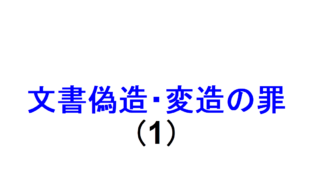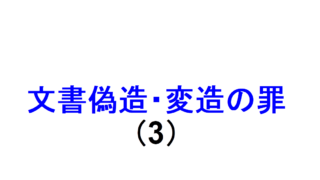文書偽造・変造の罪(2)~「文書偽造の罪の『文書』とは?」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、文書偽造・変造の罪(刑法18章)に共通する概念を説明します。
文書偽造の罪の「文書」とは?
文書の定義
文書偽造の罪(刑法18章)の客体となる文書は、大別すると、
- 天皇文書偽造・同行使罪における天皇が作成する詔書その他の文書(刑法154条、158条)
- 公文書偽造・同行使罪における公務所又は公務員が作成すべき文書・図画(とが)を始めとする公文書(刑法155条、156条、157条、158条)
- 私文書偽造・同行使罪における権利、義務又は事実証明に関する文書・図画を始めとする私文書(刑法159条、160条、161条)
となります。
刑法上、「文書」という語は、文書偽造罪以外にも、
- わいせつ物等頒布罪の客体である「わいせつな文書」(刑法175条1項)
- 公用文書・私用文書等毀棄罪等の客体である「公務所の用に供する文書」(刑法258条)及び「権利又は義務に関する他人の文書」(刑法259条)
で用いられていますが、それぞれの罪質や保護法益に応じて、「文書」の観念に差異が生じ得ることは自然なことです。
なお、有価証券も文書ですが、別途、有価証券偽造の罪(刑法162条、163条)が規定されているので、文書偽造の罪(刑法18章)の罪の対象からは除外されています。
「広義の文書」と「狭義の文書」
文書は、「広義の文書」と「狭義の文書」に分けられます。
「広義の文書」は、
文字又はこれに代わるべき可視的・可読的符号を用い、ある程度永続し得る状態において、物体上に記載された意思又は観念の表示
をいいます(大審院判決 明治43年9月30日)。
「広義の文書」のうち、
文字その他の発音的符号を用いたものを「狭義の文書」
といい、
象形的符号を用いたものを「図画(とが)」
といいます。
「図画」は、象形的符号によっている点以外は狭義の文書に準じて考えられるべきであるとされ、
- 土地の境界を明らかにする図面
- 傷害の部位を示す人体図
などは文書偽造の罪の「図画」に当たりますが、
- 純然たる美術作品の絵画
- 図面等であってもその名義人の意思又は観念の表示としての意味を有しないもの
は「図画」ではないとされます。