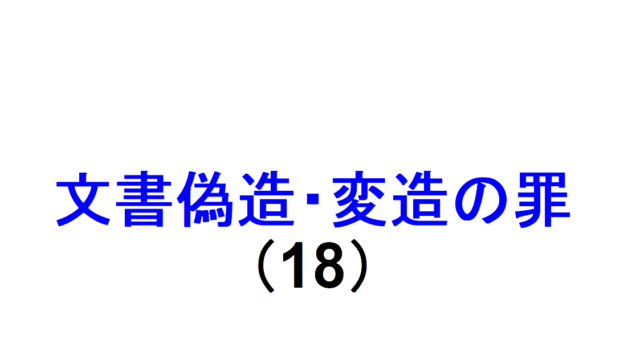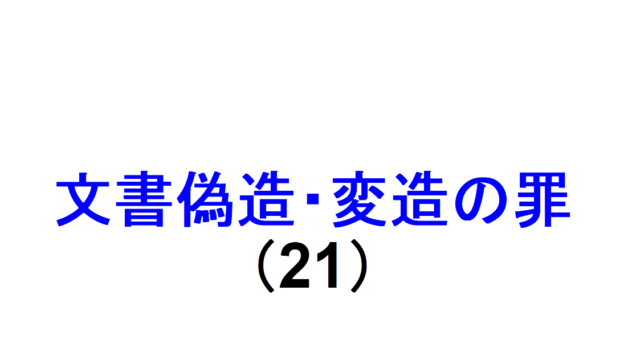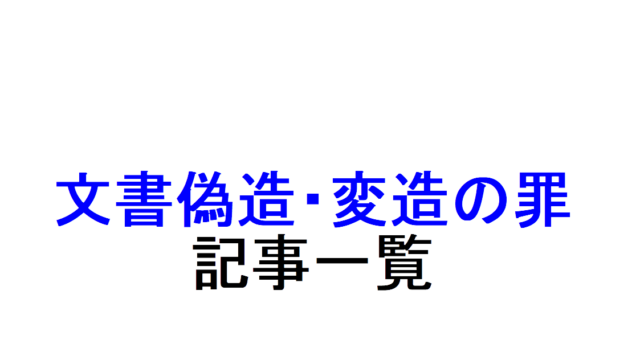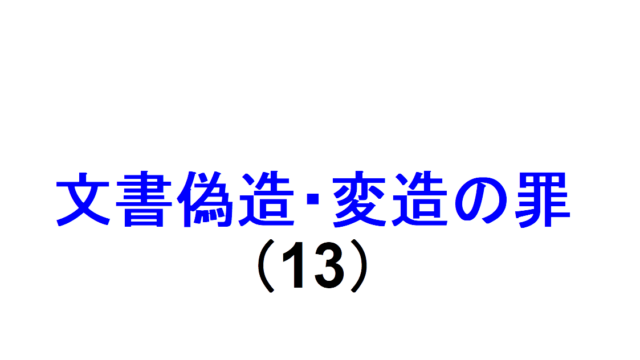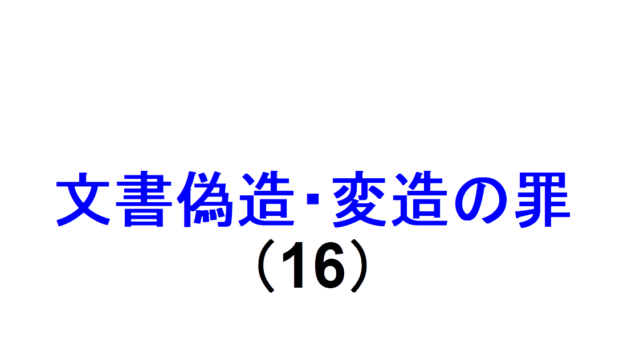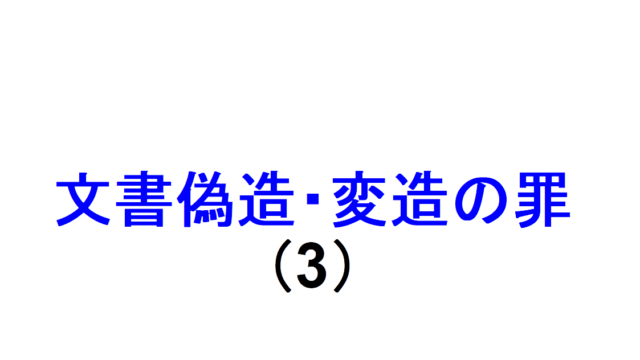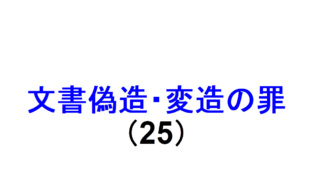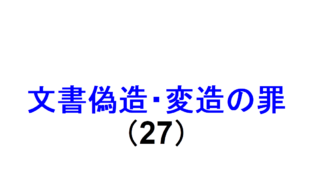文書偽造・変造の罪(26)~行使の概念⑦「偽造文書等の行使の相手が文書が偽造等されたものであることを知っていた場合は、偽造文書等の行使罪は成立しない」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、文書偽造・変造の罪(刑法18章)に共通する概念を説明します。
偽造文書等の行使の相手が文書が偽造等されたものであることを知っていた場合は、偽造文書等の行使罪は成立しない
偽造・変造・虚偽文書の行使は、
偽造・変造・虚偽文書を真正な文書として使用すること
をいうので、
相手方が当該文書が偽造・変造されたもの、虚偽文書であることを知っている場合
には、 この者に対して偽造・変造・虚偽文書を提示しても、行使罪は成立しません。
この点を判示した以下の判例があります。
大審院判決(大正3年10月6日)
裁判所は、
- 偽造文書の行使とは、全て偽造文書なるにかかわらず、これを真正なる文書として任意に共犯者以外の者に呈示する行為を指称する
と判示しました。
これに対し、仲介者を介して他人に偽造文書を提示する場合においては、たとえ仲介者が偽造文書であることの情を知っていたとしても、最終的な提示の相手方が情を知らない限り、行使罪が成立することに問題はないとされます。
この点を判示した以下の判例があります。
大審院判決(昭和11年10月14日)
裁判所は、
- 偽造文書行使の仲介者において、その偽造たるの情を知りいたりや否は、相手方に対する行使罪の成否に何ら消長を来たざるものとす
と判示しました。