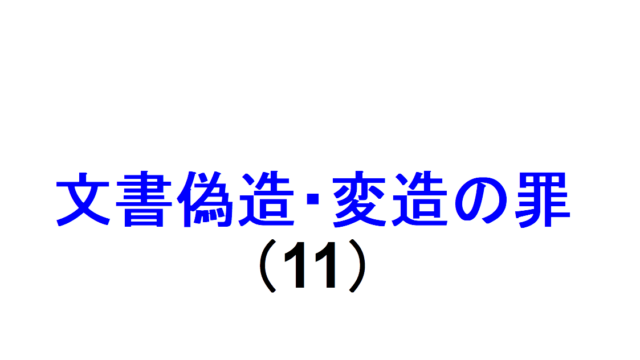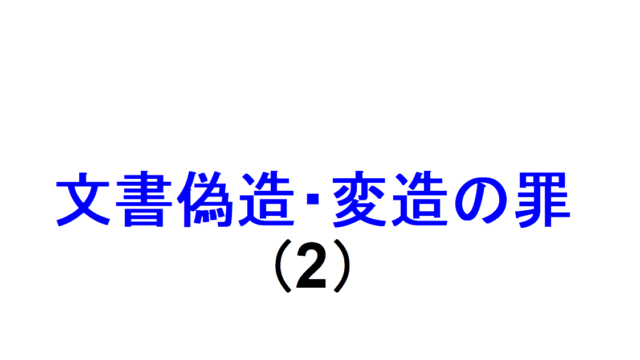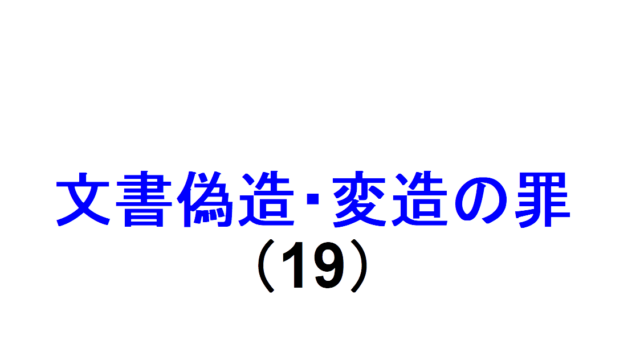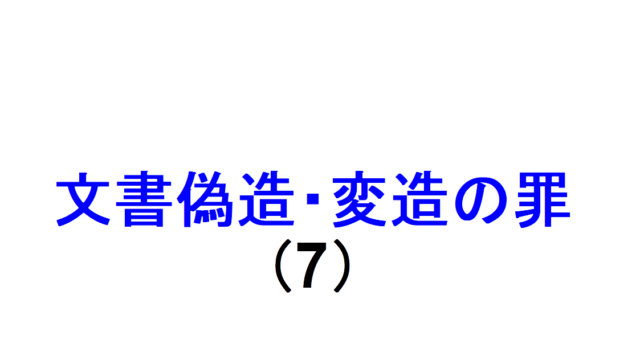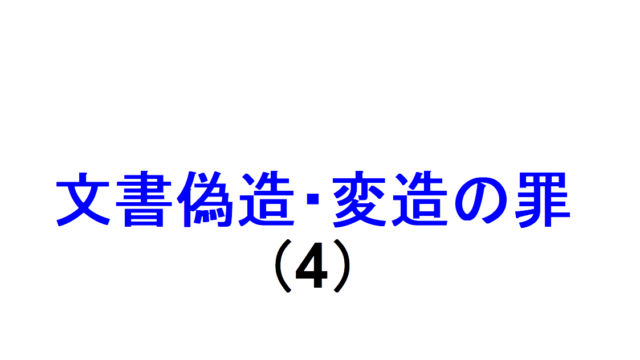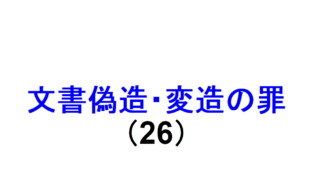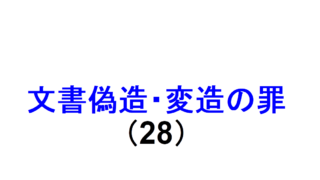文書偽造・変造の罪(27)~行使の概念⑧「利害関係のない者に対する偽造文書等の行使でも、公衆の信用が害されるおそれがあるときは、偽造文書等の行使罪が成立する」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、文書偽造・変造の罪(刑法18章)に共通する概念を説明します。
利害関係のない者に対する偽造文書等の行使でも、公衆の信用が害されるおそれがあるときは、偽造文書等の行使罪が成立する
従来の判例では、偽造・変造・虚偽文書の行使は、行使の相手方として、当該文書につき何らかの利害関係を有するものでなければならないものと解されてきました。
例えば、偽造した運転免許証を、見ず知らずの散歩中のおじさんに示しても、そのおじさんはその偽造運転免許証について利害関係がないので、偽造公文書行使罪は成立しないと考えられます。
こうした考え方を採る理由としては、
- 全く利害関係のない者に対しては、そもそも文書の用法に従った使用を考えることができないこと
- 文書の真正に対する公共の信用が害されたとして処罰する必要性もないこと
などが挙げられます。
最近の学説を見ると、公共の信用を害する可能性の全くない場合は別として、
たとえ利害関係のない者に偽造文書を提示した場合であっても、これにより不特定又は多数の者がその内容を認識し得る状況を作出したときは公衆の信用が害されるおそれがあるといえるのであるから、何らかの意味で真正な文書としてその効用に役立たせる目的のもとに使用すれば行使に該当し、相手方が利害関係を有するものでなければならないといった限定は不要である
とする考え方が通説的見解を占めるにいたっています。
判例・裁判例
従前の裁判例のうち、利害関係のない者に対する提示であることを理由に行使罪の成立を否定したものとしては、以下の判例があります。
大審院判決(大正9年12月1日)
偽造の不動産売買予約証書上の虚偽の権利関係に基づき、不動産の所有権取得の仮登記仮処分命令申請書を作成するため、同偽造証書を代書人(司法書士の前身)に提出した点が行使罪に問われた事案です。
裁判官は、
- 証書を代書人に交付するも、これを利害関係人に呈示し又は事実証明の用に供したるものというべからずして、単に自己が一定の文書を作成するに当たり自己の委託に応じ代書する者に対し作成の資料を開示したるに過ぎず、故に、これを指して文書を行使したるものというべからず
と判示し、偽造私文書行使罪は成立しないとしました。
その後、最高裁決定(平成15年12月18日)は、代書人(司法書士の前身)に対する提示が利害関係人に対する提示に該当しないとした上記大審院判決(大正9 年12月1日)とは異なり、代書人の後身ともいうべき司法書士に対する偽造文書の提示をもって行使罪が成立するものと判断し、正反対の結論を示すに至っています。
事案は、内容虚偽の金銭消費貸借契約証書を偽造した上、司法書士に対し、同証書に基づく公正証書の作成の代理嘱託を依頼する際、これをあたかも真正に成立したもののように装って交付したというものです。
裁判官は、
- 同証書の内容、交付の目的とその相手方等にかんがみ、文書に対する公共の信用を害するおそれがあると認められるから、偽造文書の行使に当たると解するのが相当である
と判示し、偽造有印私文書行使罪が成立するとしました。
このほか、利害関係のある者に対する提示と認めて行使罪を肯定した裁判例として、以下のものがあります。
大審院判決(明治42年4月22日)
偽造の約定証を訴訟事件の立証に供するため自己の訴訟代理人弁護士に交付した事案です。
裁判所は、
- 訴訟代理人は、当事者が提出する証拠書類の真否を判別し、これを裁判所に提出する当否を判別すべき職責を有するから、たとえ当事者の最終目的が裁判所に提出することにあるとはいえ、偽造の証書を真正の証書として自己の訴訟代理人に交付した行為は、訴訟代理人に対して偽造証書を事実証明の用に供したものにほかならず、行使に該当する
旨判示しました。
大審院判決(明治42年7月27日)
告訴告発人が司法警察官又は検事に提出する偽造証拠書類を自己の代人弁護士に真正な文書として交付した事案です。
裁判官は、
- 告訴又は告発の代人が証拠書類を司法警察官又は検事に提出するのが告訴又は告発本人の依頼によるとしても、代人はその真偽を判別し提出の当否を判断した上、自己の責任で行うものであり、本人の指揮命令に盲従し機械的動作をなすものではないのであるから、偽造証書を代人に真正のものとして交付した瞬間において偽造証書行使罪が完全に成立する
と判示しました。
大審院判決(大正4年5月18日)
偽造証書を裁判所に提出させるため、偽造であるとの情を知らない訴訟代理人弁護士に対し、真正文書としてこれを交付した事案で、偽造文書行使罪が成立するとしました。
大審院判決(昭和7年6月8日)
私通の相手方女性Aから将来のために貯金をしてくれるよう懇請されたものの、預金すべき金員がなかったことから郵便貯金通帳を偽造してこれをAに贈与しようと考え、偽造した通帳を真正に作成したもののように装ってAに交付した事案で、偽造文書行使罪が成立するとしました。
なお、この事案は、偽造通帳を単に私通相手Aに対して行使するにとどまらずAの下宿先に対しても未払下宿料等の担保とする趣旨でこれを交付して行使し、料金支払を一時免れて財産上不法な利益を得たという事案です。
公立高等学校の教論が、高校を中退したAと共謀の上、偽造に係る校長名義のAの卒業証書を真正に成立したものとしてAの父親に提示する行為は、単に父親を満足させる目的のみをもってなされたとしても、偽造公文書行使罪に当たるとしました。