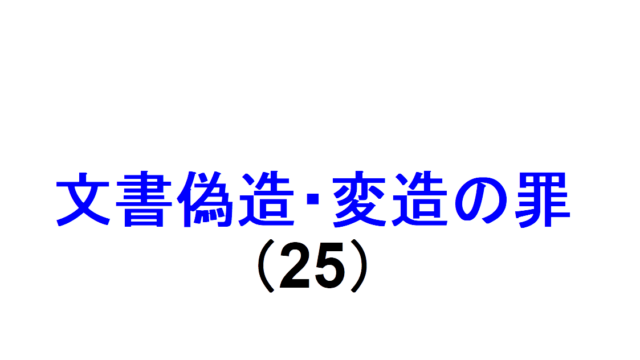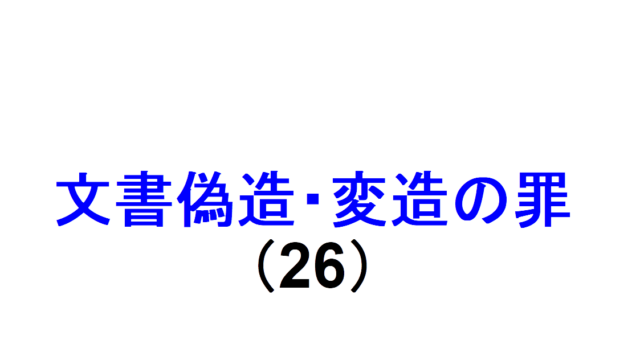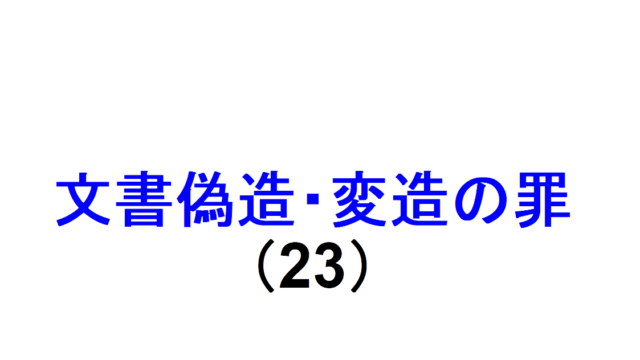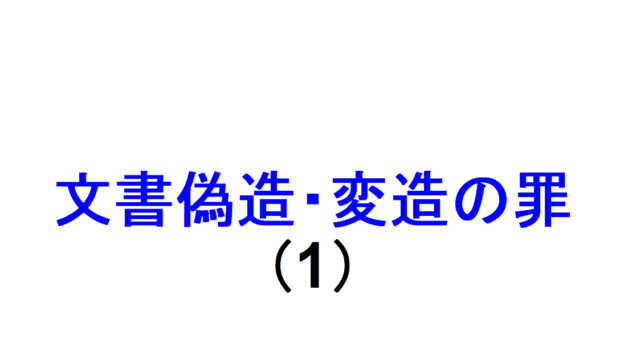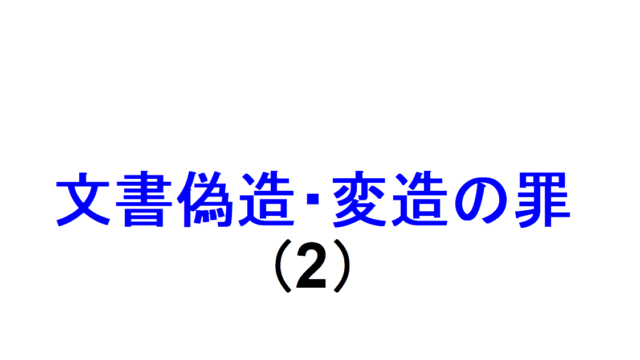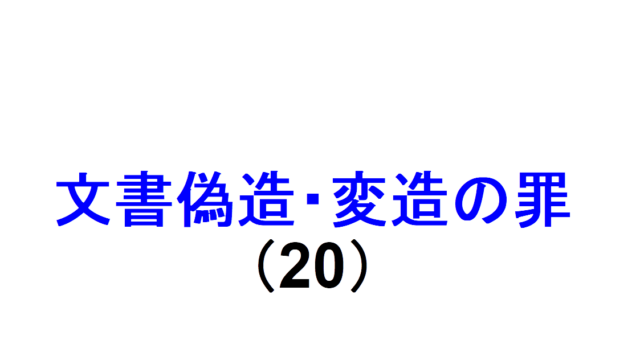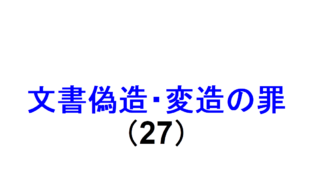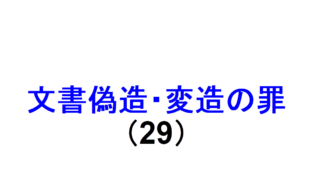文書偽造・変造の罪(28)~行使の概念⑨「偽造・変造文書、虚偽文書の行使罪の既遂時期」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、文書偽造・変造の罪(刑法18章)に共通する概念を説明します。
偽造・変造文書、虚偽文書の行使罪の既遂時期
偽造・変造文書、虚偽文書の行使は、
文書を真正に成立したものとして交付、提示等をし、あるいは備え付ける方法により、相手方にその内容を認識させ又はこれを認識し得る状態に置くこと
によって既遂に達します。
これは、そのような段階においては、
文書の真正に対する公共の信用を侵害する危険が生じたものと認められる
にいたるためです。
行使罪の既遂を認めるに当たり、実害の発生は不要である
行使罪の既遂を認めるに当たり、行使の結果、
現実に実害を生じ又は実害を生ずるおそれがあることは特に要件とされておらず不要
とされます(「既遂」の説明は前の記事参照)。
したがって、
- 相手方が、偽造・変造文書、虚偽文書の交付、提示等を受けた後に、実際に当該文書の内容を閲読するかどうかは問わない
- 一度交付、提示等をすればその後、行為者において文書を撤回ないし回収するなどして、相手方が閲読不能な状態をあらためて作出したとしても、行使罪の成否に影響することはない
こととなり、①②いずれの場合においても、行使罪は既遂に達したものといえます。
これらの関する以下の判例があります。
大審院判決(大正3年9月22日)
裁判所は、
- 行使の目的をもって文書を偽造し又は偽造文書を行使したる以上は、直ちに文書偽造罪又は偽造文書行使罪を構成すべく、これによりて現実に実害を生じ、又は生ずるおそれあることを必要とせず
と判示しました。
大審院判決(明治36年4月1日)
裁判所は、
- 文書偽造罪の完成に必要なる行使ありとするには、犯人の所為が文書の信用に対する危険を生ずるの程度に達したるのみをもって足れりとし、犯人の行為より生ずるその後の結果如何は、これを問うの必要なし
- 従って、犯人がある方法をもって偽造文書を利害関係人の閲覧に供し、利害関係人をしてその内容を知ることを得せしむべき状態に置きたるときは、利害関係人において、現にこれを閲覧してその内容を認識したると否とにかかわらず偽造文書の行使ありたるものとす
と判示しました。
郵送による行使の既遂時期
偽造文書を郵便に付して送る場合、単に発送しただけでは、いまだ相手方が文書の内容を認識し得る状態にあるとはいえないので、行使罪は既遂とはならず、
到達によって既遂に達する
こととなります。
この点を判示したのが以下の判例です。
大審院判決(明治40年1月24日)
裁判所は、
- 郵便をもって偽造文書を対手人に送付する場合には、その文書が受取人の手許に達し、又は受取人の郵便受領箱に入った時をもって行使の既遂とする
旨判示しました。
大審院判決(大正5年7月14日)
裁判所は、
- 偽造文書を郵便に付して発送しただけでは、いまだ相手方をして文書の内容を認識し得べき状態に置いたものということができず、行使罪の既遂に問うことはできない
としました。
電報による行使の既遂時期
電信為替を偽造して金をだまし取ろうと企て、電報頼信紙に発信人銀行名義を冒用して虚偽の電信文をしたため、これを郵便局に提出したが、局員に怪しまれて発電(電報の発信手続)にいたらなかったという事案で、偽造文書行使罪の既遂を認めた以下の判例があります。
大審院判決(大正3年6月20日)
裁判所は、
- 郵便局員をだまして発信の手続をさせるため偽造文書(電報頼信紙)を使用したものであるから、偽造文書行使罪が成立することはもちろんであり、行使の結果として局員が錯誤に陥り受付番号を付して発信の手続をするかどうかは行使罪の成否に影響を及ぼすものではない
としました。
備付け行使の場合の既遂時期
文書を相手方に直接交付する態様によるのではなく、備え付けて行使する態様による場合には、一定の場所に偽造文書を備え置くことによって特定又は不特定の人間が当該文書の内容を認識し得る状態が作られ、文書の真正等に対する公共の信用を害する危険が生じることからして、
備え付けるのと同時に既遂に達する
とされます。
※ 偽造文書等の「備付け行使」の説明は文書偽造・変造の罪(18)の記事参照