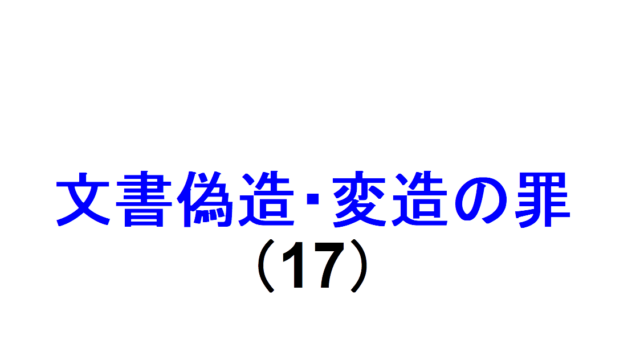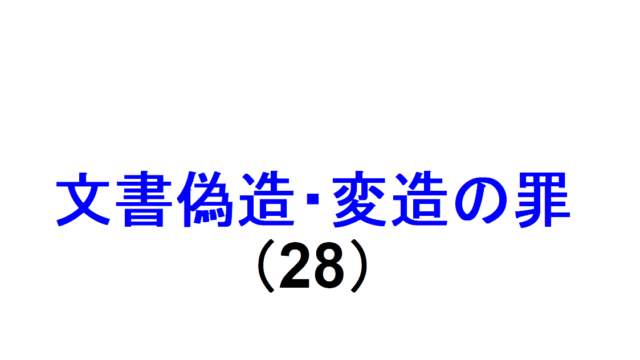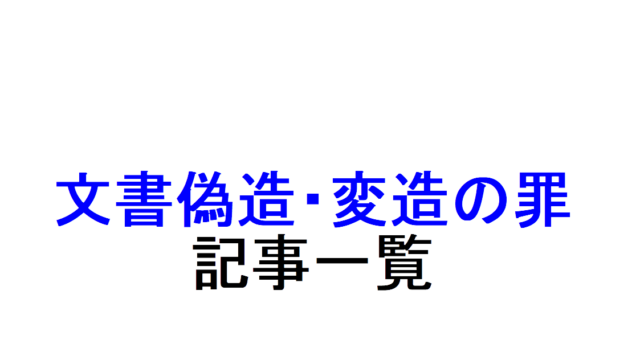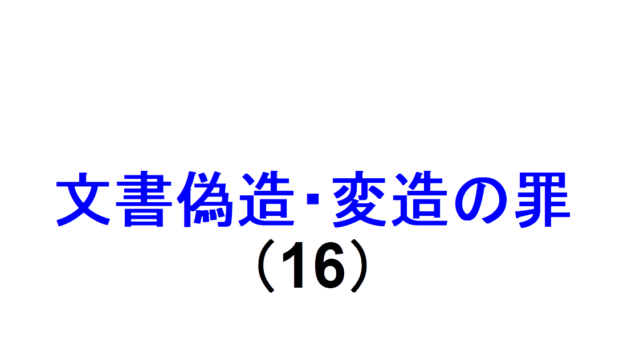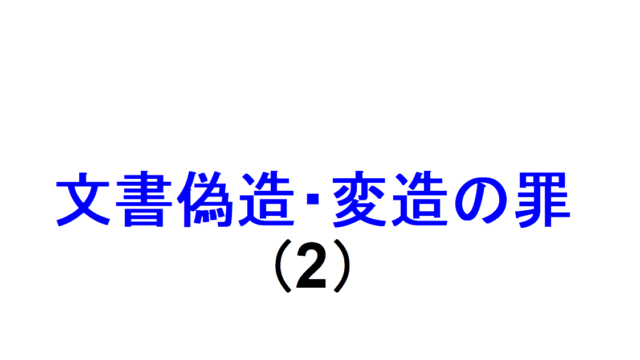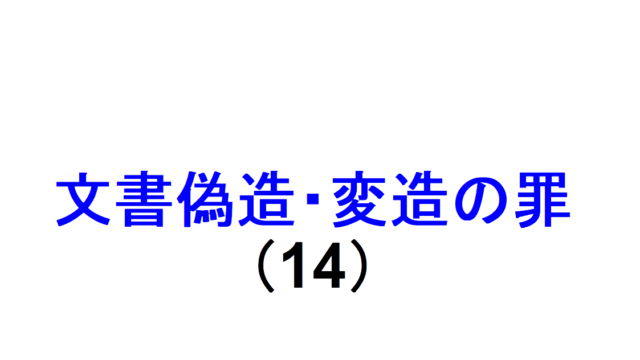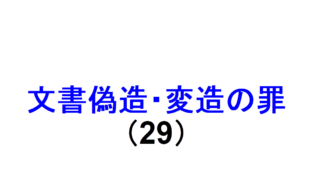文書偽造・変造の罪(30)~行使の概念⑩「偽造・変造・虚偽文書のファクシミリ、スキャナーを用いた行使」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、文書偽造・変造の罪(刑法18章)に共通する概念を説明します。
偽造・変造・虚偽文書のファクシミリ、スキャナーを用いた行使
偽造・変造した文書を写真コピーした場合、公文書偽造罪が成立します(この説明は前回の記事参照)。
ファクシミリを用いて偽造・変造・虚偽文書データを相手方に送信する場合も、写真コピーの方法により作られた写し自体を直接相手方に交付や郵送するのとほぼ等しい結果を産みます。
ファクシミリを用いた文書偽造罪、偽造文書行使罪に関する裁判例として、以下のものがあります。
広島高裁岡山支部判決(平成8年5月22日)
修正液や切り貼り等の方法を用いて改ざんした文書をファクシミリを用いて相手方に送信した行為につき、文書偽造罪が成立するとした判決です。
裁判所は、
- ファクシミリは文書の送受信用の機器であると共に、複写用の機器でもあり、右の基本原理(引用略)によって一般的に作成された受信文書は、送信文書の写しではあるが、その写し作成者の意識が介在混入する余地がなく、原本である送信文書が電気的かつ機械的に複写されるものであるといえるから、ファクシミリについても、真正な原本を原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を有する写しを作成する機能を有するものである
- 文書の本来の性質上、その存在自体が法律上又は社会生活上重要な意味をもっている文書あるいは人の重要な権利の行使に関して必要な文書などにおいては、ファクシミリによる文書の写しを原本の代用としてまでは認められないとしても、その他の分野においては、隔地者間における即時性のある証明用文書として有用なものとして利用されていることは明らかである
など理由に挙げ、文書偽造罪が成立するとしました。
この判決は、偽造文書をファクシミリを用いて送信した行為を行使と判断しているわけではなく、あたかもファクシミリの送受信双方の機器を一体として写真コピーの問題と同列に捉え、受信側でプリントアウトすることによって文書写しの作成を完成させた行為が偽造罪に当たると判断し、その上で、そのような方法により相手方に同文書写しを閲読了知させたことをもって行使罪の成立を認めたものです。
東京高等裁判決(平成20年7月18日)
改ざんした文書の形式外観に問題があることから、文書(国民健康保険被保険者証)原本の偽造を遂げたと認めることはできないが、その写しについては文書性を肯定でき、公文書偽造罪、偽造公文書行使罪の成立を認めた事例です。
事案は、国民健康保険被保険者証の写真コピー(A4大用紙)上に他のコピーから切り抜いた数字等を糊で貼り付けて、一見すると保険証のコピーのように見える物(「本件改ざん物」という。A4大のもの)を作り出し、これをファクシミリ複合機にセットして、画像データを相手方の端末機の画面に拡大表示させて閲覧させたという事案です。
裁判所は、
- 文書偽造罪が偽造文書行使罪とは独立の犯罪類型として規定されている以上、偽造の成否は当該文書の客観的形状を基本に判断すべきである
- 確かに、文書偽造罪が行使の目的をその要件としていることからすれば、偽造の成否の判断に際して文書の行使形態を考慮すべき面はあるが、その考慮できる程度には限度があるといわざるを得ない
- すなわち、本件改ざん物は、ファクシミリ複合機によりデータ送信された先の端末機の画面を通して見れば一般人をして本件保険証の原本の存在を窺わせるような物であるが、そのような電子機器を介する場合以外の肉眼等による方法では、その色合いや大きさ等の客観的形状に照らせば、これを本件保険証の「原本」と見誤ることは通常は考え難いものである
- このような物を作出した時点では、いまだ公文書である本件保険証の「原本」に対する公共の信用が害されたとは評価できないし、物の客観的形状を離れて行使形態を過度に重視することは偽造概念を無限定にするおそれがあり、当裁判所としては与することができない
と述べて、保険証原本について偽造、行使を認めることはできないと判断しました。
その一方、裁判所は、
- 公文書の写真コピーの性質と社会的機能に照らすときは、そのコピーは、文書本来の性質上原本と同様の社会的機能と信用性を有し得ない場合を除き、公文書偽造罪の客体たり得るものと解されているところ、国民健康保険被保険者証についてみれば、そのコピーは、身分確認の一手段として、原本と同様の社会的機能と信用性を有しているものと認められる
- そして、本件改ざん物は、これを直接手に取るなどして見分するならば、紙片を貼り付けた状態のままの部分があることから、改ざんが認知される可能性があるとはいえようが、国民健康保険被保険者証のコピーの呈示・使用の形態にも様々な態様が考えられ、必ずしも相手方が手に取って確認するとは限らず、相手に渡すことなく示すにとどまる場合もあることを想起すれば、本件改ざん物についても、真上から一見する程度であれば表面の切り貼り等が認知されない可能性は十分にあるといえる
- 以上の検討を踏まえ、最高裁判例の趣旨にも徴すれば、本件改ざん物は、本件保険証のコピーそのものではないけれども、一般人をして本件保険証の真正なコピーであると誤認させるに足りる程度の形式・外観を備えた文書と認めるのが相当であり、このような意味で、本件において被告人がコピーを用いて作成した本件保険証の写しについては、その文書性を肯定でき、偽造罪の成立を認めることができる
- そして、被告人は、本件改ざん物をファクシミリ複合機にセットし、その画像データを携帯電話会社宛に送信し、送信先の端末機の画面に表示させて、従業員らに閲覧させることにより、本件保険証の真正な写しとして使用しており、偽造公文書行使罪の成立も肯定できる
と判示しました。
偽造文書をスキャナーで電子的に読み取らせ、その画像を相手方のディスプレイに表示させる方法による行使
偽造文書をスキャナーを通して電子的に読み取らせ、その画像を回線で接続されたディスプレイに表示させる方法により相手方に閲読させた事案で、偽造文書の行使罪を認めた裁判例があります。
大阪地裁判決(平成8年7月8日)
自己の運転免許証の上に、他人名義の運転免許証写しから氏名欄等を切り取った紙片を置いて全体にメンディングテープを貼り付けるなどして偽造した他人名義の運転免許証を、金融会社の無人店舗に設置された自動契約受付機のイメージスキャナーに読み取らせるなどして相手方に閲読させた行為について、公文書偽造罪、偽造公文書行使罪の成立を認めた事案です。
裁判では、改ざんされた運転免許証は、表面は、メンディングテープで覆われているものの、切り貼りした工作の跡が容易にうかがわれ、また、裏面の記載が全くなかったりしており、外観上かなり問題があることが認められたことから、文書偽造罪における偽造といえるための要件、すなわち、当該文書が一般人をして真正に作成された文書であると誤認させるに足りる程度の形式・外観を備えているかどうかが問題となりました。
これについては、裁判所は、
- 当該文書の形式・外観が、一般人をして真正に作成された文書であると誤認させるに足りる程度であるか否かを判断するに当たっては、当該文書の客観的形状のみならず、当該文書の種類・性質や社会における機能、そこから想定される文書の行使の形態等をも併せて考慮しなければならない
とした上で、
- 運転免許証が広く身分証明書としての役割を果たしていることや、呈示の相手方や態様も様々である
- 近時は、相手方の面前で呈示・使用されるだけではなく、身分証明のために、コピー機やファクシミリにより、あるいは、本件のように、イメージスキャナー等の電子機器を通して、間接的に相手方に呈示・使用される状況も生じてきている(このような呈示・使用が偽造文書行使罪における行使に該当することはもちろんである)
- こうした電子機器を通しての呈示・使用も含め、運転免許証について通常想定される様々な行使の形態を考えてみると、一応形式は整っている上、表面がメンディングテープで一様に覆われており、真上から見る限りでは、表面の切り貼り等も必ずしもすぐ気付くとはいえないのであって、そうとすると、 このようなものであっても、一般人をして真正に作成された文書であると誤認させるに足りる程度であると認められる
とし、公文書偽造罪、偽造公文書行使罪の成立を認めました。