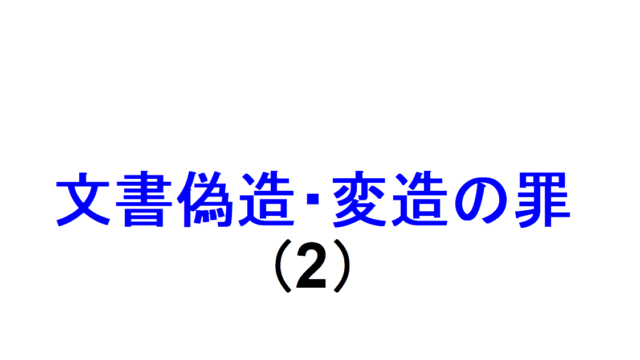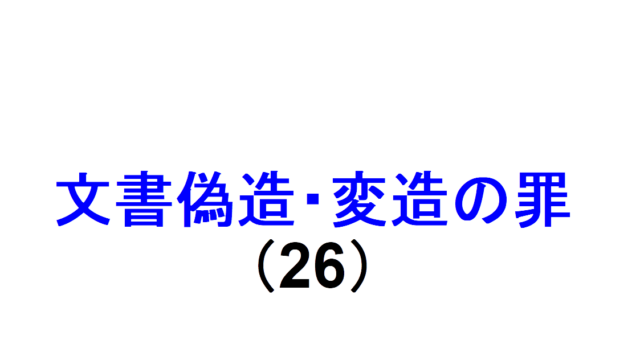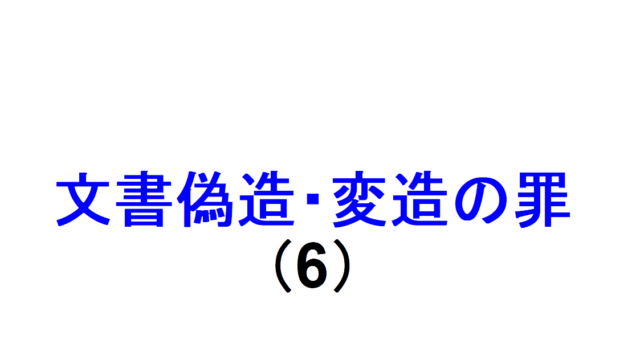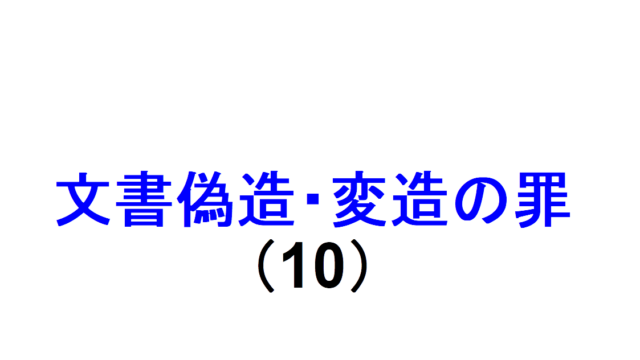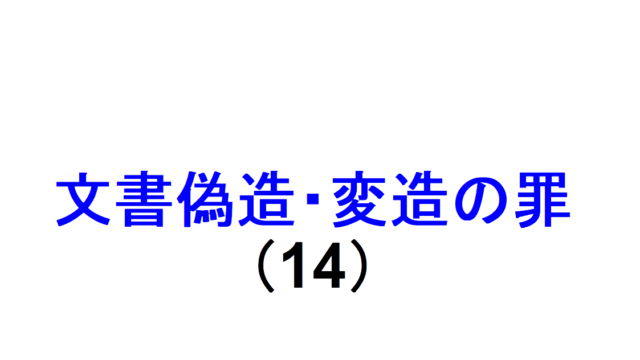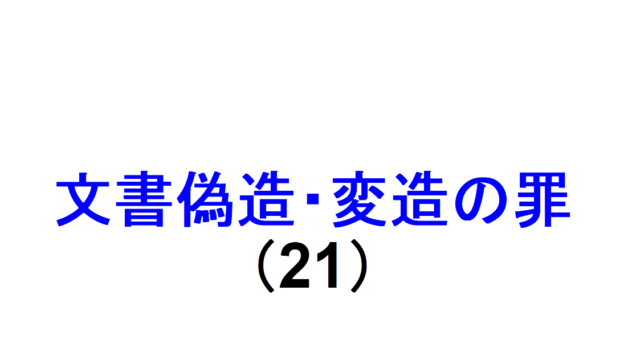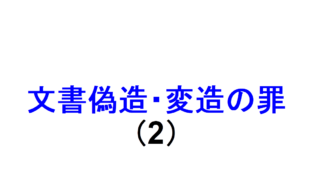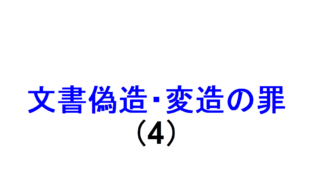文書偽造・変造の罪(3)~「文書偽造の罪の『文書』の性質・要件である『可視性・可読性』」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、文書偽造・変造の罪(刑法18章)に共通する概念を説明します。
文書偽造の罪の「文書」の性質・要件である「可視性・可読性」を説明
文書偽造の罪(刑法18章)における「文書」の性質・要件を整理すると
- 可視性・可読性
- 電磁的記録
- 永続性
- 意味の了解可能性
- 社会的重要性
- 確定性・原本性
- 認証のある写し・謄本
に分けることができます。
この記事では、「可視性・可読性」について説明します。
文書には、
- 可視性・可読性
つまり、
- 視覚により表示が直接的に認識可能であること
が必要とされます。
その理由は、文書が、
- 人の意思又は観念の表示を媒体に固定・表示したもの
であり、
- 他者により認識されることによって証拠としての意義を持ち得るため
です。
それゆえ、記載された文字が、
- 現在は使用されていない楔形文字の類であっても可読的である限りは文書となる
- 文字でなくても、これに代わる発音的符号(例えば、点字、電信符号、速記用符号、バーコード、QRコード)によって表示されたものも文書となる
となります。
ただし、暗号の類も文書ですが、本人のみ、あるいはごく限られた関係者間でのみ了解し得る符号を用いたものは文書とはいい難いとされます。
文書の内容は、必ずしも余すところなく文字その他の発音的符号によって表現されていることを要せず、他の象形的符号等とあいまって、一定の意思又は観念が表示されていれば足ります。
文字の大きさにも制約はなく、
なども、拡大鏡や顕微鏡のような一般的な器具を使えば可読である以上、文書性が認められます。
このように、文書性の判断においては、
視認性が重視される
ので、
- 透明なインクで書かれていて特殊な光線を照射することにより初めて内容が理解できるようになるもの
- あぶり出しのように化学的作用を利用して初めて内容が可視的になるものであって、未顕出の状態にあるもの
には、文書性が認められないと解されています。
レコード、録音テープ、CDなど音声を録音したもの、ビデオテープ、DVD など映像を録画したものは、再生装置を使用しない限り、その内容が分からないので、可視性・可読性の要件を満たさず、文書ではありません。