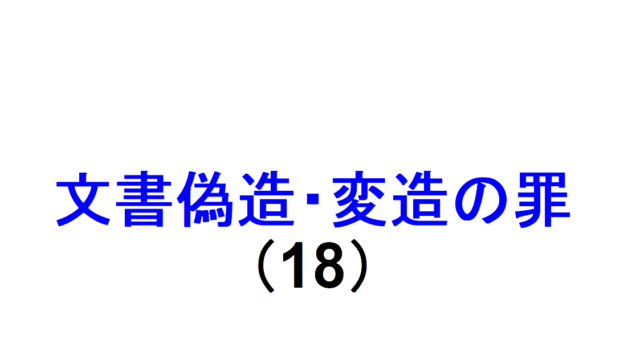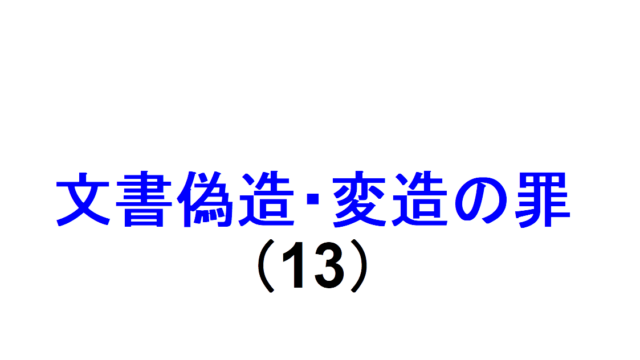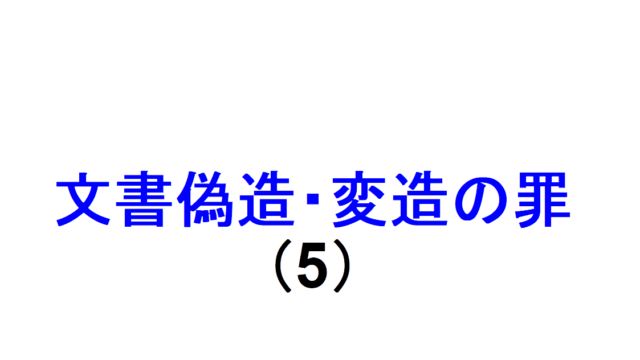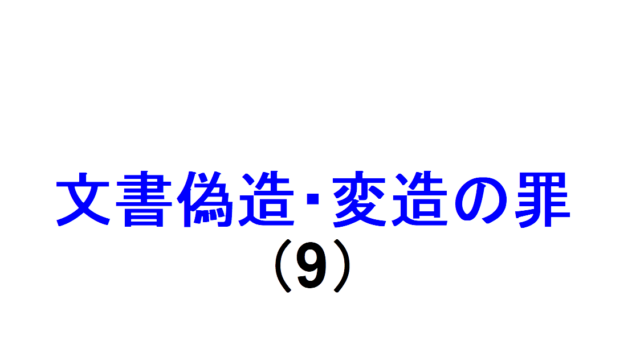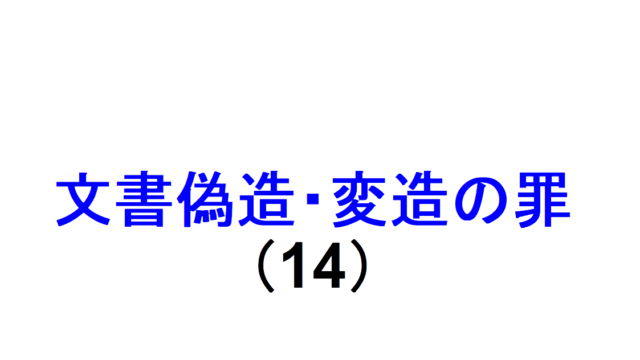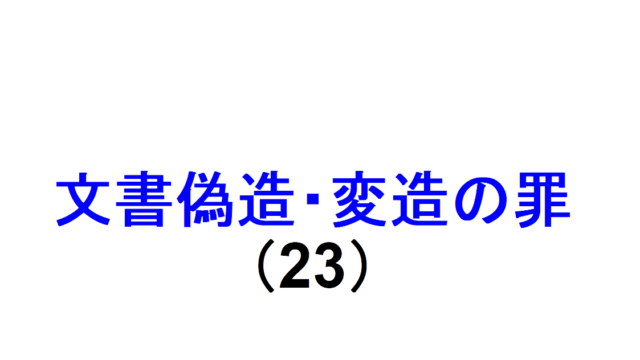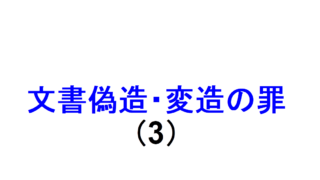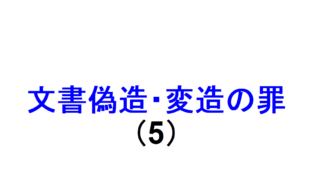文書偽造・変造の罪(4)~「文書偽造の罪の『文書』の性質・要件である『電磁的記録』」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、文書偽造・変造の罪(刑法18章)に共通する概念を説明します。
文書偽造の罪の「文書」の性質・要件である「電磁的記録」を説明
文書偽造の罪(刑法18章)における「文書」の性質・要件を整理すると
- 可視性・可読性
- 電磁的記録
- 永続性
- 意味の了解可能性
- 社会的重要性
- 確定性・原本性
- 認証のある写し・謄本
に分けることができます。
この記事では、「電磁的記録」について説明します。
「電磁的記録」は、可視的・可読的な形式で記録されたものではありませんが、ディスプレイ上に再生したり、プリンターで印刷する方法により、可視的・可読的な形態に直ちに転化できます。
それゆえに、従前は、電磁的記録の文書性が裁判で激しく争われ、自動車登録に際し、虚偽の申請をして、コンピュータシステムを採用した自動車登録ファイルにその旨登録させたことが、当時の刑法157条の公正証書原本等不実記載・同供用罪に当たるかが争われる事案が生じました。
裁判の結果、高裁判例は、電磁的記録(自動車登録ファイル)が、ラインプリンターでプリントアウトすれば文書として再生されることと不可分な関連性を有するものであることなどを指摘して、その文書性を肯定し、公正証書原本等不実記載・同供用罪の成立を認めました(名古屋高裁金沢支部判決 昭和52年1月27日、広島高裁判決 昭和53年9月29日)。
しかし、この高裁判決に対し、学説上で、電磁的記録は、電子計算機等による処理を介して、初めて人が記載内容を認識し得るという点で、文書と異なることは明らかであるし、プリントアウトする際に名義人が記載されることもないではないが、通常は電磁的記録には作成名義が明示されていないため、文書と同列の議論はできないという批判が残りました。
その後、最高裁決定(昭和58年11月24日)は、自動車登録ファイルは「権利、義務に関する公正証書の原本」に当たるとし、このような登録行為が公正証書原本等不実記載・同供用罪に当たることを認めたものの、登録ファイルの文書性そのものには言及しなかったため、学説上は、最高裁が電磁的記録の文書性を認めたものか否かが争いになりました。
そこで、昭和62年の刑法改正により、
- 刑法7条の2に「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの」を電磁的記録とする定義規定が置かれる
- 刑法157条の客体に「電磁的記録」が追加される
- 刑法161条の2として電磁的記録不正作出等の罪が新設される
という形で立法的解決が図られました。
なお、電磁的記録は、通常、作成名義が明示されておらず、偽造・変造の構成要素である作成名義の冒用を観念できないため、法文上も、「偽造・変造・虚偽文書の作成」に代えて、「不正作出」の概念が用いられています。