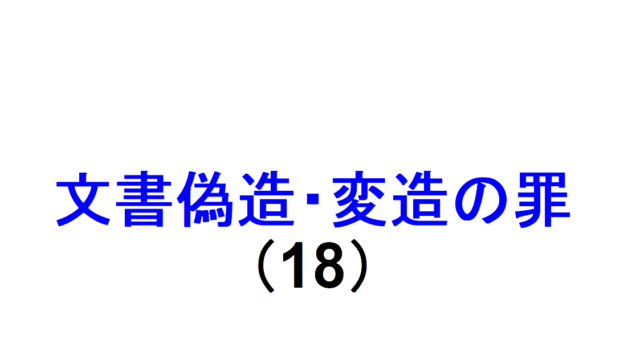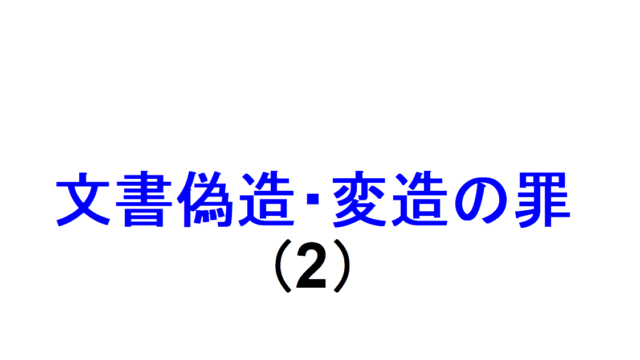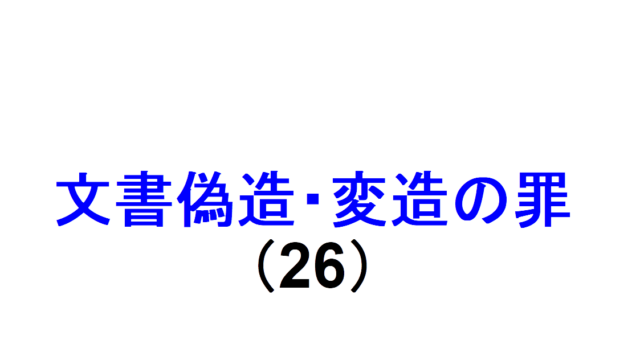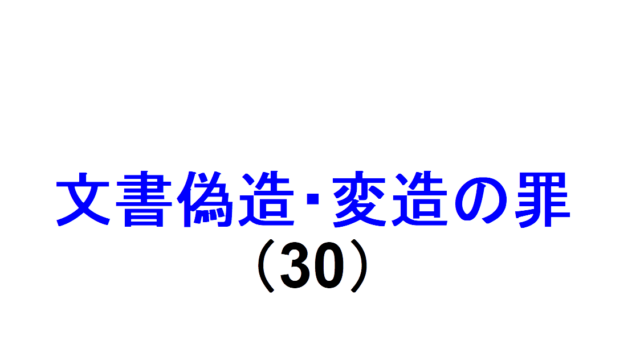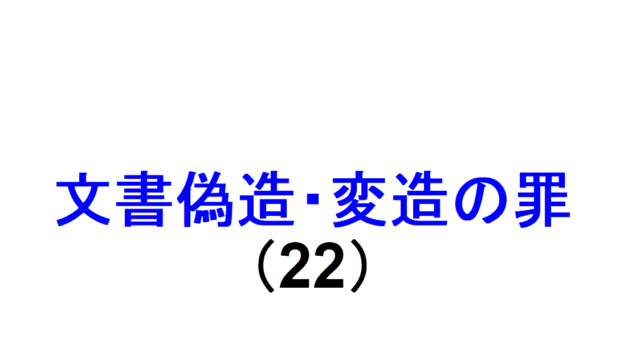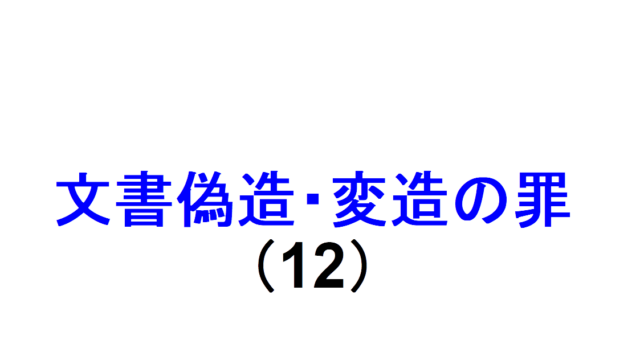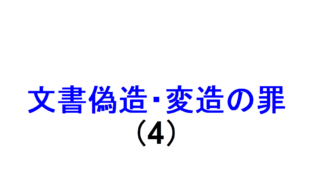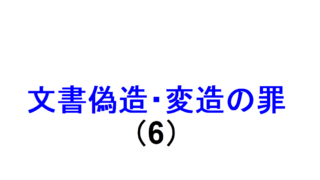文書偽造・変造の罪(5)~「文書偽造の罪の『文書』の性質・要件である『永続性』」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、文書偽造・変造の罪(刑法18章)に共通する概念を説明します。
文書偽造の罪の「文書」の性質・要件である「永続性」を説明
文書偽造の罪(刑法18章)における「文書」の性質・要件を整理すると
- 可視性・可読性
- 電磁的記録
- 永続性
- 意味の了解可能性
- 社会的重要性
- 確定性・原本性
- 認証のある写し・謄本
に分けることができます。
この記事では、「永続性」について説明します。
文書偽造の罪(刑法18章)における「文書」は、
ある程度永続すべき状態において、物体の上に表示されたものであること
を要します(大審院判決 明治43年9月30日)。
砂の上に書かれた文字や、板の上に水書きされた文字などは、永続性に欠けるから文書ではありませんが、ある程度永続的であれば足り、永久性までは要しないので、
- 黒板に白墨で記載したもの(最高裁判決 昭和38年12月24日:公用文書毀棄罪に関するもの)
なども文書となります。
また、文書は、紙その他の書面上に記載される場合が多いですが、
- 布
- 皮革
- 木板
- 石材
- 陶器
- 金属板
などでも差し支えありません(大審院判決 明治43年9月30は、入札用陶器への記載につき、文書偽造罪の成立を認めています)。
また、上記①~⑥などの物体に表示する方法についても特段の制約はなく、
- インクや墨などで書くこと
- タイプライター、印刷機、プリンターなどで印刷・印字すること
- 染料を用いて布や皮革を染め付けること
- 糸で刺繍すること
などでもよいです。
なお、コンピュータのディスプレーに映し出された画像データは文書といえるかについて、学説において、
- 記録時間が比較的短くても永続性は認められ、ハードディスク等に記録・保存された磁気による情報も、ディスプレーを通じて人に認識できる以上は可視性・可読性を肯定し得ないではない等の理由で文書性を肯定する見解
- コンピュータのディスプレーに映っているとはいえ、記載されているわけではない画像データは、永続性の要件(さらには、可視性・可読性の要件)をどのように判断するかに関わるが、スイッチを切れば消滅するのであるから、永続性の要件を欠く等の理由で文書性を否定する見解
- 要件の該当性は肯定できるとしつつ、電磁的記録の独自性を認めた刑法161条の2の趣旨が妥当する範囲では、画像データの文書性を否定すべきとする見解
があり、見解が分かれています。