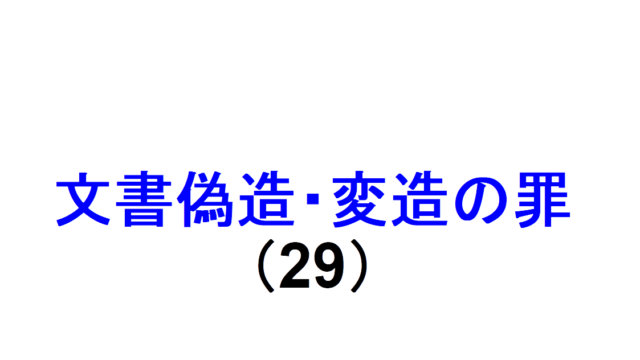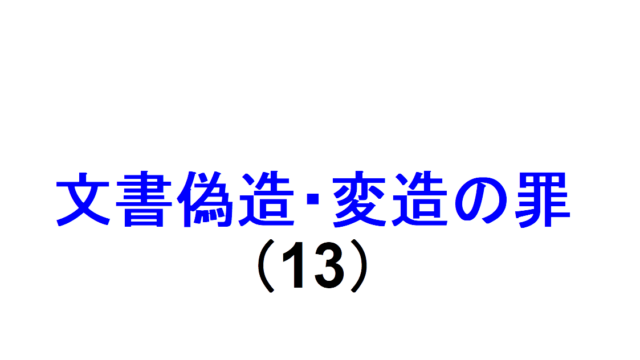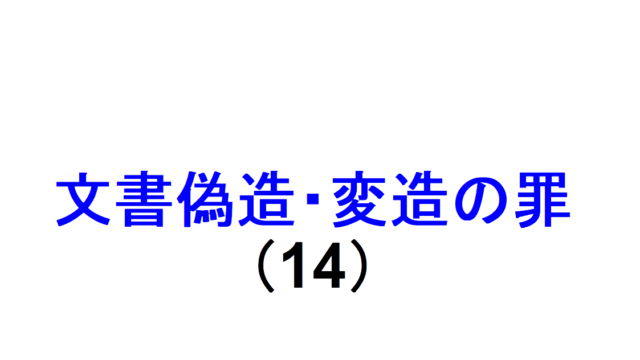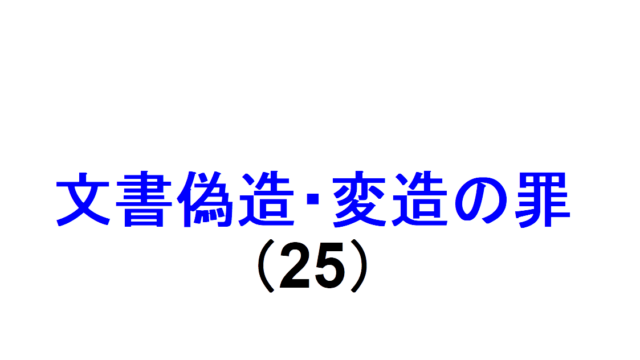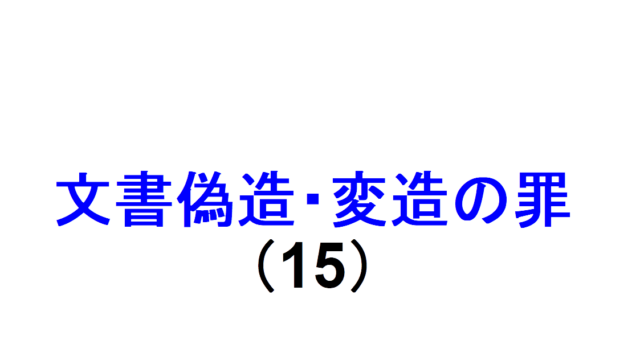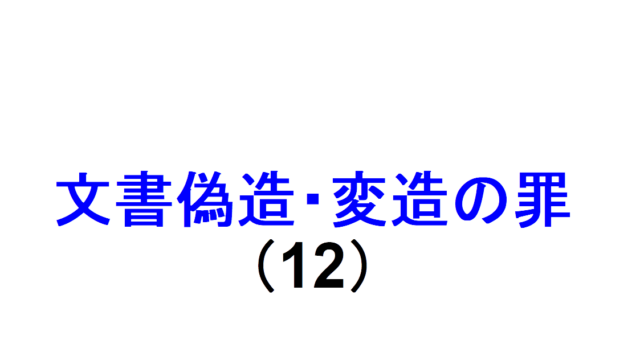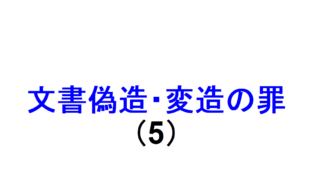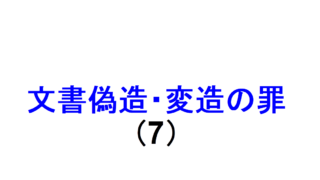文書偽造・変造の罪(6)~「文書偽造の罪の『文書』の性質・要件である『意味の了解可能性』」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、文書偽造・変造の罪(刑法18章)に共通する概念を説明します。
文書偽造の罪の「文書」の性質・要件である「意味の了解可能性」を説明
文書偽造の罪(刑法18章)における「文書」の性質・要件を整理すると
- 可視性・可読性
- 電磁的記録
- 永続性
- 意味の了解可能性
- 社会的重要性
- 確定性・原本性
- 認証のある写し・謄本
に分けることができます。
この記事では、「意味の了解可能性」について説明します。
文書偽造の罪(刑法18章)における「文書」の内容は、
- 意思又は観念の表示
であり、
- 一定の連絡した意味を持ち、客観的に理解され得るもの
でなければなりません。
具体的には、商品に付されたバーコードには文書性が認められますが、到着番号札、劇場の下足札、物品預かり札、整理票のように、
- それ自体は一定の連絡した意味を有せず、周囲の状況との関連の下に初めて何らかの意味を与えられるもの
は文書とは認められません。
名刺や門札のように、
- 人物又は事物の同一性を表示するにすぎないもの
も文書とは認められません。
また、
- それ自体が一定のまとまった意味内容の表示とみられないもの
は、単なる符号(記号)であって、文書とは認められません(大審院判決 大正2年3月11日、大審院判決 昭和3年6月26日)。
こられに対して、旧国鉄が手荷物の発送に使用する駅名札のように、
- 法令上又は慣習上、その書式と結び付いて一定の意味が付与されており、これを客観的に理解し得るもの
は文書とみとめられます(大審院判決 明治42年6月28日)。
つまり、
- 意思表示が部分的に省略されていても、一定の意味を示すもの
は、省略文書(文書の内容の表示が部分的に省略されている文書)として、文書性が認められます。
文書性が認められた判例・裁判例
近年の裁判において、印章(署名)偽造にすぎないのか、文書偽造を構成するのかが争われた事案で、文書性が認められ、文書偽造罪を構成するとされた以下の判例・裁判例があります。
郵便送達報告書の受領者の押印・署名欄に、他人である受送達者本人の氏名を冒書(文書を偽造すること)した事案です。
裁判所は、
- 郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄に他人である受送達者本人の氏名を冒書する行為は、同人名義の受領書を偽造したものとして、有印私文書偽造罪を構成する
としました。
名古屋高裁判決(平成19年10月4日)
他人名義のクレジットカードを不正に利用した者が、その売上票に他人名義の署名をした行為につき、有印私文書偽造罪が成立するとしました。