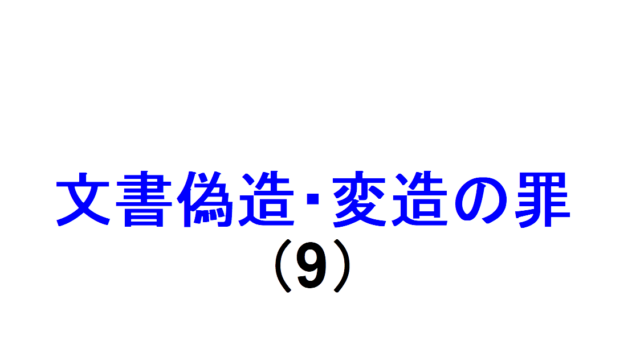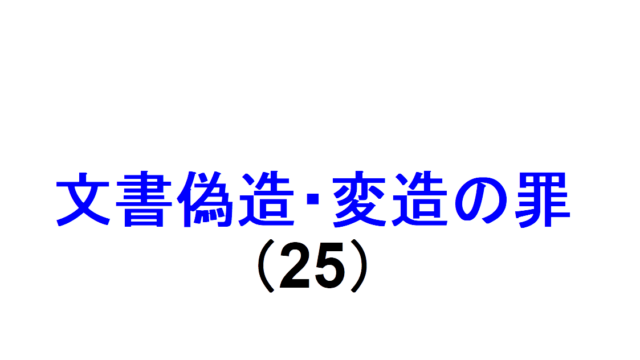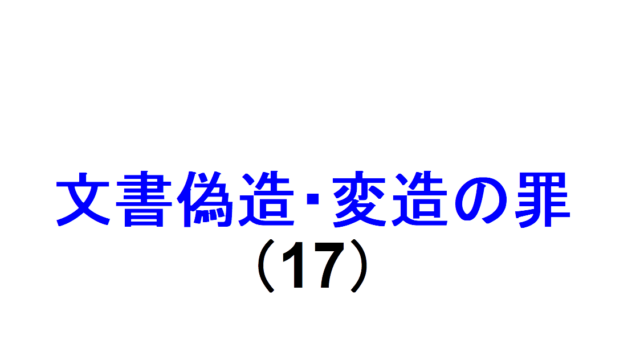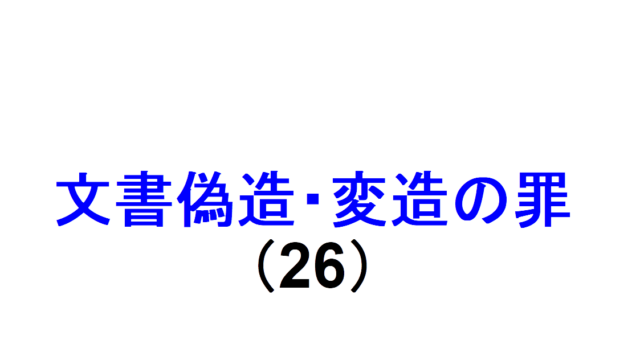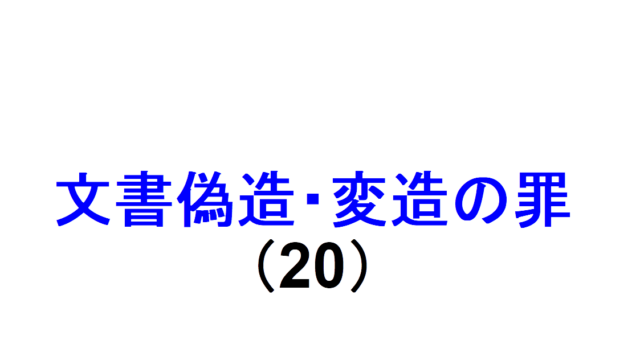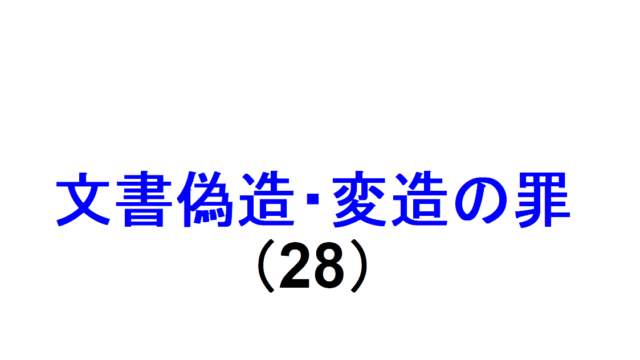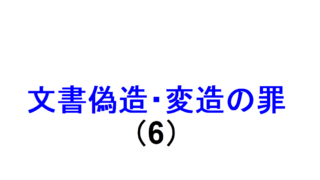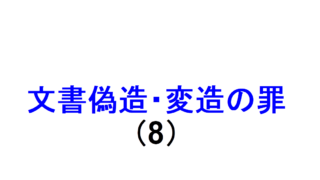文書偽造・変造の罪(7)~「文書偽造の罪の『文書』の性質・要件である『社会的重要性』」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、文書偽造・変造の罪(刑法18章)に共通する概念を説明します。
文書偽造の罪の「文書」の性質・要件である「社会的重要性」を説明
文書偽造の罪(刑法18章)における「文書」の性質・要件を整理すると
- 可視性・可読性
- 電磁的記録
- 永続性
- 意味の了解可能性
- 社会的重要性
- 確定性・原本性
- 認証のある写し・謄本
に分けることができます。
この記事では、「社会的重要性」について説明します。
「文書」は、社会生活における重要な事項について証拠となり得るものであることを要する
文書偽造の罪(刑法18章)は、社会生活上、文書の持つ証拠としての機能を保護するものです。
なので、同罪の対象となる「文書」は、そこに表示された意思や観念の表示が、直接権利義務の発生存続、変更、消減を表示するものである必要があるとともに、
- 社会生活における重要な事項について証拠となり得るもの
でなければなりません。
「文書」に表示された意思又は観念の表示が、社会生活における重要な事項について、何らかの証拠となり得べきものでなければ、刑罰をもってしてまで保護する必要性はないとされます。
なので、考え方として、
- 単なる思想を表示した小説や詩歌等は文書ではない
- 筆者の技術を表明したにすぎない芸術作品としての書画は文書ではない(大審院判決 大正2年3月27日)
- 者の技術を表明したにすぎない芸術作品としての書画に筆者の落款及び押印を加えただけで直ちに権利義務又は事実証明に関する文書となり得るものでない(大審院判決 大正2年12月19日)
となります。
「文書」には、偽造罪の対象として扱われるだけの独立性を要する
文書には、
- 偽造罪の対象として扱われるだけの独立性
が必要です。
なので、警察官が作成した捜査報告書中の他人の氏名を冒用した場合に、その部分だけを取り出して私文書偽造罪に問うことはできません(福岡高裁判決 平成15年2月13日)。
この判決では、
- 刑法159条各項にいう私文書とは、権利、義務若しくは事実証明に関する事項を証明するに足りる文書である
- 確かに、本件捜査報告書及び保管袋の各署名・指印は、前記のように何らかの事項の証明・認証というような一定の観念を表示していると解されるが、私文書偽造罪(3月以上5年以下の懲役)とは別に私印偽造罪(3年以下の懲役)という罪が設けられている趣旨を考えれば、署名、押印が上記のような観念を表示している(本件各文書において、表示される観念が一義的に特定されていない点は一応別論とする。)と解されるだけでは、直ちに署名、印章の偽造が、私印偽造罪とは別に定められ、より重い有印私文書偽造罪に当たるということはできない
- 特に、上記捜査報告書については、公文書である捜査報告書中に存する被疑者の署名、押印が、刑法上の私文書を構成するというために、その外形上公文書から独立性を有する一個の文書(例えば、上記交通事件原票における供述書欄)であることを要すると解するのが相当である
- 本件においては、上記捜査報告書の末尾に設けられた被疑者署名印欄の署名・指印をもって、その外形上捜査報告書から独立性のある文書ということはできないから、文書性を否定するほかはない
と判示しています。
私文書偽造罪においては、「文書」は、「社会生活における重要な事項について証拠となり得るもの」のほか「権利、義務若しくは事実証明に関する文書」であることを要する
文書偽造罪の対象となる「文書」が、「社会生活における重要な事項について証拠となり得るもの」でなければならないことは、文書偽造罪の基本型ともいうべき私文書偽造罪(刑法159条)が、その客体を「権利、義務若しくは事実証明に関する文書」に限定していることにも現れています。
ここにいう「権利・義務に関する文書」とは、
- 権利・義務の発生存続、変更及び消滅の効果を生じさせる意思表示を内容とする文書
をいいます。
「事実証明に関する文書」の意義について、判例は、
- 社会生活に交渉を有する事項を証明する文書であれば足りる
としています。
大審院判決(大正9年12月24日)は、「事実証明に関する文書」の意義について、
- 刑法第159条第1項にいわゆる事実証明の文書は、その証明し得べき事実を法律事項に限定すべきに非ず
- 吾人の実社会生活に交渉を有する事項を証明するに足る以上、これを事実証明の文書としてその公信力を保護せざるべからず
と判示ています。
最高裁決定(昭和33年9月16日)、最高裁判決(平成6年11月29日)は、「事実証明に関する文書」の意義について、
- 社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書
であるとしています。
【近年の判例】
近年、大学の入学試験答案が「事実証明に関する文書」に当たるかが争われ、最高裁がこれを肯定した判例があります(最高裁判決 平成6年11月29日)。
最高裁は、その理由として、
- 入学試験答案は、試験問題に対し、志願者が正解と判断した内容を所定の用紙の解答欄に記載する文書であり、それ自体で志願者の学力が明らかになるものではないが、その採点結果が志願者学力を示す資料となり、これを基に合否の判定が行われ、合格の判定を受けた志願者が入学を許可されるのであるから、志願者の学力の証明に関するものであって、社会生活に交渉を有する事項を証明する文書に当たる
と説示しました。
この説示からすれば、答案用紙上の解答形式が、マークシート式であっても結論に変わりはないと考えられています。
このほか、
- 県教育委員会が実施する公立高校入学選抜のための学力検査の答案(神戸地裁判決 平成3年9月19日)
- 運転免許試験の答案(釧路地裁網走支部判決 昭和41年10月28日)
を、それぞれ「事実証明に関する文書」に当たるとした裁判例があります。
公文書偽造罪は、私文書偽造罪と異なり、「権利、義務若しくは事実証明に関する文書」であることの要件はない
上記のとおり、私文書偽造罪(刑法159条)の「文書」は「権利、義務若しくは事実証明に関する文書」に限定されます。
しかし、公文書偽造罪(刑法155条)の「文書」には、構成要件上そうした限定はありません。
判例(最高裁決定 昭和29年4月15日)は、
- 公文書偽造罪にいう公文書とは、公務所又は公務員がその名義をもってその権限内において所定の形式に従い作成すべき文書を指し、実生活に交渉を有する事項の証明又は権利義務に関する内容を有することを要するものではない
としています。