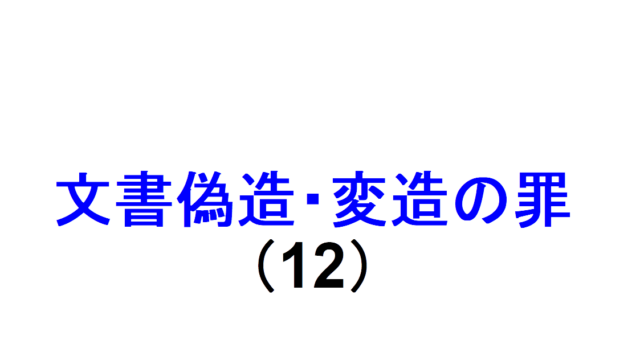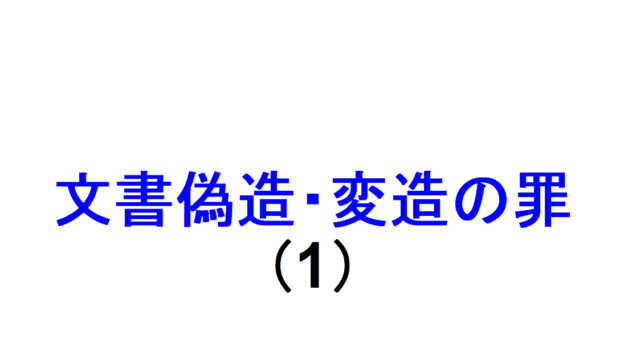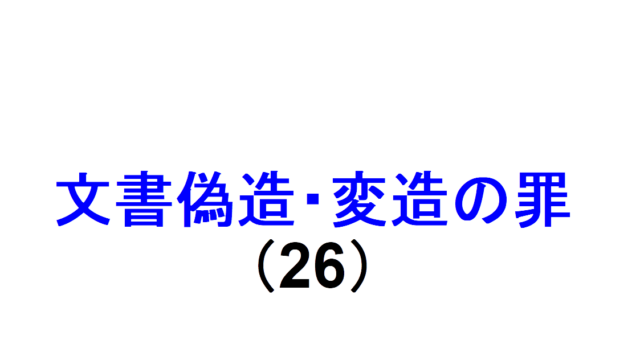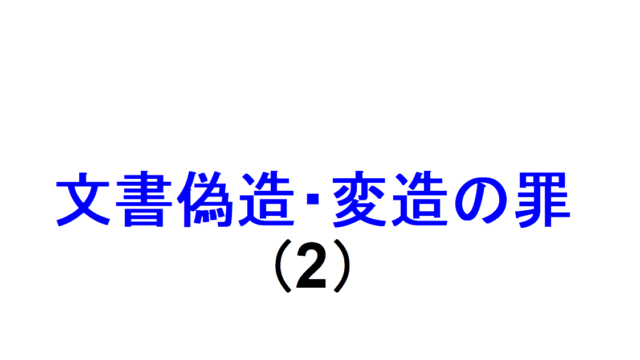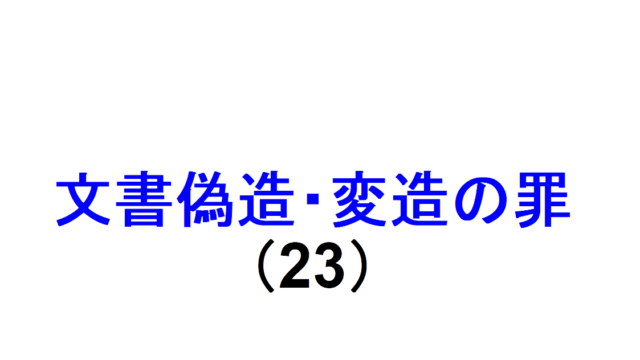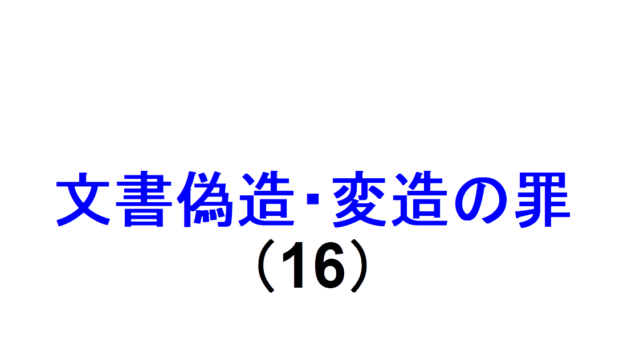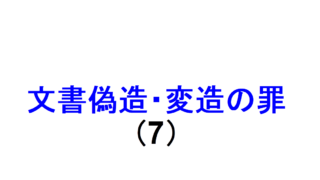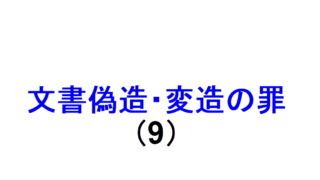文書偽造・変造の罪(8)~「文書偽造の罪の『文書』の性質・要件である『確定性・原本性』『認証のある写し・謄本』」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、文書偽造・変造の罪(刑法18章)に共通する概念を説明します。
文書偽造の罪(刑法18章)における「文書」の性質・要件を整理すると
- 可視性・可読性
- 電磁的記録
- 永続性
- 意味の了解可能性
- 社会的重要性
- 確定性・原本性
- 認証のある写し・謄本
に分けることができます。
今回は、
- 確定性・原本性
- 認証のある写し・謄本
の2つを説明します。
① 文書偽造の罪の「文書」の性質・要件である「確定性・原本性」を説明
「文書の確定性」の説明
文書偽造の罪(刑法18章)における「文書」は、その証拠としての機能から、
- ある時点において示された確定的な人の意思又は観念の表示(これを「文書の確定性」という)
であるとともに、
- 他に代替を許さない唯一のもの(これを「文書の原本性」という)
であることを要します。
「文書の確定性」の具体例について、
は確定性を欠くため、文書偽造の罪(刑法18章)における「文書」に当たりません。
この点、大阪高裁判決(昭和46年9月16日)は、
- 刑法156条にいわゆる公文書といいうるためには、それが一般人をして公務所又は公務員の権限内において作成した文書であると信ぜしめる程度に形式外観を具えるだけでは足りず、さらに確定的な意識内容の記載であり原本的なものであることを要するのであって、確定的な意識内容の記載といえない草案や草稿は右の公文書にあたらない
と判示しています。
これに対し、仮契約書や仮領収書のように、その存在意義が、本契約書や本領収書が作成されるまでという暫定的なものであっても、確定的な内容を有する限り、文書偽造の罪における「文書」に該当します。
未完成の文書が文書偽造罪の対象にならないとされるのは、そのようなものは文書偽造罪で保護する必要性が欠けるためであると考えられています。
なので、白紙委任状や白地保証書のように、内容が一部未確定であっても、それ自体作成者の意思を具体的に表示したものとして社会的に信用の認められるものは、文書に当たるというべきとされます。
「文書の原本性」の説明
「文書の原本性」について説明します。
文書偽造の罪(刑法18章)における「文書」は、原本に限られ、「文書の写し」は含まれないとするのが原則です。
この「文書の写し」とは、
- 手書きされた写し
などを想定するものです。
写し(手書きされた写しなど)には、複写の過程における誤記や誤植の可能性があるばかりか、複写をした者の恣意的な改ざん等の可能性も排除し得ず、原本に比べて信用性が低いため、文書偽造の罪における文書性が否定されます。
これに対し、文書の原本の
- 写真
- コピー
は、原本の内容が正確に再現されているため、上記でいう「文書の写し」に該当せず、文書偽造の罪における文書性が肯定されます(最高裁判決 昭和51年4月30日参照)。
これを前提に「文書の写し」について説明します。
「文書の原本」には、名義人の意思又は観念の内容が直接表示されており、その内容について名義人の保証があります。
これに対し、「原本でない写し」は、写された原本の内容及びその存在を伝達するのみで、当該写しの真実性に対する原本の名義人の直接の責任を表すものではありません。
また、写しは、その性質上、写しを作成する者の意思又は観念が入り込んで、原本の意思又は観念の内容が変更されている可能性があり、
- 内容について、名義人の保証が及ばない
ことから、社会観念上は、これらの表示内容に対する社会の信用は希薄であり、刑法上その作成の真正を保護する必要はないと考えられています。
さらに、文書偽造の罪における「文書」であるためには、名義人が表示されている必要があるところ、写しは、原本の写しであることの認証のあるものを除き、通常、
- 作成者が文面に表れていないから、名義人を特定することができない
ことからも、文書偽造の罪における「文書」に該当しないとされます。
「写」と表示されている書面が原本と解される場合がある
「文書の写し」は、文書偽造の罪における「文書」に該当しないところ、「文書の写し」に「写」と表示されている書面については原本と解される場合があります。
この点を判示したのが以下の判例です。
被告人らが、国民健康保険事業を実施するB村の運営資金として岡山県国民健康保険団体連合会から融資を受けるに当たり、同県国民健康保険融資基金規程に基づき同村村長A名義の借入金申込書に添附すべき必要書類として上記連合会に提出するため、上記借入金に関する村議会の議決も、その議決書も存在しないのに、ほしいままに、A村長から借入金に関する議案を村議会に提出して議決した旨を記載した「村議会議決書(写)」という文書1通を作成した上、これを上記連合会に提出行使したという事案で、上記文書は写しである旨を表示した趣旨の公文書と認められるとしました。
② 文書偽造の罪の「文書」の性質・要件である「認証のある写し・謄本」を説明
次に、文書偽造の罪の「文書」の性質・要件である「認証のある写し・謄本」について説明します。
文書偽造の罪における「文書」の「写し」や「謄本」に
- これは原本の写しである(※写しであることの認証)
又は
- これは謄本である(※謄本認証)
旨の認証文言が付され、その認証者の署名や押印があるものは、認証部分が1個の文書と認められます(大審院判決 大正3年1月19日)。
このように「文書」に「写しであることの認証」や「謄本認証」がある場合、その文書は、文書偽造罪の客体たる文書の原本と認められます。
「写しであることの認証」や「謄本認証」をした文書の名義について考え方は以下のようになります。
例えば、裁判官Aが作成した判決書原本につき、弁護人B が「これは判決書原本を正写したものに相違ない」と付記して、Bの記名・押印をした判決書写しについて、原本性が認められるのは、B名義の私文書としてです。
例えば、裁判官Aが作成した判決書原本につき、検察事務官Cが「これは判決書原本の謄本である」と付記し、Cの記名・押印をした判決書謄本について、原本性が認められるのは、裁判官Aではなく、検察事務官C名義の公文書としてです。