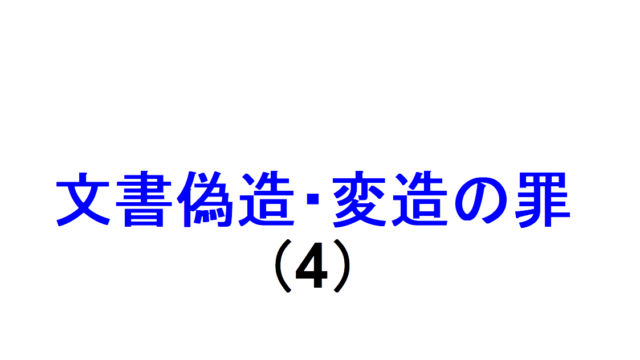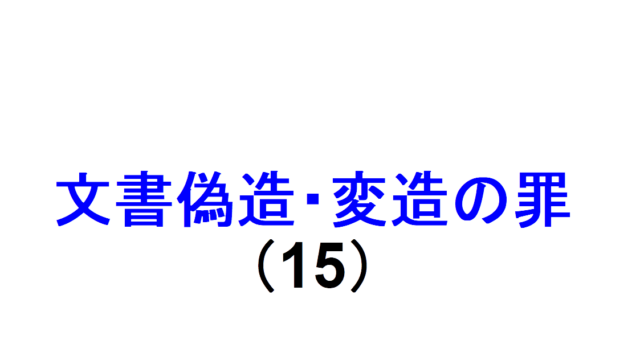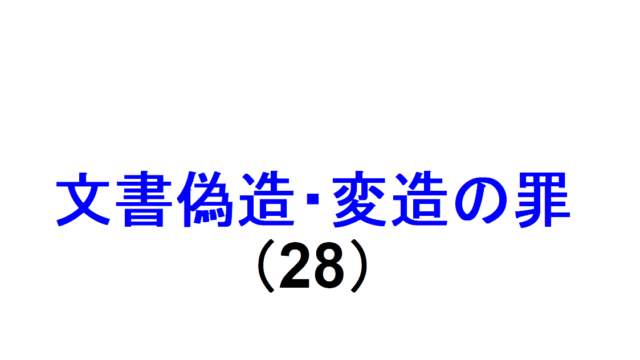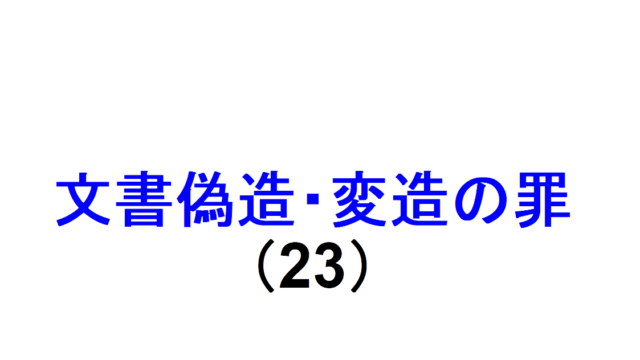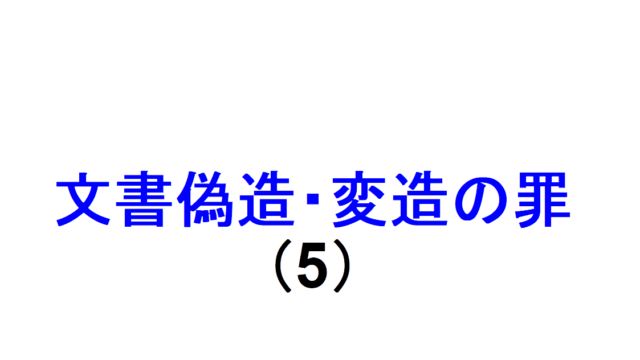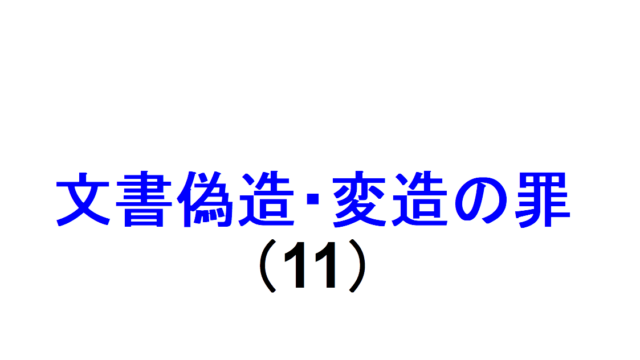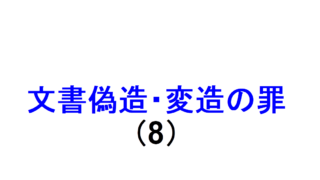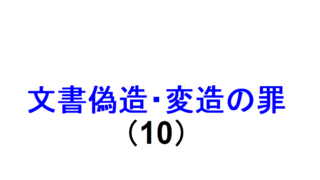文書偽造・変造の罪(9)~偽造の概念①「偽造内容の真否と文書偽造罪の成否」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、文書偽造・変造の罪(刑法18章)に共通する概念を説明します。
偽造内容の真否と文書偽造罪の成否
1⃣ 作成権限を有しない者が、他人の名義を冒用して文書を作成すれば、直ちにその文書の真正に対する公共的信用を損なう危険を生じるため、
偽造した文書の内容の真否にかかわらず、
文書偽造罪を構成します。
この点、参考となる以下の判例があります。
大審院判決(大正4年9月21日)
裁判所は、
- 公文書として成立したるものなる以上は、その内容が真実に適合するものなると否とを問わず、ほしいままにこれを増減変更したるときは、他に実害を生ずると否とにかかわらず、公文書偽造罪を構成るするものとす
と判示しました。
2⃣ すでに外部に対して発表・頒布された文書と全く同じ内容の文書を作成した場合でも、名義の冒用があれば偽造であり、文書偽造罪が成立します。
この点、参考となる以下の判例があります。
大審院判決(昭和5年6月17日)
裁判所は、
- 新聞紙の編集人又は発行人がその紙上に他人の承諾を得ずして同人名義の公告を掲載したるときは、たとえその内容が同人の作成頒布したる既存の文書と同一なる場合といえども、私文書偽造罪を構成す
と判示しました。
3⃣ 文書の内容である事実が、後日実現されても、文書偽造罪の成立に影響を来すものではありません(大審院判決 大正15年11月9日)。