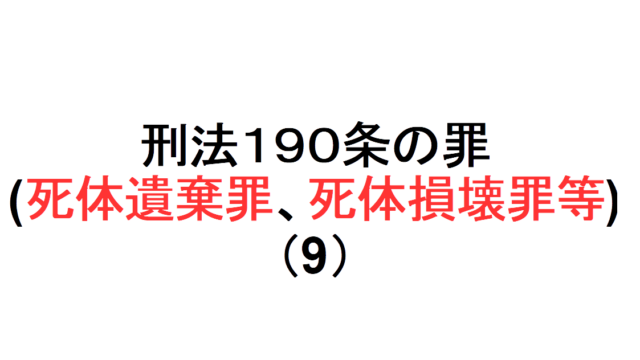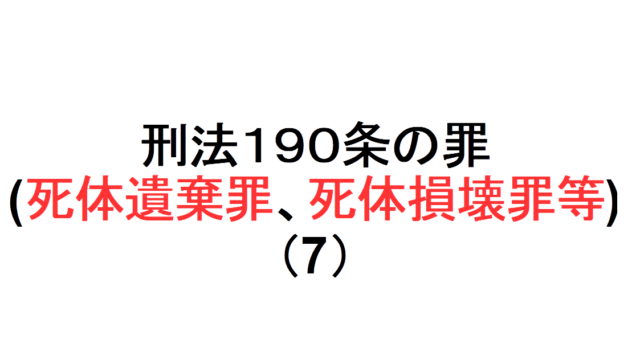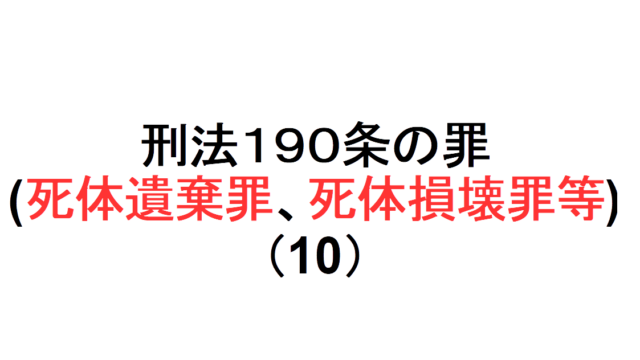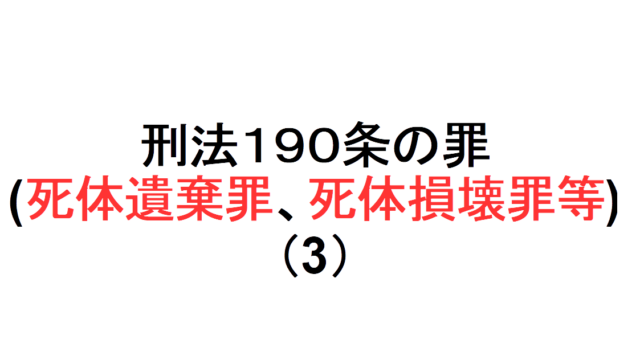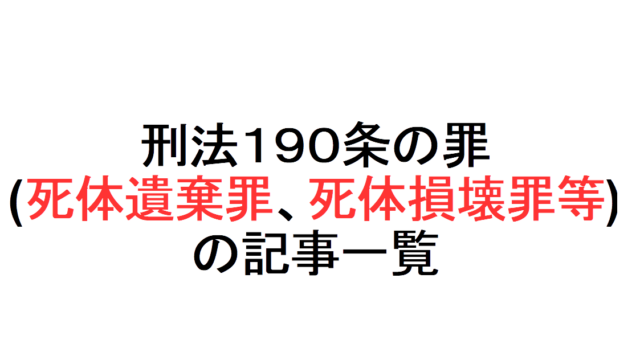死体遺棄罪等(2) ~ 「本罪の客体である『死体』」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、刑法190条の罪(死体遺棄罪、死体損壊罪、死体領得罪、遺骨等遺棄罪、遺骨等損壊罪、遺骨等領得罪、棺内蔵置物遺棄罪、棺内蔵置物損壊罪、棺内蔵置物領得罪)を「本罪」といって説明します。
本罪の客体(死体、遺骨、遺髪、棺に納めてある物)
本罪(刑法190条)の客体は、
- 死体
- 遺骨
- 遺髪
- 棺に納めてある物
です。
なお、墳墓発掘死体損壊等罪(刑法191条)との関係上、刑法190条の罪の客体である死体・遺骨・棺に納めてる物には、不法に発掘して得られたものは含まれないとする以下の判例があります。
大審院判決(大正3年11月13日)
裁判所は、
と判示しました。
不法に墳墓を発掘し、死体・遺骨・棺に納めてる物を損壊するなどすれば、本罪ではなく、墳墓発掘罪(刑法189条)と本罪の結合犯である墳墓発掘死体損壊等罪(刑法191条)が成立します。
ただし、墳墓発掘の犯人から、その死体・遺骨・棺に納めてる物を不法に領得した場合は、本罪(死体領得罪、遺骨等領得罪、棺内蔵置物領得罪)が成立するので留意を要します。
また、本罪である死体遺棄罪には死屍・臓腑等が何人のものに係るかを詳記する必要はないとする判例があります(大審院判決 昭和5年2月18日)。
本罪の客体である「死体」とは?
今回の記事では、本罪の客体である「死体」について詳しく説明します。
「死体」とは、
死亡した人の身体又はその一部
をいいます。
死体の一部も「死体」である
死体の一部も死体です。
したがって脳や臓器も本罪にいう「死体」に該当します。
火葬場で火葬に付する死体の脳を鉄棒で掻きだし領得した事案につき死体領得罪の成立を認めた判例があります(大審院判決 大正14年10月16日)。
遣骨や遺髪も死体の一部ですが、本罪の客体として別に刑法190条に列挙されているから、本罪の死体からは遺骨・遺髪は除かれます。
「死体」には、人の形態を具えた死胎を含む
本罪の「死体」には、人の形態を具えた死胎を含むとするのが判例です。
大審院判決(昭和6年11月13日)は、
- 死胎といえども、稍々人の形体を具ふるに至り、人のこれを葬祭するの程度に達したるものにありては、これを尊敬すべきこと普通死体と異なるところなきをもって、これを刑法190条にいわゆる死体中に包含するものと解せざるべからず
と判示してます。
本罪の保護法益が、「社会的秩序としての一般的な宗教的感情・習俗及び宗教的平隠」であることから、死胎も、人の形態を具えるものであれば死体と同様に宗教的崇敬の対象となり、その宗教的感情も保護に値することになります。
なお、墓地、埋葬等に関する法律2条は、妊娠4か月以上の死胎を死体に含むとしていますが、これは行政規制として一定の基準を設けたものであり、本罪にいう死体に含まれる死胎の範囲は、同法律と直接連動するものではなく、本罪の趣旨に照らして画されるべきものであるとされます。
つまり、妊娠4か月以上の死体であっても人の形態を具えず、崇敬の対象とならないものは含まれない一方、妊娠4か月未満の死胎であっても、それが人の形態を具えており、宗教的崇敬の対象となるものは含まれます。
妊娠3、4か月で流産する胞状奇胎は本罪の死体には含まれません。
「脳死した者の身体」も「死体」に含まれると解される
平成9年に臓器移植法が制定・施行されたことで、臓器移植法にいう「脳死した者の身体」が「死体」とされ、その心臓等の臓器摘出が可能となりました。
これにより、刑法自体の解釈として、臓器移植法にいう「脳死した者の身体」も本罪の客体である「死体」に含まれるものと解すべきであると考えられています(学説)。
つまり、「脳死した者の身体」を遺棄、損壊、領得すれば、死体遺棄罪、死体損壊罪、死体領得罪が成立することになります。
仮死状態は「死体」ではない
仮死状態は脳死とは異なるものであり、いまだ人であって死体ではありません。
なので、仮死状態の者を遺棄、損壊、領得しても、死体遺棄罪、死体損壊罪、死体領得罪は成立しません。
この点を判示した以下の裁判例があります。
裁判所は、
- 刑法190条にいう死体とは心臓の鼓動が完全に停止したものであることを要し、まだ仮死状態にあるものを含まない
と判示しました(札幌高裁判決 昭和32年3月23日)。
本罪の死体には仮死状態を含まないのが原則ですが、行為の時点で死亡していたのか否かが明確でない場合もあり、その擬律に検討を要することもあります。
これに関連する裁判例として以下のものがあります。
殺害行為の寸前に死亡していても殺人未遂であって、死体損壊にはならないとしました。
殺人行為に及んだ後、既に被害者が死亡したものと思い、身元の判明を困難にして犯跡を隠蔽すべく被害者の顔面にダンボール等を積み重ねて顔面を焼損した事案につき、
「被告人が被害者の死亡を確信していたこと、何人も外見上は被害者の死亡に疑いを容れる余地のない状態にあったこと、医学的にも判定が困難であること、頭部の損傷により短時間の死亡が確実であり現に死亡したこと、本件損壊行為が被害者の死亡に何らの原因を与えるものではないこと」
などを理由に、たまたま事後の解剖結果により行為時において被害者の生存の可能性を否定し得ないとしても、死体損壊罪の成立を認め得るとしました。
除雪作業中、妻を誤って雪山に埋投させたが、それに気付かず作業を終えた後に妻がいないことに気付き、雪山を掘ったところ、雪の下から妻を発見したが、その状況から既に死亡していると思い、国道に交通事故を装って遺棄したもので、法医学上の見地のみからは遺棄時における被害者死亡の事実が確定し得ない事案につき、
「鑑定結果に加え、遺棄当時の具体的状況を総合し、社会通念と死体遺棄罪という刑事責任を問い得るかどうかという法的観点を踏まえて、死亡の有無を考察すべきである」
との立場から、被害者死亡の事実を認定して死体遺棄罪の成立を認めました。
大阪地裁判決(昭和46年9月9日)
父親が生後48日の実子を遺棄した事案につき、被害者の死亡時期が不明であり、犯罪の証明が不十分として、死体遺棄罪、保護責任者遺棄罪の双方の成立を否定しました。