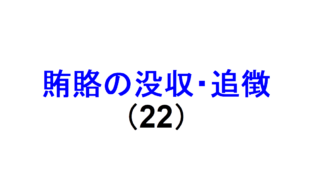賄賂の没収・追徴(23)~「株券の没収・追徴」を説明
前回の記事の続きです。
株券の没収・追徴
株券は、商品券、手形、小切手等の有価証券と同様に没収の対象となります。
株券は、株主権を表象するものであり、株券の没収は、株主権に伴う利益の没収も意味します。
株主の名義が他人でも、実際の所有者が収賄者であれば、株券を没収するのを妨げません。
この点に関する以下の判例があります。
東京高裁判決(昭和29年5月29日)
近親者等他人名義の株券を没収できるとした事例です。
裁判所は、
- 弁護人は、主文第三項掲記の株券は、現在すべて他人名義に属するものであるから、これを没収することができないと主張するのである
- なるほど経済関係罰則の整備に関する法律第4条による賄賂の没収は、その賄賂がなお犯人に属する限り行いうるのであって、これが他人に属するに至ったような場合には、没収を言い渡すことができないと解すべきこと所 論のとおりであり、また本件株券の名義が現在A、B、C、D、E、Fの6名の名義に書き換えられていることも所論のとおりである
- しかしながら、前記の規定が賄賂の没収を規定しているのは、収賄者についていえば、その収賄行為による利益を保持させないためであるから、いやしくも収賄者がその賄賂たる物に対し現に実質的に所有権者と同一の経済上の支配を有する以上は、その名義のいかんにかかわらずその支配を収賄者から剥奪する意味においてこれを没収するのが相当だといわなければならない
- もっともその物が株券である場合においてはなお若干の説明を必要とするのであって、商法第201条第2項によれば、他人を通じてその名義をもって株式を引き受けた者は、その他人と連帯して払込の義務を負うこととされており、これによってみれば、単に株主たる名義を貸したにすぎない者についても会社との間に一定の法律上の権利義務の関係が発生するわけで、むしろ会社との関係ではその名義人が株主たる地位を取得すると解せられる余地もないわけではない
- しかしながら、かりにそのような解釈をとるにしても、これは名義人に対し、その意思を表示したところに従って法律上の責任を負わしめる趣旨に出たもので、名義人を保護するための制度ではないことはいうまでもなく、この場合においても名義を借りた本人がその株券につき株主と実質において何一の支配関係を有するという事実はやはり否定するわけに行かないのである
- 収賄罪における没収の可否はまさにこの実質上の関係に着眼して決せられるべきものであって、かくのごとく収賄者がその賄賂について現に経済的な支配関係を有するにかかわらず、その没収を断念して追徴の方法によらなければならぬとすることは、没収制度の本旨に照らし到底容認することができないといわなければならない
- また、これを名義人の側について考えてみても、この場合その者は当該株式について実質上なんらの経済的利益を有しないものであるから、これを没収しても別段その者に損害を与える筋合ではなく、いわんやその者が名義の貸与を承諾しなかったような場合には商法第201条第1項後段の趣旨からいってもその者は株式につきなんらの利害関係を有しないわけであるから、これを没収しても同人の権利には別段のかかわりを生じないのであるそこで、いま本件について考慮してみると、本件株券の名義書換が単に他人の名義を借りるだけの目的のものであって、この株券に対する経済的支配が今日なお被告人に属していることは、被告人の当公廷における供述、差戻前の第二審における第34回公判調書及び検事の被告人に対する昭和23年11月6日付け聴取書中の被告人の当公廷における供述、差戻前の第二審における第63回公判調書中の証人Cの供述の記載によって明らかであり、 ことに右各証拠から認められるように名義書換に使用した名義人の印章はGが別にそのため作ったものであってこれら名義人の本来所持していた印章ではないこと及び被告人が当公廷において名義書換後においても右株式の配当金はすべて自分が受け取っていると述べていることからしてもこのことは明瞭である
- それゆえ本判決においては右株券の没収を言い渡すこととしたのであって、この点に関する弁護人の主張は採用しない
と判示しました。
株のプレミアムの場合の追徴額の算定
株のプレミアムの場合には、没収の問題は起こらず、追徴のみ問題となります。
この場合の追徴額をどう計算するかが問題になります。
参考となる判例・裁判例として以下のものがあります。
1⃣ 大阪高裁判決(昭和39年12月21日)の原審である京都地裁判決(昭和39年3月18日)
一般に入手不可能な新株、特殊株を気配値より安い売出価額で譲り受けた事案です。
裁判所は、
- 正規の売出価格による代金を支払っているのであってこの場合における賄賂の目的は株式自体ではなく判示一般人に人手することのできない関係にあるものを特に分譲を受けたことによる利益と解するを相当としてその価額を追徴すべく
- 而してその額は当時における…甲株式については近く併合を予定されていた旧株の出来値その余については判示各気配からそれぞれ代金額を控除した差額と見るを相当とする
と判示し、株のプレミアムの追徴額を「一般人に入手することのできない関係にある株を特に分譲を受けたことによる利益」と解してその価額を追徴するとしました。
証券取引所への新規上場に先立つ株式の公開に際し、公開価格で株式の提供を受けた事案については、このような株式を公開価格で取得できる利益が追徴対象となるとした判例があります。
新規上場に先立ち株式を公開価格で取得できる利益が贈収賄罪の客体になるとされた事例です。
裁判所は、
- 券取引所の新規上場に先立つ株式の公開に際し、上場時にはその価格が確実に公開価格を上回ると見込まれ、一般には公開価格で入手することが極めて困難な株式を公開価格で取得できる利益は、それ自体が贈収賄罪の客体になる
と判示しました。
【裁判の内容】
この判決は、証券取引所への新規上場に先立つ株式の公開に際し、公開価格で株式の提供を受けた事案については、間近に予定されている上場時にはその価格が確実に公開価格を上回ると見込まれ、一般人にとってはこれを公開価格で取得することが極めて困難であった場合には、このような株式を公開価格で取得できる利益それ自体が賄賂たり得るとし、公開価格で取得した株式自体ではなく、このような株式を公開価格で取得できる利益が追徴対象となるとしたものです。
この裁判の事件の一審判決(東京地裁判決 昭和56年3月10日)は、上場後の証券取引市場で現実に形成された取引価格(上場始値)と発行価格(公開価格)の差額を賄賂の対象たる利益とし、この差額(当該事案では、一株当たり1330円)を追徴額としましたが、このような構成を採った場合、
- 上場始値の形成により差益が発生しないと収賄罪が既遂にならず、上場始値が公開価格と同額か、あるいはこれを下回るといった不測の事態を生じたときには、収受罪は未遂となり、申込み・要求・約束に当たる場合以外は不処罰とならざるを得ないこと
- 収受時点では賄賂が存在しないのに収受を認めることになること
- 上場始値のみを重視する理由に乏しいこと
などの難点があり、控訴審・上告審では採られませんでした。
控訴審判決(東京高裁判決 昭和59年1月17日)は、賄賂の対象たる利益を、公開株式について「株券交付日にその株主となるべき地位」とし、この地位は「右株式の上場直後の値上がりにより、その上昇した価格と発行価格との差額を取得し得る期待的利益」を含むものと解し、関係証拠に基づいて、賄賂を授受した時点において予測された期待的利益の額を算定して追徴額を決定しました(東京高裁は、堅いところで一株当たり250円としました)。
上告審決定(上記最高裁決定)は、上場に先立つ公開株式の取得時点で賄賂の対象たる利益があるとしており、実質的に控訴審判決と同様の捉え方をしましたが、追徴額の算定については、特に判断を示していません。
3⃣ 同様の問題は、新規上場株に限らず、証券取引を利用して利益が提供される場合に生じ得るところであり、店頭登録予定の未公開株式の譲渡が問題となったものとして、以下の裁判例があります。
リクルート事件株譲渡に関する追徴額について、裁判所は、
- 賄賂である譲渡された本件A2株一万株については、既に売却処分されており、没収することができないから、賄賂相当額を追徴すべきことになるが、その追徴額は、本件A2株一万株が譲渡された昭和61年9月30日における賄賂としての利益の価額であるというべきところ、具体的には、本件賄賂の授受の時点における右A2株一万株の価格から被告人の譲受け価格を控除した額と解される
- そして、関係証拠によると、本件当時店頭登録された株式のうち、分売の方法で株式公開の行われたものの店頭登録日の初値はすべて最高分売価格となっていた上、その後の一般取引開始後の株価は相当期間にわたって初値を上回って推移していたこと、本件当時の株式市場は市況としては全体に好調であり、A2を含む不動産業界は極めて業績が良く、A2の業績も好調であり、これが店頭登録されれば、最高分売価格で初値が決定され、その後の株価も相当な期間にわたって初値以上で推移することが確実であったこと、本件株式の最高分売価格は5270円であったが、翌日以降も右価格以上の取引が続いていたものであり、現実の処分価格も5270円であったことが認められる
- そうすると、本件A2株一万株の価格は5270万円であったというべきであり、その購入価格は3000万円であったから、譲渡された本件A2株一万株の賄賂の価額は、5270万円から3000万円を差し引いた、2270万円であるというべきである
と判示しました。
【裁判の内容】
この事件は、いわゆるNTTルート、官界(文部省・労働省)ルート、政界ルートを含む一連の事件です。
元内閣官房長官に対する受託収賄罪の成立を認めた上記東京高裁判決は、1か月後に店頭登録されることが予定されており、店頭登録後確実に値上がりすることが見込まれ、一般人が入手することが極めて困難であるリクルート社の株式を、
店頭登録後に見込まれる価格より明らかに低い価格で譲り受けて取得したことをもって、賄賂を収受した
と認めた上、追徴額については、
リクルート株が譲渡された時点における賄賂としての利益の価額、具体的にはその時点におけるリクルート株の価格から譲受け価格を控除した額
とし、その時点でのリクルート株の価格については、
- 本件当時店頭登録された株式のうち、分売の方法で株式公開の行われたものの店頭登録日の初値はすべて最高分売価格となっていたこと
- その後の一般取引開始後の株価は相当期間にわたって初値を上回って推移していたこと
- 本件当時の株式市場は市況としては全体に好調であり、リクルート社を含む不動産業界は極めて業績が良く、リクルート社の業績も好調であり、これが店頭登録されれば、最高分売価格で初値が決定され、その後の株価も相当な期間にわたって初値以上で推移することが確実であったこと
- 店頭登録の翌日以降も最高分売価格以上の取引が続いており、現実の処分価格も同価格であったこと
から、店頭登録の初値と同額としました。
一連の事件の他の判決も、同様の方法で追徴額を算定しています。