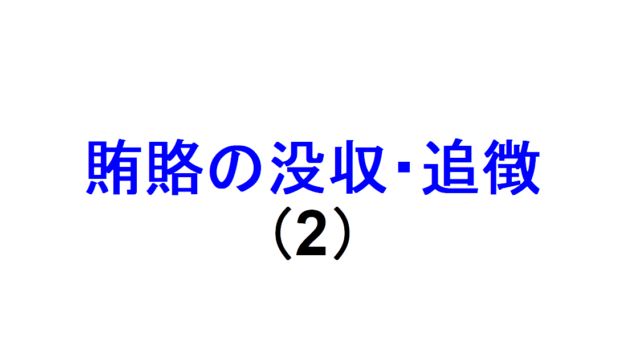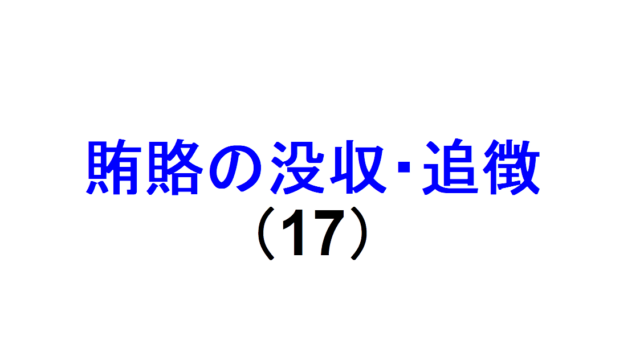賄賂の没収・追徴(6)~「贈賄者からの没収・追徴 その1」を説明
前回の記事の続きです。
贈賄者からの賄賂の没収・追徴 その1
贈賄者は、賄賂を収受する者ではないので、通常は、贈賄者が没収・追徴の対象者となることはありませんが、賄賂が収賄者や第三者に収受された後に、贈賄者に返還された場合には、贈賄者から没収・追徴すべきかが問題となります。
この問題に対する説明は、
- 収賄者が収受した賄賂が贈賄者にそのまま返還された場合
- 収賄者が収受した賄賂に相応する対価が贈賄者に返還された場合
- 収賄者が収受した賄賂の一部を贈賄者に交付した場合
- 収受した賄賂を費消後に同額を贈賄者に返還した場合
- 収賄者が賄賂の一部を費消、混同したりした後、これを補填して、全額を贈賄者に返還した場合
- 収賄者から贈賄者に返還された物が、賄賂そのものか代替物か分からない場合
に分けて、贈賄者から賄賂を没収すべきか否かを説明します。
この記事では、①、②について説明します。
①「賄賂が収受されたものの、そのまま返還された場合」に贈賄者から賄賂を没収すべきか?
賄賂が収受されたものの、そのまま返還された場合につき、大審院判決(明治45年5月6日)は当初、収賄罪成立後、賄賂を返還しても、収賄者から追徴すべきであるとしていました。
その理由は、
「没収は収賄者のみに対する一つの付加刑にして刑法は贈賄者に対しては右付加刑を科する規定を設けぜればなり」
とし返還行為は、単純費消行為と同一であるとしていました。
その後、大審院判決(大正11年4月22日)は上記判例の見解を改めて、
「法の精神は一旦授受せられたる賄賂の目的物又はその価額は常にこれを国庫に帰属せしめ収賄者又は贈賄者をして犯罪に関する利益を保持し又は回復せしめざることを目的とすること明白なるが故に、賄賂についてはこれの特別の規定を適用し、その目的物にして収賄者の手にあるときは収賄者よりこれを没収し、もし贈賄者に返還せられたるときは贈賄者よりこれを没収すべく…」
「または没収を科せらるべき収受者又は贈賄者より没収すること能わざるときはその者より価額を追徴し、賄賂を返還したる収受者に対しては価額を追徴することなし」
と判示し、その理由として、本条の前身である刑法197条2項の規定は、
「同第1項の場合における要求又は約束の目的物と既に収受したる賄賂とを区別し、これの授受せられたる利益は絶対的にこれを国庫に帰属せしむることを主旨とするのみならず、その物が贈賄者の手に返還せられるも、猶収受したる賄賂たる性質を変するものに非ざるが故にこれの場合には…右規定を贈賄者に適用するをもってむしろ法の精神に合致するもの」
としました。
その後、最高裁決定(昭和29年7月5日)も、
「刑法197条の4 (現行法:刑法197条の5)の規定は没収又は追徴の対象範囲を定めた規定であって、何人についてこれを言い渡すかの点についてまで規定したものではないと解するのを相当とし、本件のように、収受された賄賂が贈賄者に返還せられ贈賄者においてこれを費消した場合に、右の規定によって贈賄者よりその額を追徴することを不当とすべき理由はない」
として、贈賄者に賄賂が返還せられときは贈賄者から賄賂を没収するのを相当と考える立場に立ち、その後これが確立された判例となっています。
没収・追徴の付加刑的性格を考えると、賄賂の返還は単なる費消行為とする大審院の当初の考え方も一概には否定できませんが、刑法197条の5の立法趣旨を重視し、利益の剥脱を趣旨とする限り、公平の観点からも現在の判例の立場が正しいと考えれています。
なお、贈賄者が共同正犯で、その中の一人が賄賂の返還を受けた場合には、その者から没収又は追徴すべきと考えられています。
②「収賄者が収受した賄賂に相応する対価が贈賄者に返還された場合」に贈賄者から賄賂を没収すべきか?
賄賂そのものではなく、贈賄者に賄賂に相応する対価を返還した場合については、賄賂を収賄者が享受したことは明らかなので没収・追徴の対象となり、しかも、その対象は、賄賂を享受した収賄者ということになります。
裁判例として、
- 背広を収賄した後代金を贈賄者に支払った場合につき、背広の賄賂たる性質は残るから没収できるとしたもの(東京高裁判決 昭和27年12月22日)
- 賄賂として債務免除を受けた場合には、そのために代金を贈賄者に支払っても、賄賂そのものの返還ではないので、収賄者から債務相当の追徴ができるとしたもの(山形地裁酒田支部判決 昭和49年2月15日)
があります。