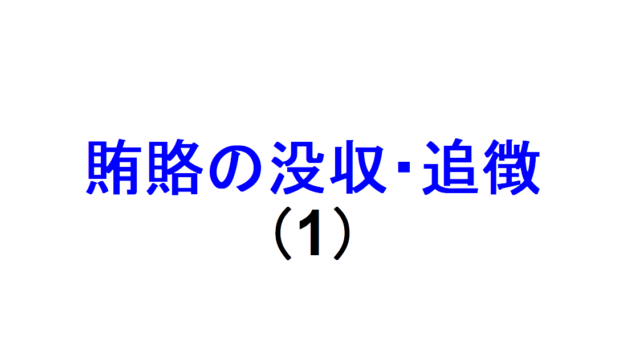贈賄罪(2)~「賄賂の『供与』とは?」「賄賂罪の供与罪の既遂時期」を説明
前回の記事の続きです。
賄賂の「供与」とは?
贈賄罪(刑法198条)の行為は、
- 収賄者に賄賂を供与し、賄賂の申込みをし、又は、収賄者との間で賄賂の約束をすること
です。
単純収賄罪は、刑法197条1項前段において、
- 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する
と規定されるところ、
- 贈賄罪の「供与」は収賄者の「収受」に対応する行為
であり、
- 贈賄罪の「申込み」は収賄者の「要求」と対比する行為
となっています。
この記事では、収賄罪の「供与」について説明します。
「供与」は相手方となる公務員が賄賂を受け取ることを要する
「供与」とは、賄賂を単に提供するにとどまらず、
相手方となる公務員が受け取ることが前提
となっています。
賄賂を提供したが、相手が受け取らない場合には、単に賄賂の「申込み」にとどまり、「贈賄罪の供与罪」は成立せず、「贈賄罪の申込罪」が成立するにとどまります。
「申込み」は、その意味で、収賄罪とは必要的共犯とはなりませんが、「供与」は収賄罪の「収受」と必要的共犯の関係にあり、「贈賄罪の供与罪」を贈賄者に認めながら、「収賄罪の収受罪」を収賄者に否定することは許されません。
この点に関し以下の判例があります。
大審院判決(昭和3年10月29日)
裁判所は、
- 原判決が一面収賄者において賄賂収受の事実を否定したるにかかわらず、被告人に対し賄賂交付の事実を認定したるは、叙上行為の共同を要件とする必要的共犯の概念に照らし失当なりといわざるを得ず
- 賄賂の交付は収受者と交付者の意思合致して賄賂を収受したる場合において認むべきものなればなり
と判示しました。
賄賂が贈賄の相手方である公務員の関係者(第三者)に供与された場合の賄賂罪の供与罪の成否
直接の相手方となる公務員に対してなされず、その妻子など特別な関係にある者に対して行われた場合
「供与」が、直接の相手方である公務員に対してなされず、その妻子など特別な関係にある者に対して行われた場合につき贈賄罪の供与罪の成立を認めた裁判例があります。
賄賂を第三者の実力支配内に置く場合に賄賂罪の供与罪の成立を認めた事例です。
裁判所は、
- 賄賂供与罪の成立には、必ずしも賄賂を直接相手方の実力支配内に置くことを必要とせず、捜査に手心を加えてもらう意図のもとに巡査部長A方に至り、同人の妻に対し清酒三升を提出して、A及び同警察署勤務巡査B、Cに一升宛渡されたいと申し向けたときは、B、Cに対する関係においても賄賂供与罪が成立する
- 相手方がその賄賂を収受し得べき状態にあるときは、これによって賄賂供与罪の成立を妨げない
と判示しました。
この裁判例の事例のように、贈賄の相手方である公務員に直接賄賂が供与されなくても、賄賂がその公務員の実力支配内に入り、その公務員が賄賂の収受行為を容認している状況がある場合は、賄賂罪の収受罪の成立が認められる場合があるといえます。
ただし、いかに公務員と特別な関係にある者が賄賂を収受したとしても、公務員がその賄賂を現実に収受したといえない状況であれば、供与があったことにはならず、単に申込みがなされたにすぎないとなります。
第三者に賄賂が渡された場合は、賄賂であることが明確に伝達されない場合があり、その場合には、たとえ公務員がこれを受け取っても、賄賂の認識がないとして贈賄罪の供与罪は成立しません。
賄賂が第三者に供与された後に、その第三者が公務員に対し、贈賄者の賄賂供与の意思表示を伝えていない場合は贈賄罪の供与罪も申込み罪も成立しない
賄賂が第三者に供与された後に、その第三者(仲介者)が、公務員に対し、贈賄者の賄賂供与の意思表示を伝えていない場合は贈賄罪の供与罪は成立しません。
そればかりかこの場合、贈賄罪の申込罪も成立しません。
もっとも、賄賂供与の相手方となる公務員に対し、贈賄者の賄賂供与の意思が伝達されていれば贈賄罪の申込罪は成立します。
この点に関する以下の判例があります。
大審院判決(大正7年3月14日)
裁判所は、
- 贈賄者が仲介者に委託し、賄賂として金銭を公務員に交付せしめんとする場合において、仲介者が公務員にこれを交付するに当たり、賄賂なること示してその収受を促し、又は公務員において賄賂なることを了知し得べき事情の下にその収受を促すことなく、賄賂提供の意思表示が公務員に伝達せられざるときは、たとえ該金銭が公務員に交付せらるるも賄賂交付罪(※現行法:賄賂の供与罪)はもちろん、賄賂提供罪(※現行法:賄賂の申込罪)も構成せざるものとす
と判示しました。
賄賂が第三者に供与された後に、公務員が賄賂の受取りを拒否し、直ちに返還のための行為を行っていた場合は贈賄罪の供与罪は成立しない
賄賂が第三者に供与された後に、公務員が賄賂の受取りを拒否し、直ちに返還のための行為を行っていた場合も贈賄罪の供与罪は成立しません。
この点に関する以下の判例があります。
裁判所は、
- 賄賂供与申込罪の成立には、相手方に賄賂たることを認識し得べき事情の下に金銭その他の利益の収受を促す意思表示をなせば足りるのであつて、相手方において実際上その意思表示を又はその利益が賄賂たる性質を具有することを認識すると否とは、同罪の成立に影響を及ぼすものではない
と判示しました。
※ 収受者の賄賂性の認識・故意の説明は、単純収賄罪(22)の記事参照
賄賂罪の供与罪の既遂時期
1⃣ 贈賄者の供与行為が完了しても、賄賂が相手方に伝達されない限り、既遂にはなりません。
相手方が賄賂を収受して、初めて賄賂罪の供与罪が成立することになります。
この点に関する以下の判例があります。
- 公務員A、Bに各別に贈賄する意思をもって、金員二口をAに交付した場合、その時にAに対する供与罪が成立するが、Bとの関係では、AがBに交付した時に供与罪が成立し、両者は別個の贈賄行為で併合罪になる
としています。
賄賂罪の供与罪の既遂時期はこのように解さざるを得ないので、両者を観念的競合と解することはできないと解されています。
2⃣ 数人が贈賄のための金員を拠出し、その数人のうちの一人がこれを管理しているにすぎない場合には、供与行為がないので、公務員がそれを知っていても、贈賄罪の供与罪は成立しません。
この点に関する以下の裁判例があります。
大阪高裁判決(昭和32年11月9日)
贈賄のため一定の割合による謝礼金を拠出しこれを贈賄者の1人が保管している場合にお いてその現実の支配が未だ収賄者に移転したものとは認められないとされた事例です。
裁判所は、
- 贈賄、収賄の各罪において、賄賂を供与し、これを収受したとなすには、原判決の説示するとおり、その目的物に対する現実の支配の移転がなければならないものと解すべきであって、今本件についてこれをみるに前示三社から拠出する謝礼金は落札の都度直ちに被告人に手渡されず、これを積立てておき、ある時期に至って初めて同人に現実に交付されるものであることは当該関係人のすべてにおいてこれを了承していたこと、而して外形の実際面から みても被告人竃谷が右拠出金の保管占有をしており、落札の都度には拠出された金員が被告人Tに交付されていないことが明白であるから、これらの事情に鑑みればいずれは被告人Tに現実交付されるにしても、三社から一定の割合による謝礼金を醵出し、被告人Kにその保管を託しただけでは未だその拠出金に対する現実の支配が被告人Tに移転したものでないとみるのが妥当な見解である
- たとえ被告人Kが拠出金を保管する間において、随時被告人Tに現在高を報告してその了解を求めた事実があったにせよ、それは被告人Tが将来右金銭を取得する立場にある関係上なされたところに過ぎず、それがため右金銭について現実支配を取得したということはできない
- 更に又被告人Kが右拠出金を流用するに当たり、被告人Tに承認を求め同人においてその流用を了解したとしても、これまた原判決の説明するように、将来の取得者として予定せられ、利害関係の最も深い同被告人にその承認を求めたというに過ぎないものとみるべきであって、被告人Tに対し現実支配が移転しない間における一事態にほかならず、かような事実あるが故に、拠出の都度その金銭が被告人Tの現実支配下に在ったといい得ないはもちろんこれによって拠出金に対する現実支配が被告人Tに移転したものとみることはできないのである
- 前示証拠に照し考察するに、被告人Kが拠出金を流用したのは将来被告人Tに贈賄さるべきものを、その保管のままの状態において流用がなされたのであり、被告人Tから自己の現実支配する金銭を被告人Kに貸付けたとか、あるいは又贈賄者以外の第三者に賄賂を供与せしめたとかいうが如き関係でなく、而して又被告人Tが被告人Kに請求したのは積立拠出金を自己に現実交付する旨請求したのであって、貸付金返済の請求の趣旨ではなかったこと、そして被告人Kが前示現金、約束手形を交付したのは前示謝礼拠出金を現実に被告人Tに手渡す意思の下になされたことが窺われるのである
- これを所論の如く被告人Tからの貸付、被告人竃谷からのその返済の事実関係であるとは証拠上到底認め得ないのである
- 以上説示するところから考えれば、結局被告人Tが被告人Kに約束に基く謝礼金の交付を請求した結果、原判示のように昭和27年3月中旬頃被告人Kからその一部として現金50万円、約束手形4通金額合計250万円の交付を受けたとき初めてそれについての現実支配の移転があって、これに関する贈収賄罪が各成立するに至ったものと判定すべきである
と判示しました。