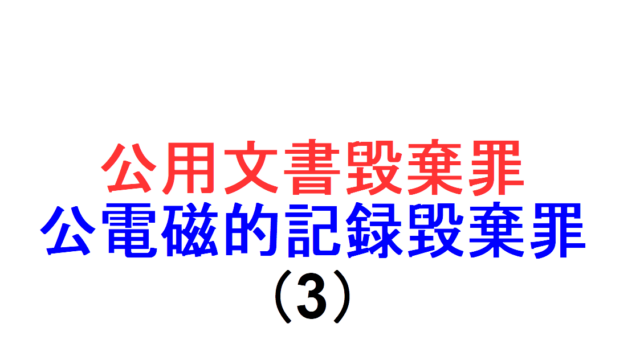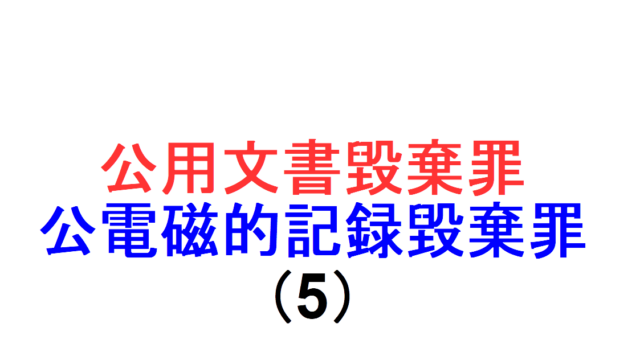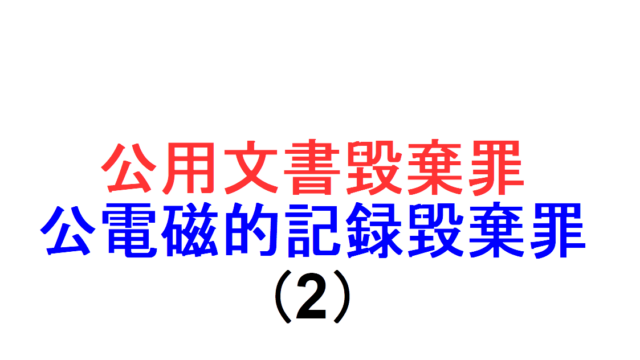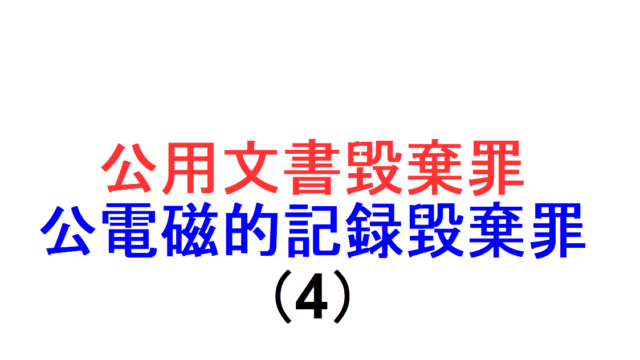公用文書等毀棄罪(1) ~「公用文書毀棄罪、公電磁的記録毀棄罪とは?」「主体・客体」「『文書』の意義」などを説明
これから5回にわたり、公用文書毀棄罪、公電磁的記録毀棄罪(刑法258条)を説明します。
この記事では、公用文書毀棄罪、公電磁的記録毀棄罪を「本罪」と言って説明します。
公用文書毀棄罪、公電磁的記録毀棄罪とは?
公用文書毀棄罪、公電磁的記録毀棄罪は、刑法258条に規定があり、
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する
と規定されます。
本罪は、
- 公務所の用に供する文書
又は
- 公務所の用に供する電磁的記録
を毀損することによって成立します。
罪名
「公務所の用に供する文書」を毀棄した場合の罪名は、「公用文書毀棄罪」となります。
「公務所の用に供する電磁的記録」を毀棄した場合の罪名は、「公電磁的記録毀棄罪」となります。
本罪の性格(財産損壊罪と公務妨害罪の性格)
本罪は、同じ毀棄罪である
と異なり、財産損壊罪としての性格があるとともに
公務妨害罪としての性格
を併有している点に特色があります。
主体(犯人)
本罪の主体(犯人)について、特段の限定はありません。
客体
本罪の客体は、
- 公務所の用に供する文書
又は
- 公務所の用に供する電磁的記録
です。
「公務所の用に供する文書」の「文書」とは?
本罪の客体となる「文書」は、
特に信用性保持の必要性の高度なものとして意思又は観念を表示した書面(文書)に限定される
と解され、それ以外の書類は、本罪の補充規定である器物損壊罪(刑法261条)の客体となるものと解されています。
判例も本罪の文書性について、「意思表示の記載」であることをメルクマールにしています。
大審院判決(昭和7年12月26日)
開票中の選挙投票紙を焼却した行為について、それが投票数を増減させる罪(旧刑233条)に該当することはあっても、「文字による意思表示の記載を包含しない投票紙は文書の範囲に属せず」として公用文書毀棄罪の成立を否定しました。
大審院判決(昭和11年7月23日)
青森県の印を押捺した衆議院議員選挙投票用紙を抜き取り毀棄した事例について、刑法258条の文書は「思想の記載」であることを要するところ、同用紙は、「正規の用紙として当該選挙の投票に使用せらるべき紙片たることの表示あるにとどまるものにして、これを一種の記号と認むるを得べきも、未だこれをもって文書なりと為すに足らず」との理由でその文書性を否定し、公用文書毀棄罪の成立を否定しました。
このほかに、参考となる判例・裁判例として以下のものがあります。
大審院判決(明治39年11月2日)
他の官庁が発布した法令を謄写・印刷した局報は、官文書に該当せず、器物損壊罪の対象になるとしました。
神戸地裁判決(平成3年9月19日)
公立高校の入試答案について、その高校の教員が誤った解答部分を消しゴムで消去した上で正解答を記入する方法で改ざんを加えた行為について、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)、偽造有印公文書行使(刑法161条1項)のほかに、公用文書毀棄罪が成立するとしました。
文書の永続性の要否
本罪の成立を認めるに当たり、文書の永続性が必要か否かという点について、必ずしも長期間の継続を要するものではなく、当該記載文言の内容の伝達に必要にして十分な期間にわたり、文字又は記号が物体上に固定され読解できれば足りると解すべきとされます。
また、「文書」(その上に文字又は符号が記載される物体)は、必ずしも紙であることを要せず、黒板や陶器の上に書かれたものも文書と認めるのが判例があります。
ただし、砂上に書かれた文字については消極に解すべきとされます。
この点、参考となる以下の判例があります。
大審院判決(明治43年9月30日)
裁判所は、
- 文書とは、文字若しくはこれに代わるべき付合を用い永続すべき状態において、あるいは、物体の上に記載したる意思表示を指称す
- 而して、その物体の種類については何らの制限なし
と判示しました。
数時間後には当然消去されるべき国鉄駅待合室掲示板に白墨で書かれた記載文言の全部を、黒板拭きをもって抹消した行為について、
- 刑法第228条にいう「公務所の用に供する文書」とは、公務所において現に使用し又は使用に供する目的で保管している文書を総称し、その文書が証明の用に供せられるべき性質を有することを要するものではない
- 日本国有鉄道の駅職員が列車の遅延、運転中止を告げ、これを詫びる旨白墨で記載して駅待合室に提示した急告板を勝手に取りはずし、その記載文言を抹消する行為は、公文書毀棄罪を構成する
と判示し、公用文書毀棄罪の成立を認めました。
図画は本罪の客体となりうるか?
本罪の文書には図画を含まないと限定的に解すべきとする見解が多数説です。
理由として、図画については、刑法155条1~3項(公文書偽造罪)などが「文書若しくは図画」と併記しているのに対し、本罪(刑法258条)は電磁的記録の部分を除けば「文書」とのみ規定されていることが挙げられます。
もっとも、図画が文書に引用・添付されるなどして文書の一部となっている場合には、当該文書の構成部分として当該図画の部分についても本罪の客体となると考えられています。
有価証券は本罪の客体となりうるか?
有価証券は、その機能として「有価証券性」と「文書性」の両面を具備しており、必ずしも「有価証券性」は「文書性」の併存を否定するものではないので、有価証券でありながら、なお文書としての側面に着目して文書毀棄罪の対象とすることも十分可能であると考えられています。
判例は、刑法259条の私用文書毀棄罪の客体として
- 手形(大審院判決 大正14年5月13日)
- 小切手(最高裁決定 昭和44年5月1日)
が含まれると解しているので、本罪においても、これらとの整合性のある解釈がなされるべきであるとされます。
信書は本罪の客体となりうるか?
信書が本罪の文書に該当するか否かについては見解が分かれています。
この問題については、信書隠匿罪(刑法263条)の解釈によって決められるところとなります。
信書の文書性は否定できないので、信書が公務所の用に供せられている限り、信書であっても信書隠匿罪ではなく本罪が適用されることになるか否かについて、
- 信書隠匿罪が信書の隠匿だけでなく破棄する等毀棄行為全体を含むとする見解を採れば、信書としての要件を満たす限り、本罪ではなく、信書隠匿罪が適用されるとする結論になる
- 信書隠匿罪は信書の隠匿にのみ限定され毀棄を含まないとする見解を採れぱ、公務所の用に供する信書の毀棄行為は、隠匿の態様による場合を除いて、本罪が適用されることになる
という解釈になります。