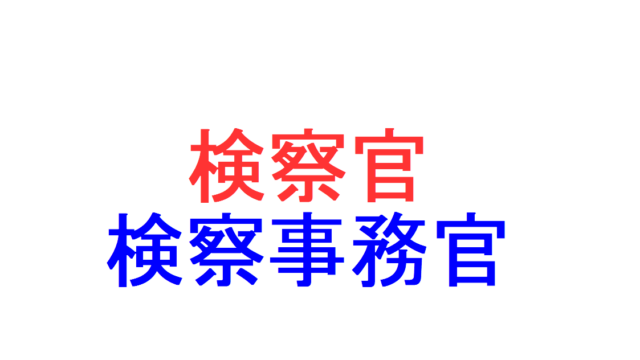弁護人とは? ~「特別弁護人」「弁護人の人数」「接見交通権」「秘密交通権」を刑事訴訟法で解説~
弁護人とは?
弁護人とは、刑事事件において、
犯人の正当な利益を守る弁護活動をする者
をいいます。
たとえば、犯罪を犯して逮捕・勾留された犯人は、法律のド素人なので、法律家である検察官や、捜査のプロである警察官の追求にうまく立ち回れないでしょう。
たとえば、
- 「話したくないことは話さなくていい」という供述拒否権(黙秘権)
- いつでも弁護人を選任できる弁護人選任権
などの犯人に与えられた権利を知らずに、捜査機関から、無理に自白を迫られるかもしれません。
そんな時に、法律家の視点から、「犯人の正当な利益」を守るためのサポートをしてくれるのが、弁護人です。
守るのは「犯人の正当な利益」である必要があります。
なので、例えば、本当は犯罪を犯しているのに、犯人に嘘をつかせて無罪をとりにいくのは正当な弁護とはいえず、やってはいけません。
弁護人の選び方
弁護人は弁護士の中から選ばれる
弁護人は、原則として、弁護士の中から選ばれます。
根拠法令は、刑訴法31条1項にあり、
『弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない』
と規定しています。
弁護人を選んだら、弁護人選任届という書面を検察官か司法警察員に提出します。
根拠法令は、刑訴法規則17条、18条にあります。
【17条(被疑者の弁護人の選任)】
『公訴の提起前にした弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を当該被疑事件を取り扱う検察官又は司法警察員に差し出した場合に限り、第一審においてもその効力を有する』
【18条(被告人の弁護人の選任の方式)】
『公訴の提起後における弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を差し出してこれをしなければならない』
特別弁護人
弁護士の中から選ぶのが原則です。
しかし、例外的に、弁護士以外から選ぶことができる場合があります。
この弁護士以外から選んだ弁護人を
特別弁護人
といいます。
根拠法令は、刑訴法31条2項にあり、
『簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる』
と規定し、裁判所が許可をしたときに、特別弁護人が選任できることになっています。
特別弁護人の例
特別弁護人の例として、
- 学校の教師、雇主などのように被告人と特別な関係にある人
- 事件について特別な学識経験のある人
などが考えられます。
特別弁護人が選任できるのは、被告人だけ
特別弁護人を選任できるのは、簡易裁判所又は地方裁判所に事件を起訴された被告人だけです。
被疑者(起訴される前の犯人)の段階において、特別弁護人は選任できません。
さらに、高等裁判所と最高裁判所で公判中の事件では、特別弁護人は選任できません。許されない(刑訴法387条、414条)。
このことは、判例(最高裁決定 平成5年10月19日)で明確化されています。
この判例において、
- 刑訴法31条2項は、例外として、弁護士でない者を弁護人に選任するいわゆる特別弁護人を選任することができる場合を認めている
- 刑訴法31条2項によりいわゆる特別弁護人を選任することができるのは、公訴が提起された後に限られる
と判示し、特別弁護人を選任できるのは、既に公訴が提起された(起訴された)被告人だけであり、被疑者の段階では、特別弁護人は選任できないことを示しました。
弁護人の人数制限
被疑者の場合
被疑者(起訴される前の犯人)の段階において、原則、弁護人は3人までしか選任することができません。
根拠法令は、刑訴法規則27条1項にあり、
『被疑者の弁護人の数は、各被疑者について3人を超えることができない』
と規定しています。
被告人の場合
被告人(起訴された犯人)の段階においては、被疑者のように弁護人選任の人数制限はありません。
法律上の理論では、総勢100人の大弁護団を結成することもできます。
とはいえ、弁護人が100人もいたら、裁判所の法廷の中が弁護人であふれてしまいます。
そこで、刑訴法規則26条において、
『裁判所は、特別の事情があるときは、弁護人の数を各被告人について3人までに制限することができる』
と規定し、状況に応じて、弁護人を3人まで制限できるようにしています。
弁護人の権限・機能
弁護人には、以下の権限・機能があります。
- 逮捕・勾留されている被疑者との接見(接見交通権、秘密交通権)
- 被疑者に対する裁判所が行った勾留の裁判に対する準抗告の申立
- 勾留理由の開示請求
- 勾留の取消し請求
- 証人尋問の立会
- 証拠保全の請求
これから①~⑥の弁護人の権限・機能ついて説明していきます。
① 逮捕・勾留されている被疑者・被告人との接見(接見交通権、秘密交通権)
弁護人は、いつでも被疑者と会って、被疑者にアドバイスなどを与えることができます。
これを「接見交通権」といいます。
根拠法令は、刑訴法39条1項であり、
『身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる』
と規定し、弁護人が被疑者・被告人と接見する権利を保障しています。
「弁護人になろうとする者」とは?
刑訴法39条1項では、弁護人のほか、「弁護人となろうとする者」との接見も保障しています。
「弁護人となろうとする者」とは、
まだ弁護人選任届を検察官や警察官に提出しておらず、正式に弁護人になっていない弁護士
をいいます。
まず、弁護士も被疑者・被告人に会って話をしてみなければ、被疑者・被告人の弁護人になるかどうかを決めかねます。
なので、正式な弁護人になっておらず、これから被疑者・被告人の弁護人になろうとする段階でも、弁護士は被疑者・被告人と接見することができるルールになっているのです。
秘密交通権
刑訴法39条1項にある「立会人なくして接見」という記載は、見逃せないキーワードになっています。
弁護人が被疑者・被告人と立会人なしで接見できるという意味は、
弁護人と被疑者・被告人の会話内容は誰にも知られないことができる
ということです。
この弁護人と被疑者・被告人の会話内容は誰にも知られないことができる権利を
秘密交通権
といいます。
弁護人と被疑者・被告人は、秘密交通権があるため、捜査機関である警察官や検察官が、弁護人、被疑者・被告人の意に反して、その会話内容を知ることは、違法行為になります。
捜査機関は弁護人が被疑者と接見することを妨げてはならない
刑訴法39条3項は、
『検察官、検察事務官又は司法警察職員(捜査機関)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、(弁護人の被疑者との)接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。ただし、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはならない』
と規定しています。
これは、捜査機関は、捜査に支障がある場合を除いて、
弁護人と被疑者の接見を妨げてはいけない
ことを意味します。
捜査機関が、捜査の理由以外で、弁護人と被疑者が接見を妨げる行為をすると違法になります。
なので、弁護人と被疑者が接見する権利は、捜査機関でも安易に妨げてはならないのです。
ちなみに、被疑者から被告人に変わると、捜査機関は、弁護人と被告人の接見の制限を一切できなくなります。
捜査を理由とした接見の制限もできないということです。
これは、捜査が終わって起訴され、犯人が被疑者から被告人の立場に変わるとともに、犯人と捜査機関の上下関係も対等なものに変わるためです。
被告人は、これから捜査機関を相手にして裁判をたたかう裁判の当事者として、捜査機関と対等になるという考え方です。
また、別の考え方として、検察官は、捜査を尽くして、犯人の有罪を確信した上で起訴しているはずであり、起訴するということは捜査が終了しているとみなすことができるので、起訴後は、捜査機関は、捜査を理由として、弁護人と被疑者の接見の制限はできないのです。
② 被疑者に対する裁判所が行った勾留の裁判に対する準抗告の申立
警察官に逮捕された被疑者は、検察庁に連れて行かれます。
検察官が身体拘束を続ける必要があると判断すれば、検察官は、裁判官に被疑者の勾留を請求します。
そして、裁判官は、被疑者を勾留する必要があると判断すれば、被疑者を勾留する裁判(勾留する判断)を行います。
弁護人は、この裁判官の被疑者を勾留する判断に対して、不服を申し立てることができます。
この不服申し立てを「準抗告」と呼びます。
もっと具体的にいうと、準抗告とは、
刑訴法429条1項に規定する項目についての不服申立て
をいいます。
その項目とは、
- 忌避の申立を却下する裁判
- 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判
- 鑑定のため留置を命ずる裁判
- 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
- 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
です。
弁護人が準抗告を行うのは、主に、②の勾留・保釈に対する裁判に対してです。
弁護人は、身体拘束されている被疑者・被告人をのために、裁判所に対し、「これ以上身体拘束を続ける必要はない!勾留をやめろ!保釈しろ!」と不服を申し立てる(準抗告する)権利をを持っているのです。
③ 勾留理由の開示請求
犯罪を犯すと逮捕されます。
逮捕された後、検察庁に連れて行かれます(「送検」というやつです)。
検察官が、犯人の身体の拘束を続ける必要があると判断すると、裁判官に対して、勾留を請求します。
裁判官が、犯人を勾留する必要があると判断すると、勾留状という令状が発付され、犯人は10日~20日の間、警察署内で勾留されることになります(刑訴法208条)。
ここで、もし自分自身が逮捕・勾留されたとしたら、どのような理由で勾留されているか知りたいですよね?
そこで、弁護人は、被疑者(起訴されていない犯人)・被告人(起訴された犯人)のために、勾留理由の開示を裁判所に求める権利をもっています。
被疑者・被告人が、自分が勾留されている理由を知る権利は、憲法34条で保障された権利です。
具体的には、被告人の場合と被疑者の場合に分けて、刑訴法に規定されています。
以下で詳しく説明します。
被告人の勾留理由の開示請求
まず、弁護人が、被告人の勾留理由の開示請求ができる法的根拠は、刑訴法82条2項にあり、
『勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。』
『勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる』
と規定されています。
裁判所は、勾留の理由を開示できる権限をもっているので、弁護人は、裁判所に対し、勾留理由の開示請求ができるのです。
被疑者の勾留理由の開示請求
次に、弁護人が、被疑者の勾留理由の開示請求ができる法的根拠は、刑訴法207条1項にあり、
『勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する』
と規定されています。
この説明を受けて、みんなさんは「分けわからん」となっていると思うので、刑訴法207条1項の理論を説明します。
まず前提として、一人の裁判官が持つ権限より、組織体である裁判所が持つ権限の方が大きいです。
そして、前述のとおり、裁判所は、被告人に対して、勾留の理由を開示できる権限をもっています。
ここで、刑訴法207条1項の規定により、被疑者の勾留に関する処分を行う裁判官は、権限がグレードアップされ、裁判所と同じ権限があると見なされます。
これにより、被疑者の勾留に関する処分に関しては、一人の裁判官の権限は、組織体である裁判所の権限と同じ権限になります。
裁判所は、被告人に対して勾留の理由を開示する権限があるのだから、裁判官は被疑者に対して勾留の理由を開示できるという理論になります。
④ 勾留の取消し請求
弁護人は、
「勾留されている被告人・被疑者が、これ以上勾留される必要はない!」
と判断したときに、裁判所に対し、勾留の取消しを請求する権限を持っています。
根拠法令は、刑訴法87条にあります。
⑤ 証人尋問の立会
事件が裁判になると、事件の目撃者などが裁判に呼ばれ、裁判官の面前で、事件を目撃したときの状況を証言することがあります。
これを証人尋問といいます。
そして、弁護人は、この証人尋問に立ち会う権利を持っています。
根拠法令は、刑訴法228条2項(228条2項は、226条・227条を引用)にあり、
『被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる』
と規定されています。
⑥ 証拠保全の請求
裁判になると、検察官は犯罪の有罪を証明する証拠を裁判官に提出します。
逆に、弁護人は、犯罪の無罪を証明する証拠など、被告人に有利に働く証拠を裁判官に提出します。
弁護人としては、被告人に有利に働く証拠が、何らかの事情でなくなっては困るわけです。
そこで、弁護人は、裁判所に対し、証拠がなくならないように、証拠を保全するよう請求する権利を持っていま。
根拠法令は、刑訴法179条にあり、
『被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回の公判期日前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる』
と規定しています。
弁護人の活動は捜査の邪魔になってはいけない
上記のとおり、弁護人には、犯人の正当な利益を守るための権利が与えられています。
しかし、これらの権利は、いつでも、どこでも、無制限に行使できるわけではありません。
弁護人は、これらの権利を行使するにあたり、捜査の邪魔になってはいけないというルールになっています。
根拠法令は、刑訴法196条にあり、
『検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他職務上捜査に関係のある者は、被疑者その他の者の名誉を害しないように注意し、かつ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない』
と規定しています。
法で規定される権利以外の権利は弁護人にはない
弁護人に認められるいる権利、上記のような法で規定されている権利のみです。
なので、法に規定されていないことに関しては、弁護人に力はありません。
たとえば、弁護人は、被疑者の取調べや、被疑者の家宅捜索などに立ち会うことはできません。
捜査中においては、裁判に提出する予定の捜査書類を見ることもできません。
ちなみに、犯人が起訴された後は、弁護人は、裁判に証拠として提出する捜査書類を見ることができます(刑訴法40条)。