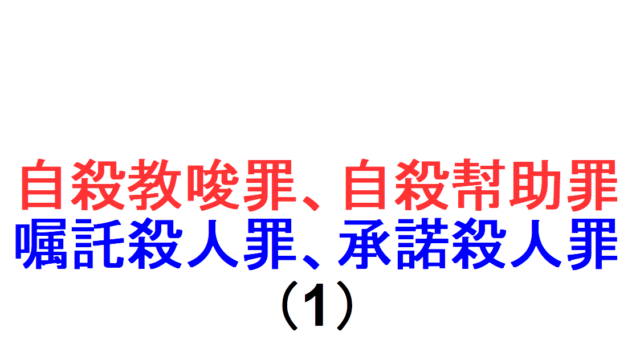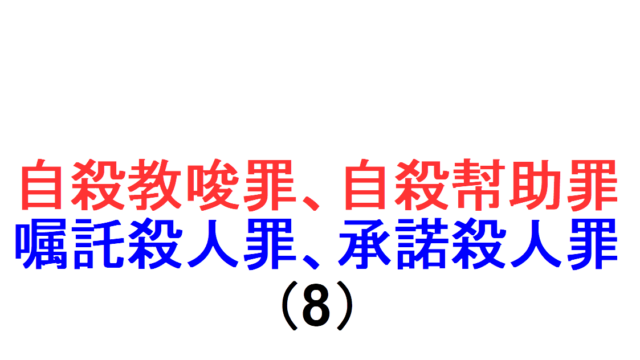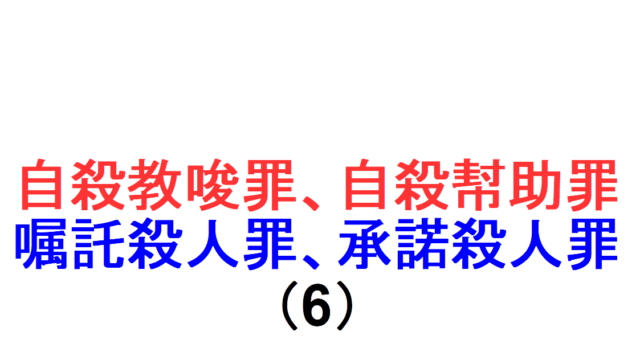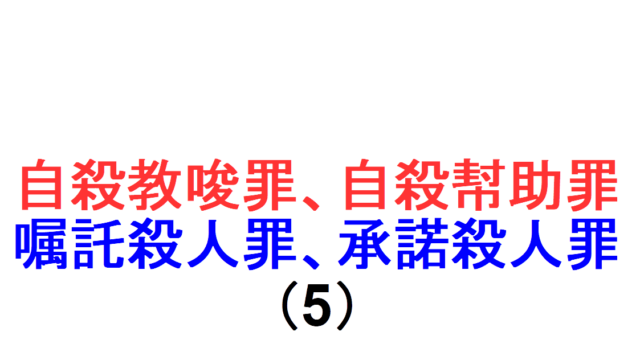自殺教唆・幇助罪、嘱託・承諾殺人罪(2) ~「嘱託殺人罪、承諾殺人罪とは?」を解説~
前回の記事の続きです。
前回の記事では、自殺教唆罪、自殺幇助罪を説明しました。
今回の記事では、嘱託殺人罪、承諾殺人罪を説明します。
嘱託殺人罪、承諾殺人罪とは?
嘱託殺人罪、承諾殺人罪は、被殺者の依頼を受け、又はその承諾を得て、被殺者を殺害する犯罪です。
この場合の嘱託や承諾は、明示的である必要があるのか、黙示的でもよいのかという問題があります。
承諾殺人罪における承諾について、必ずしも明示的、積極的であることを要しないとする裁判例(下記の札幌地裁判決 昭和43年2月22日)があります。
嘱託殺人罪における嘱託については、裁判例ではありませんが、学説において、嘱託は言語によると文書あるいは動作によるとを問わないが、明示的になされることを要すると解するものがあります。
結局のところ、嘱託殺人罪における嘱託について、明示的になされる必要があるという考え方と採ったとして、嘱託が明示的でないから嘱託殺人罪が成立しないということになったとしても、被殺者の黙示的な承諾で成立する承諾殺人罪は成立するのであるから、結局、刑法202条の罪が成立することには変わりはないという結論になります。
被殺者の黙示の承諾を認めた事例
被殺者の黙示の承諾を認めた事例として、以下の裁判例があります。
札幌地裁判決(昭和43年2月22日)
生活に窮した夫婦が、共に死ぬことを選択し、夫が妻K子の首を絞めるなどして殺害し、夫は手首を切るなどして死のうとしたが死にきれなかった事案で、検察官が夫には殺人罪が成立すると主張したのに対し、裁判官は、殺人罪ではなく、承諾殺人罪が成立するとした事例です。
裁判官は、
- 検察官主張の如く、K子を無理に殺害したものとするには、(1)被害者の死体に抵抗した形跡が全く認められないことがどうしても納得できないといわなければならない
- この点について、被告人は、(2)被害者の首に手をかけて「おれと一緒に死んでくれ。」と言ったときに、K子は何の抵抗もせず、承諾したかのように自らロをとじ、被告人のなすままに任せていたというのであるが、K子の死体の状況と対照して考えると、被告人の右の供述もあながち虚偽の弁解として否定し去ることはできない
- まして、(3)被告人と被害者とは、人一倍強い愛情で結ばれていた夫婦であって、お互いに信頼し切っていたとみられること、さらに(4)結婚当初の楽しかった生活に比べてあまりにもみじめで不安定な生活に落ちこんだ事情のもとでは、まだ17歳で冷静に熟慮する余裕とてなかったK子が、一時の感情から死をあえて恐れようとしなかったとしても、あながち理解できないわけではないことなどの諸事情を総合するならば、本件の如き具体的状況のもとでは、被害者がまさに死の直前に、黙示的にではあれ、死について承諾をしたと考えるべき余地は十分にあるといわなければならない
- そして、検察官の主張と異なり、承諾殺における承諾は、必ずしも明示的、積極的であることを要しないと解すべきである
- そうすると、被告人の本件殺害行為については、被害者の承諾がないとの検察官の主張に対しては、合理的な疑いを入れる余地があるものと言わなければならない
- 被告人がK子を殺害した事実は、前掲各証拠により十分認められるところであり、ただ、被告人の行為について、刑法199条の通常の殺人罪の刑責を問うためには、検察官において同法202条にいう被殺者の承諾がなかったことについて立証責任を負わなければならないのであって、右のように、この点が十分に立証されていない本件においては、被告人に対して、通常の刑を科することはできず、被告人の行為は承諾殺として、同法202条に規定する限度でのみ刑事責任を負うこととなる
と判示し、承諾殺人罪が成立するとしました。
新潟地裁判決(昭和46年11月12日)
被告人である母が、長女Bと心中を図り、被告人が長女の首をして殺害した事案で、検察官が被告人には殺人罪が成立すると主張したのに対し、裁判官は、殺人罪ではなく、承諾殺人罪が成立するとした事例です。
裁判官は、
- 長女Bから被告人に対して殺害の嘱託があったとまでは認められないとしても、Bは被告人と一緒に死ぬことについては堅い決意があったが、その具体的なやり方については全面的に被告人の為すがままに委ねていたものと認めるのが相当である
- このことからすれば、もし殺虫剤を飲んでも死に切れなかったときには、そこで中止するのではなく、他の適当な方法で(常識的に見て奇異な、あるいは残虐な方法でない限り)被告人の手で殺されることにつき、遅くとも殺虫剤を受け取って、飲んだ時点で、黙示の承諾を与えたものと認めるのが相当である
- なお、検察官は被告人が生き残ったことをとりあげ、被告人自身は本当に死ぬ気がなかったのではないかと疑い、そこからも承諾のない殺人であることを裏付けようとしているかのように見えるが、関係証拠によれば、被告人がBだけを殺して自分は生きていようとしたことを窺わせる事情は全くない
- 現実にも被告人はBを殺害したのち、後に述べるようにBよりも多い量の殺虫剤を飲み、それでも足りないかと思い、左腕の動脈を注射器の針で所在を確かめた上で、その付近をかみそりで切ったことが認められるので、その場でとりうる方法としては特に不足であったとはいえないし、右の自殺をはかった後、約半日間は意識不明で生死の境をさまよっていたのであり、もし発見が遅れて手当が加えられなかったら死亡するに至ったことも十分考えられることなどから見て、被告人の自殺をはかった行為は真剣なものであったと認められ、この点の検察官の主張は採用できない
- 以上述べたように、本件は普通殺人ではなく、被告人の殺害に対して被害者の任意かつ真意から出た承諾があった承諾殺人と認定すべきものであり、これを争う検察官の主張は理由がない
と判示し、承諾殺人罪が成立するとしました。
被殺者の承諾の存在を認めなかった事例
上記事例とは逆に、被殺者の承諾の存在を認めなかった事例として、以下の裁判例があります。
東京高裁判決(昭和58年8月10日)
一家心中を図り、妻が夫に鎮静剤を飲ませ、夫が鎮静剤の作用で熟睡中に夫を殺害した事案で、夫は熟睡中で承諾をなし得るような状態ではなかったとし、承諾殺人罪ではなく、殺人罪が成立するとした事例です。
裁判官は、
- 本来、刑法202条所定の被殺者の承諾は、事理弁識能力を有する被殺者の任意かつ真意に出たものであることを要するとともに、それが殺害の実行行為時に存することを必要とするところ、本件の被殺者(夫D)は、殺害の実行行為の時点においては、被告人に飲まされた鎮静薬の作用により熱睡中であって、右の承諾をなし得るような心神の状況にはなかったのである
- 夫Dは、飲まされた鎮静薬の作用で入眠するに際し、被告人に「起こせよ。一人でやるなよ。」と命じているのであるから、一家の首長として、一家心中の実行を自らの決断と指示にかからせる意思を表明したものと見られるのであって、睡眠中に被告人によって殺害されることは、夫Dの最も予想しない事態であったものと言わざるを得ない
- 本件殺害行為の時点においてはもとより、就寝直前の時点においても、夫Dに刑法202条所定の承諾があったものとは認められない
と判示し、夫Dの殺害の承諾はなかったとし、承諾殺人罪は成立せず、殺人罪が成立するとしました。
嘱託殺人の嘱託・承諾の存在を認めた事例
殺人の嘱託・承諾があったと認め、嘱託殺人又は承諾殺人が成立するとした事例として、以下の裁判例があります。
大阪高裁判決(昭和29年12月18日)
被告人が交際相手の女性A子と心中を図り、被告人が女性の喉を数回ついて殺害した事案で、情況証拠により殺人の嘱託があったと認められ、殺人罪ではなく、嘱託殺人が認定された事例です。
裁判官は、
- 本件事案におけるように情死の約束をした一方が既に死亡してしまっている場合において、果して同人の嘱託があったかどうかを判断するには、当時の状況を総合して判定するのが最も合理的である
- 生き残った他方の者が嘱託があったと供述すれば嘱託殺人になり、嘱託があったものと考えたと供述すれば通常殺人になるというように機械的に決定すべきものでないこと、いうまでもない
- 本件においては、前に掲げたように(イ)情死することについて十分な合意があったと認められること、(ロ)頸部以外に外傷はないこと、(ハ)格闘の跡が全くないこと、(二)頸部前方の創は未経験者が自分で喉を突くという常識的な自殺方法として考えられること、(ホ)夕闇せまり人通りもなくなるまでニ人で遊んでいて相互に信じ合って行動していたこと、(ホ)被殺者A子が自分で自分の喉を突いてから被告人の方に倒れかかってきて出刃包丁を差し出すように被告人の目の前に出したことなどの状況を総合すると、被告人においてA子が殺害を嘱託したものと判断したのはA子の真意に合致しており、本件殺害は被殺者A子の真意に基く嘱託によるものであったと認めるのが相当である
と判示し、情況証拠から嘱託殺人を認定しました。
福島地裁判決(昭和34年5月20日)
被告人が既婚者で、夫婦になれないことに悲観した被告人と不倫相手のB子が心中を決意し、被告人がB子を刺殺した事案で、嘱託殺人罪の成立を認めた事例です。
裁判官は、
- B子が肌着をまくり上げて、左乳房下付近を被告人に示しながら「父ちゃんここだ」と告げ、被告人に自己の胸部を突き刺し殺害すべきことを依頼し、被告人はこれに応じて直ちに所携の牛刀を右手に持ってB子の心臓部めがけて1回突き刺し、よってB子を心臓刺創に基づく失血により死亡させ、B子の嘱託を受けてB子を殺害した
とし、嘱託殺人が成立するとしました。
横浜地裁判決(平成11年10月6日)
被告人が介護していた寝たきりの母親を殺害したとして殺人罪で起訴された事案において、被害者が殺人について承諾をしていた可能性が否定できないとして承諾殺人罪を認めた事例です。
裁判官は、
- 被害者が被告人の介護に満足していて、できれば入所したくないと思う一方で、病状が悪化するにつれ次第に弱気になり、また被告人に迷惑をかけて申し訳ないという気持ちを強めていたことは想像に難くなく、被害者に「死にたい」という確定的な意思はなかったとしても、「死んでもかまわない」という程度の消極的な気持ちがあったと見る余地は十分にある
- 本件犯行時、被害者が被告人の真剣な様子を感じ取り、その殺意に応じて死んでもかまわないとの思いから、真意に基づく承諾をした可能性は否定できないと言うべきである
- このことは、犯行の際、被害者が抵抗をしたことを認めるに足りる的確な証拠がないことからも窺われる
- 被告人の本件殺害行為について、被害者の真意かつ任意の承諾がないと認めるには、なお合理的な疑いを容れる余地が十分あるものと言わなければならない
と判示し、承諾殺人が成立するとしました。
被害者の嘱託又は承諾に先立ち、犯人が殺意を有していた場合は、殺人罪が成立する
被害者の嘱託又は承諾に先立ち、犯人が殺意を有していた場合には、殺害の実行行為の際に被害者が嘱託又は承諾に及んでも、嘱託殺人罪又は承諾殺人罪ではなく、殺人罪が成立すると解されます。
参考となる裁判例として、以下のものがあります。
大阪高裁判決(昭和29年7月30日)
親子心中を企て、娘Aを絞殺した事案です。
裁判官は、
- 刑法第202条の定める「被殺者の嘱託を受け、若しくはその承諾を得てこれを殺す」(※旧法の条文)いわゆる同意殺人罪たるには、犯人の殺意が被殺者本人の嘱託又は承諾のあることにより初めて生じたときに限るものと解すべきである
- 本人の嘱託又は承諾に先立ち、既に犯人においてこれを殺害するの決意を有する場合は、その意思実行に際して、たとえ本人が嘱託又は承諾に及んだとしても同意殺をもって問うべきでなく、刑法第199条の普通殺人罪の所為が行われたものとして同罪の成立を認定すべきである
- 本件についてみるに、被告人は、娘A殺害現場に至る以前、Aを家から連れ出すときより既にA殺害の決意をなしていたことが明白であるから、その後、右現場においてAが被告人に対し早く殺してくれと言いながら自ら所持していた手ぬぐいを首の前から後へ回した所為に及んだことが窺えるところであるけれども、そのような事跡があったからとて叙上説明に照らし、普通殺人罪の認定を妨げないものというべきである
と判示し、Aの承諾よりも前にAを殺害する決意を有していたため、承諾殺人罪ではなく、殺人罪が成立するとしました。
東京高裁判決(昭和33年1月23日)
被害者Bが被告人に毒を飲まされたことを知りながら、被告人に恨み言を述べなかったというような、殺害行為終了後に承諾を推認させるがごとき事実があったとしても、遡って承諾殺人になるものでないとした事例です。
裁判官は、
- 被害者B(※Bは左半身付随)は、被告人に時々「死にたい」「死にたい」とロ走ったことがあり、昭和30年夏頃からはその回数も多くなり、時には薬局から毒薬を買って来て飲ませてくれと言ったこともあるが、Bが死にたいと言うことを口にするのは、便を催すときとか食事をするとき又は身体を拭かせるときなど自分の意のままにならぬのを立腹して言うことが多く、また良い薬があればお前らの手をかけずに死ねると言う趣旨のことを冗談のようにいう状態であった
- Bのこのような言葉は、その本心とは思っていなかった等の事情から見て、Bが本件当日、用便の始末をしていた被告人に対し「死にたい」と言ったと言うのも、これをもって真実被告人に自分を殺してくれることを嘱託した意思表示と認めることはできない
- Bが昇汞(※毒物)の水溶液服用した後、被告人に毒を飲まされたことを知りながら、これについて被告人に恨み言を述べなかったとしても、これにより本件行為が遡って承諾による殺人に当ると解することもできない
と判示し、承諾殺人は成立せず、殺人罪が成立するとしました。
①殺人罪、②殺人予備罪、③自殺教唆罪・自殺幇助罪・嘱託殺人罪・承諾殺人罪の記事まとめ一覧