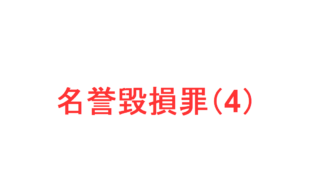名誉毀損罪(5) ~「事実の摘示(名誉を害するに足りる事実の摘示)」「名誉毀損罪と侮辱罪の事実の摘示の違い」を説明~
前回の記事の続きです。
事実の摘示(名誉を害するに足りる事実の摘示)
名誉毀損罪(刑法230条)において、摘示される事実は、
名誉を害するに足りるもの
でなければなりません。
具体的には
1⃣ 個人に対する社会的評価を低下させるもの
あるいは、
2⃣ 社会の一員としての最低限の評価を害するもの
であることが必要です。
この点、参考となる判例として以下のものがあります。
大審院判決(大正5年6月1日)
新聞記事に、「Aが巨額の借金をした」という事実を掲載したという名誉毀損罪の事案で、摘示された事実は、Aの社会的評価を低下させるものではないという趣旨の理由で名誉毀損罪の成立を否定した事例です。
裁判官は、
- 他人が借財を為したる事実を公然摘示したりとするも、現代の社会観念に照し、直ちにこれを人の社会上の地位又は価値に侵害を加うるものと断ずるを得ず
- 問題の新聞記事は、Aが、巨額の借財を為したることを意味するも、なお未だ破産に瀕することを意味する程度に達せざるものにして名誉毀損の罪を構成するものというべからず
と判示しました。
「 1⃣ 個人に対する社会的評価を低下させるもの」の説明
個人の得ている社会的評価を低下させる事実は、悪事醜行に限られません(大審院判決 大正7年3月1日)。
どのような事実が「個人の得ている社会的評価を低下させる事実」に当たるかは、相手方の有する名誉・社会的評価によって相対的に定まります。
この点、参考になる判例として以下のものがあります。
大審院判決(明治34年12月20日)
巡査部長が妓楼に登り淫酒を買ったとの新聞記事が「常人としては醜行とならざるものとするも被害者に特殊の身分あるが故にこれがため、その名誉を毀損すべきものなるときは、その記載したる事項は、すなわちその人の醜行と為るをもって誹毀罪(現行法:名誉毀損罪)を構成するものとす」としました。
「 2⃣ 社会の一員としての最低限の評価を害するもの」の説明
「社会の一員としての最低限の評価を害する事実」は、
相手方が誰であっても変わらない絶対的なものというべき
とされます(学説)。
例えば、「通常人ならば恥とするような事柄や倫理的あるいは能力的な欠陥」(例えば、犯罪行為や醜行)が該当するとされます(学説)。
プライバシーに属する事実を害した場合、名誉毀損罪が成立するか?
必ずしも明確でないのは、プライバシーに属する事実の扱いです。
通常、秘匿されている事実の公表は、本人に恥辱感をもたらし、社会的活動の障害となり得ます。
しかし、名誉毀損罪が活動の自由を直接に保護するものでない以上、対象者の
人格的評価を害する場合
に限って、名誉毀損罪の対象に含まれると考えるべきとされます(学説)。
プライバシーに属する事実の侵害(盗撮)について、名誉毀損罪の成立を認めた以下の裁判例があります。
東京地裁判決(平成14年3月14日)
裁判官は、
- 名誉毀損罪の成立要件である「事実の摘示」についてみると、被告人らは、上記のような内容(入浴中の女性の裸の映像)の本件ビデオテープにK子ら3名の全裸の姿態が録画されているという事実を摘示したものということができる
- そして、本件ヒデオテープのようないわば性的関心に向けられた商品に女性の全裸の姿態が録画された場合、撮影された女性がだれかが分かれば、その女性が周囲の人たちから好奇の目で見られたり、場合によっては嫌悪感を抱かれるなど、その女性について種々否定的な評価を生ずるおそれがあることは否定し難い
- 殊に、本件では、K子らは、実際には、入浴中にその裸体を盗撮され、自分たちの知らない間にその映像を本件ビデオテープに録画されるに至ったのであるが、本件ビデオテープは、それ自体鮮明な画像に仕上がっているなど、その映像自体を見ても、実際に盗撮の方法で撮影されたものか、一見しただけでは明らかではなく、事情を知らない者が見れば、撮影されている女性が、不特定多数の者に販売されるビデオテープに録画されることを承知の上、自ら進んで裸体をさらしているのではないかという印象を与えかねないものになっている(ちなみに被告人自身の供述を始めとする関係証拠によると、盗撮ビデオとされるものの中にも、実際にはいわゆる「やらせ」によるものがあり、ビデオの映像を見ただけではその識別が困難であることが多いなどの事情もうかがうことができる。)
- このような場合、上記のおそれにはとりわけ軽視し難いものがあるといわなければならない
- そうすると、本件で被告人らが摘示した上記の事実は、まさにK子ら3名の名誉を害するに足りる事実に当たるということができる
- そして、被告人らの上記行為が名誉毀損罪のその他の成立要件を満たすこともまた明らかであるから、結局、本件について名誉毀損罪が成立することを肯定することができる
と判示しました。
事実の摘示の精粗
事実の摘示は、他人の名誉が毀損されると認められる程度になされれば足り、摘示された事実が精密に特定される必要はありません。
この点を判示した以下の判例があります。
大審院判決(昭和7年7月11日)
裁判官は、
- 名誉毀損罪における事実の摘示は、特定せられ得る他人の名誉が毀損せらるるものと認め得べき程度に為さるるをもって足り、該事実が、時期、場所、手段等にわたりて、精密に特定せらるることを要せず
と判示しました。
名誉毀損罪と侮辱罪の事実の摘示の違い
事実の摘示(名誉を害するに足りる事実の摘示)について、名誉毀損罪と侮辱罪(刑法231条)との区別は、
名誉毀損罪が「他人の社会的地位を害するに足るべき具体的事実を公然表示する」こと
であるのに対し、
侮辱罪が「他人の社会的地位を軽侮する犯人自己の抽象的判断を発表する」こと
である点で区別されます(判例・通説)。
この点を判示したのが以下の判例です。
大審院判決(大正15年7月5日)
裁判官は、
- 侮辱罪は、事実を摘示せずして他人の社会的地位を軽蔑する犯人自己の判断を公然発表するによりて成立し、名誉毀損罪は、他人の社会的地位を害するに足るべき具体的事実を公然告知するによりて成立するものとす
と判示しました。
東京高裁判決(昭和33年7月15日)
裁判官は、
- 従来判例の示すところによれば、刑法第231条所定の侮辱罪が事実を摘示しないで他人の社会的地位を軽蔑する犯人自己の抽象的判断を公然発表することによって成立するものであるのに対し、同法第230条第1項所定の名誉毀損罪は他人の社会的地位を害するに足るべき具体的事実を公然告知す
 ることによって成立するものであって、ともに人の社会的地位を侵害する罪である点においてはその性質を同じうするものとされている(大審院大正15年7月5日判決大審院刑事判例集5巻303頁登載、同大正15年10月7日判決等参照)
ることによって成立するものであって、ともに人の社会的地位を侵害する罪である点においてはその性質を同じうするものとされている(大審院大正15年7月5日判決大審院刑事判例集5巻303頁登載、同大正15年10月7日判決等参照) - にかかわらず、一は侮辱罪、他は名誉毀損罪としてそれそれ罪名を分けてその処罰に軽重を設けたゆえんは、ひっきょう右の侵害が具体的な事実上の根拠を示すことによってなさ
 れる場合とそうでなくして単に抽象的な人の意見判断自体によってなされる場合とでは、その間一般に社会に訴える力の相違が認められるので、その侵害の危険抄言すれば一般第三者が被害者の社会的地位に対し不利益な判断をするおそれの大少について両者おのずから差があり、ひいてこれに対する刑法上保護の必要の程度をも異にすべきものと考えられるため、犯罪の構成要件上「事実摘示」の有無にしたがって両者の罪を区別するのを相当としたからであると解しなければならない
れる場合とそうでなくして単に抽象的な人の意見判断自体によってなされる場合とでは、その間一般に社会に訴える力の相違が認められるので、その侵害の危険抄言すれば一般第三者が被害者の社会的地位に対し不利益な判断をするおそれの大少について両者おのずから差があり、ひいてこれに対する刑法上保護の必要の程度をも異にすべきものと考えられるため、犯罪の構成要件上「事実摘示」の有無にしたがって両者の罪を区別するのを相当としたからであると解しなければならない - したがって名誉毀損罪を構成する要
 件としての「事実摘示」の意味内容はよろしく上に述べた立法の趣旨に基いてこれを定むべきもので、判例の説くところもまたこれと同一の軌に出たものとして理解すべきであると考える
件としての「事実摘示」の意味内容はよろしく上に述べた立法の趣旨に基いてこれを定むべきもので、判例の説くところもまたこれと同一の軌に出たものとして理解すべきであると考える - (事実とは何か、その概念は相対的なもので、この言葉を用いる目的の異るによって相違し、一概にこれを定めることはできない。具体的といい抽象的という言葉の内容についても同様である。しかして名誉毀損罪と侮辱罪との区別について前者を他人の客観的、外部的な社会的名誉を害する罪、後者を他人の主観的、内部的な名誉感情を傷つける罪として両者その保護法益を異にするものであるとする有力な学説があり、かような見地から名誉毀損罪における事実摘示の意義を論ずるとすれば、あるいは別個の結論を生ずるかも知れないー小野清一郎著「刑法における名誉の保護」315、316頁参照ーが、両者の罪の差を単に「事実摘示」の有無に求める判例の立場に立つかぎり、当然本文説示のように問題を理解するるのが相当であろう。なお刑法第230条の2が名誉毀損罪にかぎって特定の場合にいわゆる真実の証明を許していることは、まさに同罪について事実摘示がその構成要件とされていることに対応するもので、したがって右の事実とは、単なる人の意見判断ではなくしていわゆる真実の証明に適するような具体的事実ーそれ自体が他人の社会的地位を害するに足るべきーでなければならないと考えることもできるわけである。)
- いまかような観点に立って所論の当否を検討すると、検察官指摘の(ー)の点はもちろん、弁護人が「強いていえば事実摘示とみられる個所」としている点さえも、結局本件被害者の発行にかかる新聞のもつ一般的性格(社会正義を守り真実を報道する新聞でないとか、またこの種の新聞はある候補の悪口を書くときはそれと対立する候補から相当の金をもらって罰金覚悟で書くものだとか)についての被告人の意見判断を示したに過ぎず、したがってそれは判例のいわゆる他人の社会的地位を軽蔑する犯人自己の抽象的判断を発表したにほかならないもので、他人の社会的地位を害するに足るべき具体的事実を告知したものでないから、名誉毀損罪の構成要件としての「事実摘示」があった場合にあたらないといわなければならない
と判示しました。