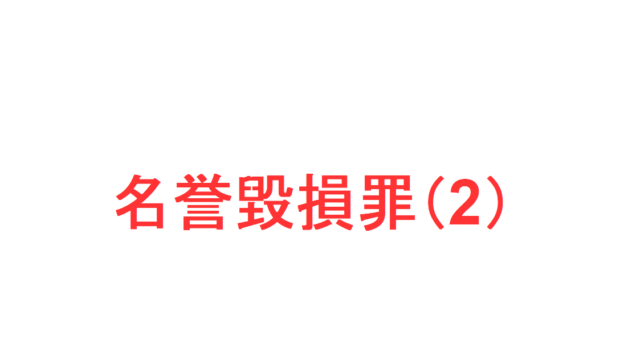名誉毀損罪(26) ~公共の利害に関する場合の特例(刑法230条の2)⑧「事実の証明の方法・程度」を説明~
前回の記事の続きです。
刑法230条の2が適用される場合は、名誉毀損罪(刑法230条)は罰されません。
具体的には、名誉を毀損する事実が摘示され、
- その摘示事実が公共の利害に関し(事実の公共性)
- 摘示の目的が公益を図ることにあった場合(目的の公益性)
には、
- 摘示された事実の真否の検討(事実の証明)
がなされ、名誉毀損罪の成否が決せられることになります。
この記事では、「事実の証明の方法・程度」を説明します。
事実の証明の方法・程度
摘示された事実の真否の検討(事実の証明)において、真実性の証明の方法・程度は、
厳格な証明により、合理的な疑いを容れない程度に証明されなければならない
とするのが下級審判例の一般的な態度です。
参考となる下級審判例として、以下のものがあります。
東京地裁判決(昭和40年5月22日)(丸正事件一審判決)
裁判官は、真実性の証明の程度について、
- 名誉毀損罪における真実性の証明は、違法性阻却の事由と解されるから、こと犯罪事実の成否に関するものである以上、その証明は合理的疑いを容れる余地のない程度の蓋然性を要するものというべきである
- また、この挙証責任が被告人にあることは右証明の程度を軽減する事由とはならない
- 蓋し、右挙証責任は、被告人に立証義務を負わしめるという趣旨ではなく、真実証明はあくまでも裁判所の職権調査事項であって、裁判所の努力にもかかわらず証明が得られなかったときには被告人の不利益に帰するというだけのものであるからである
- それ故、当裁判所はこの点に関しては冒頭に述べたとおり合理的な疑いを容れる余地のない蓋然性を必要とすると考える
と判示しました。
裁判官は、
刑法第230条の2にいう「真実なることの証明」の程度について、裁判官は、
- 刑法第230条の2にいう「真実なることの証明」は、いわゆる証拠の優越の程度では足りず、合理的な疑いをいれない程度のものであることを必要とする
と判示しました。
東京高裁判決(昭和41年11月30日)(最高裁決定(昭和43年1月18日)の原判決)
裁判官は、
- 名誉毀損罪における事実証明の要件および効果を規定した刑法第230条の2の
 規定は、真実の事実を摘示しても名誉毀損罪として処罰されなければならない同法第230条の規定を修正し、真実の事実をもってなされる正当な批判の自由を保障しようとしたものであるから、不確実な噂や、風聞ないし憶測を公表することは、そのこと自体、すでに法の保護の範囲を逸脱するものといわなければならない
規定は、真実の事実を摘示しても名誉毀損罪として処罰されなければならない同法第230条の規定を修正し、真実の事実をもってなされる正当な批判の自由を保障しようとしたものであるから、不確実な噂や、風聞ないし憶測を公表することは、そのこと自体、すでに法の保護の範囲を逸脱するものといわなければならない - かかる法意に鑑み、かつ、真実性の立証責任が被告人側にあることを合わせ考えると、この場合における真実性の証明は、それが厳格な証明を要するか又は自由な証明で足るかは別として、少なくとも裁判所にその事実の重要な点についての真実性を納得せしめるに足るだけの心証を得させるものでなければならないのであって、疎明の程度で十分であると解すべき理由はない
と判示しました。
東京高裁判決(昭和46年2月20日)(丸正事件二審判決)
犯罪にあたる事実を摘示して人の名誉を毀損した場合における真実の証明の程度について、裁判官は、
- 犯罪にあたる事実を摘示して人の名誉を毀損した場合における真実の証明は、摘示された事実が真実であることの心証を合理的な疑いを容れない程度に得させるに足りるものでなければならず、いわゆる証拠の優越の程度またはそれより低い程度のものでは足りないと解すべきである
と判示しました。
大阪高裁判決(昭和41年10月7日)(最高裁判決(昭和44年6月25日)の原判決)
裁判官は、
- 名誉毀損罪の場合に刑法230条の2の規定する摘示事実の真実であることを立証するための証拠について、特に被告人側に伝聞法則の適用を緩和し伝聞証拠を許すと解すべき理由はない
- 何となれば、犯罪の構成要件又はこれに準ずる要件に当る事実については、証拠能力があり、かつ適法に取り調べられた証拠による厳格な証明を必要とするのであって、このことは、証拠
 を提出する当事者のいずれであるか、また、攻撃、防御いずれのためにするかを問わないからである
を提出する当事者のいずれであるか、また、攻撃、防御いずれのためにするかを問わないからである - ただ、被告人は、有罪の判決があるまでは無罪の推定を受け、犯罪事実についての挙証責任は検察官がこれを負担するのが原則であるため、その結果、被告人側において積極的に犯罪事実の不存在、不成立を立証する必要がないというに過ぎない
- しかし、被告人側としても犯罪事実の不存在等を立証するための証拠を提出するに当たっては、同一の証拠法則に服さなければならないことにかわりがないのである
- 名誉毀損罪においては、刑法230条の2の規定により、人の名誉を毀損する事実を公然摘示しても、それが公共の利害に関する事実にかかり、かつ、もっぱら公益を図る目的に出たものと認められ、しかも、その事実の真実であることが積極的に立証された場合に、初めて被告人に対し無罪の言渡がされるのであって、取調の結果その事実が
 虚偽であることが明らかとなった場合はもちろん、真否不明の場合にも、真実の証明がなかったものとして、被告人は不利益な判断を受けることになっている
虚偽であることが明らかとなった場合はもちろん、真否不明の場合にも、真実の証明がなかったものとして、被告人は不利益な判断を受けることになっている - この意味において、被告人は、例外的に事実の真実性に関する挙証責任を負担しなければならないが、右規定の立法趣旨は、個人の名誉と表現の自由という両法益間の矛盾衝突を調整しようとするにあるから、右挙証責任の負担が被告人にあるからといって、この
 場合に限り厳格な証明を要しないとするわけにはいかない
場合に限り厳格な証明を要しないとするわけにはいかない
と判示しました。
東京地裁判決(昭和49年11月5日)
裁判官は、
- 弁護人は、真実性の証明は、厳格な証明による必要はなく、証明の程度もいわゆる証拠の優越の程度で足り、有罪認定に必要な程度の高度の証明は必要ないものである、と主張する
- しかし、真実性の証明は、裁判所が、被害者の名誉を低下させる犯罪行為又は非行などの存否を判断し、真実であるときは違法性がなく処罰されない、ということであるが、右は違法阻却事由であるからその存否は厳格な証明の対象になるものであって、このことは、違法阻却事由の不存在の立証責任が検察官にあると、その存在が被告人にあるとで異なるものではないとみるべきであり、また、裁判所が、真相究明の努力をしたにもかかわらず合理的疑いを容れない程度の心証を得ることができず、右事実を認めることのできる証拠が、これに反する証拠よりより多く信用できるという意味での証拠の優越の程度で右事実が証明されたものとして、摘示者の罪責を免れさせるべきものと解することは、(イ)犯罪に関するときは、刑事事件であれば犯罪者と認めるだけの証拠のない被害者を、名誉毀損被告事件の被害者として証拠の優越の程度で裁判所が真犯人である旨を判示しこれを社会から葬り去る不当な結果を招来することを法律上許容することになって不当であるのみならず(東高判昭和46年2月20日高集24巻1号97頁参照。)、(ロ)犯罪以外の非行に関しても、刑事裁判手続でその事実の存在が認定された場合の被害者に対しての社会の受け取り方、被害者に与える苦痛は民事裁判(たとえば損害賠償請求事件として)で右事実を認定された場合よりも深刻かつ重大であるから、自由な証明及び証拠の優越で足りるとする弁護人の見解には賛成できない
- たしかに、強制的捜査権を有しない被告人に合理的疑いを容れない程度の立証責任を負わせると、正当な言
 論、批判の自由を制限することにもなりかねない、という批判は十分に尊重されるべきであるが、これは言論、批判の自由の確保と被害者の名誉の保護との調和点をどこに見出すかの問題で、当裁判所は証拠の優越の程度の証明で足りるとすることで調和を求める見解は、被害者の名誉の保護に欠けるうらみがあり賛成できないのであって、この問題は、真実性についての誤信の問題として解決すべきであると考える
論、批判の自由を制限することにもなりかねない、という批判は十分に尊重されるべきであるが、これは言論、批判の自由の確保と被害者の名誉の保護との調和点をどこに見出すかの問題で、当裁判所は証拠の優越の程度の証明で足りるとすることで調和を求める見解は、被害者の名誉の保護に欠けるうらみがあり賛成できないのであって、この問題は、真実性についての誤信の問題として解決すべきであると考える - すなわ
 ち、真実性の証明がなくても、被告人が真実であると確信し、それが確実な資料、根拠に照して相当であるときは、名誉毀損の故意がなく、処罰されないが、右の確実な資料、根拠というのは、誤信の原因が社会一般人の日常生活における健全な常識に照してみて、真実であると信ずるのが無理もないと
ち、真実性の証明がなくても、被告人が真実であると確信し、それが確実な資料、根拠に照して相当であるときは、名誉毀損の故意がなく、処罰されないが、右の確実な資料、根拠というのは、誤信の原因が社会一般人の日常生活における健全な常識に照してみて、真実であると信ずるのが無理もないと 認められる程度の資料、根拠をいうものであって、検察官が公訴を提起維持するために護(ママ)得するであろう資料、根拠を基準とするものではない、と解すべきであるから、摘示者が、右の程度の資料、根拠を基にして真実と誤信したのであれば結局、真実の証明がなくても処罰されないことになり、従って、被害者を犯罪者又は非行者と認定することもなく、しかも摘示者も処罰の脅威から解放できることになり、このように解することによって始めて妥当な調和が図られるものと考えるのである
認められる程度の資料、根拠をいうものであって、検察官が公訴を提起維持するために護(ママ)得するであろう資料、根拠を基準とするものではない、と解すべきであるから、摘示者が、右の程度の資料、根拠を基にして真実と誤信したのであれば結局、真実の証明がなくても処罰されないことになり、従って、被害者を犯罪者又は非行者と認定することもなく、しかも摘示者も処罰の脅威から解放できることになり、このように解することによって始めて妥当な調和が図られるものと考えるのである
と判示しました。
東京高裁判決(昭和59年7月18日)(月刊ペン事件差戻後の二審判決)
名誉毀損罪における摘示事実の真実性を証明する方法及び程度について、裁判官は、
- 名誉毀損罪における摘示事実の真実性を証明する方法及びその程度は、いわゆる「自由な証明」及び「証拠の優越」(※証拠上いずれの側の証明度が優越しているか)では足りない
- 名誉毀損罪における摘示事実を真実と誤信したことの相当性を証明する方法及びその程度は、いわゆる「自由な証明」及び「証拠の優越」では足りない
と判示しました。