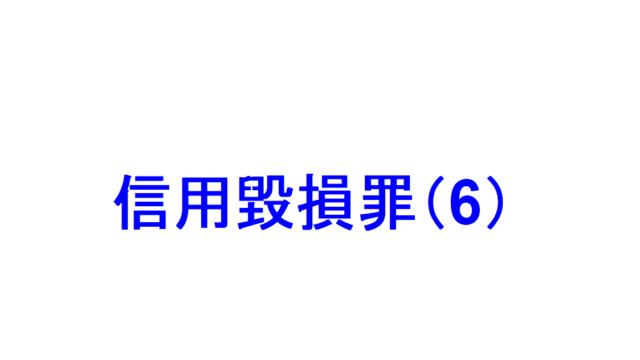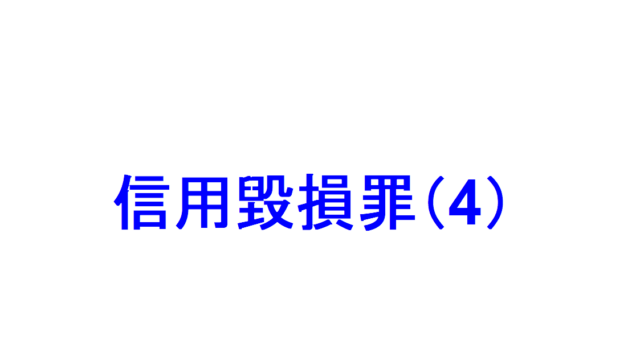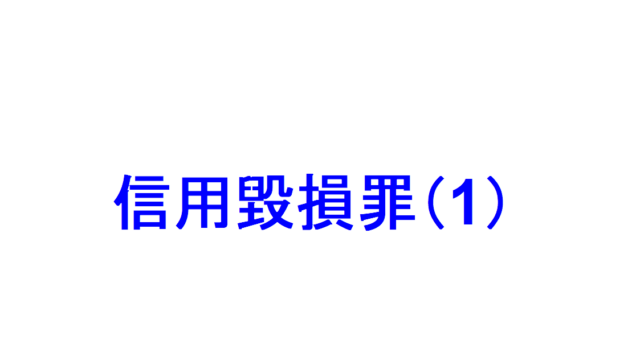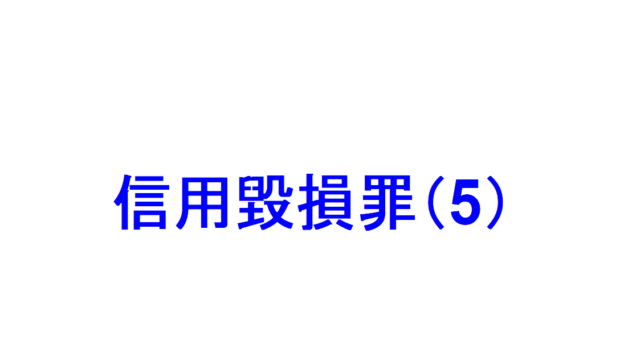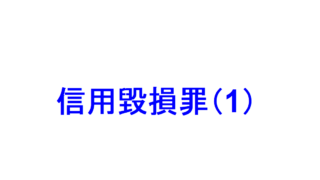信用毀損罪(2) ~「『虚偽の風説を流布し』とは?」「『偽計を用いて』とは?」を説明~
前回の記事の続きです。
信用毀損罪の行為
信用毀損罪(刑法233条前段)の行為は、
「虚偽の風説を流布し」あるいは「偽計を用いて」という手段によって、人の信用を毀損する
ことです。
①「虚偽の風説を流布し」とは?
「虚偽の風説を流布」するとは、
客観的真実と異なった内容の事項を不特定又は多数の人に伝播させること
をいいます。
「虚偽の風説を流布し」の「虚偽」とは?
信用毀損罪における「虚偽」の意義について、判例は、
「真実ならざる事実」
と判示しています。
大審院判決(明治44年12月25日)
裁判所は、
- 裁判所は、刑法第233条にいわゆる虚偽の風説を流布するとは、真実ならざる事実を多数の人に伝播するのいうにして、その伝播したる事実の具体的のものなると否と、また、これを多数の特定人に告知する否とは問うところにあらず
- 故に、被告らが虚偽の事実をを数人に伝えたる以上は、その所為は同条の「虚偽の風説を流布し」とあるに該当するものとす
と判示しました。
信用毀損罪における「虚偽」は、虚偽告訴罪(刑法172条)における「虚偽」、文書偽造罪における「虚偽」と同様に、客観的な虚偽を意味すると解すべきとされます。
文書偽造罪における「虚偽」の意義を判示したの以下の判例です。
大審院判決(大正5年6月26日)
医師が公務所に提出する診断書に虚偽の診断結果を記載した虚偽診断書作成罪(刑法第160条)の事案です。
裁判所は、
- 刑法第160条の処罰規定は、虚偽の証明を禁止するの趣旨に出でたるものなれば、いわゆる虚偽の記載たるには、その診断書等の記載が事実上、真実に違背することを要す
- 従って、その記載が事実上、真実に適合するにかかわらず、単にこれを作成する医師において不実と誤信したる場合のごときは犯罪を構成せざるものとす
と判示しました。
「虚偽」か否かは「信用を毀損するおそれがあるか否か」で判断される
「虚偽の」とは、軽犯罪法1条16号にいう「虚構の」と異なり、
全然根も葉もないことに限らず、基本たる実在の事実に虚偽事実を付加するものを含み、また、流布された事項の一部に虚偽が存する場合を含む
とされます。
どの程度虚偽であることを要するかについては、全部又は重要な部分が虚偽であることを要するとする説もありますが、
信用を毀損するおそれがあるか否か
によって決められるべきと解されます。
将来の予想を述べることによって信用を毀損する場合については、その予想の基礎となった現在又は過去の事実が真実に反するか否かによる虚偽性の判断をすべきであるとされます。
流布された風説が虚偽か否かが争われた裁判例として以下のものがあります。
東京地裁判決(昭和49年6月27日)
週刊誌に新聞社が経営不振に陥っている旨の記事を掲載した事案です。
基本となる主要事実について真実性の立証が尽くされており、その立証が十分といえない部分についても同社の経済的見地における社会的評価を更に毀損するとまでは認められないとし、信用毀損罪は成立しないとして無罪を言い渡しました。
東京高裁判決(昭和38年6月18)
音楽喫茶、酒場等の経営に関し「自身の資産を持たず、資金不足や自身の乱費を不波手形で穴埋めした」等と記載したビラを配布した事案で、ビラの内容は単なる誇大ではなく虚偽であるとし、信用毀損罪の成立を認めました。
科学的に真偽不明の事項に対する虚偽性の判断
厳密な科学的論証を必要とせず、簡単にことの真偽が確認できる場合には、信用毀損罪の真偽性の判断ができます。
しかし、新しく開発された製品で未だその効用、副作用の有無等が科学的に十分解明されていない段階において、企業間の競争から当該製品について有害であるとか欠陥があるとかいった風評が流されるケースにおける流布された事実の真偽性の判断については、解釈上、困難なものがあります。
この点の問題提起となったのが、トフロン事件に対する東京地裁判決(昭和49年4月25日)です。
この事件は、厚生大臣から食品添加物に指定され、製薬会社が特許を得て製造販売していたニトロフラン誘導体豆腐用殺菌剤(AF-2)(商品名「トフロン」)について、有毒有害な食品添加物であると記載した著書を出版した事実が、虚偽風説の流布による業務妨害罪に問われたものです。
判決は、まず、
- 本件の場合、「虚偽の風説」についての従前の理解に従うならば、「AF-2」が完全に無害であるという証明は尽くされていないのであって、将来の研究いかんによっては、発がん性等が問題となる余地も予想されないわけではなく、仮にそうなったとすれば、「AF-2」は有害であるとの被告人の記述自体は虚偽でないことになり、無罪としなければならないこととなろう
- しかし、そうであるとするならば、仮に、競争関係にある企業の関係者が、自己の利益を考え、その当時としては根拠のないことを知りつつ他社の商品を誹謗するといった事例においても、後にいわゆる科学論争に持ち込みさえすれば処罰を免れる余地があるということになるが、このような場合、後日になってその誹謗が結果的に、正当であったことが証明されえたとしても、その誹謗者は処罰されるとするほうが、世人の正義感情にかなうところであろう
と述べ、そのような問題意識に立った上で、
- 刑法233条にいう「虚偽の風説」とは、行為者が確実な資料・根拠を有しないで述べた事実である
との解釈を導き出しました。
この事案に対する判断としては、本件著書の「AF-2」に関する記載は、客観的にみる限り確実な資料・根拠に基づくものとは認め難いから「虚偽の風説」に当たるが、故意すなわち自己の言説が確実な根拠・資料に基づかないことの認識を有していたとは認められないとして、犯意の点で無罪を言い渡しました。
(故意が認められなければ無罪にあることにいては前の記事参照)
この判決の見解に対しては、学説では、支持する有力説も存するが、批判的な見解も少なくありません。
この判決は、真偽の判断が客観的に容易な事例についてまで一般的に適用されるべきものとして前記見解を示しているのか、あるいは、本件のごとく行為時において科学的に真偽を確定することが不可能な事案に限っての解決策を提示しているのか、必ずしも明らかではありません。
科学的に真偽不明の事項に対する虚偽性については、将来の予想を述べる型で信用を毀損する場合の虚偽性判断方法と同様に、その判断の基礎としている事項あるいは根拠としている資料等が現代の科学水準からみて真実に反するか否かにより判断されるべきではないかとう学説の見解があります。
「虚偽の風説を流布し」の「風説」とは?
「風説」とは、一般的には噂を意味しますが、噂という型で流布される場合に限定する合理的理由はないので、「風説」には特段の意味はなく「虚偽の風説」とは、
虚偽の事項と同義である
と解されます。
必ずしも風説の出所又は根拠があいまいなことを要しないと解されます。
また、犯人自身が創造・創作したものであるか否かを問わず、他人から聴いた話でもよいとされます。
名誉毀損罪と異なり、具体的に事実を摘示することは要件とされていません。
また、悪事醜行の観念を含んでいる必要はありません。
これらの点を判示したのが以下の判例です。
大審院判決(明治45年7月23日)
裁判所は、
- 刑法第233条の罪の成立については、虚偽の風説を流布し、又は偽計をもって他人の信用を毀損することを要するのみ
- そのこれを毀損するにつき、必ずしも具体的不正の事実を指摘することを要するものにあらず
と判示しました。
大審院判決(明治44年2月9日)
裁判所は、
と判示しました。
「虚偽の風説を流布し」の「流布」とは?
「流布」とは、
不特定又は多数人に伝播させること
をいいます。
判例は以下のように判示してします。
大審院判決(明治42年11月15日)
自己の発刊する新聞紙上に記事として虚偽の風説を掲載して発行した事案で、
- 公衆に伝播するのいうにして、世人をして伝唱せしむることを必要とせざるなり
と判示しました。
大審院判決(明治44年12月25日)
4軒の家に赴き、対話して虚偽の風説を伝えた事案で、
- 多数人に伝播するのいうにして、多数の特定人に告知すると否とは問うところにあらず
と判示しました。
大審院判決(大正5年12月18日)
村会議員集合の席で虚偽の風説を議員等に吹聴した事案で、
- 必ずしも犯人が直接に不定多数人に対して虚偽の事案を告知することを要するものに非ず
- 特定少数の人に対して虚偽の事実を告知したる場合といえども、苟も他人の口を借りて順次右事実が不定多数の人に伝播せられることを認識してこれを為し、その結果を発生せしむるにおいては、いわゆる虚偽の風説を流布したるものというを妨げず
判示しました。
大審院判決(昭和12年3月17日)
被告人宅に個別に来訪した3名に対し、虚偽の風説を告知した事案で、
- 被告人が虚偽の事実を告知したるはわずかに3名のみとするも、ひいてその者の口を借りて順次多数の人に伝播せられるおそれあること普通なれば、いわゆる流布たるを失わざるものとす
と判示しました。
既に社会の一部に流布している虚偽の風説をより広範に流布させる行為が信用毀損罪に当たるか否か
既に社会の一部に流布している虚偽の風説をより広範に流布させる行為が信用毀損罪に当たるか否かについては、そのような行為は人の信用をより一層低下させるものであることから、信用毀損罪に当たるとして積極に解するべきとされます。
この点、名誉毀損罪に関する以下の判例が参考になります。
大審院判決(昭和10年4月1日)
裁判所は、
- 名誉毀損たるには、必ずしも隠秘の事実を摘発するに限らず、既に社会の一部に宣伝せられる事実といえども、公然これを摘示するにおいては、名誉毀損罪を構成するものとす
と判示しました。
②「偽計を用いて」とは?
「偽計を用いて」の意義については、刑法233条後段の偽計業務妨害罪に関して問題となることが多く、信用毀損罪で問題になることは多くはありません。
「偽計を用いて」の意義について、
- 刑法233条にいう「偽計を用い」とは、人の業務を妨害するため、他人の不知あるいは錯誤を利用する意図をもって錯誤を生ぜしめる手段を施すことをいう(大阪高裁判決 昭和29年11月12日)
- 刑法233条にいう偽計を用いるとは、欺罔行為により相手方を錯誤に陥らせる場合に限定されるものではなく、相手方の錯誤あるいは不知の状態を利用し、または社会生活上、受容できる限度を越え、不当に相手方を困惑させるような手段術策を用いる場合を含む(東京高裁判決 昭和48年8月7日)
と判示した裁判例があります。
偽計による信用毀損罪が認められた事例として、以下の判例があります。
大審院判決(昭和3年7月14日)
駅弁業者と紛争中の者が、その業者の駅弁が不潔・非衛生である旨の不実の内容を記載した葉書一枚を鉄道局事務所旅客課長宛に郵送して同課長に到達せるという偽計を用いて、同課長に駅弁業者の営業に疑念を抱かせ、駅弁業者の信用を毀損し、かつ、駅弁業者の業務を妨害したとして、信用毀損罪とともに偽計業務妨害罪が成立するとしました。