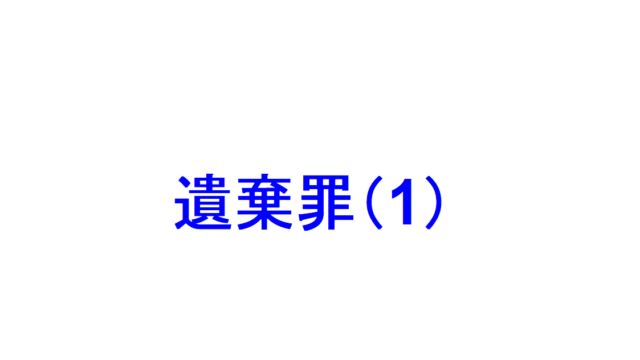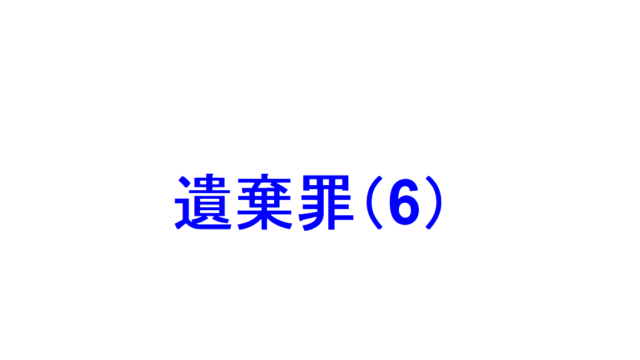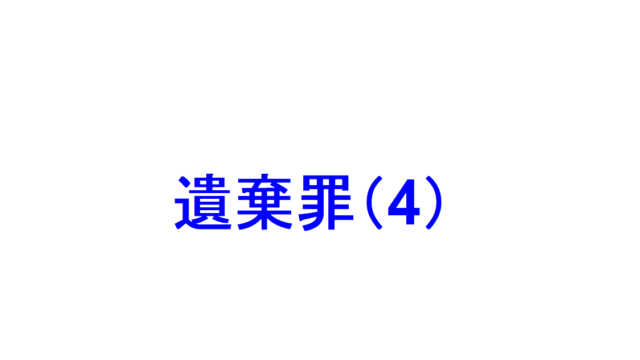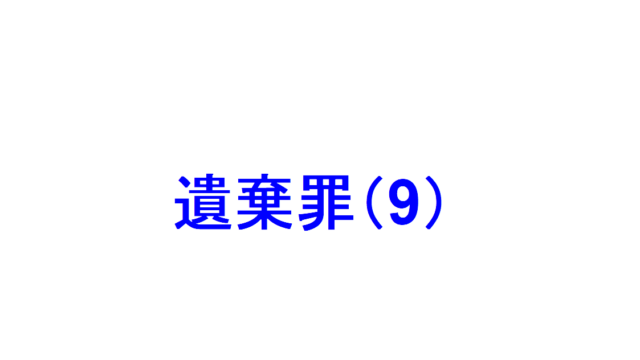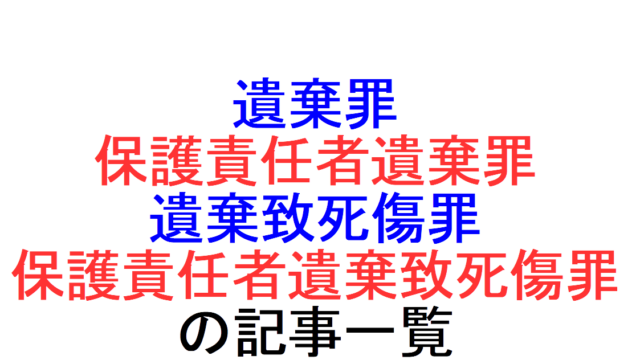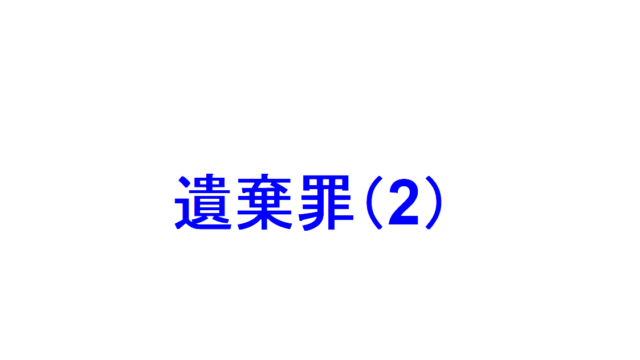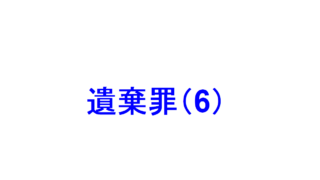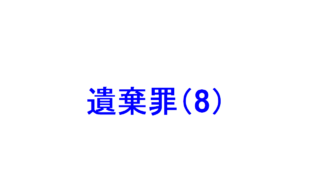遺棄罪(7) ~「遺棄罪の故意」「殺人罪又は傷害罪の故意が認められる場合、遺棄罪の故意はこれに吸収され、殺人罪又は傷害罪のみが成立する」を説明~
前回の記事の続きです。
遺棄罪の故意
遺棄罪(刑法217条)は故意犯です(故意についての詳しい説明は前の記事参照)。
遺棄罪の故意が認められるためには、
- 被遺棄者が老年、幼年、身体障害又は疾病により扶助を必要とする者であることを認識していること
かつ
- 当該遺棄行為を認識していること
が必要です。
遺棄行為による抽象的危険が生じることの認識は不要
遺棄罪の故意を認めるに当たり、当該遺棄行為によって被遺棄者の生命・身体に抽象的危険が生じることの認識は必要ではありません。
遺棄罪は抽象的危険犯です(詳しくは前の記事参照)。
抽象的危険犯とは、本来構成要件に該当する行為が行われれば何らかの抽象的危険が生じるとの擬制を行っているものです。
なので、構成要件に該当する行為の認識さえあれば十分であり、遺棄罪が生命・身体に対する抽象的危険犯であることから、抽象的危険の発生に関する認識は全く不要であるということになると考えられています。
この点を判示した以下の判例があります。
大阪高裁判決(昭和53年3月14日)
気温が摂氏5度を下回り、北風が吹き、みぞれが降ったりにわか雨が降っていた厳寒期(2月19日)の午後4時30分頃、4年3か月のひ弱な子供を毛糸の長袖セーターと長ズボン、ニットの長袖シャツとパンツという室内着のまま、素足でベランダに閉め出し、動き回ることもなく、ただじっとうずくまっているだけの同児を約14分経過しても入室させずに放置して凍死させた保護責任者遺棄致死罪(刑法219条)の事案です。
裁判官は、
- 遺棄罪の故意としては、抽象的危険の発生を基礎づける事実を認識する以上、更に右の危険自体を認識することは必要でなく、右のような事実を認識しながら右危険を認識しないのは正しく違法性の錯誤であり、それがため故意が阻却されることはないというべきである
判示しました。
殺人罪又は傷害罪の故意が認められる場合、遺棄罪の故意はこれに吸収され、殺人罪又は傷害罪のみが成立する
行為者が、当該遺棄行為が被遺棄者の生命・身体に対する抽象的危険(若しくはある程度の具体的な危険)を生じさせ得るものであることの認識にとどまらず、更に進んで遺棄行為によって被遺棄者の生命・身体に現実的な危害を加えるものであることを認識しているときには、遺棄罪の故意ではなく、殺人罪又は傷害罪の故意が認められ、遺棄罪の故意はこれに吸収されることから、殺人罪又は傷害罪のみが成立することになります。
この点については判示した判例・裁判例として以下のものがあります。
大審院判決(大正4年2月10日)
保護責任者遺棄致死罪の成否に関し、殺意が認められることから殺人罪が成立するとしました。
大審院判決(昭和3年4月6日)
保護責任者遺棄致死罪の成否に関し、危害を加える認識があれば殺人罪・傷害罪の故意があるとしながら、そこまでの故意は認められないとして保護責任者遺棄致死罪の成立を認めました。
仙台高裁判決(昭和44年8月19日)
3年9か月及び1年6か月の幼児を自宅に放置して出入口に鍵や錠をかけて閉じ込め、誰にも告げずに出稼ぎに出た行為について、出稼ぎのために出発を決意した時点で保護責任者遺棄罪が成立するものの、同時に死の結果が招来することを認容して出発したことから殺人罪が成立し、保護責任者遺棄罪は殺人罪に吸収されるとしました。
重篤な状態にある病気の被害者を引き取り、このままでは死亡の危険があることを認識しながら、シャクティパットを施したのみで、未必的な殺意をもって、必要な医療措置を受けさせないまま放置して死亡させた行為について、被告人には不作為による殺人罪が成立するとしました。
また、殺意のない被害者の親族との間で保護責任者遺棄致死罪の限度で共同正犯となるとしました。
遺棄罪、保護責任者遺棄罪、遺棄致死傷罪、保護責任者遺棄致死傷罪の記事一覧