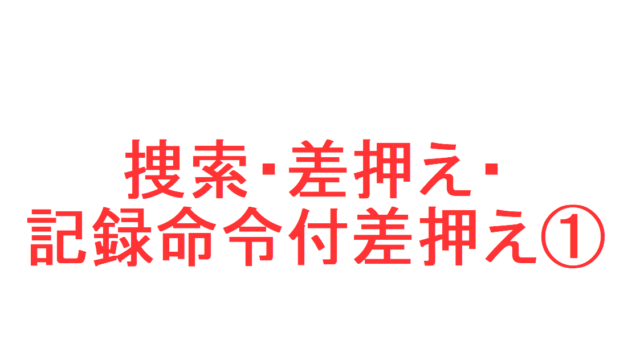逮捕・勾留の効力範囲③~「一罪一逮捕一勾留における『一罪』の意義」を説明
前回の記事の続きです。
一罪一逮捕一勾留における「一罪」の意義
同一の犯罪事実について、一人の被疑者を重ねて逮捕・勾留することは、原則として認められないとする原則を「一罪一逮捕一勾留の原則」といいます。
一罪一逮捕一勾留における「一罪」、つまり、
一罪一逮捕一勾留の原則が適用される「同一の犯罪事実」とはどの範囲の事実を指すか?
が問題となります。
これについては、見解が分かれており、「一罪」といえる判断基準について、
とがあります。
※ 一罪一逮捕一勾留の原則の詳しい説明は一罪一逮捕一勾留の原則とは? の記事でも行っているのでご参照ください。
①の「実体法上の罪数を基準として判断する説」の考え方
①の「実体法上の罪数を基準として判断する説」は、刑事手続は国家の刑罰権を実現する手続であり、実体法上一罪とされるものは、手続上も一個のものとして扱うべきで、捜査も手続の一環であることから、逮捕・勾留の段階においても実体法上の一罪を基準として判断すべきであるとします。
「一罪」を①の実体法上の一罪と解すると、数個の可罰的行為が実体法上の一罪を構成する包括一罪や科刑上一罪に当たる場合、一個の可罰的行為について逮捕・勾留した後、実体 法上一罪の関係にある他の可罰的行為について逮捕・勾留できるかという問題が生じます。
しかし、「一罪」を実体法上の一罪と解する説でも、一個の可罰的行為について逮捕・ 勾留され、同罪により起訴された被疑者が、保釈中に同罪と実体法上一罪の関係にある他の可罰的行為に及んだ場合のように、捜査官が同時に捜査して処理することが不可能であったり、著しく困難であった場合には、再度逮捕・勾留することが許されると解する説もあります。
例えば、常習累犯窃盗罪は、複数の窃盗行為を1個の常習累犯窃盗罪で処罰するものですが、1個目の窃盗行為を逮捕・勾留した後、2個目の窃盗行為を逮捕・勾留できないとすると、捜査が著しく困難となります。
そうのような場合に、再度逮捕・勾留することが許されると解されるといえます。
②の「個々の犯罪事実を基準として判断する説」の考え方
②の「個々の犯罪事実を基準として判断する説」は、一罪か数罪かは認定された事実に対する実体法上の刑罰法令適用の問題であるから、その罪数が捜査手続を規制すると解するのは妥当ではなく、逮捕や勾留の必要性を判断する際の逃亡や罪証隠滅のおそれの存否は、個々の、可罰的行為ごとに判断されるべきであるとします。
裁判例
一罪一逮捕一勾留の「一罪」の考え方について言及した裁判例として以下のものがあります。
常習の一罪一部(甲)につき保釈中の者が更に常習一罪の一部(乙)を犯した場合、右乙の罪につき勾留しても、一罪一勾留の原則に反しないとした決定です。
裁判官は、
- まず原裁判所の標榜する一罪一勾留の原則から検討するに、勾留の対象は逮捕ととも現実に犯された個々の犯罪事実を対象とするものと解するのが相当である
- したがって、被告人あるいは被疑者がある犯罪事実についてすでに勾留されていたとしても、さらに他の犯罪事実について同一被告人あるいは被疑者を勾留することが可能であって、その場合に右各事実がそれぞれ事件の同一性を欠き刑法第45条前段の併合罪の関係にあることを要しない
- それらの各事実が包括的に一罪を構成するに止まる場合であっても、個々の事実自体の間に同一性が認められないときには、刑事訴訟法60条所定の理由があるかぎり各事実ごとに勾留することも許されると解するのが相当である
- けだし、勾留は主として被告人あるいは被疑者の逃亡、罪証隠滅を防止するために行われるものであって、その理由の存否は現実に犯された個々の犯罪事実ごとに検討することが必要であるからである(刑事訴訟法第60条第1項参照)
- もっとも、同一被告人あるいは被疑者に対し数個の犯罪事実ことに当初から判明している数個の犯罪事実についてことさらに順次勾留をくり返すことは不当に被告人あるいは被疑者の権利を侵害するおそれがあり、その運用についてはとくに慎重を期さなければならないことはいうまでもない
- しかし本件においては、すでに説示した経過に徴し、再度勾留にかかる傷害事犯は最初の勾留時は勿論起訴当時においても予測できなかった新たな犯罪行為であるから、たとえそれが最初の勾留又は起訴にかかる傷害事犯とも包括して暴力行為等処罰に関する法律第1条の3の常習傷害罪の一罪を構成するに止まるとしても、これについて再び勾留する理由ないし必要性があるかぎり、本件再度の勾留は必ずしも不当とはいえない
- 右と異なる原裁判所の見解には賛同し難い
- なお、原裁判所は、本件抗告に対する意見のなかで、包括一罪について既判力の関係で一罪性を認め、勾留に関する関係では個々の犯罪事実が対象となるものとして一罪性を否定することは恣意的に一罪を分断し包括一罪を認めた趣旨を没却するものであるという
- しかしながら、公訴の提起の効力及び既判力が一罪の全てに及ぶ(刑事訴訟法第256条、第312条、第337条第1号)とされるのは同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われないいわゆる一事不再理の原則(憲法第39条)に基づく法的安定性の強い要請によるものであるのに対し、他方勾留は主として被告人あるいは被疑者の逃亡、罪証隠滅を防止するというきわめて現実的な要請によるものであり、それとこれとはそれぞれ制度本来の趣旨を異にするものであって、必ずしも直接関連するものではなく、いわゆる常習一罪ないし包括一罪の関係で、既判力の及ぶ範囲と勾留の効力の及ぶ範囲とが時にその限界を異にする場合があっても、けだしやむをえないところである
と判示しました。
福岡高裁決定(昭和49年10月31日)
甲事実で保釈中、その勾留状発付当時判明していなかった包括一罪の関係にある乙事実で再び勾留され乙事実を追加する訴因変更が行われた場合に、乙事実についての勾留を一罪一勾留の原則に反するとして取り消すことの適否について消極判断をした決定です。
裁判官は、
- 本件の本案である被告事件は数次の起訴と、これに加えて数次にわたる訴因変更手続が行われたため訴訟法律関係は著しく複雑であるけれども、原決定当時においては、第二の勾留の基礎となっている昭和49年8月5日付け訴因変更請求書に記載された各訴因と、既に同裁判所に繋属していた被告事件のうち第一勾留の基礎となっている公印偽造(福岡県教育委員会印の偽造)および偽造にかかる佐賀県教育委員会印、熊本県教育委員会印の使用による各有印公文書偽造、同行使等の各訴因とは牽連犯をふまえたうえ究極のところ包括して一罪の関係にあるものと考えられるので、第一の勾留と第二の勾留とは、同一の犯罪事実について二個の勾留状が発せられたこととなっていることは、否定し得ないところである
- しかるに、一罪につき一勾留を原則とすることは多言を用いるまでもないところであるが、包括一罪の関係にある個個の実行行為が長期に、かつ多数回にわたって行われた場合でも、実体的には一罪であって、単一かつ同一の公訴事実に包括されるもので、単純一罪の場合と何ら異るところがないようであるけれども、捜査を含む手続の諸断面は、単純一罪の場合と同一視することを許さないもののあることもまた否めないところである
- 本件の場合のごとく、一罪の一部について勾留が行われ、これについて既に保釈が許可された後、さらに余罪(実質的には一罪の他の部分)が発覚して強制捜査を行う必要がある場合は、逮捕、勾留も許されるものと解するのが相当であり、包括一罪の関係にあるか否かは、捜査を進めた後でなければ明確とならない場合もあり得るのであって(本件第二の勾留はまさにかような場合に該当するものと考えられる。)、捜査の結果既に勾留処分の行われている被告事件と一罪の関係にあることが判明した後においても一罪一勾留の原則から後の勾留が当然に違法となるものと解するのは相当ではない
- 蓋し第一の勾留状発付の当時は、第二の勾留の対象となっている事実は未だ全く予測されていなかったのであり、予測の可能性がなかった事実についてまで当然に勾留状の効力が及ぶと解することには、理論的にかなりの無理があり、他面かような場合においても一罪一勾留の原則の基本にある、不当な拘束から人権を擁護しようとする理念との調和をはかる上からは慎重な配慮と無理のない運営を必要とすることはいうまでもないところである
- 従って、第一の勾留状発付の当時、第二の勾留の対象となった事実がその一罪性とともに既に判明していて、これについても勾留の請求が可能であった場合は、第二の勾留を存続せしめる正当な理由は極めて乏しいといわねばならないが、本件の場合のごとく、第一の勾留状発付の際、第二の勾留の対象となっている事実が未だ判明していなかったため、これについて勾留の請求をなすことは不可能であり、かつ右事実が訴因変更の請求により審判の対象とされた後においても、なお罪証隠滅のおそれや、逃走のおそれがあり、これを予防するためなお身柄拘束の必要性が肯定される特段の事情がある場合は、第二の勾留を存続せしめる必要のあることは否み得ないところであって、かような場合についてまで、一罪一勾留の原則を貫こうとすることは、かえって不当な結果を招来することとなり、ひいては実体真実の発見ならびに国家刑罰権の適正迅速な実現の妨げともなりかねないので、かような場合には第二の勾留を存続せしめても、不当な拘束となるものではないというべきであって、第二の勾留を違法ならしめる理由も早や存在しないといわねばならないからである
- 福岡高等裁判所昭和42年3月24日決定(高等裁判所刑事判例集第20巻第2号114頁参照)の 判旨もかような場合をも考慮したものと解されるところである。
- もっとも、第二の勾留を存続せしめることにより一罪につき第一の勾留と第二の勾留と 二個の勾留が併存することとなるので、できるだけ一罪一勾留の原則との調和をはかる必要から、第一の勾留の必要性がさ程高いものではなく、第二の勾留により十分に目的を達し得るものと認められる場合は第一の勾留を取消すのが望ましいことはいうまでもないところであろう
と判示しました。
東京地裁決定(昭和33年2月22日)
前に逮捕・勾留された事実と科刑上一罪の関係にある犯罪事実につき、再度の逮捕状によって被疑者を逮捕した場合において、刑訴法204条、205条の勾留請求は許されるとした決定です。
裁判所は、
- 原裁判は、検察官の勾留請求を却下し、その理由として、「本件各勾留請求の事実は被告人Mについては昭和32年2月10日付けについては同年同月7日付け各勾留状記載の事実と科刑上一罪の関係にあるによる一と説明しており、その趣旨は同一の犯罪事実ないし科刑上の一罪の関係にある犯罪事実については一旦勾留等の強制処分を伴う捜査を行えば再び勾留等の強制処分を請求することはできないとする見解であると解されるので、まずこの点について審究する
- 強制処分を伴う捜査は刑事訴訟法に特別の定ある場合でなければこれをすることができないことは刑事訴訟法(以下法と略称)197条1項但書の明定するところであり、検察官が裁判官に逮捕状並びに勾留状の発布を請求しうる条件は法199条、204条、205条に定められている
- 而して、法199条3項によれば、「検察官は第一項の逮捕状を請求する場合において同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発布があったときはその旨を裁判所に通知しなければならない」と規定しており、この条章より勘案すると、検察官は前に逮捕状を請求し又はその発布をうけていても同一の犯罪事実について更らに逮捕状の請求をなしうるものであることが明らかであり、その請求により逮捕状の発布をうけた場合これに基く被疑者の逮捕並びに逮捕後の手続は前に発布された逮捕の場合と同様法201条以下の規定に準拠すべきものであることは法律上両者の取扱について別個の定がないことに徴し多言を要しない
- 然らば、検察官がその逮捕状により自ら逮捕し又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取った場合に遵守すべき手続は法204条、205条に従うべきものであって、検察官は被疑者に対し、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘東された時から所定時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しうるものと解するのが相当である
- 右の見解に対しては、(一)逮捕状の請求については法199条3項の規定が存するも、勾留状については同様の規定が存しないから、勾留の請求は逮捕状の請求と異なりこれをなし得ないとの論なきを保し難いが、法204条、205条は被疑者を逮捕した場合留置の必要がないときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならないと定めており、これと刑事訴訟法が被疑者の身柄に対する強制処分について定めている条章とを総合すれば、逮捕は勾留の前置手続ともいうべきものであって、両者は被疑者の身柄に対する強制処分として相関連した関係に立ち、留置の必要ある事件において逮捕は認められるが勾留は認められないというがごとく両者を切離した制度としてみることは相当でない
- 然らば、逮捕状について再度の請求をなすことが認められ、これによって発布された逮捕状に基づく逮捕が法204条、205条により処理されて同条所定の要件が具備する場合には、これが勾留請求に発展することは法の認容しているところといわねばならない
- (二)次に法208条が被疑者を勾留した場合その勾留期間を定め、やむを得ない事由があっても20日を超える期間勾留をなし得ないと定めている趣旨に鑑みると、同一の犯罪事実について再度の勾留を認めるときは逮捕勾留が反覆され、勾留期間を制限した法の精神に反するのではないかという疑が存するも、強制捜査を行っても必すしも公訴の提起をなしうるに十分な証拠を蒐集しうるものではなく、場合によっては相当の嫌疑があるにかかわらず捜査を一時中止する等のことも容易に推測しうるところであって、この場合、後日新たに資料を発見して被疑者の犯罪容疑か一層濃厚となった際、任意捜査によるほかその取調はできないとすることは、犯罪が国家の治安に及ぼす影響等を考えると、必ずしも公共の福祉を達する所以ではない
- 法199条1項はこの公共の福祉と法208条が企図している人権の保障との統一調和を図り、同一の犯罪事実について前に逮捕状の請求又はその発布があっても逮捕状の請求を認めるとともにこの場合にはその旨を裁判所に通知せしめ、裁判官をして、その逮捕状の請求並びに逮捕に引続く勾留請求(規148条参照)が逮捕、勾留の不当な反覆であるかどうかを検討の上慎重に請求を許否させることとしているものと解するのが相当である
- 果して然らば、本件においては、原裁判が説示しているとおり検察官が本件において勾留を請求した私文書偽造同行使の被疑事実(別紙二)と科刑上の一罪の関係に立つ公文書偽造同行使詐欺の被疑事実(別紙三)について昭和32年2月10日及び同月7日勾留状か発布されその執行があったとしても、この一事では検察官の勾留請求が直ちにその理由がないとは断定し難く、進んで(一)検察官の勾留請求は逮捕勾留の不当なくりかえしであるがどうか、(二)検察官が勾留請求に当り主張している法60条所定の事実が存するかどうかについて審究しなければならない
- よってまず(一)について審究するに、検察官提出の一件資料によれば、準抗告申立書記載(別紙一)の第一(一)にあるごとき事情が看取される
- かような多数の者が関与する事件で、重要な関係人が逃走等のため先の勾留期間中に十分な証拠収集が不能に帰し、釈放せざるを得なくなった場合において、その後相当の月日を経過してから、重要な証拠が新たに発見されたときには、再び逮捕及び勾留を請求することは、逮捕、勾留の不当なくりかえしを目的とするものとはいい難く、従って同一事実についての再勾留の請求であるということのみをもって、本件請求を却下することは相当ではない、といわなければならない
- (ニ)次に進んで、本件勾留請求が法60条の要件を具備するか否かを判断する
- 一件資料によれば、被疑者等が勾留請求書記載の被疑事実を犯したと疑うに足りる相当の理由があると認められるのみならず、準抗告申立書記載(別紙一)の第一(ニ)にあるごとき事情も認められかつ事件の内容及ひ前記の経過等を綜合すれば、被疑者らにおいて罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由もあると考えられる
- (三)以上によれば、本件被疑者両名に対する勾留請求は、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があり、かつ勾留の必要性も存すると認め得る楊合にあたるというべく、従って本件勾留請求却下の裁判は失当である
と判示しました。