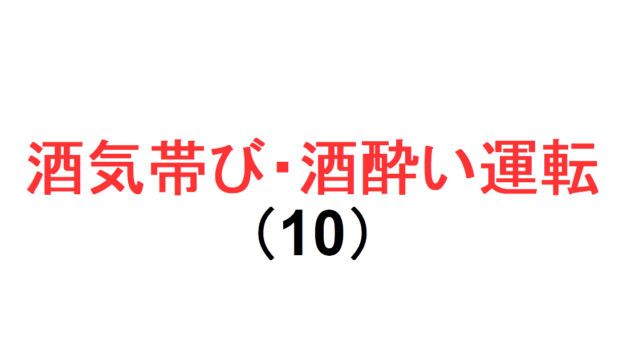道交法違反(救護措置義務違反)(5)~「道交法72条1項前段の『当該車両等の運転者その他の乗務員』とは?」を説明
前回の記事の続きです。
「当該車両等の運転者その他の乗務員」とは?
道路交通法違反(救護措置義務違反)は、道交法72条1項前段で、
- 交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない
と規定されます。
1⃣ 「当該車両等の運転者」とは、
当該交通事故の発生に関与した運転者という意味であり、その事故の発生にづいて故意又は過失のある運転者を意味するものではなく、当該交通事故を惹起させた車両等の運転者はもとより被害者の立場に立つ車両等の運転者も含む
と解されています。
したがって、例えば、明らかに相手側の一方的過失によって事故が発生しその相手側が死傷したような場合、その他一般的に不可抗力と認められるような状況があったときで、責任の全くない運転者であっても、道交法72条1項前段・後段の本項所定の義務(救護措置義務及び事故の報告義務)が課されることになります。
この点を判示した以下の裁判例があります。
山形地裁米沢支部判決(昭和37年2月20日)
裁判所は、
- 自動車運転者(原動機付自転車乗用者も含めて)は歩行者であれ、その対向車であれ、相手方も事故の発生を未然に防止しなければならない義務を負っているのであるから相手方においても規則を遵守することを期待し、行動することが許されるのは当然であろうが、だからといって、相手方が規則を無視して行動にでたからとて、自動車運転者の注意義務が除却される理由がないのである。(大審院大正14年10月3日判決集4巻570頁、昭和9年6月7日判決集13巻791頁など参照)
- 自動車運転者は、如何なる場合でも事故を未然に防止するについて最善の措置を講ずべき義務を負っているのであるから、相手方が規則を無視して行動にでたしめ、予期と異る事態が生じた場合でも、その状況より判断して、事故発生のおそれがあることを認識した場合には、これを未然に防止しなければならない業務上の注意義務を負うとするのは当然の事理に属するからである
と判示しました。
裁判所は、
- 自動車運転者の過失が認められない場合にも、自車によって負傷させた通行人を救護する道路交通法上の義務はあり、救護を怠つた場合には同法第117条、第72条第1項前段の罪が成立する
と判示しました。
2⃣ 「当該車両等の運転者」は、『双方の車両等の運転者』をいうので、道交法72条1項の義務は双方の車両等の運転者自身の責任において遂行すべき義務となっています。
したがって、他方の運転者あるいは第三者において被害者の救護等に当たったからといって、ただその一事をもって当該運転者の救護等の義務が消滅または免除されるということはありません。
この点に関する以下の裁判例があります。
福岡高裁判決(昭和37年7月7日)
負傷者が既に第三者によって病院に運び去られている場合と救護義務の有無について判示した事例です。
裁判所は、
- 原判決は道路交通取締法第24条第1項、同法施行令第67条第1項(現行法:道交法72条1項前段)の救護措置は他方の操縦者又は第三者においてその措置を講じ終った場合にまでも一方または双方の操縦者に対して救護義務を負わせる法意ではないとし、本件の場合被告人が事故現場に引返したとき既に第三者であるSが被害者を病院に連去った後で救護措置の対象を欠くにいたっていたから、被告人に救護義務違反はないとしている
- しかし、同条所定の救護義務は事故を惹起した当該車馬の操縦者等に課せられたものであって、あくまで同人ら自身の責任において遂行すべき義務であると解すべきであるから、他方の操縦者あるいは第三者において被害者の救護に当ったからといってただその一事をもって当該操縦者の救護義務が消滅又は免除されるいわれはない
- ところが、原審証人(省略)の各証言、被告人の検察官及び司法警察員に対する各供述調書によれば、被告人は本件交差点において自己運転の自動三輪車をA運転の第一種原動機付自転車に接触させて同自転車に同乗していたBに傷害を負わせたが、停車位置が交差点中央であったため自動三輪車を交通妨害とならない場所に移動して下車したところ、既に右事故を目撃したSがBを付近の病院に連去った後で「負傷者は病院に連れて行かれた」と聞いたので、そのまま同所を立去った事実が認められる
- かように負傷者が既に第三者により病院に運ばれて事故現場に居なくとも、事故を惹起した被告人としては直ちにその後を追って病院に赴き負傷者の症状如何、医師に対する治療依頼に手落がないかを確かめる等万全の救護措置を講じてこそ自己に課せられた救護義務を完遂したものといい得るのである
- ところが、被告人は負傷者は病院に連れて行かれたと聞いて自らは病院にも行かず直ちに現場を立ち去ったものであるから、その救護義務を怠ったものといわねばならない
と判示しました。
しかしながら、道交法72条1項後段の報告義務の履行の点についてはともかく、救護及び危険防止の各義務の履行については、分担しても、全員の力を合わせる場合と変わらない措置を講じることができるときは、当事者間の協議により、あるいは暗黙裡に意思を通じ合った上で、なすべき措置を分担しあって履行しても差し支えないと考えられています。
もちろん分担という以上、全員が義務を果す意思を有することを前提とするものであって、およそ義務を履行する意思を持たない者は、他の者が独自に義務を果したことによって免責されることはあり得ません。
この点に関する以下の裁判例があります。
大阪地裁判決(昭和52年12月15日)
自動車相互間での交通事故が発生した場合において、各運転者の間で救護義務及び危険防止義務を分担して履行することができるとして、被告人の道路交通法違反(救護義務違反)の成立を否定した判決です。
裁判所は、
- 検察官は、判示第二の交通事故により相手方Y及び同人運転車両の同乗者A子を負傷させたのに 被告人は同人らを救護する措置を講じなかったから、被告人は救護義務違反罪を犯したものであると主張する
- そこで検討すると、判示第二の事実に関して証拠の標目欄に掲げた各証拠のほか、医師N作成の診断書2通、医師H作成の診断書によれば、次の様な事実が認められる
- すなわち、本件交差点を信号に従い直進(ただし道路は左に曲っている)しようとした被告人運転車両と対向右折車である相手方Y運転車両とが交差点内で衝突し、被告人車は衝突地点付近に停止し、相手方車は更に進んで交差点隅のガードレールに突き当った状態で停止したこと、双方の車両とも前部付近が相当に損壊し走行不能の状態で車線を塞いで停止しており、現場は交通がひんばんであるため至急に移動させて危険を防止する必要があったこと(とくに被告人車が危険な位置で停止していたこと)右事故により相手方Yは通院加療約1週間を要する頭部打撲、左肩部打撲、右膝関節部打撲挫創、左膝打撲の傷害を、同人運転車両の同乗者で同人の子であるA子(当時3才5月)は通院加療約5日間を要する顔面打撲、右肩部左上膊部打撲、左足関節部挫傷の傷害を負い、A子は激しく泣いていたこと、被告人も通院加療約10日間を要する側頭部打撲の傷害を負ったこと、事故後被告人は直ちに車両から降り、泣いているA子を抱いて降りて来た相手方と交差点内で言葉のやりとり(被告人からは相手方の運転の仕方を責める趣旨の言葉を、相手方からは免許証を見せろというような言葉)をするうち、被告人車の後続車の運転手Mから「子供を病院へ運んでやろう」との申出があり、これに応じて相手方は被告人を現場に残し、子供を抱いてM運転車両に乗りこみ出発したこと(途中で交番に寄りそこから救急車に乗りかえて病院へ行き両名とも医師の手当を受けた)、被告人はこれを見届けたあと直ちに通行人の協力を得て被告人車を交差点隅の相手方車の横まで押して移動させたこと、被告人はこれにより 危険防止の措置を果したつもりでいたこと、その後被告人は処罰をおそれる気持等から逃走を決意し、電話をかけてくると付近の者に言い残して現場をはなれそのまま友人のT子方へ逃げ込んだこと。以上のような各事実が認められる
- ところで、車両同士の衝突事故の場合のように、救護等の義務を負う者が複数存在するとき、全員がこれらの義務を履行すべきことは言うまでもない
- しかしながら、報告義務の履行の点についてはともかく、救護及び危険防止の各義務の履行については、分担しても全員の力を合わせる場合と変わらない措置を講じることができるときは、当事者間の協議により、あるいは暗黙裡に意思を通じ合ったうえで、為すべき措置を分担しあって履行しても差し支えないと考えられる
- もちろん、分担と言う以上、全員が義務を果す意思を有することを前提とするのであって、およそ義務を履行する意思を持たない者は、他の者が独自に義務を果したことによって免責されることはあり得ない
- 本件の場合にあてはめてみると、本件は救護と危険防止の各措置を分担することが許される事案であると考えられる
- なんとなれば、負傷者の救護については、事故状況と負傷の程度に照らし、一般の外科医の診断と治療を受けさせれば十分であると思料される状況であり、他方において道路の危険防止も緊急を要する状況であったからである(本件は、事故の後始末をより迅速に遂げるという観点からいえば、当事者間で分担することがむしろ望ましいケースである)
- そして分担をするとすれば、現実の事態の進行のように、最も優先して救護すべきものがA子であったから、同人の父であるYにおいて(自らの手当も含めて)まずA子に医師の手当を受けさせ、被告人は現場に残り、双方の自動車を車道から排除する等の措置を講じたうえで、独力で自らの負傷 につき手当を受ける(現実には3日後に医師の手当を受けた)という手順が妥当であろう
- ただ本件では、被告人に負傷者を救護する意思が有ったかどうかが問題である
- 現実に逃走していること、事故直後に相手方に非難をあびせていること、Mの観察によると、被告人には負傷者を助けるような素振りがみうけられなかった(そのためMが協力を申し出た)こと等からすれば、被告人はただ相手方の運転振りを非難し、一方では一刻も早く逃げ出したいとしか考えていなかったのではないかとの疑いが存するのである
- そこで、この点に関する被告人の弁解内容をみてみると、その内容は種々変遷するが、捜査段階以来ほぼ一貫している点を拾えば、それは要するに、「相手方との若干のやりとりのあと、泣いている子供を病院へ連れていかなければと思った。その矢先にMが連れて行ってやるというので有難かった。Mに伝わったかどうかは分らないが、自分からもMによろしく頼むと頭を下げたつもりである」というのである
- この被告人の供述内容は、あながち筋が通らないものでもなく、被告人がMの車を見送ったあと、最も危険なところに停止していた被告人車を道路端まで寄せたこと(これにより、被告人は危険防止の措置を尽したつもりでいること)、逃げこんだ先のT子に対し、「事故を起したが、相手の車に子供が乗っていて怪我をしていたので病院に運んでもらった」旨述べていることをあわせ考えると前記のM証言にもかかわらず、被告人に負傷者救護の意思がなかったとは言い切れない
- そうすると、本件においては、当事者間で明示の協議がなされた訳ではないが、事故発生後被告人逃走までの経過に鑑み、Yが子供を抱いてMの車に乗りこむころ、前記した内容で措置義務の履行を分担する旨当事者間で暗黙裡に合意がなされたと見ることができ、救護を分担したYにおいて(当人自身を含め)子供に医師の手当て診断を受けさせたことにより、被告人も救護義務の点についてはその履行を遂げたと言うべきであり、よって、検察官の主張は理由がない
と判示し、道路交通法違反(救護措置義務違反)の成立を否定しました。
3⃣ 道交法72条にいう運転者は「当該車両等の運転者」のことであって、必ずしも運転免許を受けている者に限りません。
この点に関する以下の裁判例があります。
東京高裁判決(昭和57年11月9日)
無免許運転で自動車事故を起こし、被害者を救護せずに立ち去った事案です。
裁判官は、
- 道路交通法72条1項後段にいう警察官の報告義務は、車両等の交通による人の死傷又は物の損壊があったときに、道路における危険と被害の増大を防止し、交通の安全をはかるため、車両運転という絶えず事故発生の危険を伴う行為に従事している当該車両の運転者又はその他の乗務員(運転者死傷のためやむを得ない場合)に対し法定の事項についての報告義務を課したものであり、その規定の仕方からみても運転が運転者免許取得者であるかどうかを問わないと解すべきであることが明白であるから、原判決が免許を有しない被告人に右報告義務違反の事実を認めたとしても、何ら誤りはない
と判示しました。
「その他の乗務員」とは?
1⃣ 「その他の乗務員」とは、
人又は物を特定の場所に運ぶという自動車本来の運行目的において、運転者とともに、目的を達成するための責任を有する者をいう
と解されています。
したがって、この「乗務員」の範囲を定める基準は、自動車の運行目的において「責任」を有しているかどうかにかかっているといえると考えられています。
例えば、乗合自動車の車掌、ハイヤー、タクシーの助手、トラックの貨物の看視者等がこれに当たると解されています。
この点に関し、参考となる以下の裁判例があります。
裁判所は、
- 被告人Aは、自己の雇人であり、材木の切出人夫をしていたBをして自動三輪車を運転させ、みずから助手席に乗って薪の運搬をしていたのであるから、被告人Aはまさに道路交通取締法第24条1項にいうところの「乗務員その他の従業者」に該当するものというべきである
と判示しました。
しかし、単なる乗客、便乗者等の同乗者、乗務に関係のない従業者等は含まれません。
もっとも、事実上乗務に関係しておれば足り、職業ないし職制として乗務員であることを要しないと解されています。
2⃣ 当該車両等の運転者その他の乗務員(以下、「運転者等」という)は、負傷者の救護、道路における危険の防止等必要な措置を講ずることについて、各個それぞれ独立してその義務を負うと解されています。
このことに関する以下の裁判例があります。
東京高裁判決(昭和46年6月15日)
裁判所は、
- 事故直後同乗していた前妻にまかせて、その場を逃げ去り、前妻と従業員が被害者を近くの病院まで連れて行き、前妻は診察が終るまで付き添っていたが、救護義務は運転者が死亡し、又は負傷したため、やむを得ない場合とか、法第72条4項に定める特別の場合を除き、原則として運転者自身が救護等の措置に当たることを要求しているものと解すべきであり、単なる同乗者に指示して救護に当たらせたからといって、運転者自身の救護義務が免除されたものと解すべきではない
- 同乗者が前妻にあたり、自己の子供を連れていたからといって、同女の行為を運転者の行為と同一視すべき事情も認め難く、従業員が助手席に同乗していてもその行為を運転者の行為と同一視すべきいわれはない
と判示しました。