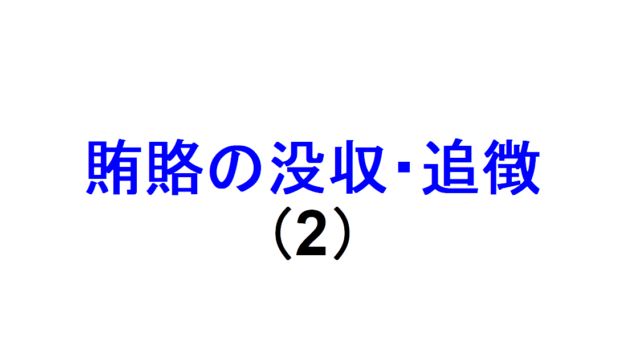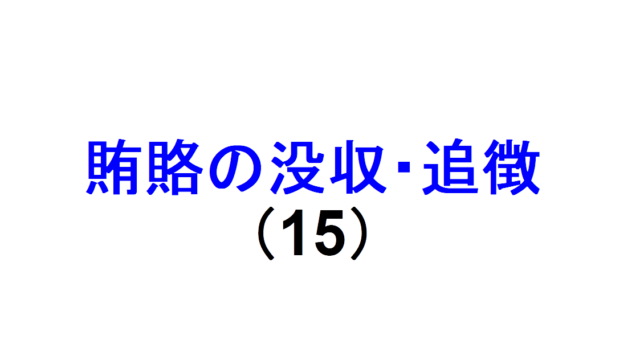単純収賄罪(19)~収受とは?③「単純収賄罪が成立するためには、『受け取った利益を自己において領得し又は享受する意思』が必要」を説明
前回の記事の続きです。
単純収賄罪が成立するためには、「受け取った利益を自己において領得し又は享受する意思」が必要
単純収賄罪(刑法176条)の「収受」とは、
- 賄賂を受け取ること
です。
そして、「収受」といえるためには、
- 受け取った利益を自己において領得し又は享受する意思
が必要です。
例えば、その利益について事実支配の移転があったとしても、
- 利益の提供を受けた者が、相手の立場や、従来の交際関係を考えて、折をみてこれを返還しようとしていた場合
- 事実返還したような場合
に、真実として、その利益を領得する意思がなかったのなら、賄賂性の認識があったとしても、収受は成立しません。
実際の裁判では、多くの場合、賄賂の収受者の弁解として、返還の意思があったと主張する例が多いので、証拠によって厳密に領得の意思の有無を決する必要があります。
その場合、賄賂性の認識がある限り、事実上の推定は、領得の意思が存在した方に強く働くことになると考えられます。
この点に関する以下の判例があります。
4月に5000円在中の鍋をもらって、その後、6月上旬になってKから先に与えられた鍋の中に現金の在中していたことを告げられ、Kから5000円を受け取ったが、そのままこれを所持していた事案で、被告人が5000円をKから受取ってこれを領得した時に賄賂収受の行為があったものと認定した事例です。
裁判所は、
- 金5000円の賄賂について、被告人はこれを贈賄者に返還するつもりで預っていたものであると弁解するにかかわらず、原判決が被告人がこれを収受したものと認定したのは、その証拠として挙げた被告人の原審公判廷における供述に徴し明らかなとをり、被告人が右5000円の賄賂たることを知りながら検挙直前まで(約3か月間)これを所持していた事情から、領得の意思を認めるに足るものとしたことによるものであって、かかる認定は不当ではない
と判示しました。
名古屋高裁判決(昭和30年6月28日)
裁判所は、
- 収賄被告人3名は、贈賄被告人らが交付した現金を返還すべく努力し、返還先が不明であったので、返還先が判明すれば、何時でも返還しようと思って、保管していたに過ぎないから、賄賂を収受する意思がなかったというにあるが、原判決挙示の証拠によれば、被告人Y5は、留守中に、妻が被告人Y1らから、原判決の現金を交付されたことを知り、昭和26年6、7月頃まで、数回、神戸町の役場又は被告人Y1方で返還しようと試みたが、受け取ってもらえなかったので、収賄被告人3名に原判示のように分配して各自が所持し、その後昭和27年3月頃、本件が司法警察員に知れ、捜査が開始せられるに及んで、はじめて返還したことが認められ、殊に被告人Y7は、受取った七千円のうち三千円を靴代金に充当し、返還する際補充したことが認められる
- 収賄被告人3名が、どうしても受領する意思がなく、あくまで返還する積りであったならば、昭和27年3月頃までに至らないうちに返還できたことが窺える
- 右の次第であるから、収賄被告人3名が賄賂を収受する意思がなかったと供述しているのは、本件発覚後、自己の罪を免れるため事実に添わない弁解を為しているものと認むるのほかはない
と判示しました。
東京高裁判決(昭和33年6月21日)
裁判所は、
- 賄賂を収受するとは、賄賂の目的物たる利益を自己において現実に取得することと解せられるのであるから、領得の意思をもってこれを受領するのでなければ賄賂の収受とは認められず、もし後日これを返還する意思で受け
取ったにすぎないときは未だ賄賂を収受したものと認められないことは所論のとおりである
と判示しました。
賄賂が無形的な利益の場合
収受した賄賂が無形的な利益(職務上の地位、異性間の情交など)の場合、「収受」といえるためには、
- 享受すること自体で領得の意思があった
ことになります。
一旦賄賂を領得した以上、その後に賄賂を他の者が領得しても収受なしとはならない
1⃣ 賄賂を一旦領得した以上、その後、他の者がその賄賂を領得・享受しても、収受なしということにはなりません。
この点に関する以下の裁判例があります。
福岡高裁宮崎支部判決(昭和33年10月28日)
供与の趣旨を了承して賄賂を一旦受領した後、妻から横取りされた事案です。
裁判所は、
- 賄賂提供者においてその意思をもって提供したとしても、相手方において犯意が認められない等の場合には相手方は処罰の対象とはならず単に賄賂提供のみ処罰せられ得ることは当然であって、被告人Kは一旦右供与の趣旨を了承の上受領する意思をもってこれを受け取ったものであるから、その後妻からこれを横取りされた(同人の妻は多分Mに対する嫉妬によりかような挙動にいでたものと推測せられる) としても、これを受領し自己の実力支配内に置くと同時に収賄の罪を構成するということができる
- 従って原判決が被告人Kにおいてこれを受領したものでないとして、被告人Bほか4名に対して単に賄賂の申込をしたに過ぎない旨認定したことは事実を誤認したものというべきである
と判示しました。
2⃣ 収受者が賄賂を自分のためではなく、他のために費消したとしても、収受者に賄賂の処分権が一任されている限り収受罪が成立します。
この点に関する以下の裁判例があります。
- 収受した賄賂を課のために費消した事例(東京高裁判決 昭和31年8月20日)
- 収受した賄賂を公の会議のために費消した事例(大阪高裁判決 昭和32年7月17日)
- 収受した賄賂を課の忘年会のために費消した事例(仙台高裁判決 昭和27年9月27日)
- 収受した賄賂を事業所の諸経費のために費消した事例(名古屋高裁金沢支部判決 昭和34年10月27日)
なお、賄賂が公務員個人に対してではなく、官公署に対する寄付として授受された場合には、第三者供賄罪(刑法197条の2)の成立はあり得ても、賄賂を受け取った公務員個人の単純収受罪(刑法197条)は成立しません。