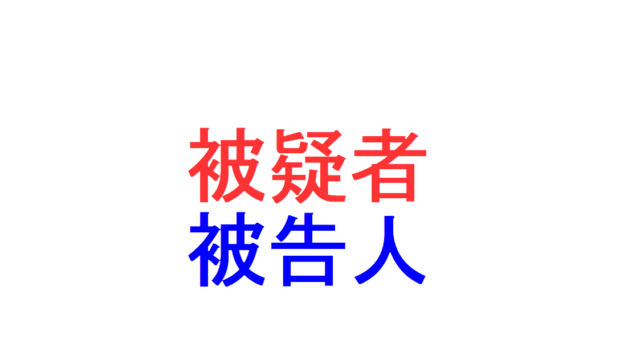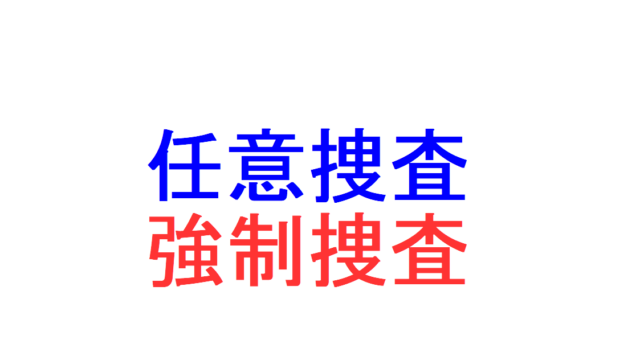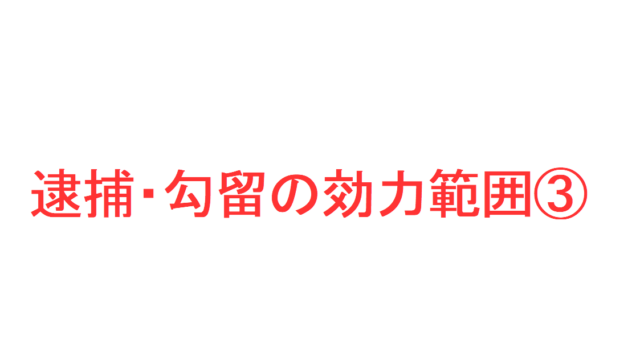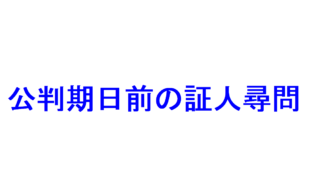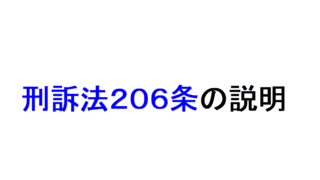「抗告、準抗告の違い」「特別抗告」「『準抗告・抗告・特別抗告』と『裁判執行停止の申立て』の関係」を説明
刑事手続において、抗告、準抗告を理解するに当たり、
- 抗告を理解する
- 準抗告を理解する
- 抗告と準抗告の違いを理解する
- 予断排除の原則を理解する
- 抗告、準抗告、予断排除の原則との関わりを理解する
という流れで理解するとよいです。
なお、抗告、準抗告(刑訴法第4章:419条~434条)は、分かりやすくいうと「不服申立て」のことです。
では順に説明していきます。
抗告とは?
1⃣ 抗告は、
裁判所(地方裁判所・簡易裁判所・家庭裁判所)のした決定に関して高等裁判所に対して行う不服申立ての方法
2⃣ 抗告はいつでも行うことができます(ただし、即時抗告の場合を除く)。
つまり、「裁判所の決定があってから〇日以内に抗告をしなければならない」といった期間の制限はありません(刑訴法421条)。
3⃣ 抗告裁判所のした決定に対しては、抗告をすることはできません(再抗告の禁止)(刑訴法427条)。
抗告裁判所のした決定に対して不服を申し立てる場合は、最高裁判所に対して特別抗告を申し立てることになります。
4⃣ 上記のとおり抗告裁判所のした決定に対して抗告をすることはできませんが、抗告裁判所に抗告が棄却された後、もう一度、同じ内容の抗告をその抗告裁判所に行うことを制限する規定はありません。
つまり、抗告が棄却されても、再トライを繰り返して、何度でも抗告裁判所に対して抗告を申し立てることができます。
ただし、この場合、抗告裁判所は、抗告の申立てが不適法として抗告を棄却する決定をすると考えられます。
よって、一度抗告が棄却されたのに、再び抗告の申立てを行うことの実益はないといえます。
5⃣ 高等裁判所の決定に対する抗告は禁止されていますが、抗告に代わる異議申し立てをすることができます(刑訴法428条)。
準抗告とは?
1⃣ 準抗告は、
- 裁判官(地方裁判の裁判官・簡易裁判所の裁判官)のした裁判(命令)
又は
- 捜査機関(司法警察職員、検察官、検察事務官)のした処分
に関して地方裁判所に対して行う不服申立ての方法です(刑訴法429条、430条)
2⃣ 準抗告の対象となる項目は、
- 忌避の申立を却下する裁判
- 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判
- 鑑定のため留置を命ずる裁判
- 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
- 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
3⃣ 準抗告はいつでも行うことができます(ただし、刑訴上429条1項4号・5号の裁判に対するものを除く)(刑訴法429条5項)。
つまり、「裁判所の裁判があってから〇日以内に準抗告をしなければならない」といった期間の制限はありません。
4⃣ 準抗告裁判所の裁判官した裁判に対しては、準抗告をすることはできません(刑訴法432条、427条)。
準抗告裁判所の裁判官がした裁判に対して不服を申し立てる場合は、最高裁判所に対して特別抗告を申し立てることになります。
5⃣ 上記のとおり準抗告裁判所の裁判官がした裁判に対して準抗告をすることはできませんが、準抗告裁判所の裁判官に準抗告が棄却された後、もう一度、同じ内容の準抗告を準抗告裁判所の裁判官に行うことを制限する規定はありません。
つまり、準抗告が棄却されても、再トライを繰り返して、何度でも準抗告裁判所の裁判官に対して準抗告を申し立てることができます。
ただし、この場合、準抗告裁判所の裁判官は、準抗告の申立てが不適法として準抗告を棄却する決定をすると考えられます。
よって、一度準抗告が棄却されたのに、再び準抗告の申立てを行うことの実益はないといえます。
抗告と準抗告の違い
抗告と準抗告の違いについて押さえておくポイントは以下の2点(「裁判所」or「裁判官」、「高等裁判所」or「地方裁判所」)です。
1点目
抗告→「裁判所」がした決定に対する不服申立てであること
準抗告→「裁判官」がした命令に対する不服申立てであること
2点目
抗告→「高等裁判所」宛てに不服を申し立てること
準抗告→「地方裁判所」宛てに不服を申し立てること
抗告と準抗告の使い分けの考え方
抗告と準抗告の使い分けの考え方は、「予断排除の原則」と密接な関係があります。
※ これを理解するに当たり「裁判所」と「裁判官」を区別することが重要です。
予断排除の原則とは、
裁判所は、第1回公判期日(1回目の公判)までは、起訴された事件についての偏見又は予断を持たずに審理に臨まなければならないとする原則
をいいます。
なお、「第1回公判期日まで」とは、「冒頭手続の終了まで」をいいます(詳しくは前の記事参照)。
ここで、上記の「裁判所は」というワードがポイントになります。
つまり、予断排除の原則があるため、
裁判所は、「裁判所として」、第1回公判期日まで(冒頭手続が終了するまで)、事件に対する予断や偏見を抱いてはいけないので、事件記録を見てはならない
ということになります。
なので、第1回公判期日前は、「裁判所」ではなく「裁判官」(具体的には、公判を担当しない裁判官)が、勾留、保釈、押収又は押収物の還付などの刑訴法429条、430条の準抗告の対象となる項目に関する裁判を行います。
上記項目の裁判をする際、裁判官は、必ず事件記録を見ることになります。
そこで、「裁判官」でも「公判を担当しない裁判官」であれば、事件記録を見ても、公判に立ち会わないことから予断排除の原則に反しないため、「裁判官」であっても「公判を担当しない裁判官」が上記項目の裁判を行うことになります。
ここで、第1回公判期日前は、「裁判所」ではなく、「裁判官」が上記項目の裁判を行うことを押さえてください。
つまり、第1回公判期日前に行われた上記項目の裁判に対する不服申立ては、
- 準抗告の要件である「裁判官」がした命令に対する不服申立て
となることから、「抗告」ではなく、「準抗告」により行われることになります。
【参考事項】
公訴提起後、第1回公判期日までは、勾留に関する処分(勾留、勾留更新、接見禁止、勾留取消し、勾留理由開示、勾留執行停止、保釈など)は、公訴提起を受けた裁判所(受訴裁判所)ではなく、事件の審判に関与しない裁判官が行う
こととされます。
これも予断排除の原則を実現するための規定であり、第1回公判期日前については、「公判を担当しない裁判官」が勾留に関する処分を行うという法律の設計になっている点が参考になります。
第1回公判期日終了後の不服申立ては「抗告」になる
第1回公判期日終了後は、予断排除の原則がなくなるため、上記項目の裁判は、「裁判官」ではなく、「裁判所」が行うようになります。
よって、第1回公判期日終了後に行われた上記項目の裁判に対する不服申立ては、
- 抗告の要件である「裁判所」がした決定に対する不服申立て
となることから、「準抗告」ではなく、「抗告」により行われることになります。
抗告と準抗告の使い分け
以上のことを総合し、抗告と準抗告の使い分けの考え方を端的にいうと、
- 第1回公判期日前に行われる不服申立ては、地方裁判所の裁判官に対して行う「準抗告」となる
- 第1回公判期日終了後に行われる不服申立ては、高等裁判所に対して行う「抗告」となる
となります。
別の言い方をすれば、
- 「準抗告」は、第1回公判期日前に行う不服申立てで、地方裁判所の裁判官に対して行うもの
- 「抗告」は、第1回公判期日終了後に行う不服申立てで、高等裁判所に対して行うもの
となります。
なお、「準抗告申立書」の宛名は地方裁判所、「抗告申立書」の宛名は高等裁判所となりますが、「準抗告申立書」と「抗告申立書」の書面自体は、両方とも地方裁判所の窓口に提出されることになります(刑訴法423条、431条)。
そして、「抗告申立書」については、地方裁判所が高等裁判所に送り届けることになります。
特別抗告とは?
1⃣ 準抗告と抗告のほかに、「特別抗告」があります。
特別抗告とは、
準抗告・抗告としては不服を申し立てることができない決定又は命令に対して、憲法違反又は判例相反を理由として、特に、最高裁判所に抗告することが許されている不服申立ての方法
「特別抗告」は、
- 被告人・弁護人、検察官が、裁判所又は裁判官に対し、準抗告又は抗告を行った
- しかし、裁判所又は裁判官は、準抗告又は抗告を認めない判断をした
- 被告人・弁護人、検察官は、その判断に納得がいかないため、更に不服を申し立てることにした→特別抗告
という状況の場合に、憲法違反又は判例違反を理由として、最高裁判所宛てに「特別抗告」が行われることとなります。
2⃣ 特別抗告の提起期間は5日です(刑訴法433条2項、55条)。
つまり、特別抗告は、準抗告・抗告としては不服を申し立てることができない決定又は命令があった後、5日以内に最高裁裁判所に申し立てる必要があります。
3⃣ 「特別告申立書」の宛名は最高裁判所となりますが、「特別告申立書」の書面自体は地方裁判所に提出されることになります(刑訴法434条、423条)。
そして、「特別告申立書」は、地方裁判所が最高裁判所に送り届けることになります。
「準抗告・抗告・特別抗告」と「裁判執行停止の申立て」の関係
準抗告、抗告、特別抗告は、裁判の執行を停止する効力はありません(刑訴法424条、刑訴法432条、刑訴法434条)。
「裁判の執行を停止する効力がない」とは、例えば、
- 勾留請求却下決定の裁判に対し、検察官が準抗告したとしても、勾留請求却下の裁判は効力を失わないので、被疑者は釈放されることになる
- 保釈許可決定の裁判に対し、検察官が抗告や特別抗告をしたとしても、保釈許可決定の裁判は効力を失わず、保釈許可となった被告人は保釈されることになる
ということを意味します。
そこで、検察官は、準抗告・抗告・特別抗告を行っている途中で、被疑者が釈放されたり、被告人が保釈されないように、裁判所に対し、「裁判執行停止申立書」を提出し、裁判執行停止の申立てを行います。
検察官の裁判執行停止の申立てが認められ、裁判所が「裁判執行停止決定」を発付すれば、準抗告・抗告・特別抗告の裁判が終わるまでの間、勾留請求却下決定の裁判や保釈許可決定の裁判は停止され、被疑者が釈放されたり、被告人が保釈されることはなくなります。
「裁判執行停止決定」を発付する裁判所
「裁判執行停止決定」を発付する裁判所は、準抗告・抗告・特別抗告のいずれについても、地方裁判所になります(刑訴法424条、刑訴法432条、刑訴法434条)。
地方裁判所である理由は、「裁判執行停止決定」は速やかに発布される必要があるものであり、高等裁判所や最高裁判所が判断を行うことにすると「裁判執行停止申立書」が高等裁判所や最高裁判所に届く頃には、とっくに被疑者が釈放されたり、被告人が保釈されているという状態になってしまうためです。
「裁判執行停止申立書」の提出先の裁判所
裁判執行停止の申立ては、準抗告・抗告・特別抗告と同時に行われるものであり、「裁判執行停止申立書」の宛先と提出先も「準抗告申立書」「抗告申立書」「特別抗告申立書」と同じになります。
準抗告であれば、「裁判執行停止申立書」の宛先は地方裁判所となり、その提出先も地方裁判所になります。
抗告であれば、「裁判執行停止申立書」の宛先は高等裁判所となり、その提出先は地方裁判所になります。
特別抗告であれば、「裁判執行停止申立書」の宛先は最高裁判所となり、その提出先は地方裁判所になります。