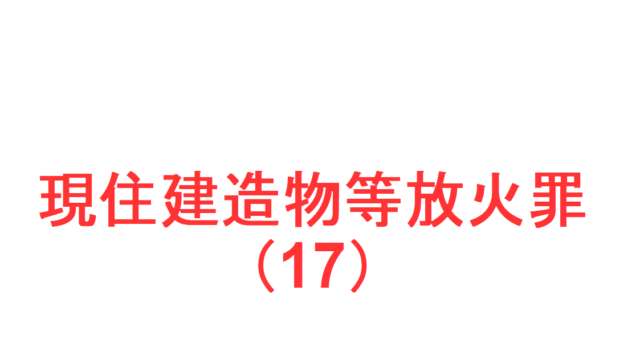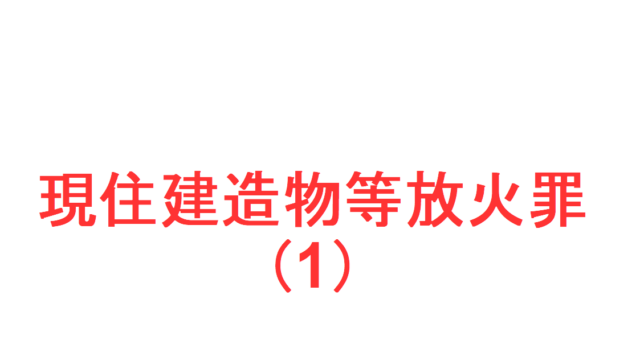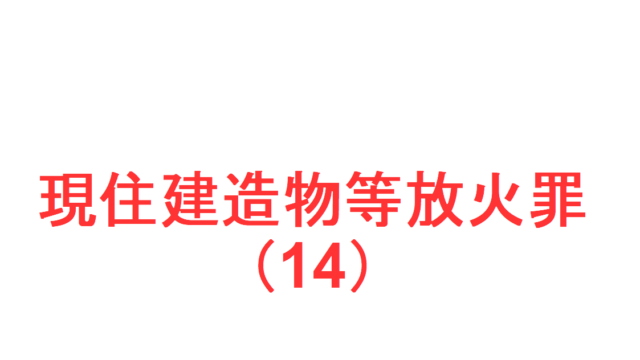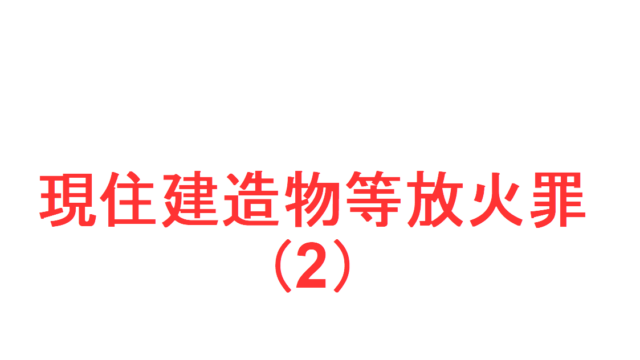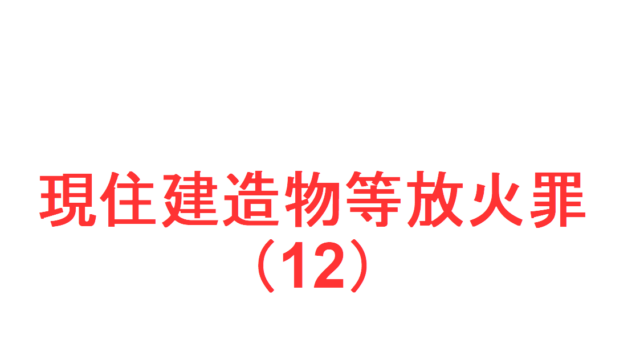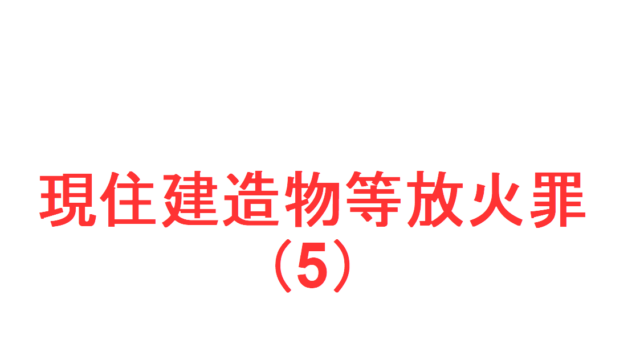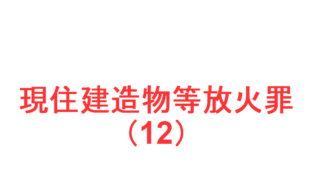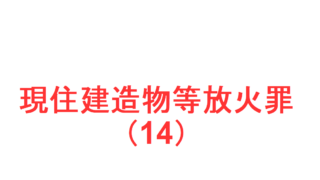現住建造物等放火罪(13) ~「故意の成立要件」を説明~
前回の記事の続きです。
現住建造物等放火罪の故意
現住建造物等放火罪(刑法108条)は故意犯です。
なので、現住建造物等放火罪が成立するには、「現住建造物を放火する」という故意が必要になります(故意についての詳しい説明は前の記事参照)。
現住建造物等放火罪の故意の成立には、
- 現に人の住居に使用し、又は現に人がいる目的物である旨の認識
及び
- これに火を放って焼損することの認識
が必要です。
この点を判示したのが以下の判例です。
大審院判決(昭和4年6月13日)
裁判官は、
- 犯人の住家を焼燬するの意思なかりし場合は本罪は成立せざるものなり
- 住家とは、犯人以外の他人居住し居る家屋のいうが、犯人においてその住居の認識を有することを必要とす
- 本条の罪の成立には、犯人において、本条の目的物を焼燬する意思をもって放火するをもって足り、進んで他人の身体財産上に危害を及ぼすの意思をを必要とせざる
と判示しました。
現に人の住居に使用するという認識を有するときは、放火行為の当時、現に人がいず、あるいは犯人が現に人がいることを認識している必要はない
現に人の住居に使用するという認識を有するときは、放火行為の当時、現に人がいず、あるいは犯人が現に人がいることを認識しなかったとしても、故意の成立を妨げません。
この点を判示したのが以下の判例です。
大審院判決(大正3年6月9日)
裁判官は、
- 裁判所の建物は、刑法の適用上、人の住居に使用する建造物なるをもって、放火の当時、人が現在せず、又は犯人において、当時、人の現在することを認識せざりしとするも、人の住居に使用する建造物なることを認識して、これに放火したる以上は、刑法第108条の犯罪を構成するものとす
と判示しました。
積極的に焼損を意欲している必要はない
焼損の結果発生の予見、すなわち目的物の独立燃焼を惹起しうべき旨の認識があれば足り、あえてその結果発生を目的とすること、あるいは積極的に焼損を意欲しあるいは希望することを必要としません。
参考となる裁判例として、以下のものがあります。
東京高裁判決(昭和36年11月7日)
現に人がいる母家に接着した物置に放火した被告人が、母家に延焼することは希望しておらず、むしろその延焼を考えて放火の決行にいささか躊躇した情況はあるものの、母家との接着の状況、放火の位置から、火勢が母家に及ぶことは当然予見していたと認められるとして、現住建造物放火の故意を認めた事例です。
裁判官は、
- 被告人が放火したところは、Y方物置内のわらが積み重ねてあった場所であり、右物置が、同家居宅の母屋の部分と別棟の建物であるけれども、右物置は前言母屋東側庇の部分と直角に接着し、殊に被告人が放火した前記わらの積み重ねてあった場所は、右物置内の前記母屋に極みて接近したところであって、同所に放火すれば、右物置を焼燬するにとどまらないで、これに接着した前記庇の部分より母屋に延焼することは必至の状況にある
- 被告人は、右物置小屋に放火することは考えていたけれども、母屋を焼く意思はなかったと主張するけれども前記の如き状況において物置小屋内のわら積みに放火すれば、当然火勢は前記母屋に及んでこれを焼損するであろうことは、被告人において十分予見していたこと記録上明瞭なところであるから、仮に被告人が右母屋に延焼することは希望しておらす、むしろその延焼をえて放火の決行にいささか躊躇した情況は認められるのであるが、少くとも前記Yら族の就寝していた前記母屋に延焼することを予見しながら、これに接着した右物置に放火した以上、現住建造物放火罪の成立することは言うをまたない
と判示しました。
行為者の意思がその現住部分以外の部分のみを焼損する意思にすぎないとしても、現住建造物等放火の故意が認められる
建造物の一部が住居に充てられ、あるいは一部に現に人がいる場合、行為者の意思がその現住部分以外の部分のみを焼損する意思にすぎないとしても、全体が1個の建造物であるとの認識があれば、建造物全体に対する故意の成立を妨げません。
逆にいえば、1個の建造物であるとの認識がなければ、現住建造物である旨の認識を欠くことになるため、現住建造物等放火罪の故意は認められず、非現住建造物放火罪が成立することになります。
参考となる判例として以下のものがあります。
裁判官は、
- 被告人が火を放った便所は、劇場建物の東側に接着するものであることは、原判決の確定するところであり、原判決の挙示する証拠、殊に強制処分における判事の検証調書の記載、同調書添付の図面によれば、右便所は右劇場に接着して建設ぜられ、右劇場の一部をなすものであることがわかる
- しかして、被告人が本件犯行にあたり、右便所を焼燬する意思のあったことは、原判決挙示の証拠上明瞭であるから、これにもとずいて、原判決が、被告人は本件劇場に放火しようと考えた旨判示したのは、相当である
- また、右劇場には、人が寝泊りしていることを被告人が知っていたこと、及び、放火の結果、既に独立燃焼の程度に達する焼燬のあったことも、右証拠に照してあきらかであるから、原判決が、被告人の右の所為に対して、刑法第108条の既遂罪をもって、問擬したのは正当である
と判示しました。
大審院判決(昭和3年2月1日)
裁判官は、
と判示しました。
故意の成立に公共の危険の認識は必要としない
現住建造物等放火罪は、抽象的危険犯であって、刑法108条所定の客体(現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑)の焼損は当然に公共の危険を生ぜしめるものと擬制され、公共の危険発生は構成要件要素ではないから、
故意の成立に公共の危険の認識を必要としない
とするのが通説になっています。