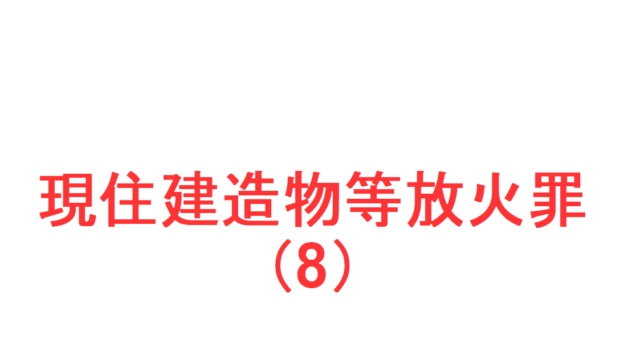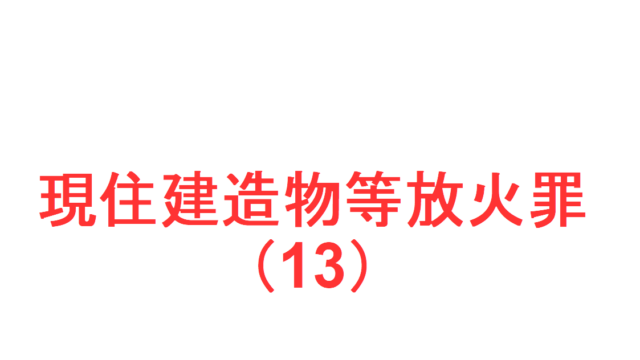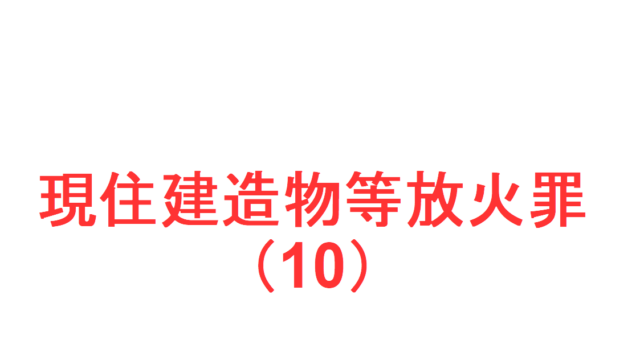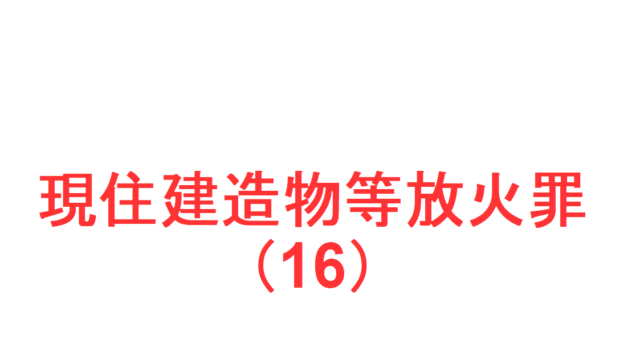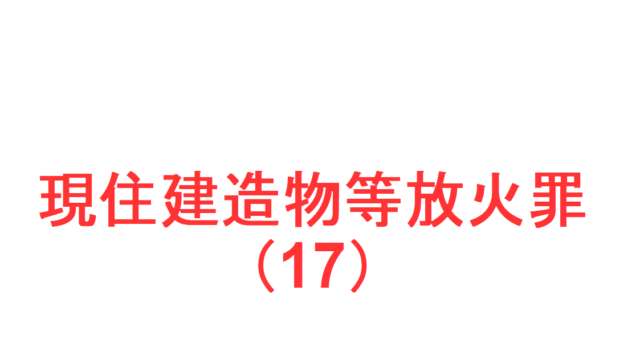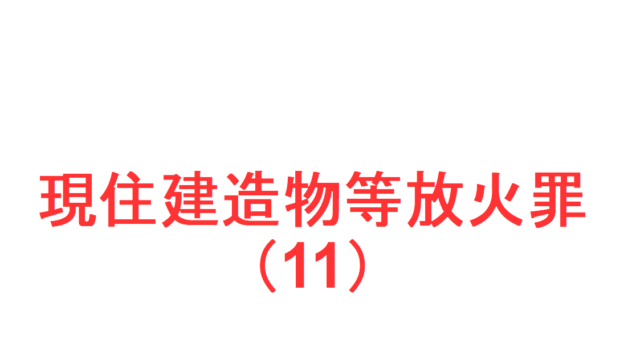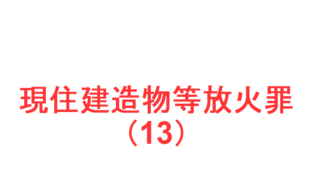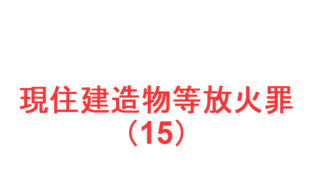現住建造物等放火罪(14) ~「未必の故意」を説明~
前回の記事の続きです。
未必の故意
現住建造物等放火罪(刑法108条)は故意犯であり、本罪が成立するには、本罪を犯そうとする故意が必要です。
その故意は、必ずしも確定的故意である必要はなく、未必の故意(みひつのこい)をもって足ります。
未必の故意とは、
犯罪結果の発生を確実なものとして認識・容認していないが、犯罪結果が発生しても構わないと考え、犯罪結果を発生させることが可能なものとして認識・容認している場合の故意
をいいます。
つまり、現に人の住居に使用し、又は現に人がいる目的物であることの認識、及びこれを焼損することの認識のいずれについても未必的認識があれば、現住建造物等放火罪の故意の成立が認められます。
※ 確定的故意と未必の故意の説明は前の記事参照
未必の故意の有無が問題となる場合として、
- 単に人を驚かすためなどのように、現住建造物を直接に焼損する目的・意欲のないまま、現住建造物に延焼する可能性のある物件に点火する場合
- 現住建造物に隣接した非現住建造物を放火する場合
が挙げられます。
未必の故意を認めた裁判例
未必の故意があったかどうか争点となり、未必の故意が存在が認められた裁判例として以下のものがあります。
建物の庇下に堆積されているわらに放火すれば、その建物及びこれに隣接する住家に延焼する危険があることは常識上認められる事柄であるから、被告人に延焼の認識があったものと認められるとした事例です。
裁判官は、
- 建物の庇下に堆積されているわらに放火すれば、その建物及びこれに隣接する住家に延焼する危険があることは常識上認められる事柄であるから、特にAの供述のようなものがない場合でも、各被告人に建物に延焼の認識があったものと認め得られる
と判示しました。
大阪高裁判決(昭和27年11月18日)
寺院の土蔵内に忍び込み、宝物を窃取する目的で土蔵の床下から床板を焼き切った事案について、窃盗目的を達する手段としての放火行為であり、土蔵を焼損する目的はないが、これが焼失する結果発生を予見していた以上、放火罪の成立は明らかだるとした事例です。
裁判官は、
- 原判決の認定するところによると被告人は雲竜院の土蔵の床下から床板の一部を焼切って土蔵内床上に忍び込み宝物を窃取することを企て、3月31日午前1時頃、右土蔵裏空地で焚き火し燃焼している棒2本を持って土蔵東側の床下通風窓から床下に忍び込み、南蔵床下西北隅にむいて東西に渡された根太と床板の間に右2本の棒を当てロでその炎を吹き起したというのであるから、原判決も被告人が本件土蔵を焼こうという意思があったとは認めていないし、判示もしていないのである
- しかし原判決は右の事情で床板を焼いた行為が放火行為に当り、その結果土蔵内部の大部分を焼失させたので放火の既遂として処断しているのである
- たとえ被告人のいうように土蔵を焼こうという目的がなかったにしても、窃盗の目的を達する手段として放火行為をした以上放火罪の責任を免れるわけにはいかない
- また、たとえ本件床下だけを焼く目的であっても、この床板を焼いた場合には、土蔵が焼けるおしれがあることが明らかであるから、本罪の成否を左右することはできない
- 殊に原判決挙示の証拠によれば、被告人は本件土蔵が焼失する結果を発生するかもしれないことを予見しながら、本件床板を焼いた事実が認められるから、たとえ被告人の目的が専ら窃盗にあったとしても放火罪の成立は明らかである
と判示しました。
東京高裁判決(昭和30年12月6日)
紙くず、わらくず等に点火し住宅に接着した塵芥箱等に接触させ、あるいはこれを倉庫に投げ込んだ場合、建物を焼損するに至ることは当然予見し得べきとした事例です。
裁判官は、
- 建造物放火罪の犯意は、建造物焼燬の結果を発生すべきことを予見するをもって足りるのであり、敢てその結果の発生を目的とすることを要しないものと解するのが相当である
- 本件において、被告人は、住宅及び倉庫に放火する方法として、ござ、紙くず、わらくず等に所携のマッチをもって点火し、これを右各住宅に接着して置かれた塵芥箱又はわらすだれに接触せしめ、あるいは右倉庫内に投げ込んだことが、原判決挙示の証拠によって認められるので、かような導火材料の燃焼作用により前示各建造物を焼燬するに至るべきことは当然予見し得ぶきところであるから、たとえ被告人にこれら建造物を焼燬しようとする積極的な意図がうかがわれないとしても、放火罪の犯意を欠くものということではきない
と判示しました。
仙台高裁秋田支部判決(昭和31年8月21日)
十分に乾燥した長さ約1.5mの枯れ芝10本を束にした物を座敷の障子より約36cmに近接した場所に置き、かつ、枯れ芝と天井桁との距離は約2.5mあるにすぎず、家が焼けた場合に電線が切れて漏電をしては他家に迷惑がかかるかもしれないと思い、あらかじめ安全器を外した上で所携のマッチで枯れ芝に点火した場合は、たとえ被告人の主たる目的は家人を脅迫するにあったとしても放火の未必的故意あるものと認められるとした事例です。
裁判官は、
- 本件枯柴のおかれた場所、その枯柴より南側障子及び天井桁あるい棟木に至る距離は極めて近接しており、この数量の枯葉が焼燬するにおいては、その火力は直ちに家屋の一部に燃え移り、該家屋を焼燬するに至るべきことは疑問の余地ない
- 更に被告人の検察官に対する供述調書には、被告人においては家が焼けた場合に電線が切れて漏電等をしてはと思ってあらかじめ電燈の安全器を開け、姉から借りて来たマッチをとり枯柴の枯葉のついている部分にマッチを擦り火をつけた旨の被告人の供述記載がある
- 更に原審における検証の際にも、同人は枯柴に火をつけたらそのまま家まで燃えるかも知れないと思い、家まで燃えた場合、安全器をそのままにしておくと漏電かなんかのために他家に迷惑がかかるかも知れないと思い、安全器を外した旨の供述をなしており、原審公判廷及び当審における検証の際にも立会人として同様な供述をなしているのである
- かつ、前述の枯柴の質と量、特にそれが十分乾燥された燃えやすいものであったこと、すなわち原審検証調書の記載によれば、小枝の多い細い柴枝であり普通乾燥して燃料に供されているものであること、しかしてその量も相当多量であり、すなわち調書の記載によれば、枯柴は約5尺長さのもので、数10本を一束にしてなわで縛ったものであると認められること、なお、その枯柴が最も燃えた時の炎の高さは約4尺5寸もありたこと等の諸事実を総合すると、被告人は前記枯柴に火を投じこれが焼燬するにおいては、本件家屋に延焼してこれを焼燬すべきことを十分認識していたものと認めるを相当とする
と判示しました。
宮崎地裁延岡支部判決(昭和33年1月16日)
住家に接続した馬小屋内のかます等に点火した上、自動車用チューブをのせて火勢を強めた事案につき、家屋焼損の未必の故意を認めた事例です。
裁判官は、
- かます、魚網、布切れ等に点火すればKらの居住するK所有の木造中2階建瓦葺住家建坪20坪位1棟に燃え広がってこれを焼燬するに至るべきことを認識しながらあえて所携のマッチ5本位を順次擦って同小屋内のかますの端に点火し、さらにその付近にあった魚網及び布切れを右のかます横に持って来て右マッチでこれらにも点火し、この上に自動車用チューブをのせて火勢を強めたため、右草葺平家建木造馬小屋建坪15坪位1棟に燃え移りさらに前記家屋に燃え拡がらせてこれを全焼せしめたものである
と判示し、未必の故意による現住建造物等放火罪が成立するとしました。
未必の故意を否定した裁判例
上記裁判例とは逆に、未必の故意を否定した裁判例として以下のものがあります。
東京高裁判決(昭和29年10月19日)
女将の客扱いに不満を抱き意地はらしのため点火した巻たばこを掛布団の布と綿の間に挿入して立ち去った事案につき、一般に家屋内の布団に放火して放置した場合、家屋の一部をも焼損する結果を招くこともあり得ることは経験上予想され、特別の事情のない限り通常人はこれを予見するものと認めるのが相当であるが、本件では当該布団が他の遊客や女中のため再び敷き延べられるもので、被告人も火事になるまでには当然消し止められると考えていたことが窺われ、被告人に放火の未必の故意は認められないとした事例です。
裁判官は、
- 被告人に住宅放火の犯意を認定したがった原判決の当否について訴訟記録を調査するに、原審及び当審で取調べたすべての証拠をもってしても被告人に本件家屋を焼燬する意思があったことを認ることはできない
- 然らば、いわゆる未必的な故意を認めることができるかどうかの点であるが、家屋の中にある布団に放火しそのまま放置すれば、その布団を焼燬し、布団を焼燬すればその付近の畳、建具その他の物件に延焼し、家屋の一部をも焼燬する結果を招くこともあり得ることは一般経験上予想せられるところであって、特別の事情のない限り通常人は何人もこれを予見するものと認めるのが相当である
- しかしながら記録によれば、判示布団は女中Mの専用として雇主から貸し渡されているもので、客との遊興が終ればその都度別室に片付け、次の客があれば更にこれを持ち出して使用し、やがで自己が就寝するときはまたこれを使用するのであって、遅くも同人の就寝時刻までには再びこれを寝間に敷き延べるもので、そのままいつまでも放置しておくものでないことが認められ、被告人に対する司法警察員の供述調書中被告人の供述として「また別な遊び客でもくればそんなに大きくならないうちに発見して火事になるまでには何とか消し止めるんだろうと思ったので知らぬふりしてその部屋を出た」との記載がある点に徴しても被告人としては右布団が火事になるまで放置されるものではないと考えていたことが窺われるのである
- のみならず被告人は当時適量以上に酒を飲み良い気嫌でK方に行き、女中Mの勧めにより遊興したのであるが、原判示のように同女及び同家女将等の客扱いに不満を抱き、その意地はらしのため点火した巻煙草を掛布団の布と綿との間に挿入して立ち去ったことが認められるのであるから、かかる情況のもとにおいては被告人が右煙草の火が布団を焼燬し、更に畳、建具その他の物件に延焼し、家屋の一部をも焼燬する結果を招くかも知れないということを予見していたとは認め難い
- もっとも被告人に対する司法警察員に対する第1回供述調書及び検察官に対する第12回供述調書中には「そのまま放っておけば火事になるのではないがと思っていた」という趣旨の記載があるが、右供述記載は前記の理由により被告人が右犯行の際家屋焼燬について未必の故意を有していたという真意を述べたものとはたやすく措信し難く、その他被告人の未必的故意を認め得べき証拠は存しない
- 然らば原審が被告人に住宅放火の犯意を認めなかったのは正当である
- しかしながら訴訟記録及び当審事実審理の結果によると、被告人が原判示の如く点火した巻煙草1本を判示掛布団の裏側の布と綿との問に挿入したまま同所を立ち去ったため、右巻煙草の火により該掛布団及び敷布団の各一部を原判示の如く焼燬し、そのまま置すれば同家建物に延焼し大事に至るべきおそれありと思料せしめるに相当な状態を生ぜしめ、因りて公共の危険を生ぜしめた事実を認めることができる
- 然らば被告人の本件所為は正に刑法第110第1項に該当するのであるのに原審が単に器物損壊罪と認定処断したのは事実の認定を誤ったものでありその誤りが判決に影響を及ぼすこともちろんであってこの点において論旨は結局理由があり、原判決は刑事訴訟法第397条により破棄を免れない
と判示し、被告人に放火の未必の故意は認められず、現住建造物等放火未遂罪は成立しないが、建造物等以外放火罪(刑法110条1項)が成立するとしました。
大阪地裁判決(昭和32年5月28日)
たばこの吸い殻を押入の敷居付近ですり消しただけで十分消えていないものを、確認もしないで押入の中に放り込んで外出したため家屋を焼損した事案につき、未必の故意を否定し、現住建造物等放火罪は成立しないとし、失火罪(刑法116条)が成立するとした事例です。
裁判官は、
- 専門家であって当時被告人を調べた証人N警部補も当公廷において「認識ある過失と未必の故意との区別を法廷で言えと言われても言いにくい」と述べる如く、その差は紙一枚であって筆のあやでどちらにでも持って行けるのであり素人がこれを区別することは不可能であるから捜査官において多少誘導したり詳細に質問したりして何れかのレールにのせるのが通常である
- 本件において被告人がダイナマイト等を持ち出すのはともかくとして、燃やすならこすって消すこともなくそのまま吸い殻を放り込むと述べているのは必ずしも嘘とばかり思えないものがあり、平素度々敷居等でもみ消しており、本件は放り込む前にこすって消す動作をしているのであるからこの決定的な動かない事実は本件が故意に基ずくものか、それとも過失によるものかを認定する重要な要素といわねばならぬ
- 被告人の各供述を素直に判断するときはそれは、放火の未必の犯意というより、むしろ失火の認識ある過失というべきである
- 被告人が翌日出火をきいてやっぱりあれかと思ったことや、友人K、Yらとの会話の内容も認識ある過失の認定と毫も矛盾しない
- 以上被告人未必の故意に関する警察、検察庁の供述調査は文章のあやというのほかなく結局信用できない
- 前記各認定した証拠によれば失火に関する限り優に証明ありというべく、従って放火の訴因については無罪であるが、検察官が予備的に失火に訴因を変更しているので、その点特に無罪の言渡をしない
と判示しました。
横浜地裁判決(平成21年10月8日)
駐車中のスクーターのハンドルに掛けられていたビニール傘に火を付け寮の柱等を焼いた事案につき、ビニール傘の燃焼力の弱さを考慮するとスクーターに容易に燃え移るとは考えられず、寮まで燃え移るかもしれないとの認識があったとは認定できないとし、現住建造物等放火罪の成立を否定し、建造物等以外放火罪(刑法110条1項)が成立するとした事例です。
裁判官は、
- 本件ビニール傘、スクーター、柱等の相互の位置関係についての客観的事実は、被告人の本件家屋に対する延焼の認識を強く推測させる事実とまではいえない
- 問題となっているのは、被告人が、ビニール傘とスクーターという2つの媒介物を経由して本件家屋へ火が燃え移るかもしれないと思っていたか否かであるところ、ビニール傘からスクーターへの燃え移りのプロセス、スクーターにおける燃え広がりのプロセス、そして、スクーターから本件家屋への燃え移りのプロセスの3つのうち、最初の2つのプロセスについては、いずれも、一般に検察官が主張するのと比べて、かなり進行しにくいとのイメージが抱かれているのであり、さらには、それらの相乗作用の点をも考慮しなければならないことに照らすと、本件当時、風が吹いていたこと等、証拠によって認められるすべての事情を総合考慮しても、被告人において本件家屋に火が燃え移るかもしれないとの認識を有していたことに向けての検察官の立証は、常識に照らして間違いないと言い切らせるには、あと一歩足りないとの感が払拭できず、結局において、現住建造物等放火罪の成立はこれを認めることができない
と判示しました。
心神耗弱者による放火で未必の故意が否定された事例
放火罪においては心神耗弱者の犯行が多くみられます。
心神耗弱者の延焼の予見の程度については、通常人より劣ることが指摘されたものが多く、それが理由で未必の故意が否定された裁判例が多数あります。
東京高裁判決(昭和29年8月9日)
物置放火に際し、心神耗弱者にはこれと約5m離れた住家への延焼の予見はできないとした事例です。
裁判官は、
- 本件物置に放火するに際し、これに火を放てば、これとわずかに約5mしか離れていないF方住家にも延焼するであろうことは通常人ならば何人も当然容易に予見しうる事柄であり、かつ予見すべきことである
- ところが、被告人の如き心神耗弱者がこれを予見しうるであろうか
- 被告人の供述調書中にはあたかもこれを予見したかの如き供述が存在するのであるが、これは取調に当たって理屈を説明されたためにこのような供述となったものと認めるのを相当とし、この供述記載があるからというて本件犯行当時被告人が住宅に延焼する事を予見していたものとは認めることはできない
- 被告人のような心神衰弱者には到底物事の推理による判断、予見の如き精神作用は期待できないと認めるのを相当とする
- 他に本件記録によっては、被告人が住宅を焼燬する目的のあったことはもちろん、住宅に延焼する事を予見した事実を認めるに足る証拠は存在しない
- しからば、原審が被告人が本件物置に放火するに当り、F方居宅にも延焼することを予見した如く認定したのは明らかに事実を誤認したものというべく、この誤認はもちろん判決に影響を及ぼすものであるから、原判決は破棄すべきものである
と判示し、現住建造物等放火未遂罪は成立しないとしました。
東京高裁判決(昭和30年12月6日)
飲酒酩酊による心神耗弱で、点火した紙くずを倉庫内に投げ込んだが、隣接する住宅まそ延焼すべきことを予見していたとはいい難いとした事例です。
裁判官は、
- 建造物放火罪の犯意は、建造物焼燬の結果を発生すべきことを予見するをもって足りるのであり、敢えてその結果の発生を目的とすることを要しないものと解するのが相当である
- 被告人がM所有の倉庫に放火するに際し、同倉庫の焼燬によってこれに隣接する社宅に延焼するに至ることあるべきことを認識していたとの原審認定は、記録を検討してもこれを首肯し難いのであって、当時の被告人の心神の状況に徴しても、消極に解するのが相当である
と判示し、現住建造物等放火罪は成立しないとしました。
大阪地裁判決(昭和43年10月30日)
真性てんかんのため知能発育の遅れた被告人には、放火した倉庫にとどまらず隣接する住宅に延焼することまで認識していたとはいい難いとした事例です。
裁判官は、
- 被告人は真性てんかんのため知能の発育が遅れ、医師T作成の精神鑑定書によれば、被告人の知能程度は通常人に比し、かなり劣っており、また観念内容は貧困で思考過程も迂遠であり末梢的な些事にとらわれ物事を全体的に把握する能力に欠けていると認められること等の事実を総合すれば、被告人の「腹いせにちょっと燃やすつもりだった。コンクリートだからよそに燃え移るとは思わなかった。」との趣旨の被告人の弁解は、犯行当時の被告人の放火の故意内容として首肯し得るところであって、周囲の状況としても犯行の時間は仕事のひけ時で人の出入りの多いタ方であり、かつすぐ近くにはM方家人ら数人の人がいて早期に発見消火されることも予想しえない状態ではなかったこと、犯行後自宅に逃げ帰っていた被告人が事の成り行きに驚いていたこと等の事実はいずれも右認定にそうものである
- 以上により、犯行当時被告人において未必的にもせよ右作業場兼倉庫にとどまらず隣接する現住建造物まで焼燬する故意を有していたと認めるに足る十分な証拠はなく(被告人の捜査官に対する供述調書中には、未必の故意を認めたかのような記載部分があるが、この点は前記諸事情と被告人の当公判廷における供述態度にてらして信用しない。)被告人の犯意は判示のように非現住建造物焼燬の限度においてその存在を認めるのが相当であって、結局被告人の本件行為については非現住建造物放火罪の既遂の成立を認め得るにとどまる
と判示しました。