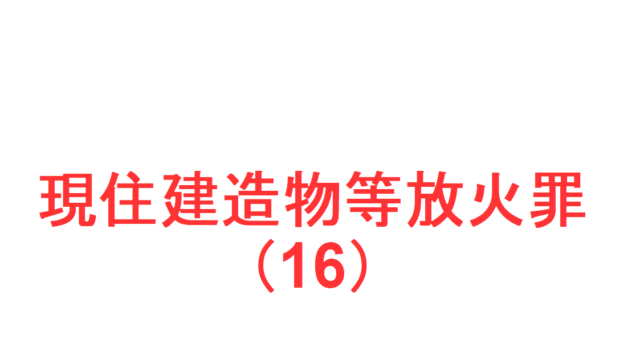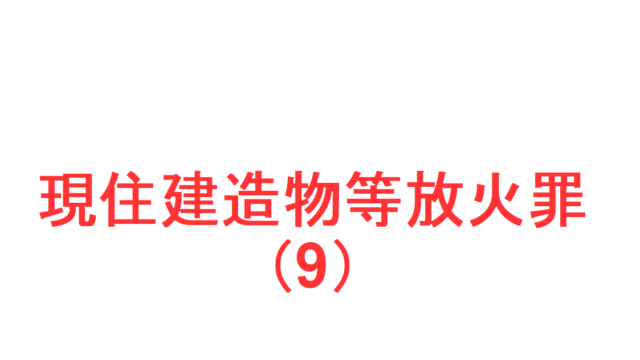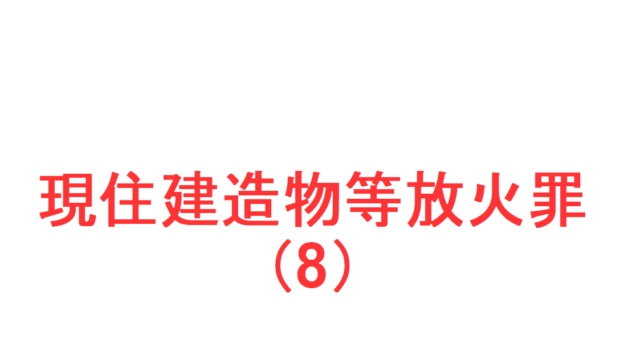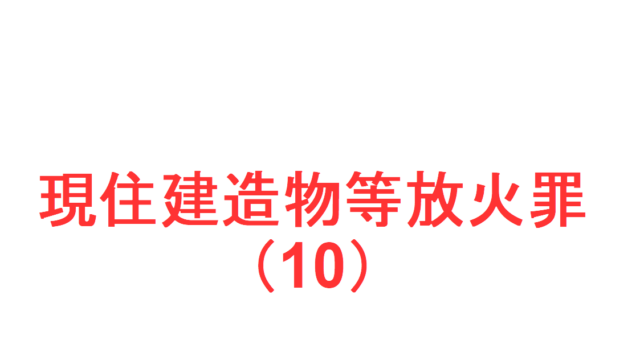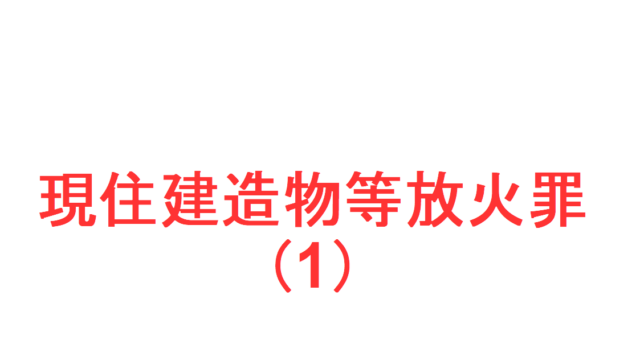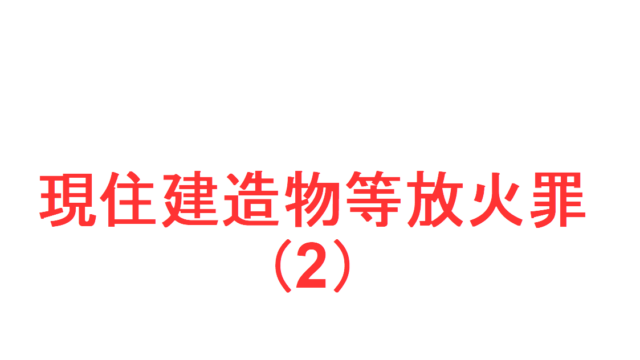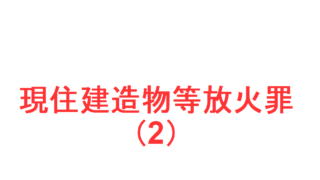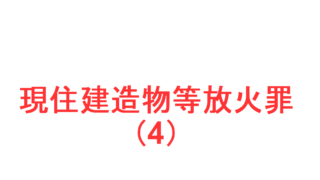現住建造物等放火罪(3) ~「複数建物の一体性の判断基準」などを説明~
前回の記事の続きです。
住居に使用しない部分、あるいは、現に人がいない部分と一体をなしている建造物全体が1個の現住建造物となる場合、その建造物に放火すれば、現住建造物等放火罪が成立する
原則として、
- 建造物の一部が現に人の住居に使用されている場合
あるいは、
- 建造物の一部に現に人がいる場合
においては、その部分と一体をなしている建造物全体が1個の現住建造物となり、その建造物に放火すれば、現住建造物等放火罪が成立します。
なので、そのような建造物について、住居に使用しない部分、あるいは、現に人がいない部分だけを焼損する意思で放火したとしても、現住建造物等放火罪が成立します。
住居に使用しない部分、あるいは、現に人がいない部分と一体をなしている現住建造物に放火し、建造物全体に対する現住建造物等放火罪の成立を認めた事案として以下のものがあります。
- 1階の一室だけを宿直室として使用し、夜間、宿直員が宿泊している私立工学校の2階部分に放火した事案(大審院判決 大正2年12月24日)
- 一棟の家屋が数戸に区分され、内一戸を住居に使用し、他の部分が空家になっている長屋の空家部分に放火した事案(大審院判決 昭和3年5月24日)
- 住宅と接合して一体をなしている工場に放火した事案(大審院判決 昭和16年2月12日)
- 人の寝泊まりしている劇場に接着して設けられた便所に放火した事案(最高裁判決 昭和24年2月22日)
④の最高裁判決(昭和24年2月22日)の判決内容は以下のとおりです。
裁判官は、
- 被告人が火を放った便所は、劇場建物の東側に接着するものであることは、原判決の確定するところであり、原判決の挙示する証拠、殊に強制処分における判事の検証調書の記載、同調書添付の図面によれば、右便所は右劇場に接着して建設ぜられ、右劇場の一部をなすものであることがわかる
- しかして、被告人が本件犯行にあたり、右便所を焼燬する意思のあったことは、原判決挙示の証拠上明瞭であるから、これにもとずいて、原判決が、被告人は本件劇場に放火しようと考えた旨判示したのは、相当である
- また、右劇場には、人が寝泊りしていることを被告人が知っていたこと、及び、放火の結果、既に独立燃焼の程度に達する焼燬のあったことも、右証拠に照してあきらかであるから、原判決が、被告人の右の所為に対して、刑法第108条の既遂罪をもつて、問擬したのは正当である
と判示しました。
複数建物の一体性の判断基準
外観上、複数の建物とみえる場合でも、それが近接し、あるいは廊下等で接続されているときには、全体を一体なものとして1個の建造物と認められることがあります。
最高裁は、複数建物の一体性について、
- 建物の物理的観点
と
- 建物の機能的観点
の双方からの判断しています。
この点を示したのが以下の判例です。
神社本庁爆破事件において、平安神宮の社殿の1個性を判断するに当たり、社殿は、本殿、拝殿、社務所等の建物が回廊等により接続され、多量の木材が使用されていて、延焼の可能性があったこと、また、昼間は拝殿で礼拝等が行われ、夜間は神職らが宿直して社殿の建物等を巡回していたことなどの事実関係を前提とした上、
- 社殿は、その一部に放火されることにより全体に危険が及ぶと考えられる一体の構造であり、また、全体が一体として日夜人の起居に利用されていたものと認められる
- そうすると、右社殿は、物理的に見ても、機能的に見ても、その全体が―個の現住建造物であったと認めるのが相当である
と判示し、現住建造物等放火罪が成立するとしました。
上記判例のほか、廊下等でつながれた複数建物の一体性が争点となった判例として以下のものがあります。
大審院判決(大正3年6月9日)
放火された本館庁舎及びこれとは独立した付属建物からなり、宿直室が付属建物内にある今治区裁判所について、宿直員が巡視するのが通例であるといった機能的観点から1個の現住建造物と認めました。
大審院判決(昭和14年6月6日)
宿直教論等の現にいる中学校校舎本館及び用務員室と現に人がいない別棟校舎とが廊下等(雨除け程度の屋根のもの)により連接した二棟の建物のうち、別棟校舎に放火した事案につき、両建物は一体として現に人がいる建造物に当たるとしました。
東京高裁判決(昭和28年6月18日)
羽目板及び壁のあるいわゆる中廊下をもって接続された数個の建物は、全体として構造上不可分一体をなしているが、柱と柱の間に羽目板もなく、木造トタン葺のいわゆる渡り廊下で接続された建物は、一体をなした建物といえないとしました。
東京高裁判決(昭和31年7月31日)
一部事務所となり現に人がいる機械仕上工場と組立工場との間には渡り廊下があって接続され、他の各工場も互いに接続して順次連絡交通できることから、たとえ右渡り廊下に柱がなく、ただ鉄骨の桁が渡してありトタン屋根で雨や雪を防ぐようにしてあるだけで、その下をトラックが自由に往来できるようになっていても、全体が構造上一体をなす1個の建造物と認められるとしました。
福岡地裁判決(平成14年1月17日)
非現住建造物である研修棟と現住建造物である宿泊棟が長さ約7.5メートルの2本の渡り廊下でつながれている建物につき全体として1個の現住建造物として起訴された事案について、研修棟と宿泊棟の間に機能的連結性を認めつつも、建造物の1個性を肯定するためには、構造上の接着性の程度、建物相互間の機能的連結性の有無・強弱、相互の連絡、管理方法などに加えて、延焼の可能性が否定できないという程度の意味において延焼の蓋然性が認められることが必要であるとし、本件ではその蓋然性を認めるには疑いが残るとして1個性を否定しました。