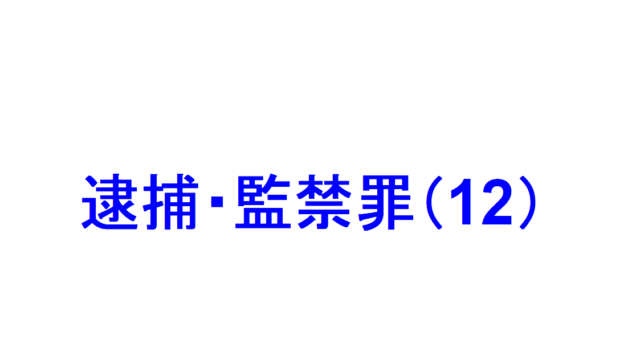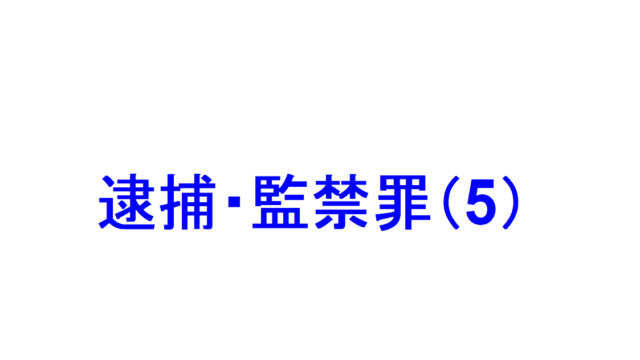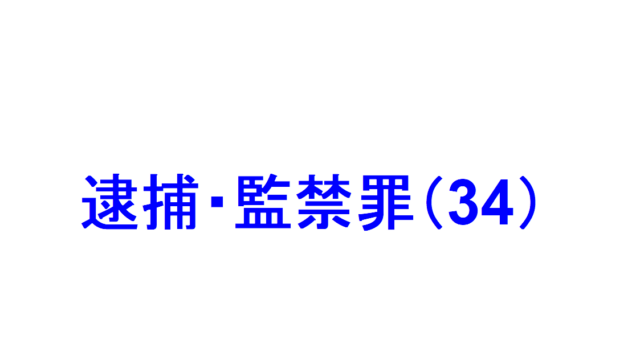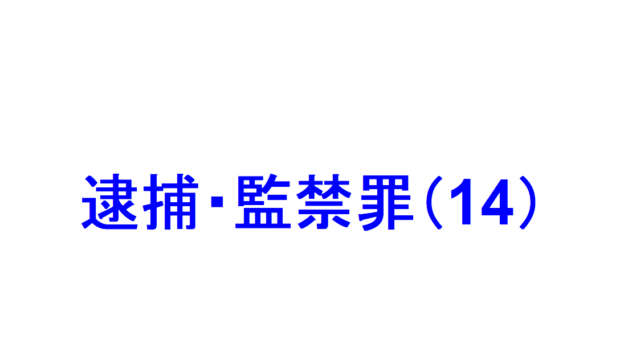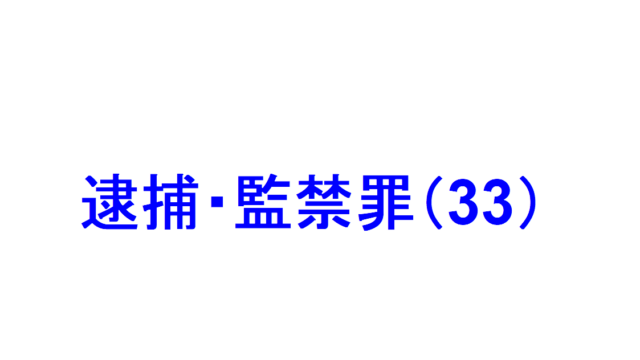逮捕・監禁罪(2) ~「被害者に意思能力・行動能力がなかった場合、逮捕罪・監禁罪は成立する」を説明~
前回の記事の続きです。
被害者に意思能力・行動能力がなかった場合、逮捕罪・監禁罪は成立する
逮捕罪・監禁罪(刑法220条)の客体(被害者)は自然人に限られます。
そして、逮捕罪・監禁罪は、人の身体活動の自由に対する侵害であるところから、逮捕罪・監禁罪の客体となり得る者は、意思能力及び行動能力を有する者に限られるかどうかについて争いがあります。
裁判例は、法律上の意思能力・行為能力を欠いても、自然的な意味において任意に行動しうるものであれば、逮捕罪・監禁罪の客体たりうることを前提とし、逮捕罪・監禁罪の成立を認めています。
参考となる裁判例として以下のものがあります。
京都地裁判決(昭和45年10月12日)
自然的な意味で任意に行動し得る生後1年7月の幼児は、監禁罪の客体として保護されるとした事例です。
事案は、被告人が、母子2人の家に金品強奪の目的で押し入り、台所から文化包丁を持ち出して母親を脅迫したが、母親が隙を窺って生後1歳7か月の男児を残したまま逃げ出し、警察に届け出たことにより、間もなく同家が警察官によって取り囲まれたことを知るや、上記男児を人質にして逮捕を免れようと考え、男児を一室に閉じ込めたうえ、約4時間半にわたり、取り囲んだ警察官らに対し「近づくと子供を殺すぞ」と申し向けて外部との交通を遮断し、さらに、歩き回る同児を手や足で押えて同部屋の片隅に留め置いたというものです。
裁判所は、
- たしかに、監禁罪がその法益とされている行動の自由は、自然人における任意に行動しうる者のみについて存在するものと解すべきであるから、全然任意的な行動をなしえない者、例えば生後間もない嬰児の如きは監禁罪の客体となりえないことは多く異論のないところであろう
- しかしながら、それが自然的、事実的意味において任意に行動しうる者である以上、その者が、たとえ法的に責任能力や行動能力はもちろん、幼児のような意思能力を欠如している者である場合も、なお、監禁罪の保護に値すべき客体となりうるものと解することが、立法の趣旨に適し合理的というべきである
- これを本件についてみるに、前掲各証拠を総合すると被害者Kは、本件犯行当時、生後約1年7月を経たばかりの幼児であるから、法的にみそ意思能力さえも有していなかったものと推認しうるのであるが、自力で、任意に座敷を這いまわったり、壁窓等を支えにして立ち上り、歩きまわったりすることができた事実は十分に認められるのである
- されば、同児は、その当時、意思能力の有無とはかかわりなく、前記のように、自然的、事実的意味における任意的な歩行等をなしうる行動力を有していたものと認めるべきであるから、本件監禁罪の客体としての適格性を優にそなえていたものと解するのが相当である
と判示し、前記幼児に監禁罪の客体としての適格性を認め、監禁罪の成立を認めました。
横浜地裁判決(平成24年1月25日)
生後約10か月の男児(長男A)に対する監禁致死罪の成立を認めた事例です。
裁判所は、
- 被告人両名は、夫婦であり、かねてより週末になると、幼い2児を自宅に残して、ニ人でパチンコ店に行くなど、外出することを繰り返していた
- 被告人両名は、共謀の上、平成23年4月29日午前9時ころ、自宅の脱衣所において、縦約36.5cm、横約28.5cm、高さ約23.5cmの段ボール箱とこれよりやや大きい段ボール箱を2枚重ねにして片側を開けたものを床に置き、その中に、あお向けにした長男Aを頭から入れ、その段ボール箱と同児の下半身を覆うように、毛布(重さ約2kg)及び布団(重さ約4kg)を順次被せ、さらに、同児の足側の布団の端に缶ビール入りのケース(重さ約8kg)を置いた上、外出して自宅近くでパチンコに興じ、同日正午ころまで、そのまま放置し、その間、同児が上記の覆いから脱出することを著しく困難にし、もって不法に監禁し、よって、そのころ、上記の覆いの中において、同児を酸素欠乏による窒息により死亡させたものである
との事実を認定し、生後約10か月の長男Aに対する監禁致死罪の成立を認めました。
大審院判決(大正10年4月11日)
精神病者を制縛監置した結果死に至らしめた事案について、逮捕監禁致死罪の成立を認めた事例です。
裁判所は、
- 被害者の致死が、加害者において、精神病者の監護上必要なる程度を超過したることを認識しながら緊縛を加えたるに存するときは、刑法第220条、同第221条の罪責を免れざるべく
- もし、その認識なくして緊縛を加え、その結果死に致したりとせば、単に過失致死罪を構成すべきをもって加害者の罪責を定るには、如上の事実を判定せざるべからざるものとす
と判示しました。
大審院判決(昭和11年4月18日)
精神病者を制縛監置した結果死に至らしめた事案について、逮捕監禁致死罪の成立を認めた事例です。
裁判所は、
- 精神病者の全身を四布掛布団に包み、上よりわら縄及び兵皃帯をもって胴膝及び上胸部辺りを縛り、更に麻縄にてその両手首、両足首を縛り、なお、頭部に四布掛布団を覆い被せたるまま、数時間放置し、よって死に至らしめたる場合の如きは、その保護上、必要なる程度を超過したるものにして刑法第220条、第221条の犯罪を構成するものとす
と判示しました。
大審院判決(昭和6年12月17日)
監護義務者でない者が、同義務者において精神病者の監置に要する法定の手続を履践していないことを知りながら精神病者を監置した行為に対し、監禁罪の成立を認めた事案です。
裁判所は、
- 監護義務者に非ざる者が、同義務者において精神病者の監置に要する法定の手続を履践せざることを知りながら、精神病者を監置したるときは、刑法第220条の罪を構成し、精神病者監督法第17条の犯罪を構成せず
と判示しました(なお、精神病者監督法は現在はありません)。
参考
精神病者である被害者の身の安全を図るなどの目的から出た監禁行為について、監禁罪は成立しないとした以下の裁判例があります。
東京高裁判決(昭和35年12月27日)
精神病者に対し、かんぬきを施し、物置小屋に収容した行為について、裁判所は、
- 被害者が徘徊することにより転倒することを防止するのが目的であって、被害者の身体の安全と平穏を保護するためにやむを得ずに執った措置であって、その自由を拘束して不法に被害者を監禁する意思ないし認識はなかったとものと認められる
旨判示し、被告人に不法監禁の犯意が認められないとし、監禁罪は成立しないとしました。
長崎地裁判決(昭和41年3月2日)
精神病の妻を監禁した行為について、裁判所は、
- 精神病者である被害者の身の安全と看護の便利を図る目的から出たもので手段方法においても社会通念上是認される相当性の範囲を逸脱したものとすることはできない
として監禁行為の違法性を否定し、監禁罪の成立を否定しました。
学説
学説上は、
- 移動の全く不可能な者
- 事実上、意思活動をする能力の全くない者
- (例えば、植物状態の人間、生後間もない嬰児や高度の精神病者)
は客体から除外されることについてにほぼ争いがありません。
これ以外の者については、逮捕罪・監禁罪の客体となることを認めています。
他人の扶助又は道具その他機械の助けを借りて行動しうる者は行動能力あるものとします。