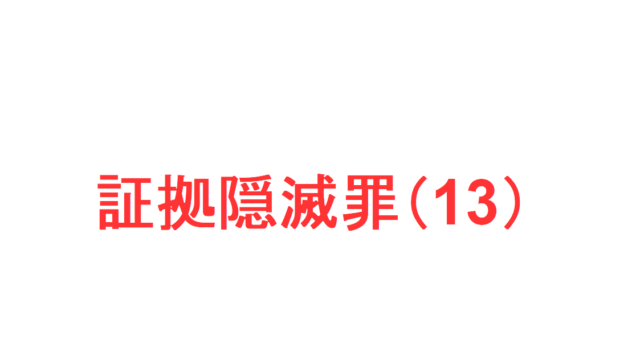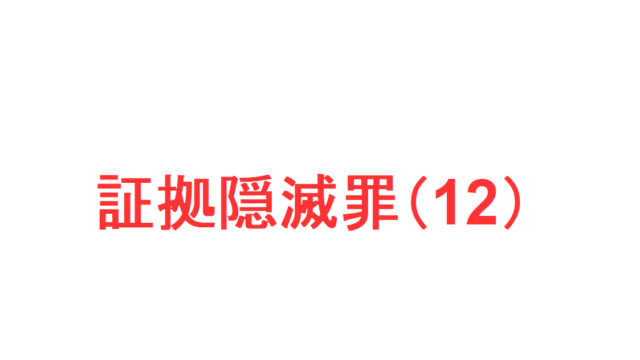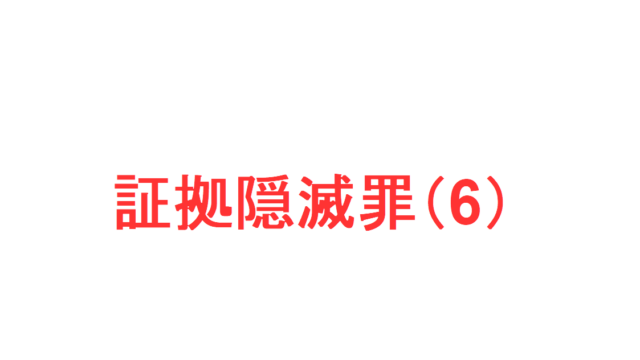証拠隠滅罪(8) ~「内容虚偽の書面(上申書、陳述書など)が作成された場合、証拠隠滅罪が成立する」を説明~
前回の記事の続きです。
内容虚偽の書面(上申書、陳述書など)が作成された場合、証拠隠滅罪が成立する
捜査中の事件に関し、検察官や警察官が参考人の取調べを行い、参考人が検察官や警察官に対し虚偽の供述(例えば、犯人は無実だとするうその供述)をし、検察官や警察官がその供述内容を基に供述調書を作成した場合、証拠隠滅罪(刑法104条)が成立するかについて、裁判例は証拠隠滅罪は成立しないとしています(詳しくは前回の記事参照)。
つまり、内容虚偽の供述調書が作成されても証拠隠滅罪は成立しません。
これに対し、供述調書ではないかたちで作成された内容虚偽の書面(上申書、陳述書など)は、証拠隠滅罪が成立させる場合があります。
この点を判示した以下の裁判例があります。
千葉地裁判決(昭和34年9月12日)
選挙買収被疑事件に関し、弁護士において、立候補者から秘書に渡された金員が、第三者から立候補者への個人献金として秘書に渡されたものであることを偽装するべく、第三者にその旨の上申書を作成させて検察官に提出させるとともに、当該金員が第三者の事務所の金庫内に以前保管されていたような状況を作出させた事案で、弁護士に対し、証拠隠滅教唆罪が成立するとしました。
東京高裁判決(昭和36年7月18日)
選挙買収事件の被疑者の弁護人が、買収金が別の経路・理由で運動員に渡ったと仮装するため、関係者にその旨の虚偽の上申書を作成させ、検察官に提出させた事案で、弁護士に対し、証拠隠滅教唆罪が成立するとしました。
東京高裁判決(昭和40年3月29日)
現に捜査中の被疑事件につき、参考人として検察官から上申書の作成、提出を求められた者Aが、虚偽の内容を記載した上申書を作成して検察官に提出したときは、たとえ右文書の作成名義にいつわりがなく、またその文書の作成が口頭による陳述に代えてなされた場合であるとしても、刑法第104条にいう証拠を偽造し、使用したことになると解するのが相当であるとし、Aに対し、証拠隠滅罪が成立するとした事例です。
裁判官は、
- 刑法第104条は、捜査裁判裁判等国の刑事司法の作用が誤りなく運用されることを期して設けられた規定であることは明らかであるから「同条にいわゆる証拠とは、刑事事件が発生した場合、捜査機関又は裁判機関において国家刑罰権の有無を断ずるに当たり関係があると認められるべき一切の資料を指称し、あらたな証拠を創造するのは証拠の偽造に該当する」とした昭和10年9月28日の大審院判決(判例集14巻997頁)の趣旨に照らし、かつたとえば「民事原告である被告人の虚偽の請求を民事被告が認諾した旨記載した口頭弁論調書のようなものは、同被告人の犯罪の成否態様を判定する資料たるべき物的材料であることはもちろんであって、右民事被告が情を知らない裁判所書記を利用しこのような虚偽の内容を有する口頭弁論調書を作成させるのは、いわゆる証拠を偽造したものとなすを妨げない」とした昭和12年4月7日の大審院判決(判例集16巻517頁)の旨意にかんがみるときは、所論のようにたとえ虚偽の内容を記載した文書の作成名義にいつわりがなく又その文書の作成が口頭による陳述に代えてなされた場合であるとしても、本件のように参考人が虚偽の内容を記載した上申書を作成しこれを検察官に提出すれは、刑法第104条にいう証拠を偽造使用したことになると解するのが、判例にしたがい現実に即した妥当な解釈といわざるを得ない(昭和34年6月20日東京高等裁判所第十刑事部判決及び昭和36年7月18日同裁判所第六刑事部判決参照)
と判示しました。
福岡地裁判決(平成5年6月29日)
窃盗犯人が、友人にアリバイ証人になることを依頼し、その旨の上申書を警察官に提出させたという事案で、証拠隠滅教唆罪が成立するとしました。
大審院判決(昭和12年4月7日)
選挙買収の罪で公判中の被告人が、被供与者から形式的に借用証を取っていたことを奇貨として、供与金が貸金であったとの証拠を作出するべく、被供与者を相手に貸金返還請求の民事裁判を提起した上、被告に請求の認諾を依頼し、情を知らない裁判所書記官に内容虚偽の認諾調書を作成させた事案で、証拠隠滅罪が成立するとしました。
単なる供述録取書を超えて、執行力を備えた請求認諾調書のように、それ自体として独立した価値を有する書面を作成させた場合には、「証拠を偽造した」に該当すると解されます。