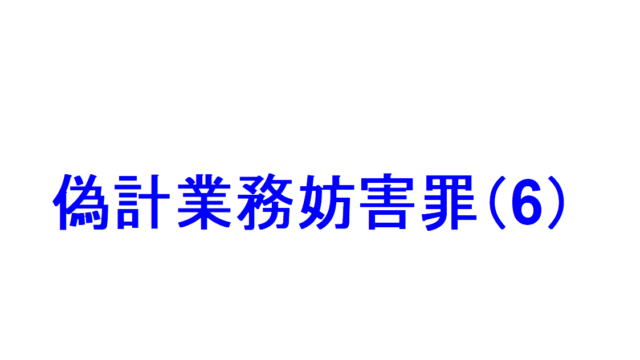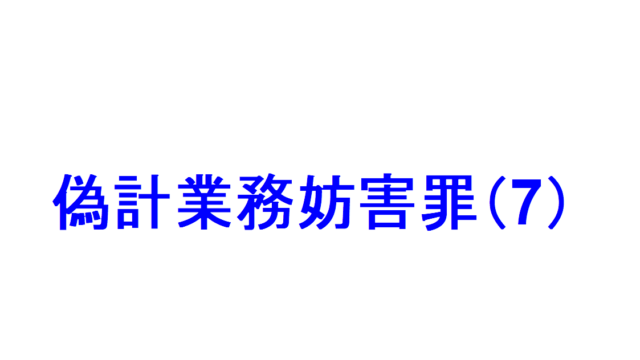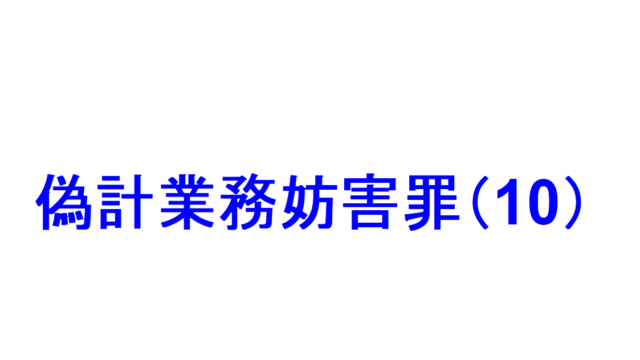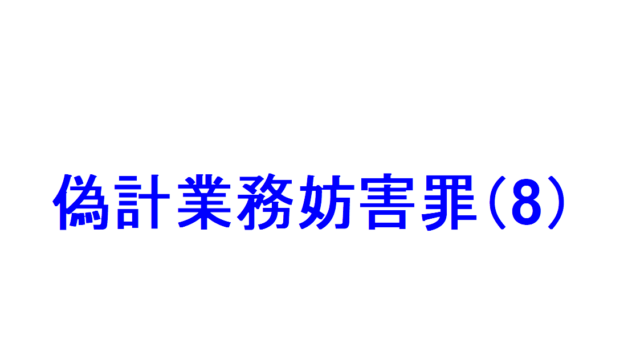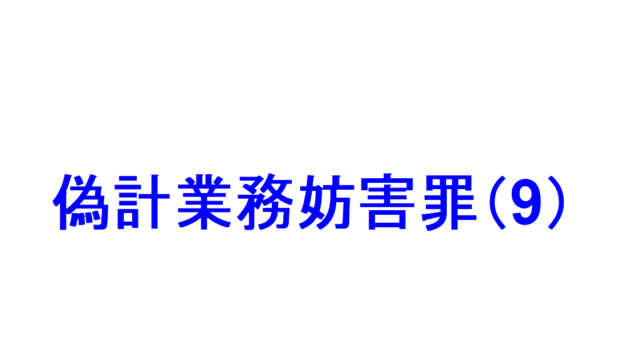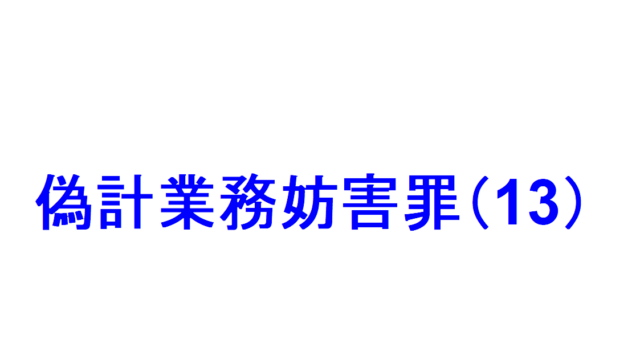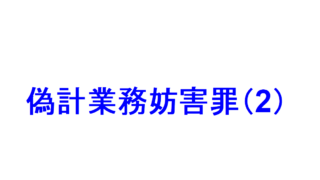偽計業務妨害罪(1) ~「偽計業務妨害罪とは?」「主体(犯人)」「客体(人の業務)、客体には法人を含む」を説明~
これから15回にわたり、「偽計業務妨害罪」「虚偽風説流布による業務妨害罪」(刑法233条後段)を説明します。
偽計業務妨害罪とは?
偽計業務妨害罪は、刑法233条後段に規定があり、
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
と規定しています。
偽計を用いて、人の業務を妨害する行為は「偽計業務妨害罪」となります。
虚偽の風説を流布して人の業務を妨害する行為は、裁判では「業務妨害罪」と呼んでいます(この記事では、「虚偽風説流布による業務妨害罪」として説明します)。
なお、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損する行為は「信用毀損罪」(刑法233条前段)となります(信用毀損罪の説明は前の記事参照)。
「偽計業務妨害罪」「虚偽風説流布による業務妨害罪」の罪質に関し、学説は、
- 財産に対する罪とみる説
- 人の社会的行動の自由に対する罪とみる説
- 財産に対する罪の性質とともに人格に対する罪の性質を併有するとみる説
の3説に分かれていますが、③説が相当であると解されています。
主体(犯人)
「偽計業務妨害罪」「虚偽風説流布による業務妨害罪」の主体に制限はありません。
法人が信用毀損罪の主体たり得るかについては、刑法所定の各犯罪は、法人がその主体となることを予定していないことから、法人ではなく、当該違反行為をなした自然人が処罰されることとなります。
この点、名誉毀損罪の判例ですが、以下の判例が参考になります。
大審院判決(昭和5年6月25日)
法人の代表者が法人の名義を用いて他人の名誉を毀損したときは行為者を処罰すべきものとするとした判決です。
裁判所は、
- 法人の代表者が法人の名義を用いて他人の名誉を毀損したるときは、その行為者を処罰すべきものとす
と判示しました。
客体(人の業務)、客体には法人を含む
「偽計業務妨害罪」「虚偽風説流布による業務妨害罪」(刑法233条後段)は、
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
と規定しています。
「偽計業務妨害罪」「虚偽風説流布による業務妨害罪」にいう「その業務」の「その」とは、前段の「人の」を指します。
したがって「偽計業務妨害罪」「虚偽風説流布による業務妨害罪」の客体は、「人の業務」です。
「人の業務」の「人」とは?
1⃣ 「人の業務」の「人」とは、 自然人であると、法人であるとを問わず、犯人以外の者をいいます。
この点、参考となる以下の判例があります。
大審院判決(昭和7年10月10日)は、株式会社三越の業務を妨害した事案につき、
「被害者の法人たると自然人たるとは同罪の成否に消長を及ぼすべき事項に非ざるなり」
と判示しています。
岡山地裁判決(昭和42年3月20日)は、
「法人の業務を妨害した場合であっても、それが実質的に被告人の経営する個人企業とみられるようなときには、他人の業務を妨害したことには当たらない」
と判示しています。
2⃣ 組合等の法人格なき団体については、実質的にみて一個の独立の組織体として社会的・経済的活動を営み、信用の帰属主体たり得る団体は、信用毀損罪の客体となるとなり得ます(通説)。
大審院判決(大正15年2月15日)は、威力業務妨害罪に関し、
「人の業務とは被告以外の者の業務をいうものにして、その者が自然人たると法人たると、また法人以外の団体たるを問わざるものとす」
と判示し、三業組合福島見番事務所に対する威力業務妨害を認めました。
3⃣ 偽計業務妨害罪の客体としての団体は、単なる人の集合体では足りず、特定の共同目的を達成するための業務主体として社会的に認められる程度の組織性と継続性を有することを要します。
会社、政党その他の政治団体、宗教団体、労働組合、各種学会等がこれに当たります。
社交やスポーツ等を目的とするものについては、学校の同窓会、クラブ等は一般的に偽計業務妨害罪の客体たり得ますが、少人数のクラス会、同好の土の集合等は定期的に開催されるものであっても、通常それ自体独立の活動を行っているとは認め難く、偽計業務妨害罪の客体とみることは困難な場合が多いと考えられます。
業務妨害罪の客体としての団体と認められた裁判例として、以下のものがあります。
- 三業組合福島見番(大審院判決 大正15年2月15日)
- 日本教職員組合(東京高裁判決 昭和35年6月9日)
- 民社党結成大会準備委員会(東京高裁判決 昭和37年10月23日)
- 日本万国博覧会協会(大阪高裁判決 昭和49年9月10日)
- 安保条約改定阻止愛知県民会議(名古屋地裁判決 昭和36年7月4日)
- 中国国際貿易促進委員会(大阪地裁判決 昭和40年2月25日)
- 関西主婦連合会(大阪地裁判決 昭和41年3月30日)
「人の業務」の「業務」とは?
1⃣ 業務妨害罪の「業務」は、
職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業
と定義されます(通説)。
業務妨害罪の「業務」には、
- 娯楽、趣味としての自動車運転、狩猟等は含まれず
- 人の生命身体に危険な業務に限定されず
- 現行法秩序に反し、社会生活上是認されないなど、刑法的保護に値しない違法な業務は除かれる
とされます。
2⃣ 業務妨害罪の「業務」は、営利を目的としたり、経済的なものである必要はなく、精神的なもの、文化的なものであってもよいとされます。
判例は、「業務」の意義につき、
- 「職業その他継続従事する事務又は事業」(大審院判決 大正5年6月26日:弁護土業務の妨害事例)
- 「精神的なると経済的なるとを問わず、広く職業その他継続して従事することを要すべき事務又は事業を総称する」(大審院判決 大正10年10月24日:新聞発行会社設立事業の妨害事例)
と判示しています。
3⃣ 業務妨害罪の「業務」は、主たる業務であると不随的業務であるとを問いません。
この点、参考となる以下の裁判例があります。
福岡高裁判決(昭和57年10月21日)
電話料金を計算するための電気的信号の送信を妨害することは有線電気通信法上の有線電気通信を妨害することに該当し、電公社の課金業務も偽計業務妨害罪の対象となる業務であると認定した事例です。
被告人の弁護人は、
- 刑法233条後段の業務妨害罪における保護法益は人の社会的行動の自由であって、財産権又は財産的利益ではないところ、被告人の原判示所為は「マジックホン」と称する電気器具を電話回線に取り付けて使用し、原判示度数計器作動に基づく通話料金の計算課金を不能にしたものにすぎないから、直接的には日本電信電話公社(以下「公社」という。)の有する通話料金請求を侵害し、その結果、間接的に公社の料金徴収業務の運営を侵害したにすぎず、公社の電気通信業務を妨害したものではないから、公社の業務を妨害したことにあたらない
と主張しました。
この主張に対し、裁判所は、
刑法233条後段の業務妨害罪における業務とは、人がその社会上の地位において継続的に行う事務をいうものであるところ、公社の営む固有(狭義)の有線電気通信活動はもとより、その効用を助けるために付帯して行うその度数料計算活動も公社がその社会上の地位において継続的に行う事務であることは明らかである
- 他方、被告人の原判示所為は公社の有する電話料金債権の帰属自体を侵害するものでも、あるいは右債権の目的たる給付を侵害して同債権を消滅させるものでもなく、電話料金を算定する度数料の登算を阻害するものであるから、所論(弁護人の主張)のように公社の有する債権を直接侵害したものではなく、公社が継続して行う右度数料計量に基づく通話料金課金事務を妨害したものであるといわなければならない
と判示し、業務妨害罪が成立するとしました。
4⃣ 業務妨害罪の「業務」は、本来の業務の準備行為等を含みます。
この点、参考となる以下の裁判例があります。
山口地裁下関支部判決(昭和45年8月7日)
労働争議行為において、会社側が争議対抗策として行った運送業を営むための準備行為としての車両分散行為(会社側がバスを手元に残しておくために行ったバス運行行為)が、会社本来の業務たる一般旅客自動車運送業の執行に密接な関係を有するとして、威力業務妨害罪における「業務」に当たるとした事例です。
裁判所は、
- 会社側の本件運行は業務のための運行を打ち切り、あるいは運行の意図のない車(50号車は事故車で運行に必要な車検証がない。)を分散の目的で運行させていたもので、かかる分散行為そのものは争議の関係においては、会社の本来の業務たる一般旅客自動車運送業の執行という範疇には属しないものと解されるが、車両分散は争議中における運行継続のため、会社側の手にバスを確保しておく目的をも持ってなされたものであることは否み難い
- そうしてみると分散行為は会社の右運送業を営む者という地位に基き、争議中右運送業を営むための準備行為、あるいは予備的一手段としてなされたものというべきで、かかる行為は右運送業の執行に密接な関係を有するものと解するのが相当である
と判示し、妨害された行為の業務性を認め、威力業務妨害罪が成立するとしました。
5⃣ 業務妨害罪の「業務」は、現実に執行している業務のみならず遂行すべき業務を含みます。
この点、参考となる以下の判例があります。
裁判所は、
- 刑法第234条の業務妨害罪にいう「業務を妨害したる」こととは、具体的な個々の現実に執行している業務の執行を妨害する行為のみならず、被害者の当該業務における地位にかんがみ、その遂行すべき業務の経営を阻害するにたる一切の行為を指称する
と判示しました。
6⃣ 「業務」とは具体的個々の現実に執行している業務のみに止まらず、広く被害者の当該業務における地位に鑑み、その任として遂行すべき業務をも指称します。
この点、参考となる以下の裁判例があります。
大阪高裁判決(昭和58年2月1日)
大学教授会で議題審議中に、被告人らの乱入により議事を妨害されたため、やむなく議長が閉会を宣言したことをもって、威力業務妨害の対第となる教授会の業務が存在しなくなったと解することはできないとされた事例です。
裁判所は、
- 威力業務妨害罪にいう業務とは、現実に執行している業務にとどまらず、広く被害者の当該業務における地位にかんがみ、その任として遂行すべき業務をも指称するところ、
 教授会の開催されていた会議室へ被告人らが乱入した時点においては、議題を審議中であり、右乱入の直後、混乱をおそれた議長がやむを得ず、教授会の途中での閉会を宣言し、混乱収拾後の再開予定を告げたことをもって、教授会の業務が終了し、妨害の対象たる業務が存在しなくなったと解することはできない
教授会の開催されていた会議室へ被告人らが乱入した時点においては、議題を審議中であり、右乱入の直後、混乱をおそれた議長がやむを得ず、教授会の途中での閉会を宣言し、混乱収拾後の再開予定を告げたことをもって、教授会の業務が終了し、妨害の対象たる業務が存在しなくなったと解することはできない - 大学教養部講師が、教室において、備え付けのマイクを使用して授業を開始した直後から、被告人ら約10名の学生が、前列の座席や教卓付近に立って、「質問。」「先週はなぜ休講したか。その理由を言え。」などと激しい口調で発言し、その後も、同講師を包囲する位置から代わる代わる大声で「大学とは何か。」「授業とは何か。」「松下問題を取り上げろ。」などと同講師らの制止を無視して発言を続けた行為は、威力を用いて同講師の授業を妨害したものに当たる
と判示し、威力業務妨害罪が成立するとしました。