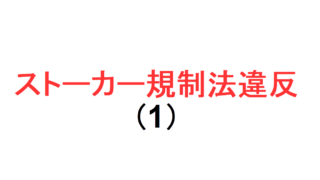少年事件(3)~「起訴強制とは?」「起訴強制の例外」「逆送事件の一部不起訴の可否」「強制起訴した場合の少年の弁護人」などを説明
前回の記事の続きです。
起訴強制とは?
前回の記事では、検察官送致決定(逆送)の説明をし、検察官送致決定には、
- 「刑事処分相当の検察官送致決定」
- 「年齢超過の検察官送致決定」…年齢超過を理由とするもの(家庭裁判所の手続を進めるなかで少年の年齢が20歳に達したもの)
の2種類があるという話をしました。
今回の記事では、①の「刑事処分相当の検察官送致決定」があった場合の
- 検察官の起訴強制
の説明をします。
なお、②の「年齢超過の検察官送致決定」については検察官は起訴強制を受けません(詳しくは前回の記事参照)。
1⃣ 刑事訴訟では検察官に広範な訴追裁量を認める起訴便宜主義がとられています(刑訴法248条)。
しかし、起訴便宜主義の例外として、検察官は、家庭裁判所から刑事処分相当の検察官送致決定により少年事件の送致(逆送)を受けた場合は、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならないとされています(少年法45条5号本文)。
これを「起訴強制」と呼びます。
このようなうになっているのは、刑事処分相当で逆送を受けた事件については、検察官の刑事政策的判断よりも、専門的・科学的な調査を経る家庭裁判所の裁判官の判断に委ねる方が少年の健全育成に資すると考えられるためです。
2⃣ 検察官は、「公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならない」とされます。
これは、検察官は逆送受けた少年事件の「犯罪の嫌疑の有無」については、家庭裁判所の心証に基づく判断に拘束されることなく、改めて捜査した上で独自の判断をすることができることを意味します。
したがって、検察官は、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑が認められないときは、嫌疑なし又は嫌疑不十分として事件を不起訴処分にすることができます。
これに対して、犯罪の嫌疑がある場合は、検察官は、家庭裁判所の刑事処分相当の判断に拘束され、事件を不起訴処分にすることはできず、起訴を強制されます。
これは、少年の犯罪事件の刑事処分相当性は、家庭裁判所が、保護的観点を踏まえた上で、専門的、科学的な検討を加え、刑事政策的な判断を行うものであるので、検察官が改めて起訴相当性の判断を行う必要性がないとされるためです。
3⃣ 検察官送致決定のあった少年の余罪事件が警察から送致された場合、その余罪事件が検察官送致決定のあった事件と併合罪の関係にあれば、検察官はその余罪事件を家庭裁判所に送致する必要があります。
しかし、その余罪事件が検察官送致決定のあった事件と科刑上一罪の関係にあるある場合は、家庭裁判所を経由することなく、検察官送致決定のなされた事件とともに起訴できるとするのが多数説になっています。
起訴強制の範囲
1⃣ 検察官は、起訴を強制されますが、家庭裁判所が認定送致した罪となるべき事実、罪名、罰条に拘束されるわけではなく、犯罪事実の同一性の範囲内においては、検察官の認定に基づいて別個の訴因、罰条で起訴することができます(名古屋高裁判決 昭和29年3月30日)。
ただし、検察官は、「犯罪事実の同一性の範囲内においては、検察官の認定に基づいて別個の訴因、罰条で起訴することができる」のであって、捜査の結果、
「検察官が特定した犯罪事実」と「家庭裁判所が認定送致した犯罪事実」とで犯罪事実の同一性がないことが判明したとき
は、検察官はあらためて事件を家庭裁判所に送致(再送致)しなければなりません。
少年に対する公訴提起には、検察官送致決定が訴訟条件であり(少年法20条、42条、45条5号)、これを経ないで公訴を提起した場合、その手続は無効であり、公訴棄却の判決がなされ、訴訟が打ち切られることになります(刑訴法338条4号)。
したがって、「検察官が特定した犯罪事実」と「家庭裁判所が認定送致した犯罪事実」とで犯罪事実の同一性がない少年事件を起訴した場合、検察官は逆送を経ていない少年事件を起訴したことになるので、公訴棄却の判決がなされ、訴訟が打ち切られることになります。
2⃣ 逆送を受けた事件が罰金以下の刑に当たる(ただし、18、19歳の特定少年の事件は除く)と判明した場合も、検察官はあらためて事件を家庭裁判所に送致(再送致)しなければなりません(奈良簡裁判決 昭和38年11月11日)。
起訴強制の例外
家庭裁判所の刑事処分相当との判断は、検察官を拘束し、起訴を強制しますが、これには、例外が定められています。
具体的には、家庭裁判所の刑事処分相当の判断の基礎となった事情が変化した場合には、起訴強制が働かず(少年法45条5号ただし書)、このように起訴強制が働かない場合には、検察官は家庭裁判所に事件を再送致しなければならないと定められています(少年法42条本文)。
これは、少年の事件についての刑事処分相当の判断は、あくまでも家庭裁判所に行わせる趣旨であるとされるためです。
以下で起訴強制の例外の具体例を説明します。
① 送致を受けた事件の一部について、公訴を提起する犯罪の嫌疑がないとき
家庭裁判所が、A、B、Cの3つの犯罪事実の事件について検察官送致決定をしたが、A事実については公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がない場合は検察官はどうすべきかについて、
- B・C事実は起訴して、A事実は家庭裁判所に再送致すべきとする見解(①説)
- A・B・Cの3つの事実は家庭裁判所に再送致すべきとする見解(②説)
があります。
①説が積極説とされており、その考え方は、
少年法45条5号ただし書の規定である
「ただし、送致を受けた事件の一部について公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないか、又は犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため、訴追を相当でないと思料するときは、この限りでない」
という規定を
「事件の一部について公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないため、訴追を相当でないと思料するときは、この限りでない。」
と読み、A事実に犯罪の嫌疑がない場合にも、検察官が、B及びCの事実だけで訴追が相当であると思料するときは、公訴を提起することができ、訴追を相当でないと思料するときには家庭裁判所に再送致すれば足りる
とするものです。
②説は消極説とされており、その考え方は、
少年法45条5号ただし書の規定を、
「事件の一部について公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がない…ときは、この限りでない。」
と読み、検察官は、B及びC事実について、直ちに公訴を提起することはできず、A・B・Cの3つの事実を必ず家庭裁判所に再送致しなければならない
とするものです。
刑事処分相当性は、A、B、Cという複数の事実を総合的に検討して初めて肯定される場合もあれば、B、Cの事実は比較的軽微な犯罪であるが、Aが重大な犯罪であり、Aとともに処理することで、B、Cの事実についても刑事処分相当性が肯定される場合もあります。
また、B、Cの事実のみでも刑事処分相当性が認められる場合もあります。
②説は、検察官に送致された複数の事実の一部(A事実)について犯罪の嫌疑が認められないときは、残部の事実(B、C事実)について刑事処分相当性が認められなくなる場合もあるので、その場合には家庭裁判所の判断を介する必要があるとするものであり、家庭裁判所先議の原則を貫こうとするものです。
①説に対しては家庭裁判所先議の原則が貫けるかという点の批判が強く、また、消極説に対しては少年に手続の重複、身柄事件の場合の拘束の長期化などの負担を負わせることになり、実際上の不都合を生じる場合があるという点の批判があります。
② 犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため、訴追を相当でないと思料するとき
起訴強制の例外事由として、少年法45条5号ただし書に「新たな事情を発見したため、訴追を相当でないと思料するとき」とあります。
「新たな事情を発見したとき」とは、
- 家庭裁判所が検察官送致決定(少年法20条)をした時に、いまだ認知していなかった事情を新たに発見した場合
を意味し、その事情は、検察官送致決定後に生じたものはもとより、決定前に存在していた場合を含むと解されています。
「新たな事情」とは、
- 犯罪の動機、原因、態様、結果等の情状に関する事実に関する新たな事情
が挙げれらます。
「新たな事情」には、犯罪事実の同一性は認められるが、認定罪名を異にするに至った場合(例えば、家庭裁判所が殺人として送致したが、捜査の結果、傷害致死の事実しか認められない場合)も含むと解されています。
③ 送致後の情況により訴追を相当でないと思料するとき
起訴強制の例外事由として、少年法45条5号に「送致後の情況により訴追を相当でないと思料するとき」とあります。
「送致後」とは、検察官送致決定(少年法20条)をなした時期以後をいい、決定当時に存在していた事情は、決定後に判明したとしても、これに含まれません。
送致後の情況とは、
- 被害の弁償、示談の成立、被害者の宥恕
- 法令の改正
- 告訴の取下げ又は取消し
- 少年又は保護者の反省
が挙げられます。
逆送決定後、公訴提起前に少年が成人に達した場合に起訴強制の効力が存続するか?
逆送決定後、公訴提起前に少年が成人に達した場合、起訴強制の効力が存続するかについては議論があるところ、起訴強制の効力が存続しないとする説が有力となっています。
逆送事件の一部不起訴の可否
1⃣ 逆送された事件全部の犯罪の嫌疑が認められる場合、
- 検察官が一部の事件を不起訴にすることを認める見解
- 検察官が一部の事件を不起訴にすることは認められないとする見解
があります。
①の「検察官が一部の事件を不起訴にすることを認める見解」は、その理由として、
- 起訴しなくても少年の処遇に全く影響がないと思われる軽微な事件を不起訴としても、家庭裁判所の先議権侵害や少年が刑事処分も保護処分も受けないことを防止する法の趣旨に反するとまではいえないこと
- 訴訟経済の要請からむしろ好ましい場合もあること
が挙げられます。
②の「検察官が一部の事件を不起訴にすることは認められないとする見解」はその理由として、
- 起訴強制の例外は少年法45条5号ただし書の場合に限定されること
- 少年の処遇についての家庭裁判所の先議権を侵すことになりかねないこと
- 検察官送致の場合の家庭裁判所の判断は、少年の行為(犯罪事実)に重点がおかれていること
- 検察官送致は刑罰による道義的責任の追及ばかりでなく、刑罰による矯正・教育という観点も併せ考慮されているので、犯罪事実の全部につきその責任の所在を明確にすることは少年の教化改善に必要なことであり、手続経済上の理由で、一部のみを起訴し他を不問に付することは刑事手続における教育的効果を無視するものであること
- 少年法45条5号ただし書、42条の趣旨は、少年の犯罪について起訴もされず、保護事件としての終局処分も受けないような事態を防止することにあり、一部起訴の余地を認めることはこれに反すること
が挙げられます。
2⃣ もっとも、検察官が逆送を受けた事件の一部のみを起訴したとしても起訴が無効となるわけではありません。
この点を判示した以下の裁判例があります。
裁判所は、
- 家庭裁判所から少年法20条による送致を受けた事件の一部について同法四五条五号但書の事由がある場合に、その余の事件についてのみ公訴が提起されたとしても、起訴された事件自体が起訴価値を有するときは当該起訴を無効とすべきいわれはない
と判示しました。
逆送を受けた少年事件を検察官は簡易裁判所に公訴提起することもできる
逆送を受けた少年事件を検察官は地方裁判所ではなく簡易裁判所に公訴提起することもできます。
この点を判示した以下の裁判例があります。
裁判所は、
- 検察官は、家庭裁判所から送致を受けた少年に対する窃盗事件について少年法第20条の規定あるの故をもって、その公訴を必ず地方裁判所に提起するを要するものではなく、簡易裁判所に提起するも違法でない
と判示しました。
強制起訴した場合の少年の弁護人
弁護士である少年の付添人は、刑事処分相当の検察官送致決定がなされたときには、弁護人とみなされます(少年法45条6号)。
この弁護人は、検察官が事件を公訴提起した後も弁護人の地位を有します(刑訴法32条1項)。
そのため、検察官は、公訴提起と同時に、公訴提起する裁判所に対し、家庭裁判所に差し出された付添人選任届を提出しなければなりません(刑訴規則165条2項)。
少年事件の記事一覧
少年事件(1)~「少年事件の刑事手続の流れ(警察から検察庁への事件送致、家庭裁判所から検察官への事件の逆送)」を説明
少年事件(2)~「検察官送致決定(逆送)とは?」を説明
少年事件(3)~「起訴強制とは?」「起訴強制の例外」「逆送事件の一部不起訴の可否」「強制起訴した場合の少年の弁護人」などを説明