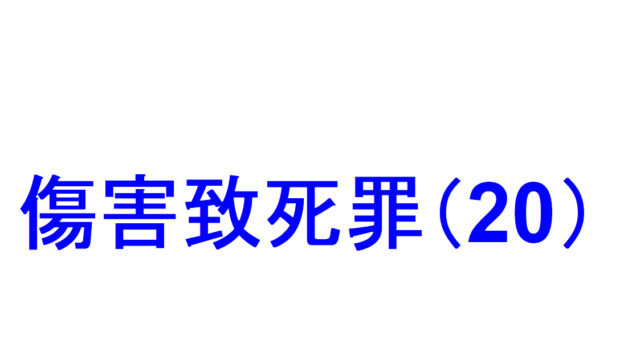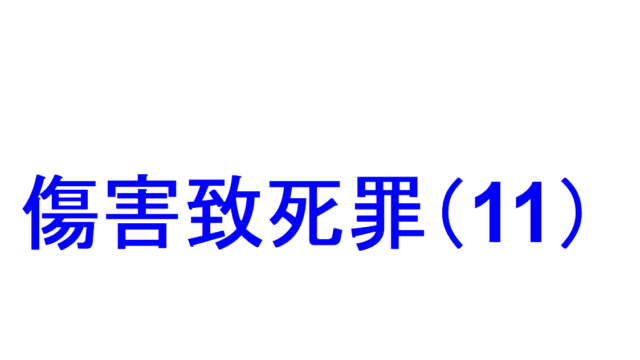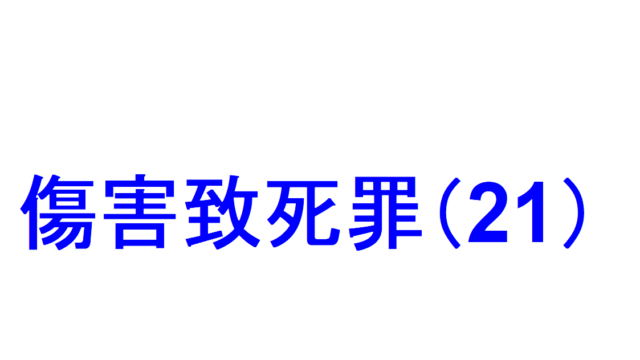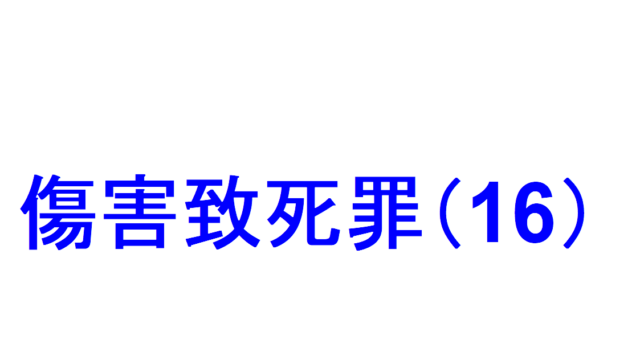傷害致死罪における教唆犯・幇助犯
暴行の結果的加重犯でもある傷害致死罪においては、暴行の教唆・幇助により、正犯が傷害致死又は殺人を犯した場合、傷害致死の教唆犯・幇助犯が成立することになります。
この点について、以下の判例があります。
傷害致死の教唆犯を認めた判例
大審院判決(明治29年5月18日)
この判例は、暴行を教唆した者に、その結果生じた傷害致死罪の教唆犯が成立するとしました。
裁判官は、
- 殴打罪(※現在の暴行罪)は、犯人において、被害者を創傷するの意思あると否とを論ぜず、結果によってその罪を構成するものなるが故に、殴打致死(※現在の傷害致死)の場合において、その殴打を教唆したるものは、すなわち殴打致死罪(傷害致死罪)の教唆者として処断す
と判示し、教唆者が実行者に対し、暴行を教唆したが、結果として実行者が被害者を暴行により死亡させた場合、教唆者に対して、暴行罪ではなく、傷害致死罪が成立するとしました。
大審院判決(大正13年4月29日)
この判例で、裁判官は、
- 人の身体を不法に侵害する認識をもってなしたる意思活動により、人を死に致したるときは、傷害致死罪を構成するものとす
- これをもって、人を教唆して、他人に暴行を加えしめたる以上は、その暴行の結果、他人の身体を傷害し、よって死に致したるにおいては、教唆者は傷害致死の罪責に任せざるべからざるや、事理の当然というべし
と判示し、人を教唆し、被教唆者に暴行を加えさせた以上は、その結果、被害者が死亡した場合、教唆者に対し、傷害致死罪が成立するとしました。
大審院判決(大正11年12月16日)
この判例で、裁判官は、
- 傷害罪の犯意は、人の身体に暴行を加えるの認識あるをもって足り、傷害の結果につき認識あることを必要とせず
- 他人に対して、暴行を加えるべきことを教唆したる以上は、たとえ傷害の結果を認識せざるも、教唆者の暴行によって生じたる傷害の結果につき責任を負うべきものとす
と判示し、人を教唆し、被教唆者に暴行を加えさせた以上は、その結果、被害者が死亡した場合、教唆者に対し、傷害致死罪が成立するとしました。
大審院判決(昭和6年10月22日)
この判例で、裁判官は、
- 他人に対し、暴行の教唆をなし、被教唆者がこれを実行するにより、被害者を死に致したる以上は、教唆者において、この結果を認識せざるときといえども、傷害致死罪につき教唆の責任を負担すべきものとす
と判示しました。
傷害致死罪の幇助犯と認めた判例
大審院判決(昭和2年3月28日)
傷害行為を幇助して、傷害の実行者が被害者を死に至らしめて傷害致死罪を犯した場合、傷害行為を幇助した者に対しては、傷害致死幇助が成立するとしました。
裁判官は、
- 刑法第206条は、傷害の現場において、単なる助勢行為をなしたる者を処罰する規定にして、特定の正犯者を幇助して、その傷害行為を容易ならしめたる場合においては、傷害罪の従犯をもって論ずべく、同条を適用すべきものにあらず
と判示し、正犯者(傷害の実行者)の傷害行為を幇助した場合、現場助勢罪(刑法206条)ではなく、傷害致死幇助が成立するとしました。
幇助につき、傷害の認識で匕首(短刀)を貸与したところ、正犯(傷害の実行者)が殺人罪を犯した事例で、殺人ではなく傷害の認識で短刀を貸与した幇助者に対し、傷害致死幇助の成立を認めました。
裁判官は、
- 被告人の認識したところ、すなわち犯意と現に発生した事実とが一致しない場合であるから、刑法第38条第2項の適用上、軽き犯意についてその既遂を論ずべきであって、重き事実の既遂をもって論ずることはできない
- 原判決は、右の法理に従って、法律の適用を示したもので、幇助の点は客観的には、殺人幇助として刑法第199条、第62条第1項に該当するが、軽き犯意に基き、傷害致死幇助として、同法第205条、第62条第1項をもって処断すべきものであることを説示したものであることは、判文上極めて明かであって、原判決の法律の適用は正当である
と判示しました。
不作為による幇助を認定した事例
不作為による幇助を認定した事例として、以下の判例があります。
札幌高裁判決(平成12年3月16日)
被告人である妻が、内縁の夫による当時3歳の子供Dに対するせっかんを放置して、内縁の夫Aによる傷害致死を容易にさせた事案で、傷害致死幇助の成立を否定し無罪とした第一審判決を破棄して、傷害致死幇助の成立を認めました。
裁判官は、
- 不作為による幇助犯は、正犯者の犯罪を防止しなければならない作為義務のある者が、一定の作為によって正犯者の犯罪を防止することが可能であるのに、そのことを認識しながら、右一定の作為をせず、これによって正犯者の犯罪の実行を容易にした場合に成立し、以上が作為による幇助犯の場合と同視できることが必要と解される
- 子供Dが夫Aから暴行を受けることを阻止し得る者は、被告人以外存在しなかったことにかんがみると、子供Dの生命・身体の安全の確保は、被告人のみに依存していた状態にあり、かつ、被告人は、子供Dの生命・身体の安全が害される危険な状況を認識していたというべきであるから、被告人には、夫Aが子供Dに対して暴行に及ぶことを阻止しなければならない作為義務があったというべきである
- 被告人には、一定の作為によって、夫Aの子供Dに対する暴行を阻止することが可能であったところ、関係証拠に照らすと、被告人は、本件せっかんの直前、夫Aが寝室で子供Dを大きな声で問い詰めるのを聞いて、夫Aが子供Dにせっかんを加えようとしているのを認識していた上、自分が夫Aを監視したり制止したりすれば、夫Aの暴行を阻止することができたことを認識しながら、いずれの作為にも出なかったものと認められるから、被告人は、右可能性を認識しながら、前記一定の作為をしなかったものというべきである
- 関係証拠に照らすと、被告人の右不作為の結果、被告人の制止ないし監視行為があった場合に比べて、夫Aの子供Dに対する暴行が容易になったことは疑いがないところ、被告人は、そのことを認識しつつ、当時なお夫Aに愛情を抱いており、夫Aへの肉体的執着もあり、かつ、夫Aとの間の第二子を懐妊していることもあって、子供Dらの母親であるという立場よりも夫Aとの内縁関係を優先させ、夫Aの子供Dに対する暴行に目をつぶり、あえてそのことを認容していたものと認められるから、被告人は、右不作為によって夫Aの暴行を容易にしたものというべきである
- 以上によれば、被告人の行為は、不作為による幇助犯の成立要件に該当し、被告人の作為義務の程度が極めて強度であり、比較的容易なものを含む前記一定の作為によって夫Aの子供Dに対する暴行を阻止することが可能であったことにかんがみると、被告人の行為は、作為による幇助犯の場合と同視できるものというべきである
と判示し、被告人は暴行を制止する措置を採るべきであり、かつ、これを制止して容易に子供を保護できたのに、その措置を採ることなく放置したとして、不作為による傷害致死幇助の成立を認めました。
傷害致死罪において同時傷害の特例が適用された事案
傷害致死罪についても、同時傷害の特例(刑法207条)の適用が認められます。
この点について、以下の判例があります。
この判例で、裁判官は、
- 2人以上の者が共謀しないで他人に暴行を加え、傷害致死の結果を生じ、その傷害を生じさせた者を知ることができない場合は、共同暴行者はいずれも刑法207条により、傷害致死罪の責任を負う
と判示し、傷害致死罪においても、同時傷害の特例(刑法207条)が適用されることを示しました。