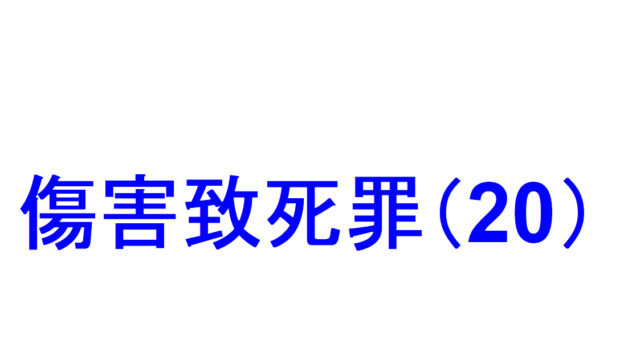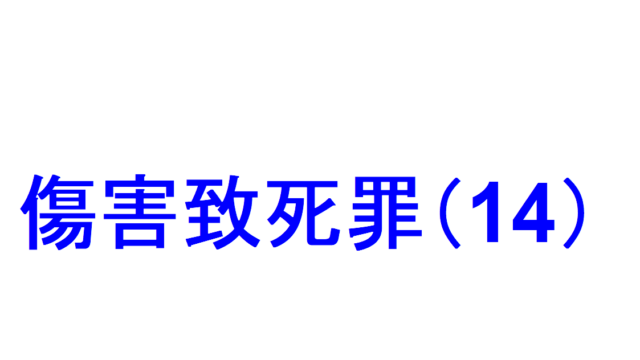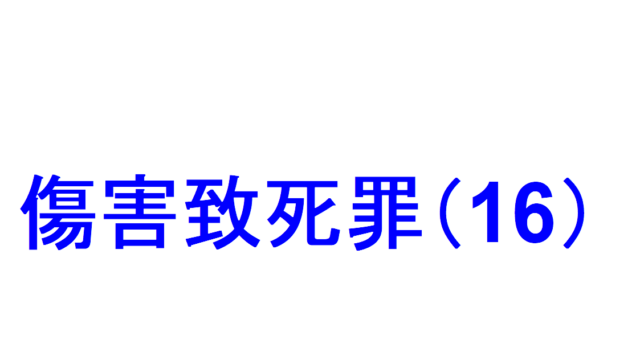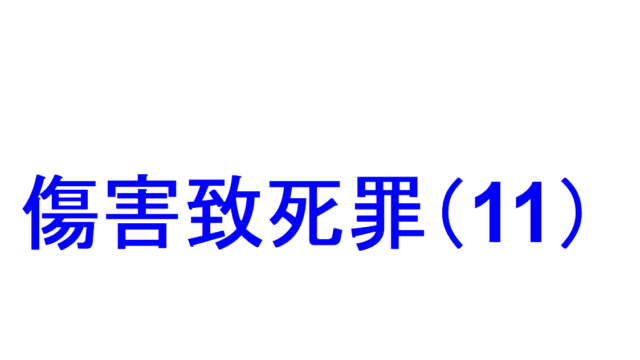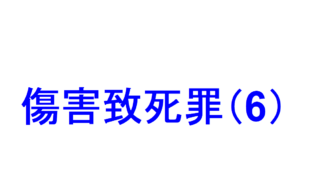傷害致死罪と殺人罪の関係
殺人罪が認められず、傷害致死罪が認定されるにとどまった事例
傷害致死罪(刑法205条)は、殺人罪(刑法199条)の起訴に対して殺意が否定され、傷害致死罪が成立するにとどまるとされる判例が多数あります。
これは、傷害致死罪が、「未必の故意をもってする殺人罪」と限界を接するためです。
「未必の故意をもってする殺人罪」とは、殺すことを明確に意識していないが、「もしかしなら死んでしまうかもしれない」や「死んでしまって構わない」という認識・容認の下に人を殺害した場合をいいます。
検察官が殺人罪で起訴した事件について、裁判官が殺人の故意は認められないとして傷害致死罪が成立するにとどまるとした事例として、以下の判例があります。
神戸地裁判決(昭和35年9月17日)
被害者との関係、動機、暴行の態様、凶器の有無、暴行後の行動等の状況証拠に照らして未必的殺意を否定し、殺人罪ではなく、傷害致死罪を認定した事例です。
裁判官は、
- 被告人の本件犯行直前の激昂の度合は相当強く、犯行の状況も被害者の上に馬乗りとなって喉首部を両手で集中的にしめ、前頸部擦過創、前頸部筋肉内出血、及び舌骨骨折等の傷害を負わせたうえ、間もなく窒息死させている情況のみを取りあげるならば、あるいはこれを殺意に結びつけ得ないとはいえない
- しかし、一方、証拠によると、被告人と被害者Y子は婚約までしていたほどの関係にあり、Y子から虚構の金策を頼まれた際にも、真実と思い込んでそのために奔走したのであって、犯行の直前まで、Y子を殺さねばならないような決定的な動機と考えられるものがない
- のみならず、舌骨骨折を与えるほどの集中的に強力を頸部圧迫についてみても、被告人は頑健な体躯をしており、日頃から力仕事をしていて、人一倍腕力が強く、これがいつにないY子の反抗的態度に激したすえ、興奮のあまり合理的な判断を下す余裕もなく、たまたま強力に作用したものと考えられる
- また、首を締めるに至った直接の動作は、Y子をはねのけた際、被告人の片方の手がY子の首にかかったためであることが窺え、絞首の行為も全く素手で紐類その他の用具を用いていないことが明らかである
- そのうえ、やや我に返ったのち、Y子の鼻血を拭きとるうち、その異様な形相を見て、Y子の死の予感にかられるとともに驚き、慌てふためいて衣服を着るゆとりもなく、アパートを飛び出し、街頭で初めて衣服をまとっている事実は、被告人が前記自己の行為とY子の死の結びつきを全く予期しなかったことを窺うに足りる
- そうすると、前示情況も未だ未必的殺意を認めるには充分でなく、他にこれを確認するに足る証拠は何もない
と判示し、未必的殺意を否定し、殺人罪ではなく、傷害致死罪を認定しました。
大阪地裁判決(昭和44年7月26日)
帰宅途中、被害者にからまれ、ナイフで刺して死亡させた事案において、被害者とそれまで面識もなく、動機が薄弱であり、凶器も死後のため所持していた小型のナイフであり、酒の酔いもあり、被害者にからまれ、恐怖感、被害妄想の結果、防衛的本能により攻撃したもので、ことさら胸部を狙ったものではないことなどから、殺意を否定し、殺人罪ではなく、傷害致死罪を認定しました。
殺人罪を認めず傷害致死罪を認めた理由として、裁判官は、
- 検察官は、本件は未必の殺意による殺人罪であると主張し、被告人は公判廷において一貫して殺意を否認するものの、ナイフを使って被害者の胸部等を数回突き刺し、同人を死に致した犯行の態様および捜査段階においては未必的殺意を認めるが如き供述記載があるので、殺意の存否につき以下検討する
- 被告人は仕事を終え、酒の酔いも手伝って、大声でボヤきながら帰途についたが、被害者が被告人を呼び止め、被告人をにらんで向かってきそうなので、空腹のうえに酒を飲んでいた被告人は、にわかに恐怖感、被害妄想に襲われ、後に説示する如く著しく是非善悪の弁別能力の減退した精神状態のもとで、被害者をナイフで突き刺したことが窺われ、被害者とは、それまで面識もなく何らの遺恨もなかったこと等を考え合わせると、殺人の動機は薄弱である
- 次に、各証拠によると、被告人が使用した肥後守ナイフは、いわゆる通常の肥後守よりは若干大きいが、刃渡り約9.5cmの比較的小さな凶器であり、たまたま被告人が似顔絵描きという仕事の性質上、鉛筆けずりのため所持していたこと、被告人が被害者の左前胸部、頭部、右腕等数回突き刺し、就中左前胸部刺創はぶつかるようにして約11cmもの深さに刺入したものであるが、以上の部位、程度態様は前記のとおり被告人の恐怖感、被害妄想の結果、とっさに防衛的本能が働き攻撃を加えたもので、ことさら胸部を狙って刺したものでもなく、また数回にわたり突きかかっていることも、他の一般の場合のように、これをしつような攻撃と評価すベきではなく、ぶつかるようにして刺したことも被告人の左上下肢の運動機能障害がそういう姿勢をとることを余儀なくさせたものと考えられ、ことさら意識的に右のような攻撃方法を選択したものとは認め難い
- また、被告人は犯行後、被害者が謝ったので、自分の持ち物を拾い集め、帰途につきかけたところ逮捕されたもので、被告人としてはさほど重大な犯行を犯したとの自覚がなかったものではないかと考えられる
- 被告人の未必的殺意を認めるが如き供述調書の記載があるがこれは、被告人が被害者を死に致した結果、極度に悔悟の念にとらわれ、罪の意識にさいなまれていたために、捜査官の理詰めの質問にあって未必的殺意を認めるに至ったと解するのが相当であり、殺意の点についての、右の如き供述記載は、必ずしも被告人の真意を的確に表現しているものとは解せられないのである
- 以上の諸事情を総合勘案すると、本件は確定的殺意はもちろん未必的殺意を認めることも困難であり、傷害致死罪に該当すると認めるのが相当である
と判示しました。
東京高裁判決(昭和53年11月29日)
被告人が、自室において、被害者であるAと酒を飲んでいるうちに些細なことで喧嘩になり、本件犯行の少し前に、被害者及びBが他の部屋の者から借りてきてチーズなどを切るのに使用したあと、たまたま被告人の前に置かれていた果物ナイフで被害者の胸を刺したところ、心臓部に突き刺さって死亡させた事案で、被告人の行為を傷害致死罪にあたると認定した事例です。
裁判官は、果物ナイフで左胸部を1回突き刺して死亡させた行為について、
- 殺意の有無を判断するには、犯行に至る経緯、犯行の動機、凶器の形状およびその殺傷能力、加害行為の態様、被害者の受傷の部位・程度など諸般の事情を総合して認定すべきものである
- そして、右のうち、凶器の形状、加害行為の態様、受傷の部位の程度は、特に殺意認定の重要な要因となる場合が多い
- 本件当時、被告人と被害者との間には特段深い交際がなかったこと、犯行直前ころから被告人は泥酔状態となっており、そのころ被害者との間に言い合いはあったものの、それ程緊迫した雰囲気ではなく、そのことからも被告人が被害者を攻撃するに至った原因は極めて些細なことであったと窺われること、被告人はたまたま目の前にあった果物ナイフを使用したものであり、その態様もすわったままの姿勢で1回だけ被害者を刺したにすぎず、犯行後は直ちに被害者の救助に努めていること等の諸点に、被告人が捜査以来、ほぼ一貫して、本件犯行時相手を殺害しようとの意思は全くなかった、また犯行についても酒の酔いのため、いっさい記憶がない旨供述していることを合わせ考えると、被告人が原判示のように殺意をもって本件犯行に及んだものと断定するには躊躇を感ぜざるをえない
- そして、本件記録を精査しても、他に被告人が殺意をもって本件犯行に及んだと認めるに足りる証拠はない
- そうすると、被告人の本件行為は、傷害致死罪にあたると認めるのほかないといわなければならない
と判示し、殺意の存在を断定しえないとし、殺人罪ではなく、傷害致死罪を認定しました。
東京地裁判決(平成元年10月25日)
文化包丁で被害者に心窩部・上胸部刺創を負わせて死亡させた行為につき、行為態様等から被告人に殺意が認められないとして、殺人罪ではなく、傷害致死罪を認定した事例です。
殺人罪を認定せず傷害致死罪を認定した理由について、裁判官は、
- 被告人が犯行時における殺意を認めた供述記載部分は、被告人の公判段階における供述からも窺えるように、文化包丁を使用して被害者を死亡させたという結果の重大性、刺創が被害者の胸部から心臓にまで達するという被害者の刺傷の部位・程度に基づく捜査官からの追及に抗しきれなくなった被告人が、その都度、誘導に応じて供述していったものとの疑いがあるのであって、本件犯行時における殺意を認めた捜査段階における被告人の供述記載部分は信用し難い
- 本件犯行時における被告人の殺意を認定するには合理的な疑いが残るというべきであるから、被告人の本件犯行は殺人罪には該当しない
- しかし、被害者の心窩部の刺創は、被告人が強く支持した文化包丁の上に被害者が倒れ込むことにより、また、上胸部の刺創は、被告人が右包丁を持った右手を前方に突き出したことにより、それぞれ生じたものであって、いずれも、被告人が自ら被害者にぶつかりもみ合ううちに生じさせたものであるから、被告人については、少なくとも暴行の故意を認めることができ、そのため、本件犯行については傷害致死罪に該当すると認定したものである
と述べました。
函館地裁判決(平成9年1月21日)
被害者の左胸部等を柳刃包丁で刺突して死亡させたとの事案につき、殺意を認める被告人の捜査段階における供述調書の信用性を否定するとともに、脅迫目的で包丁を突きつけたところ、もみ合いとなって刺さったものと認定して殺意を否定し、殺人罪は成立せず、傷害致死罪に成立するにとどまるとされた事例です。
裁判官は、
- 致命傷となった刺創は、人の急所である心臓部にあり、殺傷力のある危険な刃物によって突き刺されたことによるものである
- しかし、このような刺創が被告人と被害者とがもみ合う状況の中で形成されたことや、被告人が柳刃包丁を持ち出した経緯などを考慮すれば、凶器の種類と損傷の部位のみから、殺意を認定することはてきない
と判示し、殺人罪は成立せず、傷害致死罪が成立するにとどまるとしました。
横浜地裁判決(平成10年4月16日)
口論のあげく、憤激のあまり16歳の娘に出刃包丁を投げつけて後頭部に命中させて死亡させた事案につき、動機、犯行態様、犯行後の行動等から殺意を否定し、殺人罪ではなく、傷害致死罪の成立を認めた事例です。
裁判官は、
- 本件行為態様は、出刃包丁を約3メートル余り下方の階段上を降りていく被害者に1回投げつけたというものである
- これにより、本件では、たまたま包丁が被害者の後頭部に命中して刺さったとはいえ、一般的にみてこのような行為により被害者の死亡という結果が発生する危険性はそれほど高くはないこと、動機についてみても、被害者の無断外泊行為に腹を立て、被害者の態度に憤激したとはいえ、日ごろ大変かわいがっていた実の娘に対し、確定的故意をもって殺害を決意したというにはいかにも薄弱であること、「ぶっ殺してやる。」と怒鳴った、あるいは「殺してやる。」とつぶやいたなどというのも、被告人の日ごろの言動に照らし、単に強がりで述べた可能性があり、これらをもって殺意を有していた根拠とするには足りないと言わざるを得ないこと、もし確定的故意を抱いていたというのであれば、それ相応のより積極的な行為に出るのが自然と思われるが、被告人は、被害者が逃げ出しても直ちに追跡せず、衣類をまき散らすなどして当たり散らし、また、屋外に出たのち、歩いて降りて行く被害者を発見しても、直ちに接近して直接刺すことは可能であると思われるのにこのような行為に出ていないし、さらに、包丁を投げつけたのちも、歩いて行く被害者の後をついて行くだけで、それ以上の行為に出ていないこと、以上の点を指摘することができるのであって、これらに照らせば、被告人が被害者殺害について、確定的故意を有していたとは認めがたい
- また、以上の諸点に加え、被告人が実の娘が死亡してもかまわないと認容していたと認めるには動機が弱いことなどからすると、被告人が未必の故意を有していたことにも疑問を抱かざるを得ない
- したがって、被告人に殺人の故意は認めがたい
- 以上により、被告人には傷害致死罪が成立すると考える
と判示し、殺人罪ではなく、傷害致死罪の成立を認めました。